【仕事術】同じ質問を何度も繰り返す部下に試してほしい3つの対処法

「部下が何度も同じことを聞いてくる」
「部下に一度で指示が伝わらない」
今回はそんな悩みを抱える上司に向けた記事になります。
部下への指導は上司の大事な仕事ですが、何度も同じことを聞かれては、さすがにイラっとしてしまうこともありますよね。
彼らにはどう対応するのがベストなのか。3つの対応策をご紹介します。
↓【関連資料】5つの質問に答えると、完全無料でDLいただけます。
※【部下との関係構築できてる度チェックシート】の資料はこちら!
※【50の質問付き!1on1個人面談記録シート】の資料はこちら!
何度も同じことを聞いてくる部下への対処法
①業務の目的について話し合う

何度も同じことを聞いてくる。それはもしかしたら、業務の目的や、業務をする際に重要なことなど、業務の根本的な理解ができていないからかもしれません。
あるいは、そもそもそうしたコミュニケーションができておらず、最初から表面的な手順しか伝えていないため、業務の全体像が見えないから、何度聞いても覚えられないという可能性もあります。
この業務は何のためにやっているのか。
全体としてどんな流れになっているのか。
どんな関係者に影響しているのか。
この業務で重要なことは何なのか。
この業務を間違うとどんな影響があるのか。
このような「業務の根本的なこと」について、同じ質問を繰り返す部下と一度きちんとコミュニケーションをとってみましょう。
ここでは「一度話す」ではなく、「コミュニケーションをとる」ということがポイントです。教えるほうから一方的に話をすると、聞いている部下は「受け身」になってしまい、教えた内容が残らない可能性は大いにあるからです。
部下の今の認識を確認しながら、それを修正していくかたちで、双方向のコミュニケーションによって業務そのものに対する理解を深められるようにしましょう。
【関連セミナー】
【8/31】即実践!明日から使える1on1面談ノウハウ~現代コミュニケーションの新しい常識~
②自分で業務マニュアルを作ってもらう
また、同じ質問が繰り返される業務のマニュアルを、その部下自身に作ってもらうのも一案です。
すでにマニュアルがあったとしても、何度も同じことを聞かなければ業務が進められないということは、その業務マニュアルの内容が不十分ということも考えられます。
「業務マニュアル」があっても、「業務フロー」などの手順だけが書いてあるということはありませんか。もしくは「OJTで」という名目で、業務マニュアルすらないということはないでしょうか。
慣れている人には、「業務フロー」だけあればわかるような業務でも、多くの場合、実際に業務をしてみると「こういうときは、こう対処する」などの細かい「ノウハウ」や「判断ポイント」があります。今まではそれを「OJT」として口頭で伝えて問題がなかったのかもしれませんが、目の前にいる部下は、それでは対応できないのです。
であれば、対応できるように、マニュアルにはなかった「こういうときは、こう対処する」の部分を1つ1つ明確にし、マニュアル化したりチェックリストにしたりして、自分で確認できるような状態にしていけば、同じことを繰り返して確認しなくてもよくなるのではないでしょう。
日々の業務をこなすなかで時間をとるのはなかなか難しいかもしれませんが、部下に成長してもらうためにも、今の業務をしながら
・何がわからないのかを、自分で明確にする。
・それを自分の言葉で整理してまとめていく。
という「わからないことをマニュアル化していく」作業に取り組んでもらうのはいかがでしょうか。
社会で働き方改革への意識が高まるなか、日々の業務に加えて業務マニュアルやチェックリストを作る時間を生み出すのは容易ではありませんが、ここで一度業務マニュアルを整理し、それを部署のノウハウとすれば、引継ぎのときにも大いに役立ちます。ぜひ、検討してみてください。
【関連記事:部下とコミュニケーションをとるなら1on1面談が欠かせない!】
【シート付】1on1ミーティングで使える50のテーマ例を使ってネタ切れ解消!
③何で覚えられないのか?の根本的な問題に向き合う
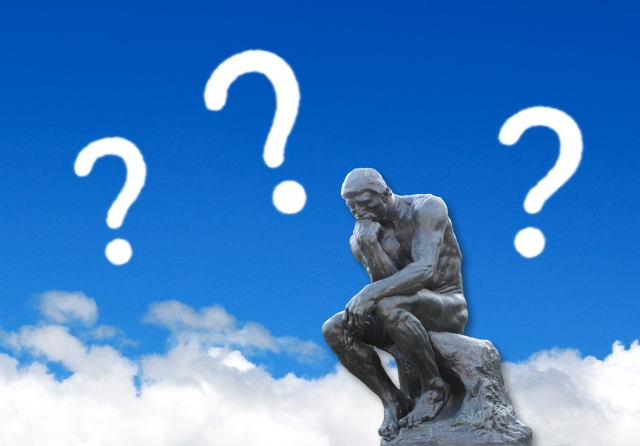
部下が同じことを何度も聞く場合、それは部下の問題だけではない可能性もゼロではありません。
例えば、教える側が「細かいけれど大事なこと」を「こんなの当たり前」だと思って、つい伝え忘れている。
その場で部下の理解を確認していないので、こちらは「教えた」と思っても部下は「よくわからない」という状態になっている。
上司や先輩社員がイライラしているのが部下に伝わり、部下はその緊張感から教えてもらったことを忘れてしまう。
あるいは「本当はこれも聞きたい」ということが聞けない。
など、コミュニケーションにおいて「教える側」でも何か改善できることがあるかもしれません。業務マニュアルを自分でつくってもなお、何度も聞いてくるような場合には、「なぜ覚えられないのか?」という根本的な問題に対して、その部下からきちんと話を聞く必要があります。
ただしもしヒアリングを行う場合には、当事者である直属の上司や先輩社員に対しては言いにくいこともあるため、話を聞くのは人事部など直接関係のない第三者が行ったほうが効果的です。
少し遠回りにのように見えますが、根本的なコミュニケーションの問題が改善できたら、部下も成長し、状況も大きく変えられるでしょう。
↓【関連資料】5つの質問に答えると、完全無料でDLいただけます。
※【部下との関係構築できてる度チェックシート】の資料はこちら!
※【50の質問付き!1on1個人面談記録シート】の資料はこちら!