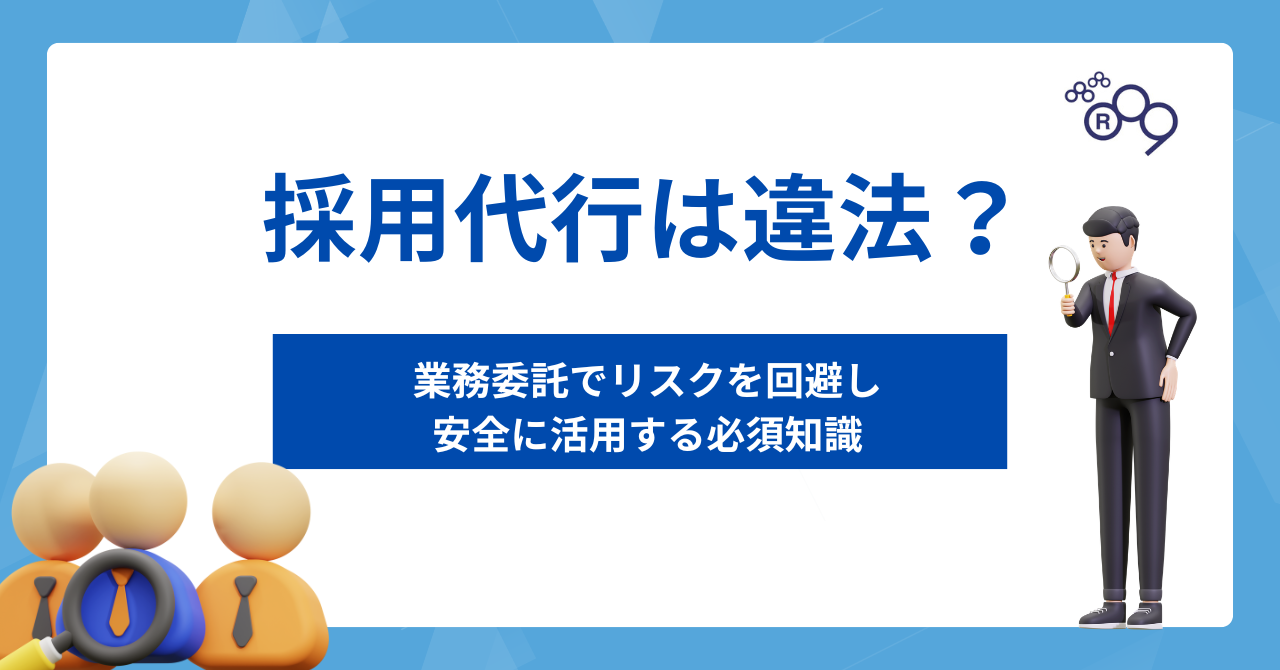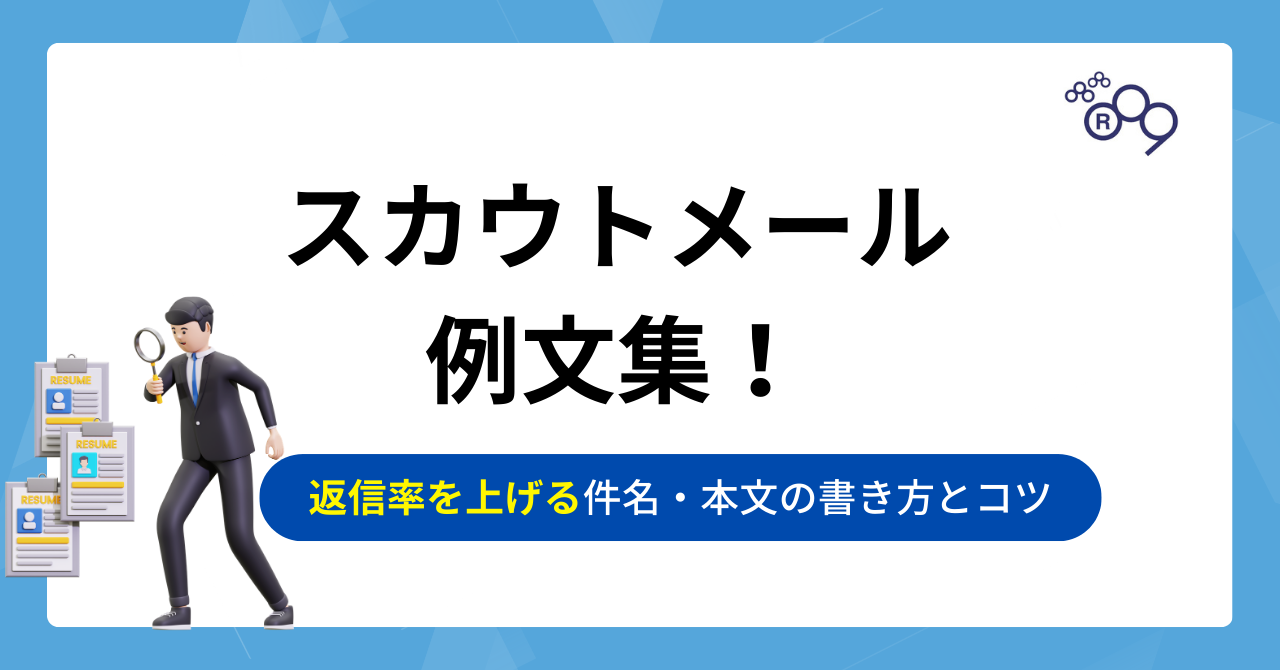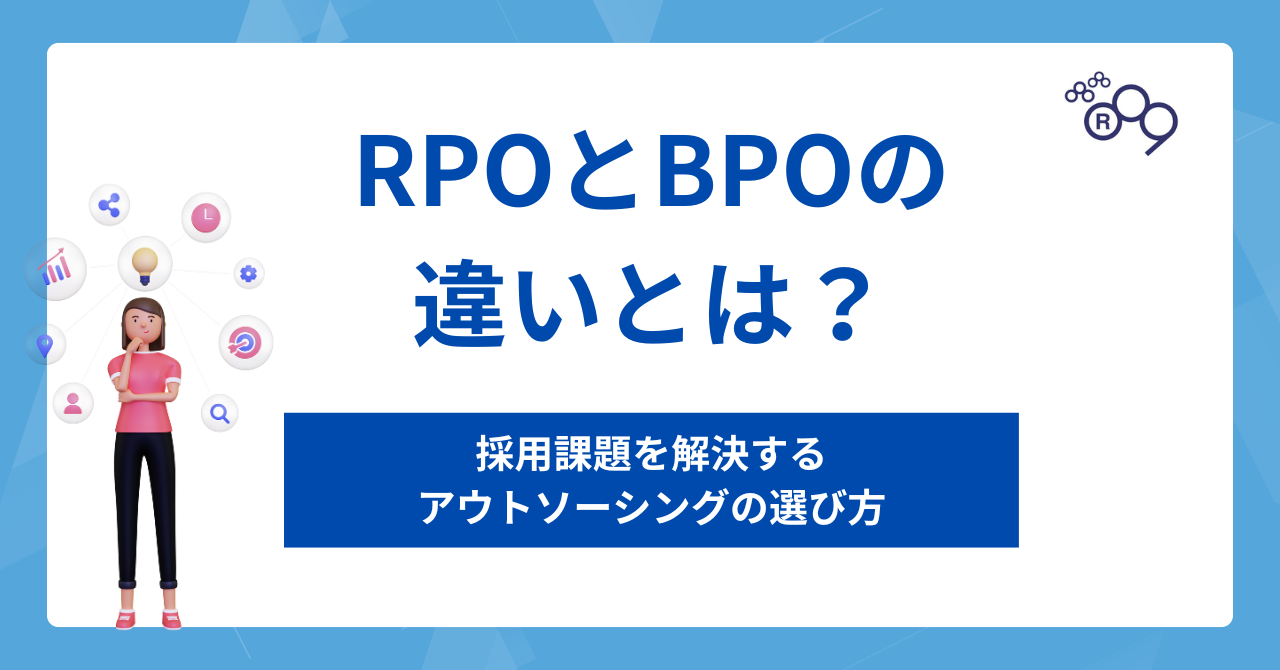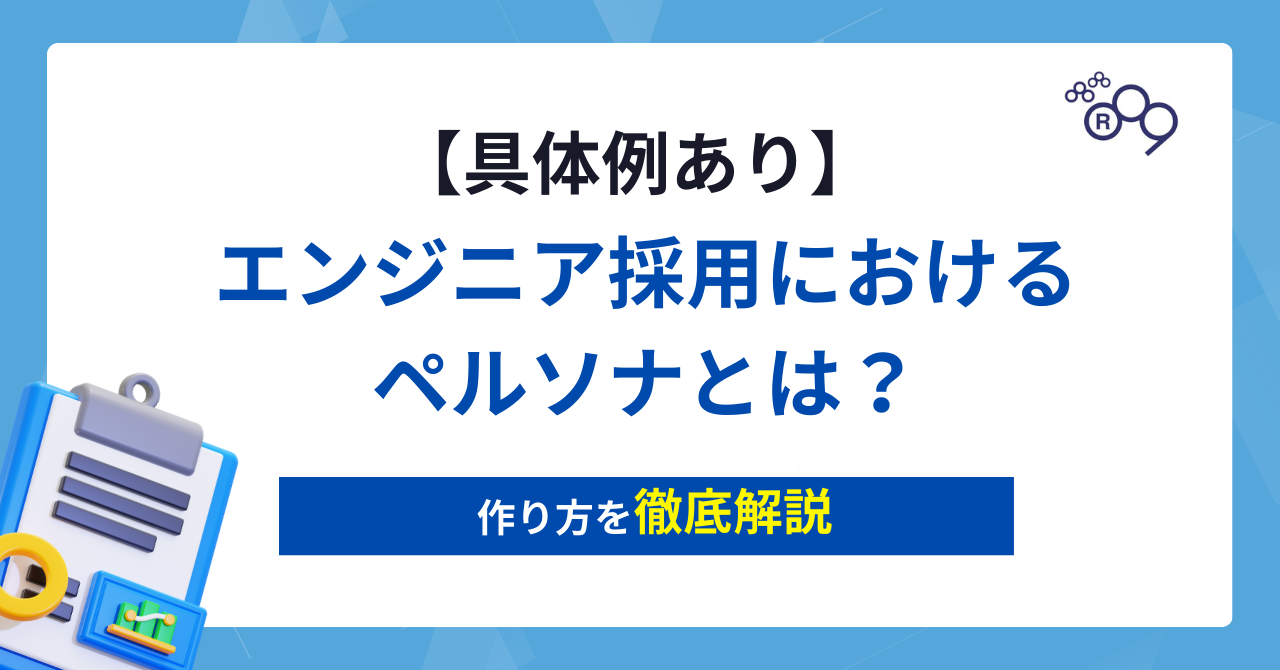採用プロセスを改善する9つの具体的方法とは【効果絶大】
公開日: 2022年06月21日 | 最終更新日: 2025年03月27日

「採用活動が思うように進まず、必要な人数を確保できていない」
「自社が欲しいと思う人材を獲得できない」
「せっかく採用コストをかけて人材を獲得しても、早期に離職してしまう」
このような採用活動に関する悩みは、人事担当者の多くの方が抱えているのではないでしょうか。
採用活動の悩みを解決するためには、もっと「母集団形成」に力を注ぐべきだという結論に至るケースが多くありますが、実は自社の採用プロセス部分に改善の余地が残されている場合が多々あります。
採用活動全体を各プロセスに分解して理解し、自社の課題となるプロセスに改善を加えることで再現性の高い採用成功に繋がります。
今回の記事では、採用プロセスの流れや、採用プロセスの課題を発見する方法、および改善する具体施策について解説いたします。
この記事から、現在、自社が抱える採用課題のボトルネックはどこにあるのかを理解し、しっかりとした対応策を講じていきましょう。
採用プロセスの流れ7ステップ
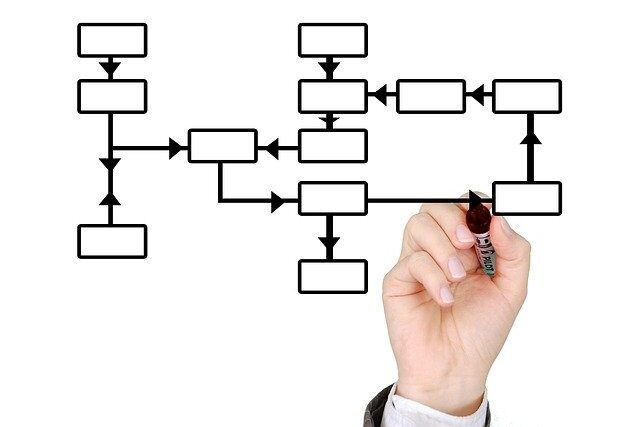
まずは、採用プロセスの流れについて解説していきます。
今まで、各プロセスの意識はせず、流れに任せて採用活動を進めていたという担当者の方もいるのではないでしょうか。
各プロセスの目的や、各プロセスで対応すべきことを分解して理解することで、各フェーズでのパフォーマンスを上げることができます。
「採用活動の改善」という漠然とした課題では何から手をつけたらいいのか悩みますが、各プロセスの課題まで分解することで具体施策も見えてきます。
1つ1つのプロセスをしっかりと理解していきましょう。
1. 採用計画の策定
採用プロセスで、最初に行うべきことが採用計画の策定です。
いつまでに、何人、どのような人材が必要となるのかなどを整理し、目標を達成するための採用手法の選定や、使えるリソースを含めて計画立てていきます。
採用計画は採用活動の指針となるものですので、計画に不備や不足があれば後々の採用活動に綻びが出てきます。
採用計画は時間をかけてでも、実現可能性が高い説得力のある計画を立てる必要があります。
採用計画は、以下のような流れでブレイクダウンしていくことを理解しておきましょう。
企業活動の目標
↓
経営戦略(企業活動の目標を達成するための戦略)
↓
採用目標(経営戦略を遂行するための採用目標)
↓
採用計画(採用目標を達成するための計画)
採用計画を立てる際は、採用目標を達成するための計画であることはもちろん、経営戦略や企業活動の目標を念頭に置いたうえで策定していくことが重要です。
2. 母集団形成
綿密な採用計画が固まったら、実際の行動へと移していきます。
最初に行動すべきは、多くの候補者を集めるための母集団形成です。
母集団形成のプロセスでは、各採用手法を用いて、多くの候補者に自社へ興味を持ってもらい、自社求人へ応募してもらうことが目的となります。
この後の選考では、人材の適性を判断するプロセスに入るため候補者は減っていきます。
そのため、初動の母集団形成の段階でより多くの人員を集めるとともに、自社が求める人材にアプローチして候補者の質を高めることが重要となります。
3. 書類選考
ここから先は「選考プロセス」に入ります。
ここでしっかりと人材を見極めることが、入社後に活躍する人材を増やし、社員の定着率を高めることに繋がります。
選考プロセスの第一段階である書類選考では、履歴書や職務経歴書といった応募書類をもとに適正判断をします。
採用計画を策定する段階で、自社の求める人物像である「採用ペルソナ」を明確に定義しておくと、ブレのない採用判断を円滑に進められます。
書類選考で得られる情報は限られるため、書類選考の段階で厳しくふるいをかけるのではなく、自社のリソースが許す限り、気になる人材がいた場合は次のステップへ進めて採用合否の判断を行うことが好ましいでしょう。
4. 採用面接
書類選考の後は、採用面接です。このプロセスで、しっかりと人材を見極める必要があります。
ここで見るべきポイントは、「活躍」と「定着」です。入社した後に能力や経験を活かして活躍できる人材であるか。
また、自社のビジョンや社風にマッチし定着する人材であるか。この2点を中心に適性を判断をしていきましょう。
面接では、担当者の質問力や判断力が問われます。必要に応じて、外部研修で面接の力を養うこともいいでしょう。
ここでの見極めが自社にとっても、候補者にとっても重要となるため、しっかりと準備をして臨むようにしましょう。
5. 採用判断
面接が終了したら採用可否を判断します。
ここで、気をつけなければいけないのは、曖昧な印象で採用可否を判断しないということです。
「面接でなんとなく印象が良かったから」という理由で採用してしまう担当者の方もいますが、そのような場合、入社後に後悔するケースが多々あります。
印象だけに左右されず、なぜ採用したいと思ったのかを明確にし、採用ペルソナに求める要素に適しているかを判断することが重要です。
6. 内定通知
採用が決定したら、候補者へ内定通知をします。
強く獲得したいと思う候補者には、オファー面談や条件交渉の機会を作ることもあります。
内定通知に関しては、時間を空けず可能な限り迅速に対応することがポイントです。
候補者は基本的に自社だけに応募しているケースは少なく、他社も一緒に応募していることを理解しておきましょう。
そのため、内定通知が遅れるにつれ、他社に獲得されてしまう可能性も高まります。また、時間が経過することで、自社への熱量が冷めてしまうことも考えられます。
そのため、獲得したい人材には迅速に内定通知を出し、候補者への想いを熱意を持って伝えていくことが必要です。
7. 内定者フォロー
候補者が内定を受諾した後も、フォローすることが大切です。
候補者は内定をもらっていても、入社までの期間が空くことで不安を感じてしまいます。
不安が大きくなれば、内定を貰った後でも辞退してしまう可能性が高まります。そのため、内定者と定期的に連絡をとり、不安を解消してあげることが必要です。
また、内定者フォローを行うことで自社とのエンゲージメントが高まり、入社後の意欲や定着率も変わってきます。
内定通知を出したからと気を緩めず、しっかりと内定者へフォローを行っていきましょう。
入社後のフォローも大切
ここまでが採用プロセスの流れですが、入社をした後もしっかりフォローすることが大切です。
採用活動のゴールは、「採用をすること」ではありません。「自社で活躍する人材を増やすこと」です。
採用した人材が入社後に活躍できているかをチェックし、入社後もしっかりフォローをしていくように心がけましょう。
採用プロセスの課題を発見する3つの方法

続いて、採用プロセスの課題を発見する方法について解説していきます。
採用活動のパフォーマンスを向上させるためには、まず、どこに課題があるのかを見つけなればなりません。
ここで課題発見力を養っていきましょう。
1. どの採用プロセスで歩留まりが悪いかを分析する
採用プロセスの課題を発見するためには、どの採用プロセスで歩留まりが悪いかを分析するのが一番です。
採用活動での歩留まりとは、各採用プロセスで進んだ人数の割合を指します。
各プロセスに分けて歩留まりを数値化し、どのプロセスで歩留まりが悪いか把握していくことが大切です。
例えば、そもそもの応募者が少ないということであれば「母集団形成」のプロセスで歩留まりの課題を抱えているということです。
このように歩留まりを分析し、優先的に改善を進めるプロセスを発見していきましょう。
2. 採用単価を確認する
採用単価を確認することでも、採用プロセスの課題を見つけられます。採用単価=採用にかけた費用÷採用人数です。
1人を採用するにあたっての費用がかかりすぎている場合は、採用手法や採用条件を見直さなければなりません。
また、採用単価は抑えられているものの、必要人員数を確保できていないという場合は、もう少し採用コストを増やしてでも、行動量を増やすという戦略を練ることもできます。
このように、採用単価を確認することで、採用プロセスの課題を把握できます。
3. 採用手法のパフォーマンスを確認する
採用プロセスの課題を発見するために、採用手法のパフォーマンスを確認するという方法もあります。
自社で用いている各採用手法の獲得人数、費用対効果などを含めたパフォーマンスを確認することで、どの採用手法に課題があるのかを把握できます。
各採用手法のパフォーマンスが把握できれば、改善をする、別の採用手法に切り替えるといった判断へ進めることができます。
採用プロセスを改善する9つの具体施策

続いて、採用プロセスを改善する具体施策について解説いたします。
採用プロセスの流れを理解し、課題の発見ができるようになれば、あとは1つ1つの課題を順番に解決していくだけです。
自社が今、課題としているものから、具体施策を実践していきましょう。
1. 採用ペルソナを明確にする
採用プロセスを改善する具体施策の1つは、採用ペルソナを明確にすることです。
採用ペルソナが曖昧な場合、選考基準がその都度変わったり、採用手法をいくら変えても満足なパフォーマンスを出せなかったりという結果に繋がります。
採用ペルソナは、採用計画を立てるプロセスで定義する採用活動の軸の1つです。
明確な軸がなければ、人材獲得までの道のりを真っ直ぐ進むことはできません。
採用計画を立てる際は、獲得したい人物像が具体的にイメージできるまでしっかりと定義していきましょう。
2. 採用目標や採用計画を関係者で共有する
選考プロセスで起こり得る問題が、評価のブレです。
面接官によって評価の尺度が違う、現場責任者と人事担当者で求める人物像が異なるという問題が起こることは少なくありません。
そのような問題を起こさないためには、関係者間でコミュニケーションを積極的にとり、採用目標や採用計画について同じ認識を持つことが必要です。
面接の評価尺度を関係者で話し合ったり、採用ペルソナのイメージを現場責任者と共有したりといった段取りをしておきましょう。
人事担当者だけで情報を完結させるのではなく、経営層、現場責任者なども含めて、採用活動に関する情報共有をすることが大切です。
3. 募集要項を見直す
人材が思うように集まらないという場合、募集要項で条件を求めすぎている可能性があります。
「できれば欲しい」「あったら良い」という条件が多く並んでしまっている場合、人材は集まりにくくなります。
絶対必要な条件である「MUST」と、できれば欲しい「WANT」を切り分けて考える必要があります。
世間的に有能であると評価される資格や能力も、自社では不要となることもあります。
一般論で考えるのではなく、自社にはどのような資格、能力、経験を持つ人材が必要なのかを整理していきましょう。
4. 採用手法を見直す
採用プロセスを改善する際、採用手法の見直しも必要です。
用いる採用手法によって、集まる候補者の人数、候補者の質は大きく変わります。
加えて、採用手法ごとに採用コストや、リーチできるターゲットも異なってきますので、どの採用手法を選ぶかは採用プロセスに大きな影響を与えます。
定期的に各採用手法のパフォーマンスを数値化し、必要に応じて変えていくようにしましょう。
5. 求人掲載内容を見直す
採用プロセスの改善施策として、求人掲載内容を見直すことも必要です。
前述した求人要項はもちろん、自社がアピールしたい情報がしっかり記載されているか、業務内容を具体的にイメージできる内容か、ペルソナに刺さる内容となっているかなどの観点で見直しをしましょう。
自社の目指すビジョン、社風、強みなどを記載して、自社のことを深く知ってもらうことで、自社とのマッチング率を深めることができます。
また、具体的な業務イメージが掴める内容になっていれば、入社後のミスマッチを減らすことにも繋がります。
反響を見ながら、求人掲載内容も改善を繰り返していくようにしましょう。
6. 自社のホームページを充実させる
自社のホームページを充実させることは、採用プロセスの改善にも繋がります。
候補者の多くは、応募時や選考プロセスに進んだ際、自社のホームページを確認します。
ホームページを通して、自社のビジョンや方向性を理解し、就業した後に自分が働く姿などをイメージします。
自社のホームページから情報を得ることで自社への興味が高まるため、応募率や内定受諾率にも良い影響を与えます。
採用プロセスを進めると同時に、自社のホームページも充実させていくようにしましょう。
7. 内定者フォローを見直す
採用プロセスの課題として意外と多いのが、内定辞退です。
候補者の多くは、自社の他にも複数の企業を受けています。
まずは内定を獲得して、その後に複数企業と比較して考えたいと思う候補者も多いです。
そのため、内定通知を出したからといって安心はできません。
内定通知を出した後は、候補者の不安を取り除くとともに、自社の魅力をより知ってもらうことに注力しましょう。
内定者フォローで築いた信頼関係は、入社後の定着率にも良い影響を与えます。
内定通知後も気を緩めず、しっかりとフォローしていくようにしましょう。
8. 採用管理システムを導入する
採用プロセスの改善には、採用管理システムの導入も効果的です。
複数の採用手法や、採用プロセスごとの情報を管理していくのは煩雑で、漏れや誤りが起こりやすいです。
また、データを入力することに手一杯となってしまい、本来の目的である分析ができないという本末転倒な状況に陥ることもあるでしょう。
そのような場合は、各採用手法のパフォーマンスや各プロセスの歩留まり、候補者の情報など、採用プロセスの全てを一元管理できる採用管理システムを導入することをおすすめします。
分析することを前提としてデータが整理されるため、採用プロセスの分析にも大きな力を発揮します。
9. 採用プロセスをアウトソーシングする
採用プロセスに課題を感じている場合、採用プロセスをアウトソーシングするのも効果的な方法です。
リソースが足りない、母集団形成で人員が集まらない、ノウハウがなく採用をどう進めれば良いかわからない。
そのような場合、採用課題を多く解決してきた実績のある採用コンサルティングに依頼をするのがいいでしょう。
採用活動において一番重要なのは、採用目標を達成することです。
目標達成のためにアウトソーシングをするというのも1つの有効な選択肢です。
まとめ
今回は、採用プロセスの流れや、採用プロセスの課題を発見する方法、および改善するための具体施策について解説いたしました。
採用プロセスを見直すことで、採用率だけではなく、入社後の定着率も改善されます。
採用プロセスの改善は、企業の業績にも大きなインパクトを与えます。
自社で対応すべきことと、アウトソーシングを活用できることを切り分け、採用目標を達成していきましょう。
1. 採用計画の策定
2. 母集団形成
3. 書類選考
4. 採用面接
5. 採用判断
6. 内定通知
7. 内定者フォロー
入社後のフォローも大切
◆採用プロセスの課題を発見する3つの方法
1. どの採用プロセスで歩留まりが悪いかを分析する
2. 採用単価を確認する
3. 採用手法のパフォーマンスを確認する
◆採用プロセスを改善する9つの具体施策
1.採用ペルソナを明確にする
2.採用目標や採用計画を関係者で共有する
3. 募集要項を見直す
4.採用手法を見直す
5. 求人掲載内容を見直す
6. 自社のホームページを充実させる
7. 内定者フォローを見直す
8. 採用管理システムを導入する
9. 採用プロセスをアウトソーシングする
この記事の監修者:
1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。