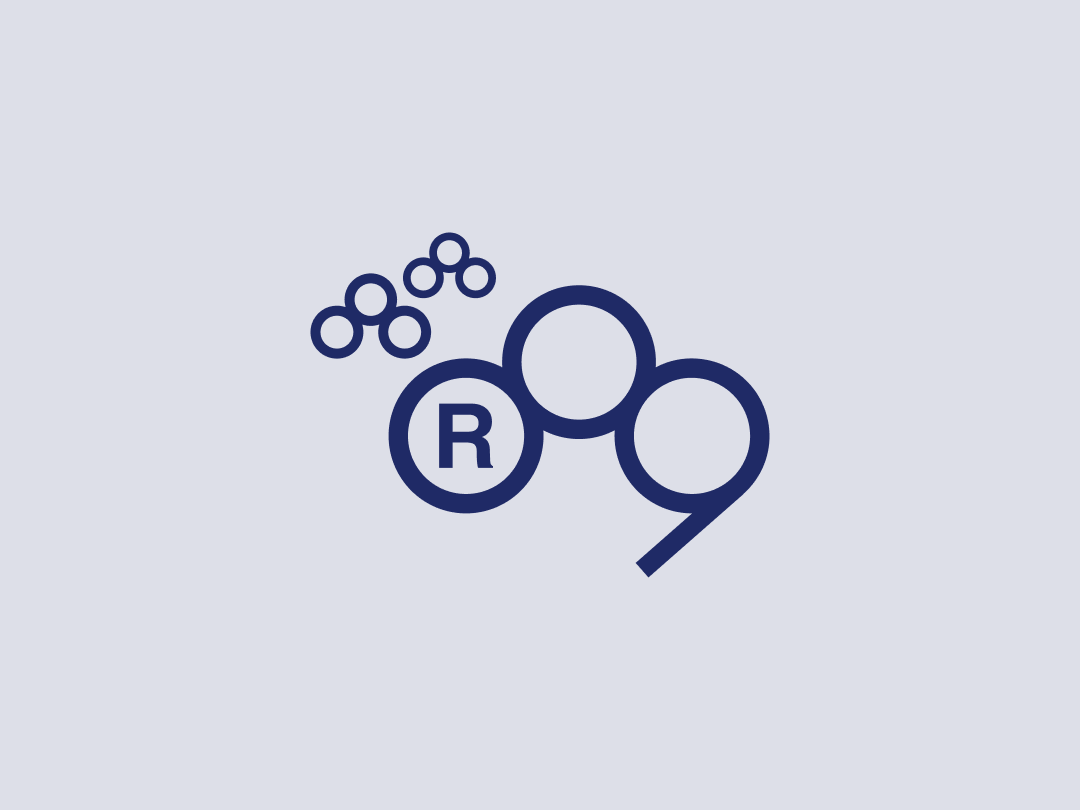【テンプレート付き】採用ペルソナの設計8ステップ|具体例・活用法まで徹底解説
公開日: 2024年12月02日 | 最終更新日: 2025年11月20日

「応募が集まらない」「早期離職が多い」「社内で“求める人物像”が定まらない」
そんな採用課題を解決する鍵が“採用ペルソナ”です。
採用ペルソナとは、自社が採用したい人物像を年齢・経験・価値観・行動特性まで具体化したもの。誰に・何を・どう伝えるかが明確になり、採用のミスマッチを防げます。
この記事では、すぐ使えるテンプレート付きで、下記について実践的に解説します。
- 採用ペルソナの意味とターゲットとの違い
- 作り方の基本と8つのステップ
- 活用時の注意点と改善のコツ
採用ペルソナとは?
「ペルソナ(persona)」とは、もともとマーケティングで使われる概念です。
ある商品やサービスを“誰に届けるか”を明確にするために、その典型的なユーザー像を具体的に描き出す──それがペルソナです。
たとえば
30代後半、共働きの母。週末は家族でショッピングモールへ。時短で使える便利グッズに価値を感じる。
このように、年齢・職業・価値観・ライフスタイルまで踏み込んで描くことで、伝えるべきメッセージやアプローチ方法が明確になります。
採用におけるペルソナ=「採りたい人を、ひとりの人物として描くこと」
このマーケティングの考え方を採用に応用したのが「採用ペルソナ」です。
単に「20代・営業経験あり」といった条件ではなく、
- どんな価値観を持っていて、
- どんな経験をしていて、
- どんな言葉に心が動くか
まで含めて具体化することで、求人票やスカウト文面、面接の設計に一貫性が生まれ、本当に欲しい人材に届く採用活動が可能になります。
採用ペルソナと採用ターゲットの違い
「ペルソナ」とよく似た言葉に「ターゲット」があります。
どちらも「どんな人を採用したいか」を考えるうえで重要ですが、大きく異なるのは“粒度(解像度)”です。
たとえば──
- ターゲットの例:
30代前半、年収400〜500万円、営業経験3年以上、都内勤務希望 - ペルソナの例:
32歳女性、都内在住、前職はITベンチャーで法人営業を4年担当。責任感が強く、チームで成果を上げる働き方にやりがいを感じる。休日は読書と料理。転職理由は、成果主義の職場で孤独を感じたため。安定と成長の両方が得られる環境を探している。
このように、ターゲットは“層”を捉えたもの、
ペルソナは“具体的な1人の人物”を描いたものです。
ペルソナを設定することで、「その人に響く言葉は?」「その人が惹かれる魅力とは?」といった視点が持てるようになり、求人票やスカウトの設計に“深み”と“納得感”が生まれます。
採用ペルソナを構成する3つの要素
採用ペルソナをつくる際は、「どんな人に来てほしいか」を感覚ではなく、具体的な情報で設計することがカギです。以下の3カテゴリに分けて整理することで、チーム内での認識共有や求人票への反映がスムーズになります。
- プロフィール情報(性別、年齢、居住地、家族構成など)
- 職務・スキル情報(職歴、経験年数、専門領域、業績など)
- 志向・パーソナリティ情報(価値観、行動傾向、働き方に対する考え方など)
1. プロフィール情報
求職者の生活背景や環境をイメージする項目です。
- 年齢・性別
- 居住地(例:都内から30分圏内、地方都市など)
- 学歴・家族構成
- 通勤手段・生活スタイル など
これは「この属性が良い/悪い」と線引きするためのものではなく、どんな生活環境にいる人が自社に興味を持ちやすいかを考えるための前提設定です。
例:子育て中の時短勤務経験者→フレックス制度や育児支援に関心をもつ可能性が高い
2. 職務・スキル情報
- 業種・職種経験(年数、企業規模など)
- 担当領域(プレイヤー/マネジメント)
- 保有スキル・資格
- 年収帯・役職 など
このパートは「MUST(必須)」「WANT(望ましい)」「NEGATIVE(不要)」で分類しておくと、選考やスカウトで活用しやすくなります。
例:MUST=法人営業経験3年以上、WANT=SaaS業界経験、NEGATIVE=個人営業のみの経験
3. 志向・パーソナリティ情報
入社後の“活躍”や“定着”に影響する、いわゆる人となりの部分です。
- 価値観(例:安定志向/挑戦志向、個人重視/チーム重視)
- 性格傾向(行動的、思慮深い、几帳面、柔軟 など)
- モチベーションの源泉(社会貢献性、成長実感、働きやすさなど)
- ライフスタイル(副業志向、育児中、転勤NGなど)
この領域を丁寧に描いておくと、求人票での言葉選びや、面接でのコミュニケーションもブレなくなります。
一人の“仮想人物像”が浮かび上がる
この3つの要素が揃ったとき、条件の羅列ではなく、「あ、こういう人に来てほしい」と具体的な顔が見えてくるようになります。
その状態まで作り込めれば、スカウト文、求人票、面接すべてに一貫性と説得力が生まれます。
採用ペルソナをつくる8つのステップ
採用ペルソナの設計は、実際の社内情報や市場データに基づいて設計することが重要です。以下では、実務で活用できる形に落とし込むためのステップを具体的に解説します。
1. 経営陣・現場へのヒアリングで「求める人物像の仮説」を立てる
- 配属予定の部署が期待している役割や成果をヒアリングする
- 経営目線で「どんな人材が今後必要になるか」もすり合わせる
- 「いま活躍している人」に共通する要素を洗い出す
Point:スペック情報だけでなく「性格」「価値観」「行動スタイル」といったパーソナリティ情報も重視するとズレが生じにくくなります。
2. 条件をカテゴリごとに書き出して整理する
- 前章で紹介した「プロフィール」「職務・スキル」「志向・パーソナリティ」のカテゴリで整理
- 付箋やワークシートなど、視覚的に並べながら全体像を把握
Point:記入時には「MUST(必須)」「WANT(あると望ましい)」「NEGATIVE(避けたい)」の区分も並行して検討しておくと、実務への落とし込みがスムーズです。
3. 「なぜ転職するのか」を想定し、転職理由の仮説を立てる
求職者が「転職しよう」と考える背景や動機を仮説立てしておきます。
- 給与やポジションへの不満
- 成長機会やキャリアの停滞
- 働き方や人間関係への不安
Point:ここを想定しておくことで、「うちの会社なら〇〇を提供できる」という訴求ポイントの設定に役立ちます。
4. 「なぜうちを選ぶのか」の応募動機を構築する
転職理由の仮説を踏まえ、自社に応募する理由を設計していきます。
- どんな環境や制度が魅力になり得るか?
- どんな言葉で自社を紹介すれば響くか?
Point:現場メンバーへの「入社理由ヒアリング」なども、リアルな言葉の抽出に有効です。
5. ペルソナ像を一人の人物として設計する
ここまでの情報をもとに、「〇〇さん(仮名)」というように、一人の人物像として組み立てます。
- 年齢・性別・家庭環境
- 経験・スキル・仕事観
- 転職理由・希望・人生観
Point:見た目・性格・行動スタイルまで想像できるくらい具体的にして資料にまとめましょう。
6. 社内関係者と認識をすり合わせる
ペルソナが完成したら、関係者と共有・確認を行いましょう。
- この人物像で合っているか
- 理想が高すぎないか
- 現場とギャップがないか
Point:修正の余地があれば、柔軟に調整し、共通認識を確立します。
7. 実際の採用施策に落とし込む
設計したペルソナをもとに、各種施策に反映させます。
- 求人票のトーンやメッセージ
- スカウト文の訴求ポイント
- 面接での質問設計
Point:全フェーズで一貫性のある体験を提供できるようにします。
8. 定期的に見直してブラッシュアップする
採用活動の結果やフィードバックをもとに、定期的なアップデートを行いましょう。
- 応募が少ない:要件が厳しすぎないか再検討
- ミスマッチが多い:パーソナリティの仮説にズレがないか再点検
- 経営戦略の変更:求める人物像が変わった場合の再設計
この8ステップを踏めば、単なる“条件の列挙”ではなく、実務に活かせる「戦略的なペルソナ設計」を行うことができます。
採用ペルソナを設計する3つのメリット
採用ペルソナをしっかり設計することで、採用活動は“なんとなくの勘”や“場当たり対応”から脱却し、構造的な改善が可能になります。具体的には、以下の3つのメリットが得られます。
- 求める人材に響くメッセージが届く
- 社内で「どんな人を採用したいか」がズレなくなる
- 入社後の活躍・定着につながる
それぞれのメリットについて、もう少し詳しく見ていきましょう。
1. 求める人材に響くメッセージが届く
誰に向けた求人なのかが明確になると、その人物が「自分ごと」として受け取れるメッセージを届けることができます。
たとえば、ただ「成長できる環境です」と伝えるよりも、
「チームで支え合いながら、早期にプロジェクトリーダーを任される環境」と伝えたほうが、ピンポイントで魅力が伝わります。
こうした言葉のチューニングこそ、ペルソナ設計の力です。
2. 社内で「どんな人を採用したいか」がズレなくなる
採用活動には、経営層、人事、現場といった多くの関係者が関わります。
このとき「求める人物像」が曖昧なままだと、選考基準のブレや評価のズレが生まれ、結果的に意思決定が遅れたり、ミスマッチが起きやすくなります。
ペルソナを設定しておけば、「この人のような人を採りたい」と共通の基準を持つことができ、選考の軸が整います。
3. 入社後の活躍・定着につながる
ペルソナ設計は、単なる“採用のための施策”ではありません。
その人物が「なぜ転職を考えているのか」「どんな環境で力を発揮できるか」まで想定することで、
選考中の訴求ポイントや、入社後の配属・育成方針にも活用できます。
結果として、「思っていた職場と違った…」という早期離職のリスクを減らすことができ、定着率や満足度の向上にもつながります。
ペルソナ活用ガイド
設計したペルソナは、作って終わりではなく“使いこなす”ことが大切です。
以下の観点で、実際の採用施策にどう落とし込むかをチェックしてみましょう。
求人票での活用
ペルソナの「志向性」に合った訴求ができているか?
例:成長志向の若手層なら「年間50件以上の新規PJに挑戦可」など挑戦機会を明記
汎用的な表現ではなく、具体的な言葉で魅力が伝わっているか?
例:「働きやすい環境」→「月平均残業10時間/PC自動シャットダウン」
求人票内の文章に“自分ごと”として読めるストーリーがあるか?
例:「2年前に入社した○○さん(同年代・同キャリア)のストーリー」掲載
スカウトメールでの活用
ペルソナの転職理由に合った切り口でアプローチしているか?
例:「前職では幅広い業務でやりがいが見えづらかった方へ」など、共感導入
ペルソナの価値観に響く言葉を選べているか?
例:「裁量をもって働きたい方へ」→「“あなたの提案で組織を変える”仕事です」
“なぜこの人に声をかけたか”が伝わる構成になっているか?
例:「〇〇のご経験を拝見し、当社の新規事業と強くマッチすると感じました」
面接設計・質問項目での活用
ペルソナに期待するスキルや価値観を確認する設問を入れているか?
例:「周囲を巻き込んだ経験は?」「変化にどう対応してきたか?」
活躍の再現性を見極める質問があるか?
例:「成果を出した場面で、どんな行動・判断をしたか?」
面接官全員が共通の“見極めポイント”を持っているか?
例:面接官マニュアルに「観察すべき行動特性」として記載
採用チャネル選定での活用
ペルソナが情報収集しているチャネルを使っているか?
例:「SNSで企業の雰囲気をチェックする層」→TwitterやYouTube活用
ペルソナが“出会いやすい”場を選べているか?
例:「キャリアチェンジ希望の20代」→Wantedlyのストーリー活用
採用活動のふりかえりに活用
想定したペルソナ通りの応募があったか?
例:応募者アンケートにて「転職理由/応募動機」が想定通りか検証
通過率や辞退に偏りがあれば、どこにズレがあったか言語化しているか?
例:「志向性は合っていたが、スキル要件が厳しすぎた」などのフィードバック記録
チーム内でペルソナに基づく振り返りができているか?
例:定例の採用ミーティングで「今年のペルソナ像」共有→翌年に反映
ペルソナ設計の注意点
ここからは、ペルソナ設計の際の注意点を解説します。
1. ペルソナを細かく設計しすぎない
ペルソナは「鮮明な人物像」を描くことが目的ですが、あまりに詳細すぎると実在する候補者が極端に限られてしまうリスクがあります。「選考の目安」になる情報だけを残し、こだわりすぎず柔軟に考えることが重要です。
- NG例:「週末はキャンプ派」「iPhoneユーザー」「都内在住」など、業務と直接関係のないこだわり
- OK例:業務遂行に関わる志向や働き方(例:裁量を持って仕事したい、フレックス勤務を希望)
2. 目的のない要素は盛り込まない
ペルソナの設計では、「なぜこの情報が必要か?」を常に意識しましょう。項目を埋めることが目的ではなく、“伝えたい相手”を具体化することが目的です。
- 趣味・SNS利用・休日の過ごし方などは、明確な意図がなければカットしてOK
- 逆に、「価値観を知るヒントになる」「面接で共通点になる」など理由があれば活かせます
3. MUST・WANT・NEGATIVEを切り分ける
どんなに理想的な人物像でも、現実の人材市場に存在しなければ意味がありません。分類しておくと、実際の選考でブレずに判断しやすくなります。
- MUST:業務に不可欠な条件(例:実務経験3年以上)
- WANT:あると望ましい条件(例:マネジメント経験があれば歓迎)
- NEGATIVE:自社ではフィットしにくい条件(例:転勤前提のポジションに転勤NGの方)
4. 定期的にブラッシュアップする
ペルソナは“一度作って終わり”ではなく、採用活動の中でアップデートしていく前提で設計しましょう。四半期ごと、あるいは採用のたびにペルソナをレビューすると、採用精度が高まります。
- 採用結果にズレがある場合、どこに原因があったのかを振り返る
- 経営戦略や組織の変化にあわせて、求める人物像も見直す
まとめ:採用活動を“構造化”するペルソナ設計の力
採用ペルソナは、「誰に向けた採用なのか?」を明確にするための設計図です。
年齢や経験といったスペックだけでなく、価値観や働き方、モチベーションまで含めて一人の人物像を描くことで、求人票やスカウト文、面接設計に一貫性と納得感が生まれます。
本記事では、採用ペルソナの基本から実践まで、以下の内容を解説しました。
- ペルソナとターゲットの違いと、それぞれの役割
- ペルソナ設計によって得られる3つの効果(訴求力/社内の共通認識/定着率向上)
- ペルソナを形作る3つの構成要素(プロフィール/職務・スキル/志向・パーソナリティ)
- 実践に役立つ8ステップの設計フローとテンプレートの使い方
- 設計・運用時に注意したい4つの落とし穴
採用難の今、「この人に来てほしい」という想いを言語化し、戦略に落とし込める企業が選ばれていきます。
ペルソナ設計は、少し手間がかかる分、採用活動全体の“迷い”を減らしてくれます。
まずは1人、自社にフィットする人物像を描くことから始めてみませんか?
この記事の監修者:
1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。