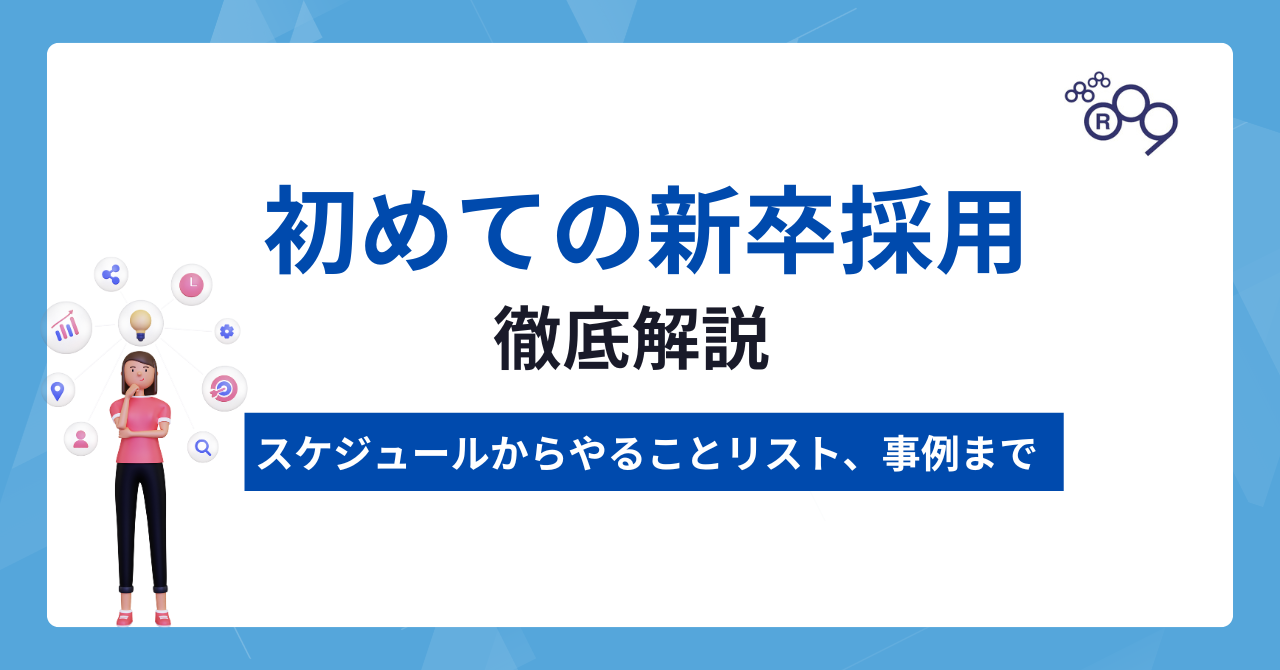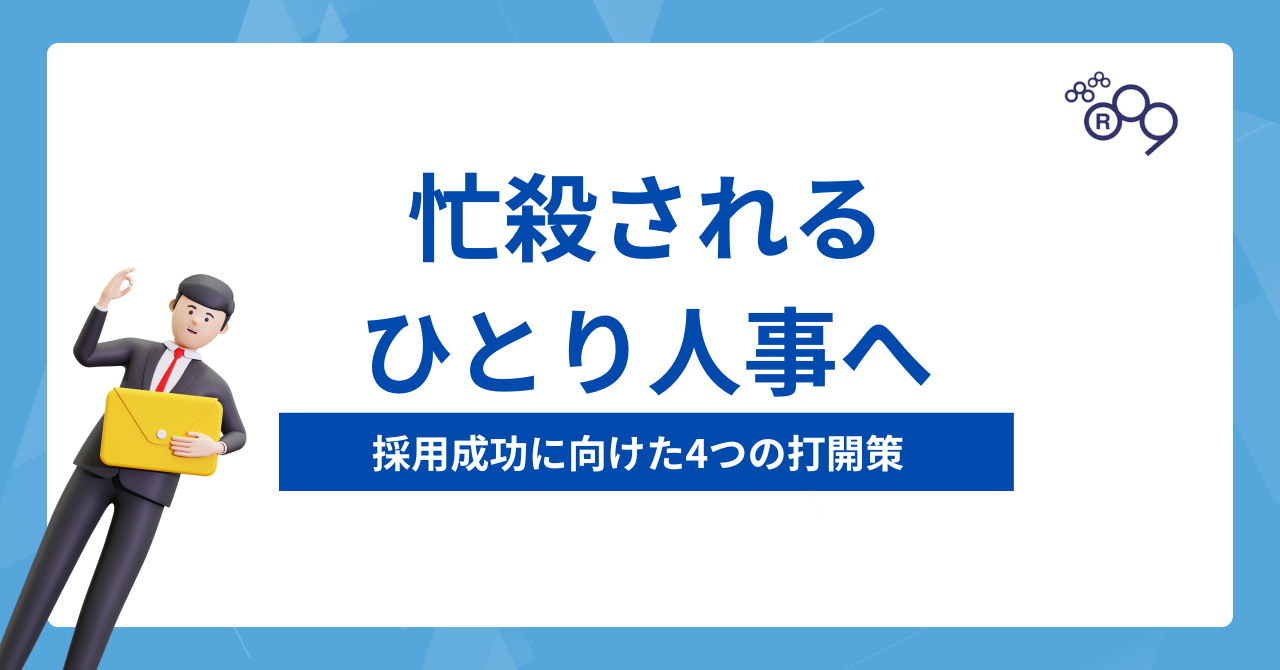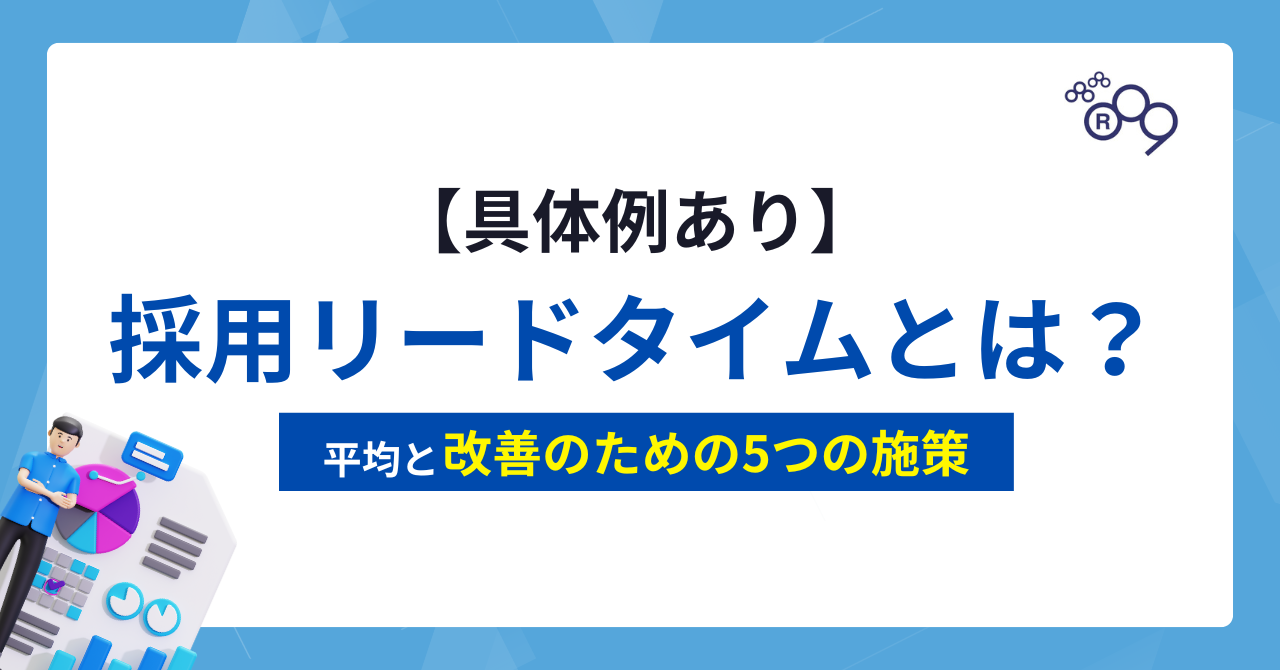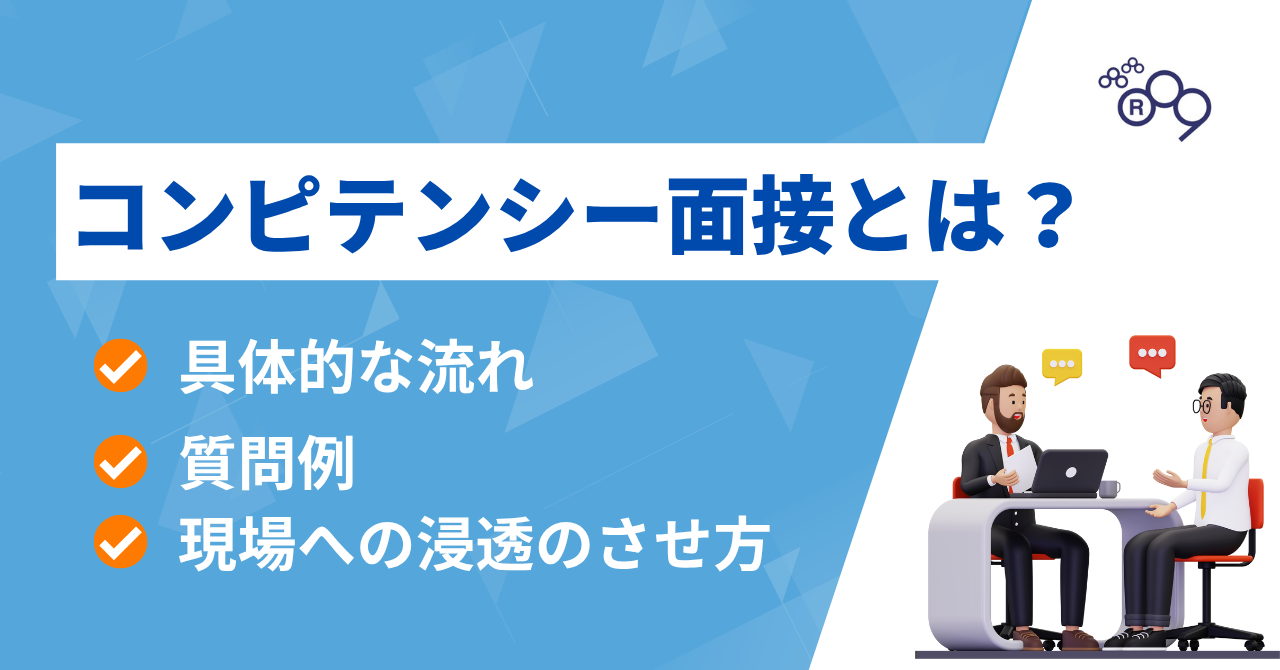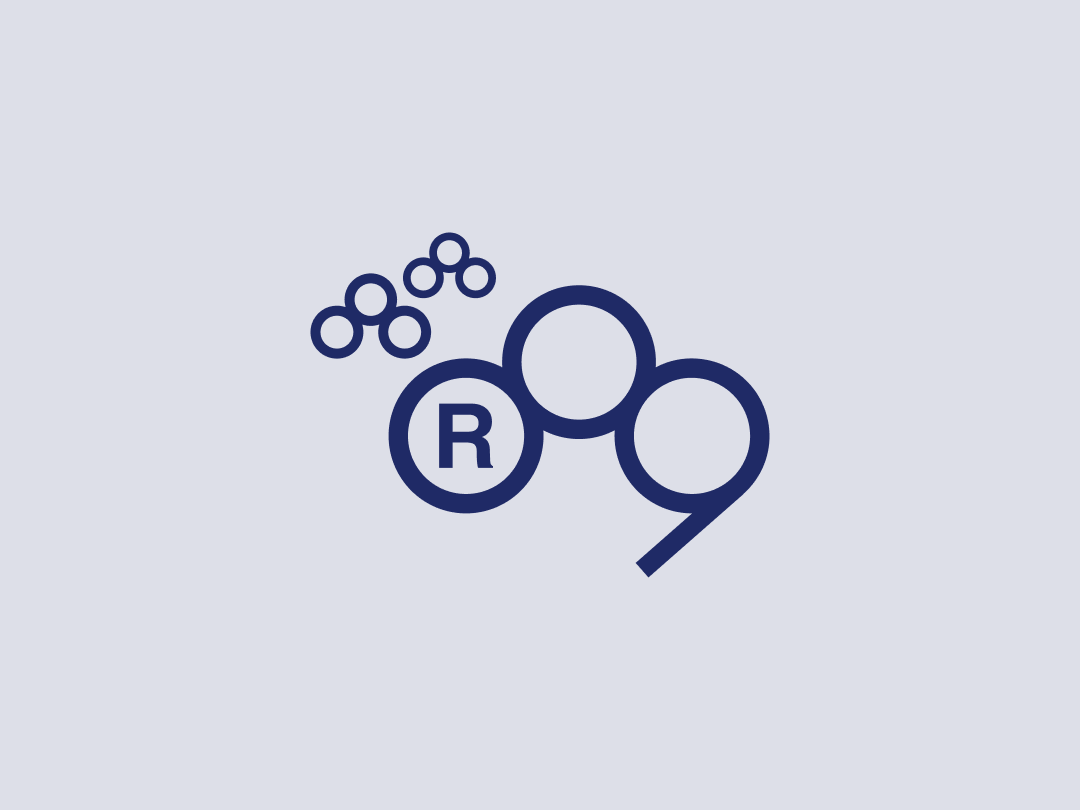ベンチャー企業の採用が難しい理由と今すぐ試せる解決策5選
公開日: 2025年04月30日 | 最終更新日: 2025年11月11日
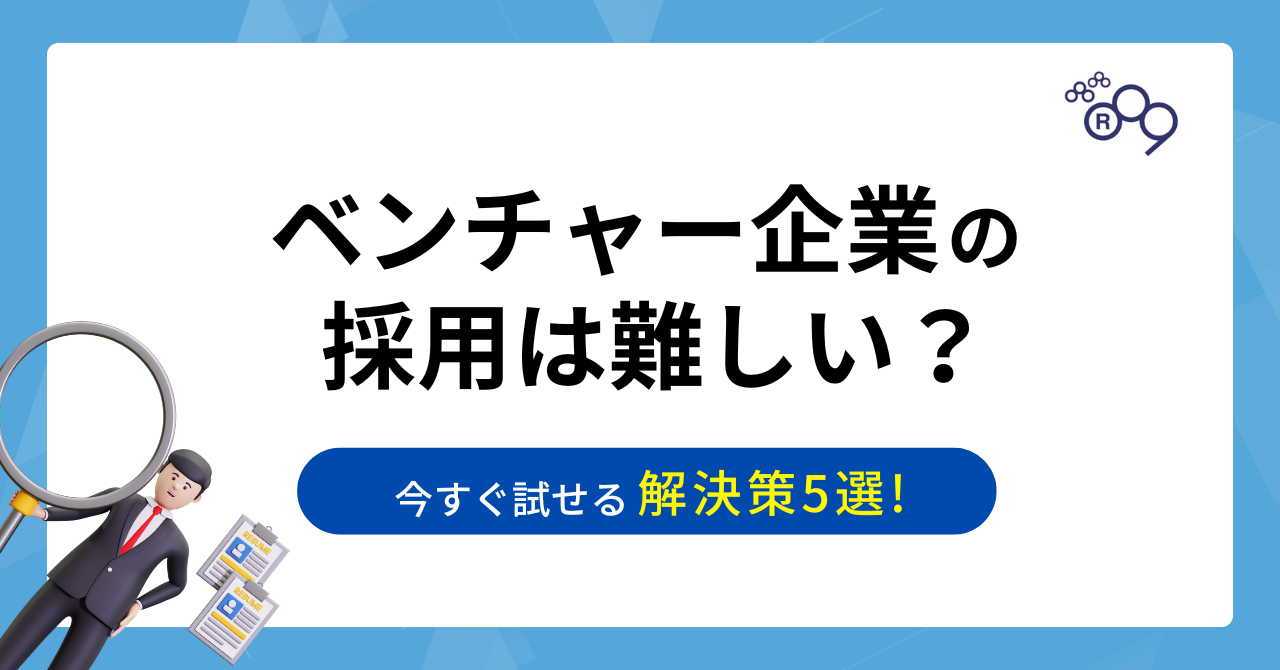
限られたリソース・知名度・実績の中で、いかに優秀な人材を確保するかは、ベンチャー企業の採用担当者や経営者の多くが頭を悩ませる経営課題の一つです。
一方で、採用がうまくいっている企業も存在します。その違いはどこにあるのでしょうか?そして、ベンチャー企業が採用競争を勝ち抜くには、どのような戦略と工夫が必要なのでしょうか?
この記事では、ベンチャー企業の採用が難しいとされる4つの根本的な理由を明らかにし、大手企業との違いを踏まえた上で、実践的な5つの採用改善策をご紹介します。さらに、限られた人員でも採用活動を強化できる手段として注目が高まっている「採用代行(RPO)サービス」の活用方法についても、具体的な事例を交えながら解説します。
ベンチャー企業の採用が難しい4つの理由
ベンチャー企業で人材採用に苦戦する背景には主に次の4つの理由があります。
1. リソース(人材・時間・予算)の制約がある
ベンチャー企業は大企業に比べて採用に割けるリソースが限られています。
専任の人事担当者がおらず経営者や現場社員が採用業務を兼任していることも多く、日々の業務に追われて十分な時間を採用活動に充てられません。その結果、採用ノウハウが社内に蓄積されにくく、「何をどのように進めればよいかわからない」と悩むケースも少なくありません。
また、潤沢な採用予算を確保できないため利用できる求人媒体や採用手法が限られ、母集団形成(候補者集め)が難航しがちです。
こうしのリソース不足により、候補者へのフォローが手薄になってミスマッチや辞退を招くなど、採用成功のハードルが上がってしまいます。
2. まだ企業の知名度・ブランド力が高くない
認知拡大の途上であることも、ベンチャー企業の採用にとって乗り越えるべきテーマです。
広く知られていない企業だと求人情報を出しても他社の求人に埋もれて応募者に気付いてもらいにくく、そもそもの応募母集団が十分に集まりません。
特に大企業や有名企業と比較すると、候補者にとって将来性や安定性を見極める材料が限られることもあり、関心を持ってもらっても最終的な決断に至らないケースも見られます。
だからこそ、自社のビジョンや実績、カルチャーを具体的に発信し、「この環境だからこそ得られる成長や経験」を伝えることが重要です。知名度の高低にかかわらず自社の魅力を的確に発信できれば応募数・応募質の向上につながる可能性があります(後述する施策参照)。
3. 採用ノウハウ不足で採用計画や採用ターゲットが不明確
ベンチャー企業では採用計画やターゲット人材の明確化が不十分なまま手探りで進めてしまうケースがあります。
たとえば「どんなスキル・マインドを持つ人材が自社に必要か」が具体化されていないと、求人票の内容も抽象的なものになりがちです。結果として、応募があっても自社にマッチする人材か見極めにくく、採用ミスマッチが発生するリスクが高まります。
また、採用ノウハウが社内に蓄積されていないため効果的な採用戦略を描けず、試行錯誤を繰り返す状況に陥りやすいでしょう。
このように戦略不足やターゲット不明確だと、限られたリソースをどこに投下すべきか判断できず、貴重な時間と費用を浪費してしまう恐れがあります。
4. 採用体制が未整備のため採用プロセスに時間がかかりすぎている
採用体制が整備されていないことで、採用プロセスが必要以上に長期化しがちなのもベンチャー採用の難しさです。
応募が来ても日常業務の合間に対応するため選考スケジュールが後手に回り、他社より内定出しが遅れて、優秀な人材を確保する機会を逃してしまう可能性があります。特に大企業に比べて採用体制が整っていないと、選考スピードで劣ることが課題になります。
さらに、ベンチャー企業では一人ひとり慎重に選びたいあまり面接回数が増える傾向もあり、結果として内定までに時間がかかりすぎて候補者の温度感が下がってしまう場合もあります。
昨今は優秀な人材ほど複数企業からオファーを得ており、採用市場全体が売り手市場(人材不足)です。しかし指摘されているように、採用を後回しにしていてはタイムリーに優秀層を確保できません。
ベンチャー企業が大企業と人材獲得競争で戦うには、スピード感を持ってプロセスを進める工夫が欠かせないのです。
大手企業の採用との違い
上記のような課題は大手企業との違いを意識すると一層明確になります。ベンチャー企業と大企業では、採用活動の前提条件が大きく異なるためです。主な違いは以下の3つです。
1. 企業ブランド・知名度の差
まず大きいのが企業の知名度やブランド力の差です。
大手企業はそれ自体が求人広告のようなもので、会社名を出すだけで多くの応募者を惹きつけます。新卒採用であれば学生の人気企業ランキングに入るような社名が保証となり、応募ハードルが低いでしょう。
一方企業名や事業内容がまだ広く知られていないケースも多く、まず「その会社を知ってもらう」ことから始めなければなりません。そのため、認知や信頼の醸成に時間を要し、応募の母集団形成に工夫が求められる場面も出てきます。
このように採用広報・ブランディング力において、大企業とベンチャーではスタート地点が大きく異なるのです。
2. 採用体制・プロセスの違い
採用に投入できる人員や予算の規模も大きく異なります。大手企業では人事部門が充実しており、採用専門チームが年間計画に沿って動いています。新卒・中途それぞれ専任担当がいて、大学とのパイプづくりや大量の応募者対応、内定者フォローまで仕組み化されたプロセスが確立されている場合が多いです。
一方、ベンチャー企業では、前述のように人事担当が兼務であったり非常に少人数であるため、計画的・継続的な採用体制の構築には一定のハードルがあります。
例えば大手企業なら複数の求人媒体に同時掲載し大量のスカウト送信を行える一方で、ベンチャー企業はコストやリソースの観点から媒体選定やアプローチにも優先順位をつけながら取り組む必要があります。
また、選考プロセスも、大手企業は毎年蓄積されるデータやノウハウを元に効率化・標準化されていますが、ベンチャー企業は各現場の裁量にゆだねられており、選考プロセスが一定化しづらい場合があります。このように採用に投下できるリソース(人・金・ノウハウ)の差によって、採用結果に差が出やすい傾向があります。
3. 提供できる待遇・環境の違い
候補者が企業に求めるものにも、大手企業とベンチャー企業では違いがあります。
大手企業は一般的に高水準の給与や充実した福利厚生、安定した雇用が提供でき、これらは多くの求職者にとって魅力的です。研修制度や明確な昇進ステップも整備されており、「将来のキャリアの見通しが立てやすい」という安心感があります。
一方ベンチャー企業は即戦力を求める傾向が強く、給与水準や待遇面で大企業に見劣りするケースが少なくありません。その代わりに、ベンチャーならではの成長機会や裁量権の大きさ、事業への貢献実感といった魅力を打ち出しています。
すなわち「安定と福利厚生の大手」vs「成長機会と自己実現のベンチャー」という構図になることがありますが、どちらが優れているかではなく、“どちらに魅力を感じるか”は人それぞれです。
ベンチャー企業は自社が提供できる価値(ビジョンややりがい等)を明確にし、それを共感してくれる層に響く採用活動を展開する必要があります。
優秀な人材を採用するための5つの実践的施策
ベンチャー企業が採用で直面する課題を乗り越え、優秀な人材と出会うためには、戦略的かつ実践的な施策の実行が求められます。
ここでは実践的な5つのポイントを紹介します。自社の状況に合わせて取り入れることで、採用成功の可能性を高められるはずです。
1. 自社のミッションやビジョンを強く発信し、魅力的な採用ブランディングを確立する
まず取り組みたいのは、自社の魅力の言語化と発信です。
ベンチャー企業の武器は、大企業にはないビジョンの新しさや成長フェーズならではのやりがい、組織のフラットさなど様々あります。これらを社内で改めて洗い出し、「なぜ我が社で働く価値があるのか」を明確なメッセージにして伝えましょう。
さらに、大企業と比べて報酬や福利厚生で劣る分、働き方や制度面での“柔軟性”を打ち出すことも、採用ブランディングの一環として効果的です。
例えば、
- ストックオプションや業績連動インセンティブの導入
- フルリモート・フレックス制度など、時間や場所に縛られない働き方
- 副業や育児との両立支援
- スピード昇進や職種横断など、自由度の高いキャリア設計
これらは、自律的にキャリアを考える優秀層から高く共感されます。「この会社は、自分らしい働き方や成長を尊重してくれる」という印象を与えられれば、知名度の課題を超えて興味を持ってもらえるきっかけになります。
このように、ビジョンと柔軟性の両軸で自社の魅力を打ち出すことで、質の高い母集団形成や共感による応募者獲得が可能になります。採用は“選ばれるための活動”でもあります。だからこそ、求職者に「この会社で働きたい」と感じてもらえるようなブランディングを継続的に行いましょう。
2. 採用ターゲット(求める人物像)を明確にして、候補者に合わせた効果的なアプローチを行う
「誰でもいいから応募を増やしたい」そう考えてしまうのが、採用に苦戦しているときに陥りがちな罠です。それを避けて採用を成功させる鍵は「誰を採るべきかを先に決めること」にあります。
まずは、現場の社員や経営陣とすり合わせて、
- 自社カルチャーとの相性
- 成長可能性を感じる資質
- 最低限必要なスキルや経験
といった人物要件(ペルソナ)を具体的に定めましょう。
求める人物像の定義を明確にすると、求人内容やスカウト文面が改善され、面談化率や内定承諾率が向上しやすくなります。採用活動の初期フェーズでこの設計を怠ると、無駄な母集団形成や面接のミスマッチを引き起こします。
さらに、ペルソナに基づいて候補者がよく使う媒体や、響く言葉・訴求ポイントを設計し、求人票やスカウトに反映させることで、必要な人に、しっかり届く採用活動が実現できます。
3. 多様な採用チャネルを活用して母集団を拡大する
限られた媒体に頼った“待ちの採用”だけでは、優秀な人材と出会うチャンスは限られます。そこで重要になるのが、採用チャネルの多様化と最適化です。
具体的には、以下のようなチャネルの組み合わせ活用が効果的です。
- ダイレクトリクルーティング:求人サイトで応募を待つだけでなく、スカウトメールなどを通じて、企業側から直接候補者にアプローチします。優秀な人材は“まだ転職活動をしていない”潜在層にいるケースも多く、攻めの採用に欠かせません。
- 専門エージェントの活用:業界や職種に特化したエージェントと連携することで、自社にフィットした質の高い候補者と出会いやすくなります。特に専門職や経験者採用では有効です。
- 社員紹介(リファラル採用):現場の社員が知人や前職のつながりから紹介することで、企業文化とのマッチ度が高く、定着率にも優れる傾向があります。紹介者からの信頼も後押しになるため、面接前から候補者の不安を和らげられます。
- SNS・オウンドメディアの活用:日常的な社内の雰囲気や価値観を発信することで、企業のファンを増やし、母集団形成と採用ブランディングを両立できます。
これらのチャネルは、単体で完璧な成果を出すものではありません。だからこそ、自社のフェーズや採用ターゲットに応じて柔軟に組み合わせ、運用しながら改善していくことが大切です。
こうした戦略的なチャネル活用は、限られた人員・予算で最大限の成果を出すことが求められるベンチャー企業にとって、非常に心強い武器となります。母集団の数を増やすだけでなく、質の高い候補者との出会いを増やすために、採用チャネルの選定と運用に注力していきましょう。
4. 選考プロセスを最適化し、候補者体験を向上させる
優秀な人材に選ばれるためには、採用プロセスそのものの見直し、スピードと候補者体験(採用CX)を両立させることが不可欠です。
前述のとおり採用はスピード勝負の側面があるため、内定まで時間がかかるフローは致命的です。選考スピードこそベンチャー企業最大の競争力であるため、応募から面接日程調整、内定出しまでできる限り迅速に進められるよう、社内調整の手間を減らしましょう。
具体的には、
- 書類選考を即日で返す体制
- 面接回数の削減(1回+カジュアル面談)
- 面接官の予定を事前ブロック
- 内定通知後、24時間以内のフォロー
などが効果的です。
加えて、エントリーから内定まで候補者がポジティブな印象を持てるよう候補者体験(CX, Candidate Experience)の向上にも努めましょう。
具体的には、
- 応募後の受付連絡や面接後のフィードバックを迅速かつ丁寧に行う
- 面接では一方的に質問するだけでなく会社の魅力もしっかり伝える
- 希望があれば現場社員と気軽に話せる機会を設ける
等です。
たとえ知名度で劣っていても、「対応が誠実で好印象だった」「ここで働くイメージが持てた」と感じてもらえれば入社承諾率は格段に上がります。逆に「連絡が遅い」「雑な対応をされた」という印象を与えてしまうと他社に流れてしまいます。
限られたリソースでも工夫次第で採用プロセスの質は高められるので、定期的に見直して改善しましょう。
5. ポテンシャル人材の積極採用と育成
即戦力にこだわるだけでなく、将来の戦力となるポテンシャル人材の採用も、ベンチャー企業にとって有効な手段です。
現時点で経験やスキルが不足していても、高い意欲や柔軟な適応力を持つ人材は、研修やOJTを通じて大きく成長する可能性があります。特にエンジニアや専門職など、競争が激しい領域では、経験者の奪い合いよりも、未経験でも素質ある人材を見極めて育てる方が定着しやすく、長期的なリターンにつながるケースが多く見られます。
ポテンシャル人材の採用で重要なのは、表面的な経歴や話し方にとらわれず、内面の資質=本質的な優秀さを見抜くことです。学歴や前職のブランドに引っ張られず、行動特性や思考の深さ、成長意欲を丁寧に掘り下げていく面接(=「STAR面接」)を導入するなど、ポテンシャル評価を取り入れた面接設計が有効です。
また、採用後の活躍を支えるためには、育成を前提とした受け入れ体制の整備も不可欠です。
例えば、
- メンター制度の導入
- 段階的にスキルを習得できるカリキュラムの用意
など、ポテンシャル人材が安心して力を発揮できる環境を整えましょう。
ベンチャー企業にとって、ポテンシャル人材は“磨けば光る原石”です。
見極めて迎え入れ、丁寧に育成することができれば、将来の中核を担う貴重な存在となります。
採用代行(RPO)を活用した採用課題解決のアプローチ
上記の施策を実行しようにも、「自社だけでは手が回らない」「ノウハウがなくて上手く進められない」という企業も多いでしょう。
そこで検討したいのが採用代行(RPO: Recruitment Process Outsourcing)サービスの活用です。採用代行とは、企業の採用業務を専門会社に外部委託(アウトソーシング)するサービスで、採用課題を解決するためのプロフェッショナルな支援を受けられます。ベンチャー・中小企業の 「採用が難しい」問題に対して実績のあるRPO会社に依頼することで、次のようなアプローチで課題解決が可能です。
関連記事:採用代行(RPO)とは?委託できる業務やメリット、注意点など徹底解説
1. 専門チームによるマンパワー不足の解消
採用代行を利用すると、採用のプロフェッショナルチームが自社の一員としてプロジェクトに参画し、採用業務全体を担ってくれます。内部の人手不足を即座に補えるため、求人票作成から応募者対応まで各工程に十分なリソースを割くことができます。
例えば求人媒体への掲載やスカウトメール送信といった手間のかかる母集団形成業務も、RPO側で代行してもらえます。実際、専任担当者不在で採用が滞っていた10名規模の企業が、採用代行サービスの求人媒体運用代行+スカウト代行を利用したところ、短期間で理想の人材に出会えたという事例があります
関連記事:専任の担当者なしで目標達成!採用代行で工数不足を解消し、自社にマッチした人材を確保
このように、RPOの活用によって「やりたくても人手が足りずできなかった」施策を次々と実行に移せるようになるため、結果として採用成功率の向上が期待できます。
2. 採用プロセス全体の効率化とスピードアップ
採用代行を導入すると、日程調整や応募者連絡といった業務負荷の高い工程をアウトソースでき、社内担当者は面接や意思決定といったコア業務に専念できます。
RPOチームは多数の案件を通じた運用経験からプロセス管理に長けており、候補者への連絡の遅れや、対応漏れを防ぎ、常に適切なタイミングで選考が進むよう調整してくれます。
例えば、前述の従業員10名規模の会社においては、採用代行サービス導入後わずか2カ月で内定3名という採用目標を達成できました。短期間で成果を出せた要因として、的確な求人媒体の選定や迅速なスカウトアプローチなどデータに基づく戦略推進が挙げられています。
関連記事:専任の担当者なしで目標達成!採用代行で工数不足を解消し、自社にマッチした人材を確保
3. ノウハウ提供と客観的視点で採用の質を向上
RPO企業には数多くの採用支援を行ってきた豊富なノウハウがあります。
自社に採用の知見がない場合でも、RPO側が市場動向や効果的な手法を踏まえて最適な戦略を提案してくれます。
例えば「募集要件の練り直し」や「求人票の表現改善」といったポイントでアドバイスをもらうことが可能です。実際、従業員100名規模の会社において、1人で採用業務を担う限界を感じRPOを導入したところ、最適な媒体やエージェントを調査・選定してもらい、採用の質を高められたという事例もあります
関連記事:「ともに採用を作るパートナー」ひとり人事、新卒・中途エンジニア採用に成功
社内だけでは気づけなかった改善点も、外部の客観的視点が入ることで明らかになり、選考基準の統一や面接手法の見直しなど質的向上につながります。
さらにRPOチームが進捗データを細かく分析し、歩留まり(各選考段階の通過率)をチェックして改善提案を行ってくれるため、PDCAサイクルを回しながら採用精度を高めていくことが可能です。
このようにRPOを活用すれば、自社だけでは実現できなかったスピードと効率で採用活動を進めることが可能になります。優秀な人材を競合他社より先に確保するためにも、専門家の力を借りてプロセス全体を最適化する価値は大いにあるでしょう。
まとめ
ベンチャー企業の採用が難しい理由と、その解決策について解説してきました。リソース不足や知名度が高くないといった課題はありますが、工夫と施策次第で優秀な人材を採用する道は開けます。実際に、ここで紹介したような施策を講じたり、必要に応じて採用代行サービスを活用して採用課題を解決することで、採用成功を収めているベンチャー企業も数多く存在します。
人材採用はベンチャー企業の成長において避けて通れない壁ですが、本稿で挙げたポイントを実践することで、その壁を乗り越える一助となれば幸いです。
優秀な人材との出会いを諦めず、適切な戦略によって採用難を乗り越えていきましょう。
この記事の監修者:
1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。