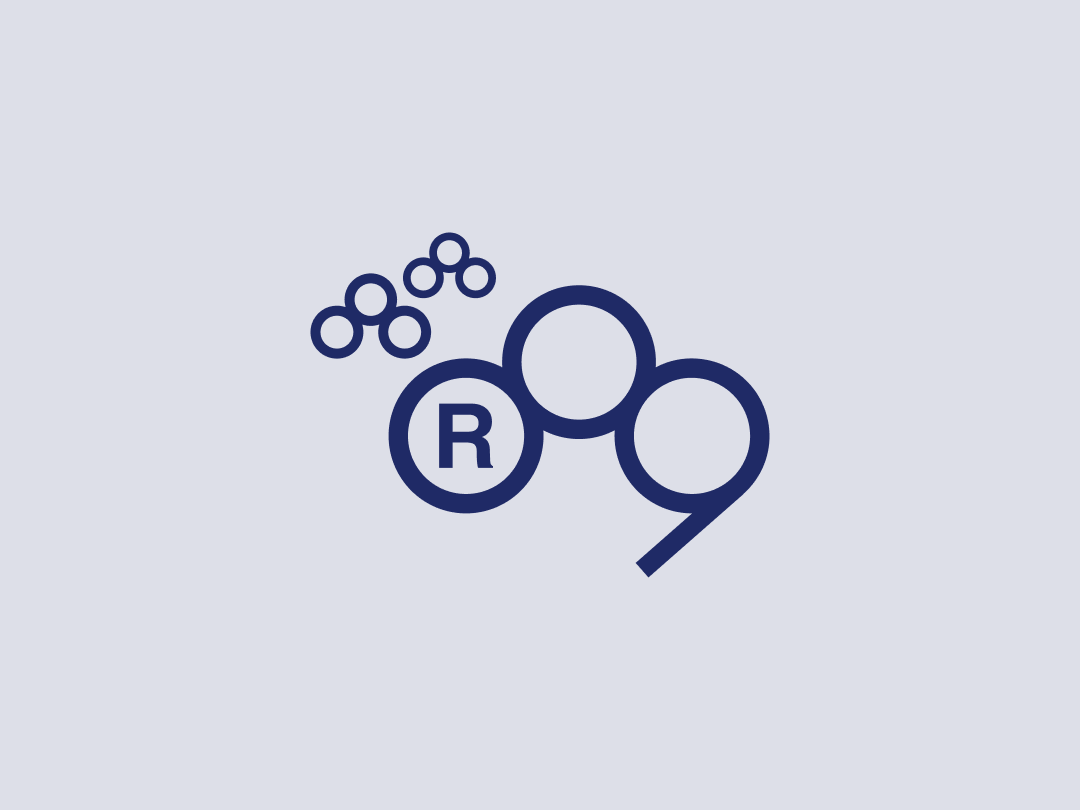スタートアップ採用の完全ガイド|戦略設計から実行・改善まで6ステップで解説
公開日: 2025年05月02日
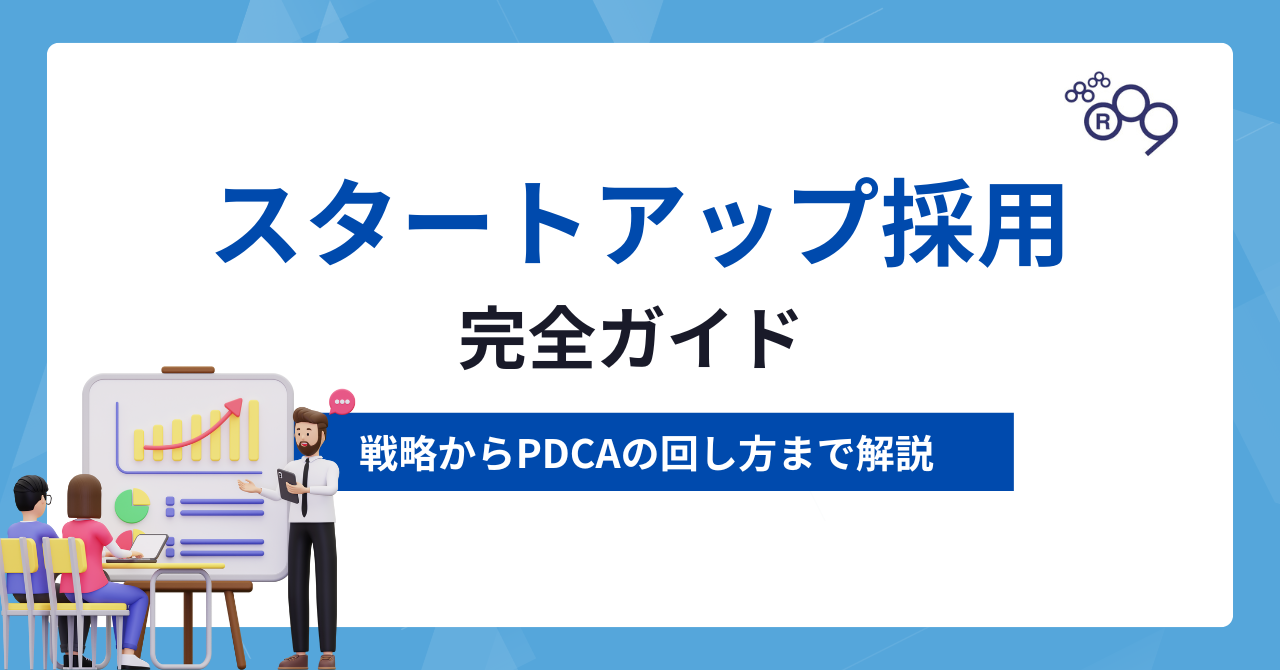
スタートアップの採用は、いつも“時間がない・人がいない・うまくいかない”。
そんな中で、「今あるリソースでも採用を成功させたい」と考える企業は少なくありません。
本記事では、成果を出すスタートアップに共通する
「採用を戦略的に設計し、良質な体験を通じて選ばれる構造」を、6つのステップに分けて徹底解説します。
感覚や場当たり的な採用から脱却し、
限られたリソースでも再現可能な「強い採用力」をつくるための道筋を、以下の順でお伝えします。
【本記事でわかること】
- 採用活動を“経営戦略”と結びつけて設計する視点
- 採用チャネルの選び方と組み合わせ戦略
- 面談や面接など“接点”の設計で志望度を上げる方法(採用CX)
- スタートアップでも始められるPDCAと改善文化のつくり方
採用が上手くいくスタートアップは、特別な手法ではなく、“戦略と思考の順番”が違います。
その順番、ぜひこの記事で整理してみてください。
なぜスタートアップの採用は難しいのか?
スタートアップやベンチャー企業にとって、「優秀な人材の確保」は事業成長のカギを握る最重要課題の一つです。しかし実際には、採用がうまく進まず、思うように人が集まらないという声も多く聞かれます。
では、なぜスタートアップは採用に苦戦するのでしょうか?
ここでは、特に多く見られる4つの課題を紹介します。
1. 知名度・ブランド力が十分でなく、応募が集まりづらい
設立から間もない企業や小規模なベンチャーは、求職者からの認知度がまだ低く、「知らない企業には応募しづらい」「信頼できるのか不安」といった心理的ハードルが生まれがちです。
求人を見てもらえない=母集団形成のスタートラインにも立てない
といった事態に陥りやすくなります。
2. 採用専任担当者がいない/ノウハウ不足
スタートアップでは、経営陣や現場社員が採用を兼任しているケースも多くあります。
そのため、以下のような悩みがよく見られます。
- どの媒体を使えばいいか分からない
- スカウトや面接の進め方が手探り
- 応募管理や日程調整が煩雑
リソース・知識の両面で限界を感じやすい点が、採用を難しくする大きな要因です。
3. 人材獲得競争が激化している
特にスタートアップが狙う「即戦力」や「将来の中核人材」は、大手企業や他の急成長ベンチャーからも強く求められている存在です。
- 給与や福利厚生の比較で不利になる
- 志望度が高くても、内定後に辞退される
- 他社にスピードで負けてしまう
といった形で、他社に採用されるケースも多く、競争は一層激しさを増しています
4. 採用プロセスが属人的・非効率になりがち
面接の内容や評価基準が担当者ごとにバラバラ、対応に時間がかかって候補者の熱量が下がってしまう…。このように、選考体験が整備されていないことで候補者が離脱するケースも少なくありません。
【POINT】スタートアップこそ「選考体験のクオリティ」が志望度に直結します。
このように、スタートアップの採用には
「知名度の壁」「リソース不足」「競争の激化」「プロセスの未整備」という、いくつものハードルが立ちはだかります。
では、これらをどう乗り越えるのか?
次章では、スタートアップが採用成功に向けて押さえておきたい戦略を解説していきます。
スタートアップに必要な採用戦略とは?
採用活動がうまくいかない理由は、個別のノウハウ不足だけではありません。
スタートアップが採用を成功させるためには、全体の流れを「戦略的」に設計することが必要です。
以下は、成果を出している企業に共通する6つの視点です。
本記事ではこの流れに沿って、スタートアップならではの課題と解決策を具体的に解説していきます。
- 目的と目標を明確にする
└ 「なぜ採用するのか?」を事業戦略から逆算して整理 - 現状を分析する
└ 数字・現場の声・競合との比較からボトルネックを把握 - 採用ターゲット(ペルソナ)を決める
└ 求める人物像を価値観・思考特性まで言語化 - チャネルを“目的×コスト”で選ぶ
└ 限られたリソースで成果を出すチャネル設計と組み合わせ戦略 - スケジュールを“体験設計”として組む
└ 接点タイミングと印象の設計で志望度を高める - 活動を振り返り改善する
└ データ+候補者体験から改善点を抽出して次へ活かす
この6つのステップを軸に、
「戦略なき採用」から「経営を支える採用」へ。
スタートアップでも再現できるノウハウをお届けします。
■ステップ①|採用の“目的と目標”を明確にする
── 採用は「今ほしい人を集める作業」ではなく、「事業成長を加速させる戦略」
スタートアップの採用活動では、つい「人手が足りないから急いで採用しなきゃ」といった動機になりがちです。
しかし、本来の採用は“経営課題を解決する手段”であるべきです。
たとえば以下のように、事業戦略や組織課題とつなげて考えることが重要です。
▼目的設定の例
- 経営課題:プロダクト改善のスピードが競合に劣っている
- 組織課題:エンジニアチームのリーダー層が不足している
- 採用目的:自走できる中堅エンジニアを採用したい
- 求める人物像:不確実な状況でも自ら動き、チームを巻き込める人材
このように“誰をなぜ採用するのか”を事業とひもづけて明確化することで、採用後の活躍まで見据えた活動が可能になります。
■スタートアップ採用にありがちな“目的のあいまいさ”
- 「いい人がいたら採用する」→判断軸がブレてミスマッチに
- 「何となく同業で経験がある人」→カルチャー不一致で早期離職
- 「目標人数だけ決めて動く」→プロセスが属人化し改善しづらい
目的があいまいだと、候補者にも魅力が伝わらず、辞退や離職のリスクが高まります。
■POINT|採用ターゲットの定義は“戦略の出発点”
目的と目標が明確になれば、採用ペルソナの設計やチャネル選定、選考設計にも一貫性が生まれます。
これは、マーケティングにおける「誰に・何を・どう届けるか」の設計と同じです。
まずは「なぜこの採用が必要なのか?」を、経営目線で言語化することから始めましょう。
■ステップ②|現状を“感覚”ではなく“データと実態”で分析する
── 採用の課題は、「思い込み」ではなく「可視化」から見えてくる
スタートアップでは、日々の業務に追われて「現状把握」がおろそかになりがちです。
特に人事専任がいないフェーズでは、
「何となく応募が少ない気がする」
「最近、辞退が多いかも」
といった“感覚ベース”で判断しがちです。
ですが、成果につながる採用改善には、「データと実態の両方」を使った冷静な分析が欠かせません。
■まずは数字で採用フローを棚卸しする
次のような指標を簡単にでも集めてみましょう。
- 応募数(媒体別)
- 書類通過率、面接通過率、内定率、承諾率
- 辞退や不通の発生タイミングと理由
- 採用にかかった費用(媒体・紹介・工数)
これらを時系列やチャネル別で並べるだけでも、「ボトルネック」が見えてきます。
例
- 書類通過は高いのに、1次面接で急に離脱が多い
- 応募は来ているが、承諾率が極端に低い
- あるチャネルからの応募は質が安定しない
■アールナイン式の“2つのアプローチ”で現場と戦略をつなぐ
「理想」と「現実」を両方の視点から見ることが重要です。
下記のようなアプローチを意識すると、思い込みに偏らない設計ができます。
①演繹的アプローチ(戦略 → 要件定義)
事業戦略や組織課題から、求める人物像を導き出す
②帰納的アプローチ(現場 → 設計への反映)
実際に活躍している人材の共通点や、辞退理由・入社後の声から逆算
この両軸で整理することで、「理想の人材像」と「現場に合う人材」のギャップを埋めながら、実行可能な戦略に落とし込むことができます。
■競合比較で「勝ち筋」が見えてくることもある
スタートアップでは、「どうせウチなんて…」と自社の魅力を過小評価してしまいがちです。
ですが、求職者は企業名や福利厚生だけで決めているわけではありません。
・対応スピードが早かった
・社員の雰囲気がよかった
・選考中のフォローが安心感につながった
こうした「勝ちポイント」は、競合と比較してはじめて見えてくることもあります。
可能であれば、辞退者や選考離脱者から「他社を選んだ理由」などをヒアリングしてみると、選ばれない理由だけでなく、“選ばれる可能性”にも気づけます。
■POINT|「現状を知ること」は、最もローコストでできる改善施策
分析に予算はかかりません。
まずは「採用がどこで詰まっているか?」を数値・声・実感で把握することから始めてみてください。
それだけでも、次の一手の精度は大きく変わってきます。
■ステップ③|採用ターゲット(ペルソナ)を言語化する
── スキルよりも「カルチャーへの適応力」を見極める
スタートアップ採用において最も重要な視点のひとつが、“誰を採るか”の定義を曖昧にしないことです。
特に組織が小さく、ひとりの影響力が大きいスタートアップでは、
「どんな価値観を持った人が、自社の成長フェーズにフィットするか」
を見極めることが、スキル以上に重要です。
■ペルソナ設計は“スペック”ではなく“深層価値観”から
年齢・職歴・スキルのような表面的な情報だけでは、ミスマッチを防げません。
以下のような深層的な要素まで踏み込んで、人物像を描いていきましょう。
▼考えるべき観点例
・どんな判断軸や行動特性を持つ人か
・変化や不確実性に対して、どんなスタンスで動くか
・社内で活躍している人と共通する思考傾向は何か
・どのような働き方・成長に魅力を感じるか
■カルチャーフィットを“感覚”で終わらせない
スタートアップでは「ウチっぽい人かどうか」という感覚的な評価が行われがちですが、それでは属人化・選考のブレが生まれてしまいます。
アールナインでは以下のような方法で、カルチャー適応性を言語化しています。
・活躍社員への1on1やアンケートを通じて、行動特性・価値観を抽出
・「地道に積み重ねられる人」「曖昧な状況でも前向きに動ける人」などを定義化
・面接でも「◯◯のような行動経験があるか?」と具体質問で確認できる状態にする
■面接官・現場とも共有して“共通言語”にする
ペルソナは人事担当だけのものではなく、面接官・経営陣・現場メンバー全員で共通認識を持つことが重要です。
「誰を採りたいのか」がバラバラな状態では、いくら応募が来ても採用精度は上がりません。
▼ペルソナをすり合わせるための具体視点
・どんな人生経験・キャリア志向を持っていそうか?
・どのような情報(ストーリー・数字・社員の声)に響きやすいか?
・現場でどんな成長を遂げそうか? どんな課題でつまずきそうか?
こうした視点まで踏み込んだペルソナ像があると、
求人原稿の表現、スカウト文、選考質問、フォロー面談に至るまで一貫した設計が可能になります。
■POINT|スタートアップにおけるペルソナ設計は“魅了設計”でもある
誰に向けて何を伝えるかが明確になることで、採用マーケティングの精度も飛躍的に高まります。
「自分のことを理解してくれている」と感じてもらえる選考体験が、最終的な承諾率や定着にもつながっていきます。
■ステップ④|採用チャネルは「目的」と「コスト」で選ぶ
── “なんとなく出す”では成果は出ない。限られた予算で最大効果を出すチャネル戦略とは?
スタートアップの採用では、「みんなが使っているから」「媒体営業に勧められたから」といった理由でチャネルを選びがちです。
しかし、本当に成果を出すには、自社の採用目的に対して“どのチャネルが効果的かを設計する視点”が欠かせません。
■まず整理したい2つの軸:「目的」と「コスト」
アールナインでは、採用チャネルを以下の2軸でマッピングしながら選定しています。
- 目的:認知拡大/動機形成/歩留まり改善/母集団形成 など
- コスト:媒体費・紹介手数料・工数(人件費)を含めたトータルコスト
このようにマッピングすることで、リソースをかけるべきチャネル・削るべきチャネルが明確になります。
■単体での施策ではなく、「組み合わせ」が成果を生む
特にスタートアップでは、「1つの施策に頼る」と失敗しやすくなります。
目的に応じて複数のチャネルを組み合わせることで、成果につながりやすくなります。
▼例①:認知不足で応募が集まらない
→ SNS採用広報 × 採用広報型プラットフォーム(Wantedly等) × 社員のリファラル
▼例②:選考途中の離脱が多い
→ DR(ダイレクトリクルーティング) × カジュアル面談 × 現場社員との座談会
▼例③:内定辞退が多い
→ LINEフォロー × 動画コンテンツ × 経営者との面談
目的を明確にし、その解決策としてチャネルを組み合わせるという視点が、チャネル設計の本質です。
■外部パートナーを“指示待ち”にしない
媒体営業、紹介会社、スカウト代行など、外部パートナーに業務を任せる場合も、成果を上げるにはコミュニケーションが重要です。
・KGI/KPIをしっかり伝える(◯月までに◯名面接設定したい、など)
・成功事例・過去の反応なども積極的に共有する
・やるべきことは厳しく、動いてくれたらしっかり感謝を伝える
というスタンスで接することで、「まる投げ」から「成果を共に出すためのパートナー」に変わるケースが多くあります。
■POINT|チャネルは「費用対効果」で見るより、「戦略とのつながり」で判断する
広告媒体が安いからといって、欲しい人が集まらなければコストは無駄になります。
逆に、費用が高くても即戦力が確実に採れるなら、費用対効果は高いと言えます。
「なぜこのチャネルを選ぶのか」を戦略と結びつけて説明できる状態を目指しましょう。
■ステップ⑤|スケジュールを“体験設計”として組む
── 選考スピード=競争力。タイミングと接点の質が志望度を左右する
スタートアップの採用では、選考スピードと候補者の体験(採用CX)が企業の印象を大きく左右します。
採用CX(Candidate Experience)とは、候補者が採用プロセスを通じて企業に抱く印象や感情のこと。
「選ばれる採用」を実現するには、スケジュール設計を通じて良質な体験を提供する視点が欠かせません。
■採用CXを高める3要素:戦略 × 設計 × 接点
- 戦略:誰を採るか・自社の魅力・競合との違いを言語化
- 設計:フローの流れ、選考期間、接触頻度を最適化
- 接点:スカウト文面・面談・面接の質を高める
このうち「設計」と「接点」はスケジュールに強く関わる要素です。
■接点は“回数”と“質”の両方が重要(ザイオンス効果)
心理学で言う「ザイオンス効果(単純接触効果)」では、人は何度も接する対象に好意を抱きやすくなるとされています。
採用においても、候補者と月1回以上接点を持てている企業は、承諾率が高い傾向にあります。
ただし注意したいのは、「回数を増やすだけでは意味がない」ということ。
接点の“質”が伴っていないと、むしろマイナス印象につながるリスクもあります。
■実際にあった学生の声(ネガティブ事例)
・エントリーから初回接触まで2ヶ月以上空き、企業名も印象も忘れてしまった
・他社との接点が多く、比較されて志望順位が下がった
・面談が定型的すぎて、自分に関心を持ってくれているとは思えなかった
これらのような体験は、志望度を著しく下げる原因になります。
■採用CXを意識した接点設計の例
- 1週間以内に返信・日程調整を実施
- 面談ごとに「目的」や「話すテーマ」を事前共有
- カジュアル面談 → 社員座談会 → フィードバック面談 など多層的な接点
- 経営者からのメッセージ動画など“人”を感じる演出
- リクルーター(第三者)が学生の不安を解消する場を設ける(ウィンザー効果)
こうした“気持ちの良い接点”をスケジュールに組み込むことが、企業の魅力を正しく伝えることにつながります。
■POINT|スケジュールは「行程」ではなく「印象設計」
スケジュール設計を「社内都合で詰める工程表」としてではなく、
「候補者にどんな体験をしてもらいたいか」という視点でデザインすることが、スタートアップ採用の強力な武器になります。
■ステップ⑥|活動を振り返り、改善する(PDCA)
── 採用は“やりっぱなし”では成果につながらない。改善こそ、スタートアップ採用の強化ポイント
採用活動は「終わったら終了」ではなく、終わってからが本番です。
実施した施策や対応をしっかり振り返り、次の活動へ改善をつなげることで、スタートアップでも“再現性のある強い採用”をつくっていけます。
■スタートアップにありがちな「振り返りができない」原因
- 忙しくて記録が残っていない
- 感覚で「良かった/悪かった」を判断してしまう
- 現場や経営と共有できるような形に整理できていない
この状態では、せっかくの学びや気づきも積み上がっていきません。
■改善につなげるための「見える化」項目例
・媒体ごとの応募数/通過率/コスト
・選考フローごとの歩留まり
・辞退・内定辞退の理由とタイミング
・面談・面接時の満足度(アンケート・ログ)
・面談官ごとの承諾率やフィードバック内容
これらを記録・定量化することで、
「なんとなくうまくいった」から、「再現可能な成功パターン」へと昇華できます。
■採用CXの視点からも、PDCAは不可欠
採用CXは候補者の体験そのものです。
満足度の高い体験を提供できていたかを測るには、候補者の声や行動ログを振り返ることが必須です。
- 学生がどのタイミングでテンションが上がったか/下がったか
- カジュアル面談やリクルーター面談は印象にどう影響したか
- 初回接点から承諾までに「何が志望度に効いたか」
こうした情報を集めて検証することで、次の施策の“打ち手”がはっきりしてきます。
■アールナイン式|「ログ文化」を小さく始める
改善文化を社内に定着させるためには、完璧な分析資料は不要です。
まずは小さく、“会話のログ”を残すことから始めてみましょう。
たとえば以下のような共有で十分です。
・「この面談で学生がすごく安心した様子だった」
・「○○という伝え方にすごく反応していた」
・「日程調整が2日早ければ内定承諾もあったと思う」
こうした温度感を言語化して残していくことで、属人性の高い採用活動が“共有知”に変わっていきます。
■POINT|スタートアップの採用は「高速PDCA」が最大の武器
リソースが限られていても、改善のサイクルを回せる企業は、確実に採用力を高めていきます。
うまくいった理由・うまくいかなかった理由を人任せにせず“構造化して次に活かす”ことが、強い採用組織への第一歩です。
スタートアップに向いている採用チャネル・手法
どんなに良い戦略を描いても、それを実行する「チャネル選び」が間違っていれば成果にはつながりません。
スタートアップのようにリソースが限られる環境では、費用対効果が高く、自社に合った人材と出会いやすいチャネルの見極めがカギになります。
ここでは、特に活用しやすい主要チャネルを5つご紹介します。
1. 採用広報・SNSを通じたブランディング(Wantedly含む)
まだ知られていない企業にとって、まず必要なのは「興味を持ってもらうこと」です。
その入口として有効なのが、採用広報やSNSを活用した認知・共感の獲得です。
たとえば:
- noteやX(旧Twitter)で社員インタビューやカルチャーを発信
- 経営者や人事がSNSで自社のビジョンや想いを発信
- Wantedlyを使って“共感ベース”で人と出会う
【POINT】Wantedlyは「ビジョンに共感できる企業に出会いたい」層との相性が良く、スタートアップとマッチしやすいチャネルのひとつです。
まだ応募に至らない潜在層とも接点を持つことができ、長期的なファン層づくりにもつながります。
2. ダイレクトリクルーティングでピンポイントに声をかける
「待ちの採用」から脱却する手段として、スタートアップでも広まりつつあるのがダイレクトリクルーティング。
求職者データベースに登録されている人に対して、企業側からスカウトを送るスタイルです。
- 自社が求める人材像に合致した人に直接アプローチできる
- スカウト文に熱意や想いを込めることで、知名度を補える
- コストを抑えつつ、ピンポイントで会いたい人に会える
「興味を持ってくれたら即カジュアル面談」など、スピーディな運用がしやすいのもメリットです。
3. 人材紹介を活用して、即戦力人材との接点を持つ
スタートアップが早急に人を採りたい場合や、自社の力だけではターゲットにリーチしづらいときには、人材紹介会社(エージェント)の活用も有効です。
- 求める要件にマッチした候補者を提案してもらえる
- 応募の母集団形成にかける手間が大きく削減できる
- 専門性の高い人材やハイクラス人材とも出会える
ただし、成功報酬型のため費用が高額になりがちという点には注意が必要です。
スタートアップでは、「初期メンバー採用」など勝負どころでピンポイントに活用するケースが多く見られます。
4. 採用代行(RPO)を導入し、実務をプロに任せる
「戦略はあるけど実行する時間も人手もない…」というスタートアップには、採用代行(RPO)も有効な選択肢です。
- スカウト送信、面接調整、選考進行などの実務を委託できる
- 採用ノウハウを持つプロが運用設計から支援してくれる
- 社内の採用担当者のリソースをコア業務に集中させられる
【補足】「スカウトだけ」「面接の同席だけ」といった部分的な依頼も可能なので、段階的に取り入れやすいのもメリットです。
少人数体制で採用を進めるスタートアップにとって、“効率”と“質”を両立させる手段として注目されています。
5. リファラル採用(社員紹介)を最後の一手に
スタートアップにおける“最強チャネル”とも言われるのが、リファラル採用(社員紹介)です。
コストをかけず、かつカルチャーフィット率が高い採用手法として、非常に有効です。
- 社員経由で紹介されるため、企業のリアルが伝わりやすい
- 入社後のミスマッチが起きにくく、定着率が高い
- 採用スピードが早く、心理的なハードルも低い
とはいえ、「声をかけてほしい人が思い浮かばない」という社員も多いので、
紹介しやすくなるための仕組み(声のかけ方、インセンティブ、ツールの導入など)を整えるのがポイントです。
このように、スタートアップにとっての採用チャネルは、「何を目的にするか」「今の体制で実行できるか」によって最適な選択肢が変わります。
次章では、こうした手法選びの中で実際に起こりがちな“失敗”と、それをどう回避するかについて解説します。
よくある採用の失敗とその対策
スタートアップの採用では、「正しいと思ってやったこと」が結果的に失敗につながってしまうケースも少なくありません。特に、初めて本格的に採用に取り組むフェーズでは、“見落としがちな落とし穴”に注意が必要です。
ここでは、実際によくある4つの失敗と、その対策を紹介します。
1. 優秀な人材を狙いすぎてミスマッチが起こる
スタートアップの成長には「できる人材」が必要。そう考えて、スキルや経歴のスペックが高い人ばかりに目が行ってしまうことがあります。
しかし、どれだけ優秀でも「自走できない」「スピード感についていけない」「ベンチャーの不確実性に合わない」などの理由で、カルチャー面でのミスマッチが発生しやすくなります。
対策:
- スキルだけでなく、価値観や働き方への適応度も評価する
- 面接での「志向性」や「スタンス」にもしっかり注目する
- 現場との相性を確かめる場(カジュアル面談や現場面接)を設ける
2. 選考中のコミュニケーション不足で辞退される
応募者が面接後に辞退してしまう理由の多くは、「この会社で働くイメージが持てなかった」「不安を解消できなかった」といったコミュニケーション不足に起因しています。
スタートアップでは、面接が忙しい業務の合間に組み込まれることも多く、「面談の温度感」「対応のスピード」「フォローの丁寧さ」が後回しになってしまいがちです。
対策:
- 面接後のフォローメールや個別連絡で、熱量や期待を伝える
- 面接の中で一方的に見極めるのではなく、「双方向の対話」を意識する
- カジュアル面談や社内見学など、安心感を高める場を設ける
3. 入社後のオンボーディングが不十分で早期離職に
やっと採用に成功しても、「入社後の受け入れ体制」が整っていないと、すぐに離職されてしまうことがあります。これは意外と多い、見過ごされがちな失敗です。
スタートアップは変化が激しく、属人的な業務も多いため、オンボーディングの設計がされていないと「何をすればいいか分からない」「聞ける人がいない」という状況に。
対策:
- 1ヶ月〜3ヶ月のオンボーディングプランを簡単にでも作成
- 初日のアジェンダ・担当者・業務のゴールなどを明示する
- 先輩社員との1on1やメンターメンバーを設定し、相談しやすい空気をつくる
4. 採用フローが整っておらず、候補者が離脱する
選考期間が長すぎる、面接日程がなかなか決まらない、評価の軸が面接官ごとに違う…。
こうした採用フローの整備不足は、候補者体験を下げ、せっかくの出会いを逃す原因になります。
特に、他社と並行して選考を受けている候補者にとっては、スピード感のない対応=「この会社は本気度が低いのでは?」という印象にもつながります。
対策:
- 選考ステップをなるべくシンプルに設計(面接は原則2回まで など)
- 社内で評価基準を共有し、見極めポイントを明文化する
- 面接日程調整や連絡スピードを徹底して早くする
こうした「つまずきポイント」は、事前に意識しておくだけでも回避できるケースが多くあります。
大切なのは、“理想の採用”ではなく“現実的に実行できる採用”を設計し、試行錯誤を重ねていくことです。
次章では、そんな採用活動を進めるうえで欠かせない「社内体制の整え方」について解説していきます。
採用成功に向けた社内体制の整え方
どんなに優れた戦略やチャネルを活用しても、社内体制が整っていなければ採用は進みません。
スタートアップでは限られたメンバーで採用を兼任することが多いため、「現場との連携」や「チームとしての推進力」が成果を分けるポイントになります。
ここでは、採用を組織として成功させるために押さえておきたい体制づくりのポイントを4つご紹介します。
1. 採用活動をチームで進める「スクラム採用」の考え方
「採用は人事だけの仕事」と捉えると、どうしてもスピードと質が頭打ちになります。
そこでおすすめなのが、現場・人事・経営陣が一体となって採用に取り組む“スクラム採用”の考え方です。
- 現場メンバーが面接官として参加し、リアルな情報を伝える
- カルチャーフィットの観点から、配属予定部署が評価に関わる
- 経営者が面談に登場し、候補者の志望度を高める
【POINT】「全社で採用に向き合う」文化は、会社の雰囲気づくりや内定後の定着にもつながります。
2. 魅力づけは「現場からの声」を活用する
候補者に対して、待遇や制度だけを伝える時代は終わりつつあります。
今はむしろ、「このチームで働きたい」「この人たちとなら頑張れそう」と思ってもらうことの方が重要です。
そのためには、現場社員の声を使った魅力づけが効果的です。
- 社員インタビューを選考中にシェア
- 面接で現場メンバーとの座談会を実施
- 内定通知後に、実際の配属予定メンバーと話せる機会を設ける
“会社”ではなく“人”で惹きつける、というスタートアップらしい魅力発信が、志望度アップに直結します。
3. 採用担当者に求められる3つのスキルとは?
スタートアップでは、採用担当が一人しかいなかったり、他業務との兼任であることも多いです。そんな状況下でも成果を出すために、以下のようなスキルが求められます。
- 情報設計力: 求人票やスカウト文を通じて「誰に・何を・どう伝えるか」を設計する力
- 社内巻き込み力: 面接官や現場メンバー、経営陣をうまく巻き込む力
- 選考進行力: 候補者に寄り添いつつ、スピード感と丁寧さを両立させる力
スキルがすべて備わっていなくても、「今何が足りないか」を意識するだけで採用の質は上がります。
4. 足りない部分は外部のプロをうまく使う
採用に100%コミットできる人が社内にいない場合、無理せず外部に頼る判断も戦略のひとつです。たとえば:
- スカウト送信や面接調整などの実務面だけを代行
- 採用戦略やチャネル設計の企画段階からの相談
- 面接官トレーニングや評価項目設計などのノウハウ支援
自社に不足している部分を冷静に見極めて、「内製」と「外部リソース」のバランスをとることが、無理なく採用を進めるコツになります。
採用は、仕組みやツールだけではなく「人」と「組織力」があってこそ成立するものです。
スタートアップこそ、“社内でどう連携し、どう魅力を伝えるか”という視点が、最終的な成果を左右します。
次章では、これまでの内容をまとめつつ、「仕組み化」の重要性と資料DLへの自然な導線へつなげていきます。
まとめ|“採れる”スタートアップ採用は、戦略×体験設計でつくられる
スタートアップの採用において、いきなり人が集まる・即戦力が採れる、ということはありません。
だからこそ、事業や組織の状況に合わせて「戦略的に採用を設計する視点」が求められます。
本記事で紹介した6ステップは、どんなフェーズの企業でも応用可能な「採用の土台」です。
- 採用の目的と目標を明確にする
- 現状を分析する(数字と感覚の両面で)
- ターゲット(ペルソナ)を定義する
- チャネルを目的×コストで選ぶ
- スケジュールを“体験設計”として組む(採用CXの視点)
- 振り返りと改善(PDCA)を回す
特に⑤⑥でご紹介した「採用CX」や「改善の仕組み」は、限られたリソースで成果を出すスタートアップにとって大きな差別化ポイントになります。
“感覚や属人性に頼らない採用”を実現するために、まずは小さくても、自社の採用戦略をこのステップに沿って言語化してみてください。
この記事の監修者:
1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。