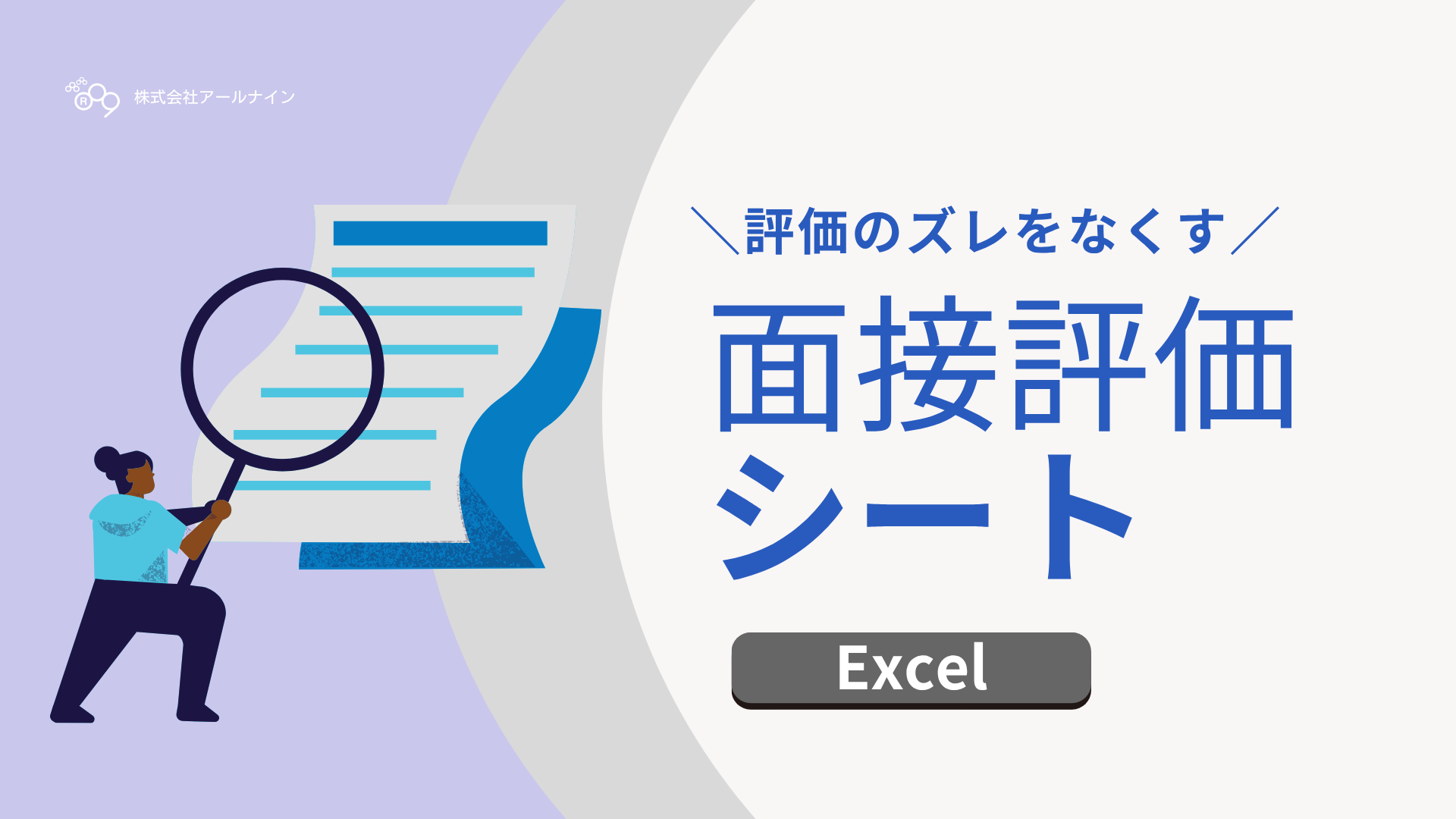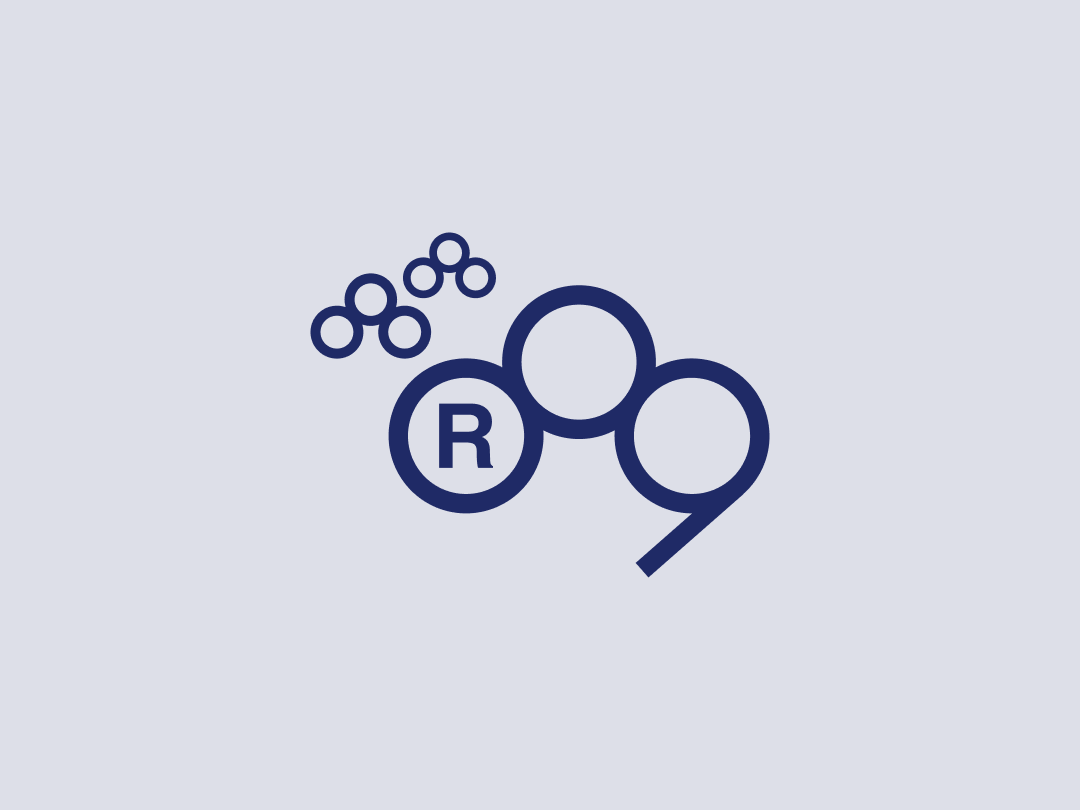【完全ガイド】面接官による評価基準のズレをなくす5ステップ|納得感ある採用の仕組み化とは?
公開日: 2025年08月05日 | 最終更新日: 2025年09月03日
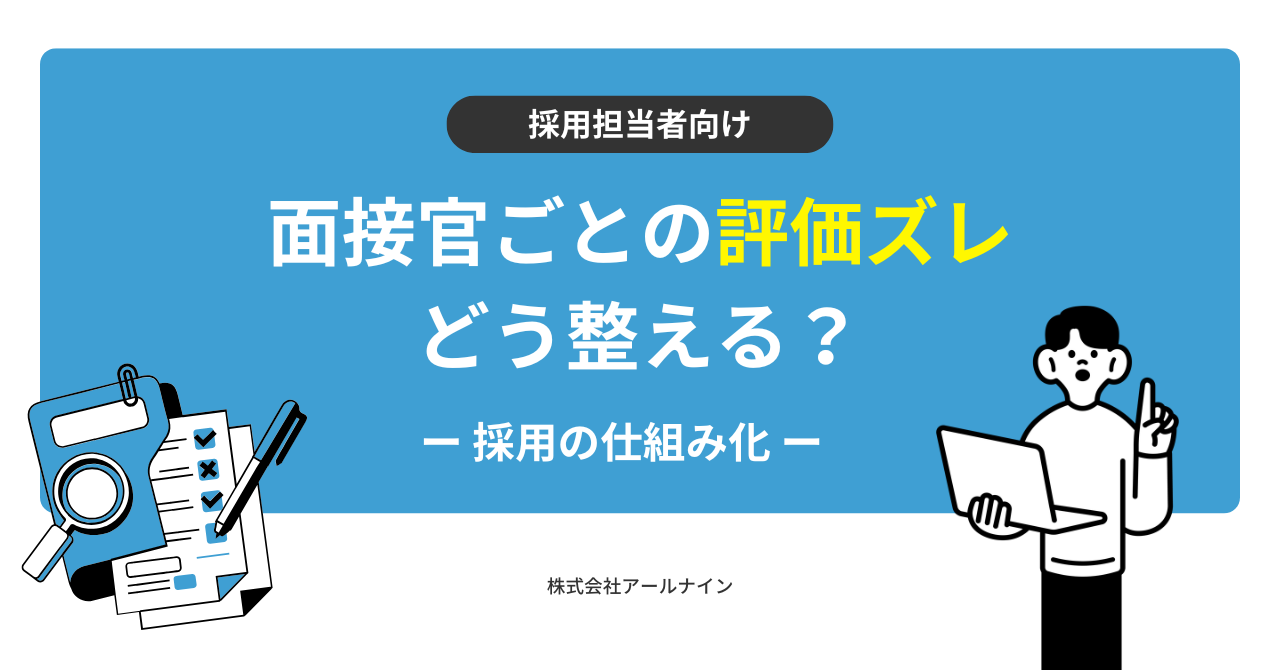
いま、採用活動の中でも「面接の精度」がこれまで以上に問われています。
候補者の志向が多様化するなかで、面接官ごとに評価の基準がバラバラなまま選考が進んでいる企業も少なくありません。
「同じ候補者なのに、面接官によって合否判断がまったく違う」
「評価コメントが抽象的すぎて、議論にならない」
「採用したのに、現場とのミスマッチですぐに辞めてしまう」
こうした“ズレ”は、単なる認識の違いではなく、評価の属人化・不透明な判断軸・振り返りの仕組み不在といった構造的な課題によって生まれ、拡大していきます。
アールナインがこれまで支援してきた800社以上の企業でも、この「面接官の評価基準のズレ」による採用の失敗を数多く見てきました。
本記事では、そんな「なんかズレてる気がする」という直感を出発点に、
- 評価がズレる原因と可視化の方法
- 面接評価を整える具体的な5つのステップ
- 評価制度づくりに役立つテンプレートや支援の選択肢
をまとめて解説します。
“評価のズレ”を、放置せず整える。
それだけで、面接の納得感と採用成果は大きく変わってきます。
面接官の評価がズレる3つの原因
評価がズレる――これは、個々の面接官のせいではありません。
その背景には、組織的に整備されていない「仕組みの弱さ」があります。ここでは、特に現場でよく見られる3つの原因を紹介します。
① 評価基準が言語化・共有されていない
「主体性がある人がいい」
「カルチャーフィットするかを見たい」
――面接官の口から出る言葉は似ていても、その中身は人によって異なります。
たとえば「主体性」の定義ひとつとっても、
- 自ら手を挙げて行動するタイプを評価する人もいれば、
- 周囲を巻き込む調整型を評価する人もいる
というように、何をもって高評価とするかが一致していないのです。
つまり、「評価するための言葉」はあっても、共通の意味づけがされていない状態。これがズレの根本的な要因になります。
② 評価項目がそもそも存在しない/属人的になっている
面接官が「自分なりの基準」で判断してしまう背景には、会社としての評価項目が定まっていないという問題もあります。
特に中小企業や成長フェーズの企業では、
「面接は現場に任せている」
「それぞれの目で見極めてほしい」という属人化が起きやすく、
結果的に評価軸が個人の経験値や勘に依存するかたちになります。
これでは面接官が交代するたびに、候補者の合否が左右されるのも当然です。
③ 面接官同士で“すり合わせる機会”がない
採用要件のすり合わせや面接前後の情報共有を、
形式的な引き継ぎやSlackの一言で済ませているケースも少なくありません。
しかし、「どこをどう見るか」をすり合わせないまま複数の面接官が関わると、
- 評価の観点が分散する
- 面接の質問内容が重複/抜け漏れする
- 合否判断が不透明になる
といった事態が頻発します。
実際、アールナインの支援現場でも、
「最終面接だけ雰囲気が違って辞退された」
「評価コメントがふわっとしていて比較できない」
といった声が、面接官同士の“すれ違い”によって起きている例は珍しくありません。
このように、評価のズレは「個人のスキルの差」ではなく、評価設計の欠如と組織のコミュニケーション不足によって起きる問題です。
次の章では、こうしたズレを“見える化”するための第一歩をお伝えします。
ズレを“感覚”で終わらせない|ファクトで見える化する方法
「なんとなくズレてる気がする」
「合否の判断に納得感がない」
その“感覚”を、行動につなげる一歩目は“見える化”です。
評価のズレを感覚論で終わらせず、数値や言語で捉えられる“ファクト”に変えることで、対話が可能になります。
ここでは、現場でもすぐ実践できる3つの可視化方法を紹介します。
① 面接官ごとの通過率・合否傾向を集計する
まずは、定量的なデータを比較するところから始めましょう。
- 面接官ごとの通過率(一次通過/最終通過)
- 面接評価→配属後の定着率
- 同じ候補者に対する評価結果の差分
これらを一覧にするだけでも、
「A部長は通過率が極端に低い/高い」
「B課長は判断が甘く、辞退率が高い」といった傾向が見えてきます。
※無理に評価を揃えるのではなく、ズレの構造を可視化するための入口と捉えることが重要です。
② 評価コメントを“質”で比較する
評価シートに記載されたコメントを見てみると、
ある面接官は「話し方がしっかりしていた」と書いている一方、
別の面接官は「論理性に欠ける印象」とコメントしていた――というような、主観・抽象コメントのズレが散見されます。
評価コメントを集めて並べるだけで、
- 何を見ているか
- どう言語化しているか
の“ばらつき”が明らかになります。
特に、「なぜ高評価だったのか」が書かれていないコメントは、
すり合わせも改善も難しくなります。
③ 適性検査などの「共通前提」を面接前に持っておく
事前に性格特性・価値観・ストレス耐性などを把握できる適性検査を使うと、
面接官がそれぞれの視点で候補者を見る際の“補助線”になります。
例
- ストレス耐性が低め→その傾向を確認する質問を設定
- 主体性高→過去の経験で裏付けがあるかを深掘る
面接で得た印象を検証しやすくなることで、
「ズレたまま通してしまう」「主観だけで否定してしまう」といったリスクを防げます。
評価のズレを構造として整えていくには、まず「事実を共有する土台」をつくることが最初の一歩です。
次の章では、その土台の上にどう“仕組み”を築いていくかを解説します。
ズレを整える5ステップ|評価の仕組み化戦略
面接官ごとの“評価のズレ”は、個人の能力の差ではなく仕組みの不在による構造的な課題です。逆に言えば、評価の仕組みさえ整えば、面接官が変わってもブレのない選考が可能になります。ここでは、アールナインが多くの現場で実践している面接評価の仕組み化5ステップをご紹介します。
STEP 1|ズレを“共通課題”として社内で共有する
ズレが起きていることは、データを集めればすぐに見えてきます。
ただし、本当に大事なのは「ズレていること」を組織全体の共通課題として扱えるようにすることです。
- 面接官ごとの通過率や合否傾向を一覧に
- 抽象コメントと具体コメントを比較
- 面接後のすり合わせミーティングを定期化
目的は、「誰が悪いか」を指摘することではなく、“見ているものが揃っていない”という前提を全員で共有すること。 このステップがあるだけで、次の設計がスムーズになります。
📌 目的:ズレを“言える空気”にし、次の改善へつなげる
STEP 2|活躍人材像を定義し、評価項目を設計する
評価項目をつくるうえで最初にすべきは、「どんな人が活躍しているか」の可視化です。
- 業績が出ている人の共通点(スキル・行動特性)
- 長く定着している人の志向や価値観
- 社内で評価されている人物のふるまい・思考傾向
こうした観点をもとに、スキル・志向・カルチャーフィットの3層で評価項目を構成します。 抽象的な言葉でなく、「具体的にどう見極めるか」まで落とし込むことが重要です。
📌 目的:“なんとなく合いそう”を言語化し、判断の物差しを共通化する
STEP 3|面接評価シートを整備する
設計した評価項目を、面接現場で使えるかたちに整えます。ポイントは、「誰でも使える」「記録が残る」構造にすることです。
- 5段階評価+理由記入欄
- 合否判断ガイド(合格の目安・懸念パターン)
- 評価項目と質問例の対応(例:主体性を見る質問)
この評価シートがあることで、感覚での判断を防ぎ、会話の記録を残せるようになります。
📌 目的:見たこと・聞いたことを“言葉と点数”で残す評価ツールに変える
STEP 4|面接官間で評価の観点をすり合わせる
評価シートを配っただけでは、評価のズレはなくなりません。
面接官同士の「どう見ているか」「なぜそう判断したか」を対話する時間」が必要です。
具体的には:
- 事前の読み合わせ(どの項目をどう見るか)
- 過去の評価事例を使ったケースディスカッション
- ロールプレイや同席面接による実践共有
こうしたすり合わせによって、評価基準が「使われるもの」として浸透します。
📌 目的:評価基準を“使える状態”に落とし込み、判断のブレを縮める
STEP 5|評価運用を定着させ、継続的に見直す
評価シートと基準を整備したら、運用→振り返り→改善のサイクルを回していきましょう。
- 評価内容と内定辞退・早期離職との相関を分析
- 定量評価(通過率)と定性評価(コメント)の質を定期レビュー
- 面接官からのフィードバックを受け、シート内容もブラッシュアップ
面接評価は、一度つくって終わりではありません。
むしろ、実際に使いながら組織ごとに最適化していく仕組みこそが、ズレを減らす最大の武器になります。
📌 目的:評価の精度を“仕組み”として継続的に育てる
この5ステップを踏むことで、「なんとなくズレている」状態から、“なぜズレているか”を言葉と構造で捉えられる組織へと変わります。
次章では、「とはいえ社内で進めづらい…」というときに有効な第三者支援の使い方をお伝えします。
社内で言えないなら「第三者の声」を使う選択肢も
「評価のズレが気になっている。けれど、自分からは言い出しづらい」
そんな声を、私は多くの人事担当者から聞いてきました。
特に、面接官が現場のマネージャーや経営層である場合、
「この面接、ズレてませんか?」とは言いづらいもの。
関係性や社内の力学を考えると、“わかっていても動けない”構造が生まれがちです。
そんなときは、第三者の視点/仕組み/ファシリテーションという3つの外部の力を活用してみてください。
① 外部パートナーによる「評価設計・面接支援」
評価の仕組みそのものを、外部の採用支援会社に設計・導入してもらう方法です。
- 活躍人材の分析と評価項目の策定
- 面接評価シートの設計・運用支援
- 面接官トレーニングやロールプレイの設計
評価に対する共通言語を持てるようになり、人事が“言わなくてもよくなる”構造が整います。
② 外部ファシリテーターによる「対話設計」
社内メンバー同士では生まれにくい本音の対話や、価値観のすり合わせを中立的なファシリテーターが支援する方法です。
- 面接官MTGに同席し、議論の交通整理をする
- 言いにくいことを“問い”として投げかけてくれる
- 立場を超えた合意形成を支援してくれる
評価に対するズレを「誰のせいでもなく、組織として整えるもの」に変えてくれる存在です。
③ 第三者データや比較指標を活用して「客観視点」を持ち込む
自社だけの価値観だと、どうしても判断が感覚的になります。
そこで、他社事例・統計データ・適性検査結果などを使って共通の前提を持つことも、立派な“外部視点”のひとつです。
- 通過率・辞退率の他社比較
- 面接評価のベンチマーク項目
- 評価結果と配属後パフォーマンスの相関分析 など
「この判断、他社と比べてどうなんだろう?」という視点があるだけで、主観を言語化・客観化しやすくなります。
どの方法を選ぶにせよ、「社内で全部やろう」としないことがポイントです。
- 自分が指摘役になることで関係性が悪くなる
- 面接の質の改善が“現場のスキルの話”で終わってしまう
- 評価が整わないまま、いつの間にか別の課題にすり替わる
そんな事態を避けるためにも、社外の力を“中立な軸”として使うことは、有効な手段のひとつです。
【無料DL】面接の仕組み化に役立つ3つのテンプレート
評価のズレを仕組みで整えたい――
そう思っても、いきなり制度をつくるのは難しい。
だからこそ、まずは手軽に使えるテンプレートから始めてみませんか?
ここでは、アールナインが提供する3つのテンプレートをご紹介します。
それぞれ目的が異なるため、課題に応じて個別にダウンロードできます。
① 面接官用・評価基準シートテンプレート
主観に頼らず、ブレない面接を実現。
スキル・志向・カルチャーフィットの3分類で構成された、実務向けの評価シートです。
- 5段階評価+コメント欄付き
- 合否判断の目安も明記
- 面接官同士の認識ずれを防止
② 面接力チェックシート
面接官のスキルを“見える化”。
4つのレベルで面接力を可視化できるセルフチェックツールです。
- 姿勢・聴く力・見極め力・伝える力を診断
- 面接前の振り返りや育成に活用
- 面接同席者のフィードバックにも便利
③ 学生が気になる質問24戦&回答準備シート
逆質問こそが、惹きつけのチャンス。
よくある質問とその背景を整理し、回答のすり合わせに使える実践フォーマットです。
- 学生の関心が高い質問24選
- 回答の意図やポイントを明記
- 面接官間の回答統一に役立つ
評価に関する課題は、1つのツールだけで解決できるものではありません。
自社の状況に応じて、必要なものから少しずつ整えていくことが“ズレ”をなくす近道です。
どこから手をつける?課題別おすすめアクションガイド
「評価がズレているのは感じている。でも、正直どこから始めればいいのかわからない…」
そんな方のために、課題タイプ別に“最初に着手すべきこと”を整理しました。
自社の状況に近いものを参考に、無理のない一歩から始めてみてください。
| 課題・状態 | 最初に取り組むアクション |
|---|---|
| 評価シートが存在しない/項目がバラバラ | 評価基準テンプレートをベースに、自社用にカスタマイズしてみる |
| 評価項目はあるが、使われていない | 面接官とのMTGで、項目の意味・判断ポイントをすり合わせる |
| 面接官の判断が主観的すぎる | 適性検査や事前情報を併用し、前提を揃えてから面接する |
| 面接コメントの精度が低い | 評価シートに「なぜそう思ったか」を記述する欄を追加する/例文共有 |
| 面接官ごとに通過率が違いすぎる | 通過率レポートや傾向を可視化し、面接官ごとにフィードバックする |
| 経営層や現場に言いづらい | 第三者に評価設計やトレーニングを依頼し、“中立的な提案”に乗せる |
正解は一つではありません。
評価の整備は、“自社に合う順番”で段階的に進めるのが成功のコツです。
よくある質問Q&A
ここでは、面接評価の整備を進める際によくいただく質問をQ&A形式でまとめました。
ちょっとした不安や引っかかりも、事前にクリアにしておきましょう。
Q1. 評価項目はいくつに絞るのが適切ですか?
A. 5〜7項目が最も実用的です。
多すぎると面接官の運用負荷が増え、主観の入りやすい評価になりがちです。
おすすめは以下のように分類し、それぞれから1〜2項目ずつ設定する構成です:
- スキル・思考:課題解決力、論理的思考力など
- 志向性・価値観:成長意欲、挑戦意識、キャリア観など
- カルチャーフィット:協調性、誠実さ、社風との親和性など
▶「どこを見るか」だけでなく「どう見て、どう判断するか」まで言語化しましょう。
Q2. 面接官の主観的な評価をどう扱えばいいですか?
A. 主観は“否定”ではなく、“翻訳”すれば武器になります。
人の印象を完全に客観化することはできません。
重要なのは、「なぜそう思ったか」を記録し、後から共有できる状態にしておくことです。
おすすめアクション
- 評価コメント欄に“理由や根拠”を必須とする
- ロープレや評価すり合わせ会で“判断の癖”を共有する
- NG例・OK例を共有し、評価観点のズレを言語で整える
▶ 感覚は「共感可能な意見」に変えることができます。
Q3. 適性検査は入れるべきですか?どう併用すればいい?
A. 面接の“補助線”として有効ですが、判断の代用にはなりません。
適性検査は、面接官による主観評価を補う“客観材料”として効果的です。
特に見えにくい志向性やパーソナリティ傾向を知るのに役立ちます。
活用法の例
- 面接前に検査傾向を確認し、質問を調整
- ストレス耐性や協調性のスコアとエピソードの整合を確認
- 社内活躍人材の傾向と照らし、フィット度を判断
▶ 合否の決定には必ず面接とセットで活用しましょう。
Q6. 評価の仕組みを、現場にどう浸透させればいいですか?
A. 「なぜ必要か」を伝え、“使いたくなる仕組み”にするのがポイントです。
面接官の反発やスルーは、「手間がかかる」よりも「意味が伝わっていない」ことが原因です。
浸透の工夫例
- 導入初期は項目数を絞った“簡易シート”からスタート
- 面接官同士で評価傾向を共有するMTGを設ける
- 実際の面接コメントを見ながら、評価のズレを体感してもらう
- 「候補者にとっての納得感を高めるため」という目的を伝える
▶ “チェックシート”ではなく“共通の見方をつくるツール”と伝えることで、現場に受け入れられやすくなります。
Q7. 現場が「人柄で見ている」とき、どう伝えるべきですか?
A. 感覚的な“人柄評価”は、言語化して評価項目に昇華できます。
「なんとなく合いそう」「フィーリングが合う」という声も、評価観点のヒントです。
たとえば:
- 「落ち着いている」→ 顧客に安心感を与えられるか?
- 「話しやすい」→ 協働において信頼関係を築けそうか?
- 「柔らかい雰囲気」→ 社風との親和性があるか?
▶ 人柄を言語化し、再現性のある評価に変えることで、主観と制度が共存できます。
まとめ:評価の“ズレ”は、見える化と対話で整えられる
「なんとなくズレている気がする」それは、現場の感覚で済ませるべきものではなく、採用の質を底上げするための重要なサインです。
面接官ごとの評価のズレには、必ず原因があります。
本記事でご紹介したように、評価のズレは仕組みで整えることができる課題です。
- データと対話でズレを共通課題に変える
- 活躍人材像をもとに評価観点を明文化する
- 面接評価シートや対話機会でブレを防ぐ
- 第三者視点やツールを使って“仕組み化”を加速させる
こうした一つひとつの取り組みが、「納得感のある面接」「ミスマッチのない採用」につながっていきます。
面接の質は、評価の透明性で決まる。
採用の現場にそんな共通認識を根づかせるために、まずは小さな違和感から向き合ってみませんか?
\ 評価の見直し、今すぐ始めたい方へ /
評価項目のすり合わせにすぐ使えるテンプレートを無料配布中です。
面接の“感覚ズレ”をなくし、共通言語での判断を進めたい方は、ぜひご活用ください。
「自社でも整えたいけど何から始めるべきか分からない…」という方は、お気軽にご相談ください。
この記事の監修者:
1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。