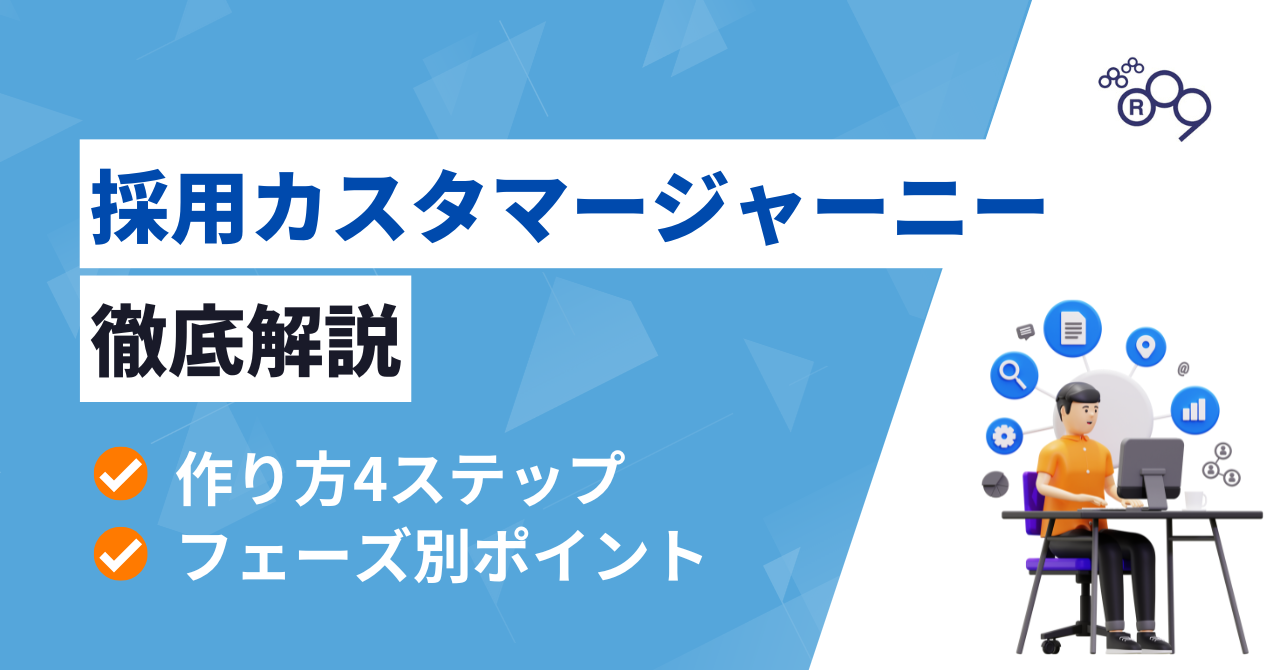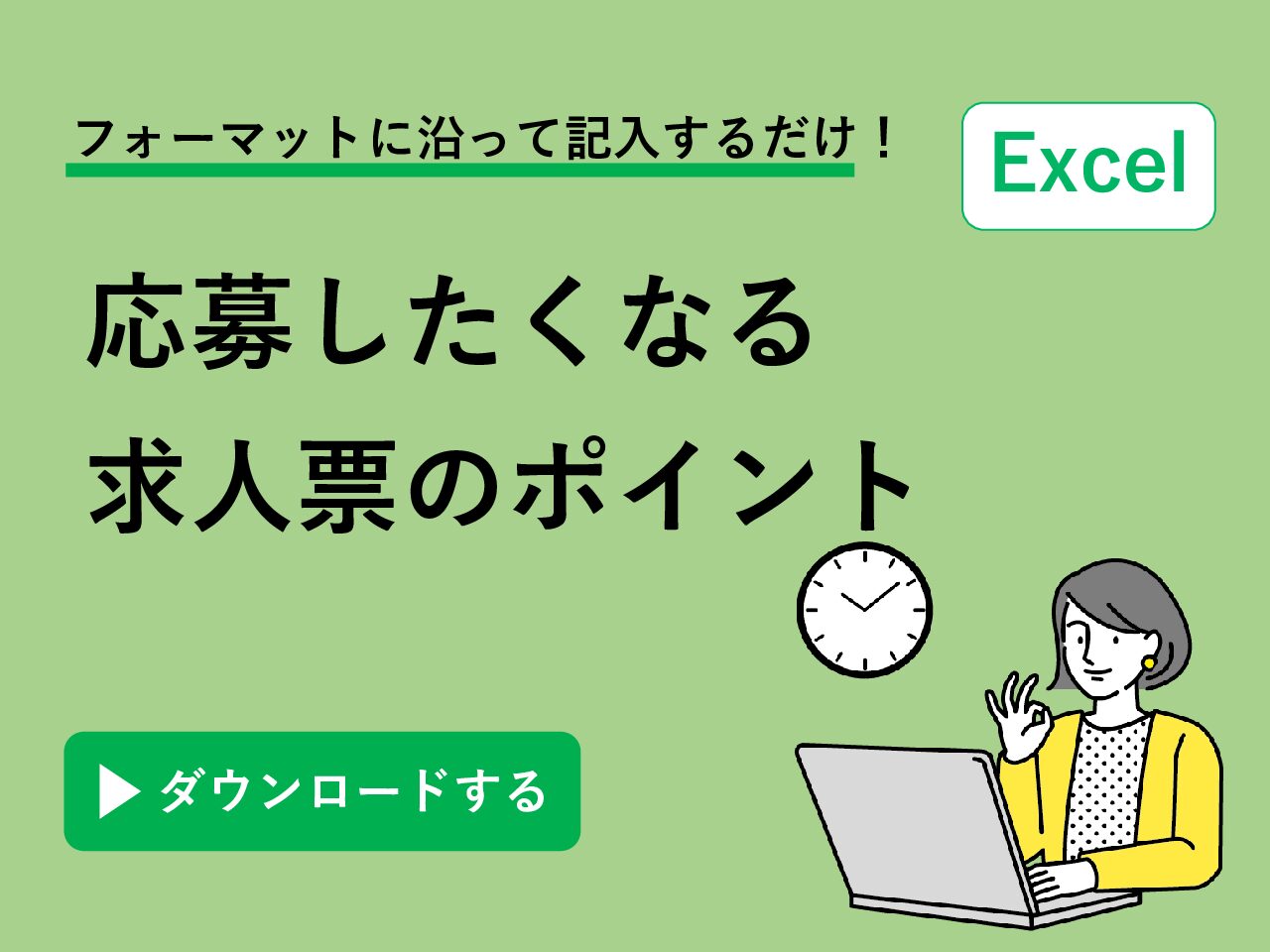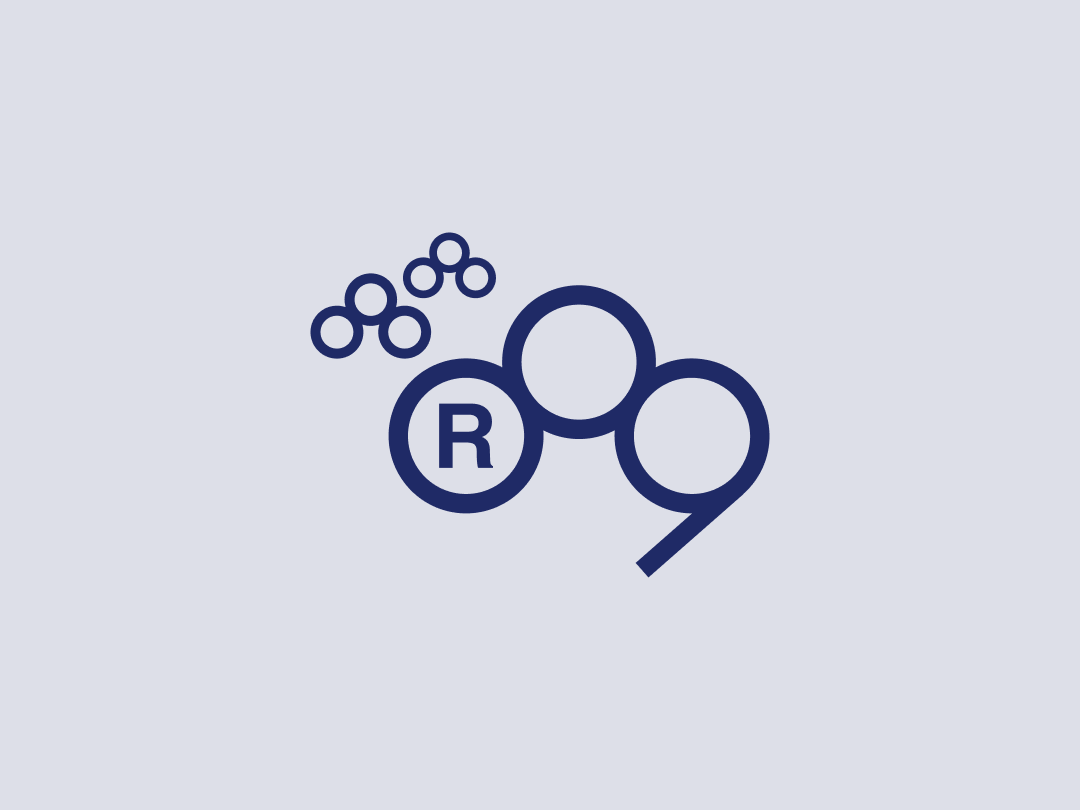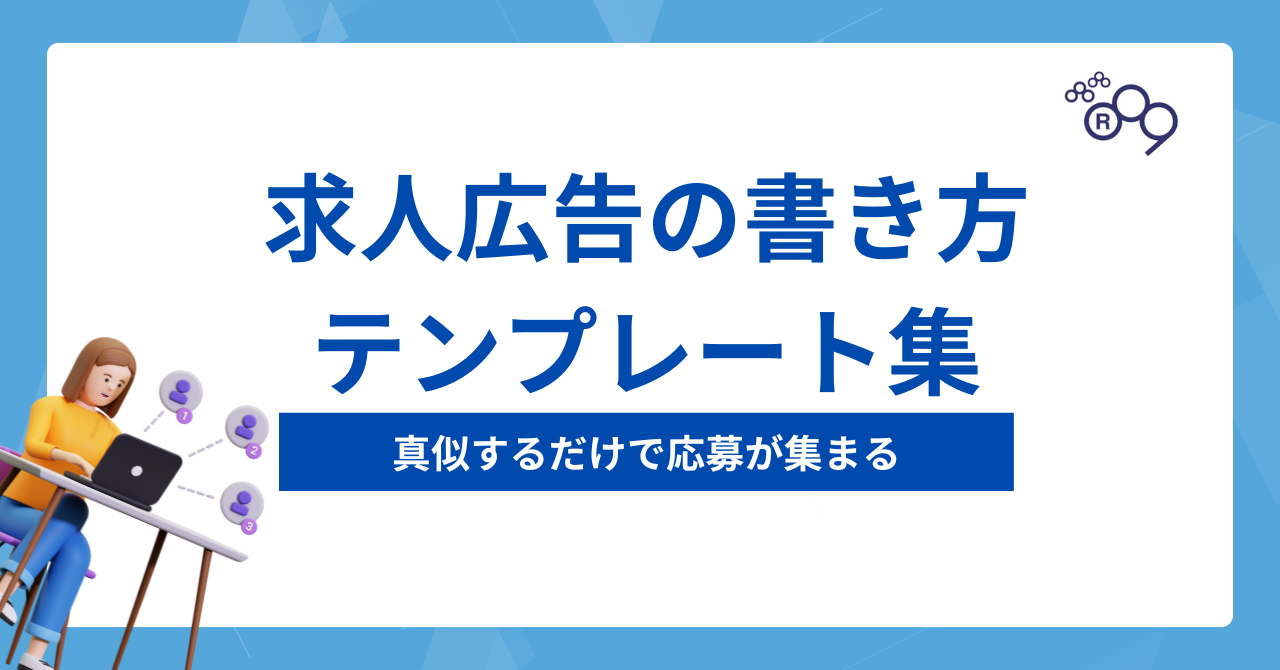【事例あり】会社の魅力を伝えるには?言語化するための3ステップ
公開日: 2025年09月03日 | 最終更新日: 2025年11月11日
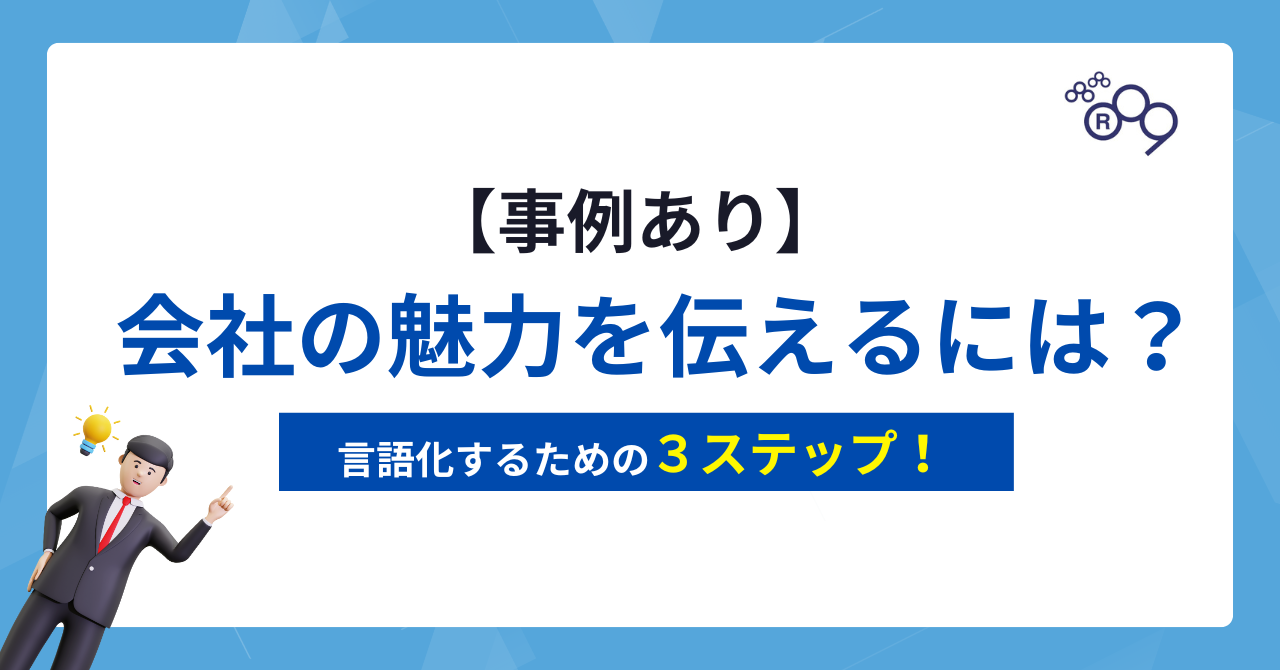
現代は、企業が候補者を「選ぶ」時代から、候補者に「選ばれる」時代へとシフトしています。そんな中で、他社と差をつける鍵となるのが企業が持つ“魅力”を、わかりやすく、かつ共感を呼ぶ言葉で伝えることです。
「会社の魅力」をただ羅列するだけでは反応は得られません。採用における成果に直結するのは、“候補者が得られる価値”を言語化する取り組みです。
本コラムでは、そんな「会社の魅力」を芯ある言葉に整理し、採用活動の成果につなげる方法を、3ステップでわかりやすく紹介します。また、会社の魅力を言語化したことで、採用を成功させた事例も紹介します。
なぜ「企業の魅力」を言語化する必要があるのか?
企業の魅力を言語化することは、採用活動において非常に重要です。自社の魅力を明確な言葉で表現することで、企業のブランドイメージを確立し、伝えたい相手に的確にメッセージを届けることができます。その企業がどのような価値観を大切にしているのか、どんな未来を描いているのかを発信することは、候補者にとって企業を理解する大きな手がかりとなります。
また、候補者に企業の魅力がしっかりと伝われば、共感してくれる人材とのマッチングも高まり、ミスマッチの防止や定着率の向上にもつながります。
だからこそ、企業の魅力の言語化は「なんとなく」ではなく、丁寧に、戦略的に行うことが大切です。採用広報・求人票・面接など、あらゆる接点で一貫したメッセージを届けることで、企業の想いが確実に届きます。
企業の魅力が伝わらないと、候補者はなぜ離脱するのか?
採用活動において、どれだけ良い人材と出会えても「企業の魅力」がしっかりと言語化されていなければ、候補者は離脱してしまいます。
その理由は「よくわからない企業に、自分の未来を託すことはできない」からです。
魅力が伝わらないことで、 具体的には以下のような懸念が挙げられます
- 自分に合う企業なのか判断できない
- 他社と比べて魅力が見えず、選考の優先順位が下がる
- 働く姿がイメージできず、入社後のビジョンが描けない
- やりがいや成長機会がわからず、将来の展望が持てない
こうした状態では、候補者は安心して意思決定ができません。逆に、企業が大切にしている価値観や社風、やりがい、成長環境などをしっかりと言語化し、伝えることができれば、候補者は「ここで働く自分」を具体的にイメージできるようになります。
採用成功のカギは、「候補者に、企業の魅力をどう届けるか」にあります。ぜひ、言語化の質にこだわって、企業の魅力をしっかり伝えていきましょう。
魅力を「明文化」できていない企業が抱えがちな課題
企業の魅力を明文化していない場合、採用活動とブランディングに大きな課題が生じます。自社の魅力や価値観が言語化されていない状態では、候補者に必要な情報が十分に伝わらず、結果として採用のミスマッチや選考中辞退・内定辞退が発生しやすくなります。
採用活動で起きる課題
- 候補者に魅力をアピールできない:何が魅力なのか、どんな価値を提供できる企業なのかが不明確なため、候補者に伝わらない
- 他社との差別化ができない:企業独自の強みが明文化されていないと、数ある企業の中に埋もれ、印象に残らない
- 求めるターゲットに届かない:自社が求める人物像やマッチする価値観が言語化されていないことで、ターゲットが曖昧になり、興味を引けない可能性がある
- 採用後のミスマッチが発生する:企業理解が浅いまま入社した結果、「思っていた企業と違った」というギャップが生じ、早期離職の原因になる
企業ブランディングで起きる課題
- ブランドイメージの一貫性がない:社内外への発信内容に統一感がなくなり、企業イメージがぼやけてしまう
- 信頼関係が築きにくい:何を大切にしている会社なのかが見えにくく、候補者との信頼構築にも影響する
企業の魅力を言語化することは、単に言葉にするだけではありません。
「自社らしさ」を社内外で共有することで、候補者との共感が生まれ、採用の精度が高まります。また、企業としての一貫性あるメッセージが打ち出せるため、ブランド力の強化にもつながります。
そもそも「企業の魅力」とは何か?
企業の魅力とは、その会社が持つ強み・価値・他社にはない特徴のことを指します。
「この企業に関わりたい」「ここで働きたい」と候補者に思わせる、企業ならではの魅力的な要素のことです。企業の価値観や働く人の雰囲気や環境など総合的な企業らしさが含まれます。特に、企業理念・事業内容・働き方・社風は候補者の注目ポイントであるため具体的に記載できるようにしましょう。
候補者にとっての“魅力”とは?5つの視点で分解
ここでは、候補者が特に注目している企業の魅力5つのポイントを紹介します。
① 理念・ビジョン(共感や動機形成に直結)
企業の価値観や存在意義、目指す未来像に候補者が共感できるほど、入社への動機づけが強まります。特に、独自性のある理念や事業目的は他社との差別化につながりやすいです。
例:「〇〇な社会をつくる」「△△の常識を変える挑戦をしている」
② 働き方・制度(安心感・生活との両立)
ワークライフバランス(WLB)や柔軟な働き方は、今や多くの候補者が重視するポイントです。フレックス制度・リモート勤務・有給取得率・年間休日数などは、具体的に記載することで安心感を与えることができます。
例:「月の平均残業時間は15時間」「年間休日125日/フレックス導入」
③ 社風・組織風土(なじめるかどうかの判断軸)
職場の雰囲気や人間関係、コミュニケーションの文化は、「この企業に自分が合うか」を判断する重要な材料です。社風の背景や変遷(歴史・改革)を含めて説明すると、表面的ではない「らしさ」が伝わります。
例:「上下関係よりもチームワークを重視する文化」「創業以来、毎朝の“ありがとう共有”が定着」
④ 社員メンバー(リアルな職場像)
実際に働く上司や同僚、経営陣がどのような人なのかは、候補者にとって非常に気になるポイントです。 社員インタビューや日常エピソード、働く姿の紹介によって、リアルな働くイメージと親近感が湧きます。
例:「子育てと両立しながら活躍する社員の声」「20代で新規事業を任された入社3年目の社員紹介」
⑤ 労働・職場環境(働きやすさと生産性)
快適なオフィス環境、設備、チーム体制なども、働く上での満足度やパフォーマンスに影響します。具体的な制度や取り組み、業務の進め方などを伝えることで、候補者の不安を解消できます。
例:「1on1面談を月1回実施」「業務ツールやシステムを定期的に改善」
これらの5つのポイントは、候補者が「ここで働きたい」と思うかどうかに大きく影響します。 採用担当者は、自社では当たり前になっている魅力を言語化し、具体的に伝えることが重要です。
企業の魅力はどう定義づけするのか?
企業の魅力を理解したら、次のステップは「魅力の定義づけ」です。これは、企業の強みや個性を明確にし、誰が見ても「この会社はこういう価値を持っている」と伝わる状態にすることを意味します。 採用活動においては、単なる情報発信ではなく、「自社らしさ」をしっかりと言語化することが候補者に伝わる鍵となります。
魅力の定義づけは以下のステップで行います。
① 自社の「らしさ」を洗い出す
まずは、企業の本質的な価値や特性を見つめ直します。
内部メンバーだからこそ見えている魅力に気づくための問いかけが重要です。
- なぜこの企業が生まれたのか(創業の想い)
- 自社はどんな価値を社会や顧客に提供しているのか
- どんな文化・風土があり、どこが競合と違うと言えるのか
② 外部視点を取り入れる
自社の中だけで考えると、「当たり前」が「魅力」だと気づけないことがあります。
だからこそ、外部の声から見える魅力や評価ポイントを把握することが重要です。
- 候補者や顧客は、何に惹かれてこの会社に興味を持っているのか
- 信頼や好感を持ってくれているポイントは何か
- 面接や商談でよく質問されることは何か
外部の視点を取り入れるのは、思っている以上に難しいことです。その中で自社の魅力を客観的に見つめ直すためには、採用代行会社やコンサルティング会社といったプロに見てもらうことができます。
そういった企業は、数多くの企業を見てきた専門家であり、第三者だからこそ気づける視点や、自社では当たり前になっている魅力を言語化してくれる力を持っています。
魅力の言語化に不安を感じているなら、一度利用してみることも良い方法かもしれません。
③ 言語化して整理する(本質を形にする)
最後に、自社の魅力が伝わる言葉に落とし込んでいきます。
抽象的な表現ではなく、共感や納得を得られるストーリーやキーワードにすることがポイントです。
- 自社らしさを象徴するキーワードやエピソードを集める
- それをもとに、タグラインやステートメントをつくる
※タグライン:企業やブランドのコンセプトや価値を短いフレーズで表現したもの
※ステートメント:理念やビジョン、ブランドイメージなどを簡潔に表現するもの
企業の魅力を定義づけるとは、単なるスローガンを作ることではなく「企業の本質を考えて伝える準備をすること」になります。このプロセスを行うことで企業の共感力が高まります。
自己満足型の魅力発信を避けるためのチェックポイント
企業が「これがうちの魅力だ」と思っていても、それが候補者にとっての魅力とは限りません。
採用活動で魅力を伝える際に陥りやすいのが、「自己満足型の魅力発信」です。せっかく魅力を言語化しても、それが伝わらなければ意味がありません。
ここでは、魅力を「候補者に響くカタチ」で伝えるための4つのチェックポイントをご紹介します。
① 候補者目線で魅力が語られているか?
企業視点だけでなく、「相手にとっての価値」に変換できているかを確認しましょう。
- 悪い例:フレックスタイム制
良い例:子育てやプライベートの予定に合わせて柔軟に働ける環境
制度そのものを並べるのではなく、それによってどんなメリットが得られるのかを候補者目線で表現することが大切です。
② 採用競合と比べて“自社らしさ”が伝わっているか?
他社と似たような表現ばかりになっていないか、差別化できているかを見直しましょう。「風通しがいい」「若手が活躍」など、どの会社でも言えてしまう言葉では、印象に残りません。
- 自社にしかない文化や取り組み
- 社員の行動特性やチームの雰囲気
- 独自の成長支援や評価制度 など
「らしさ」を引き出す具体的な事例や言葉で語ることで、他社との差別化が生まれます。
③ 「ここで働くと何が得られるか」が具体的に書かれているか?
候補者は「ここに入社したら、どんな経験ができて、どんな未来が描けるのか」を知りたいと考えています。
- 先輩社員の実際の声を紹介する
例:新卒社員が感じた入社理由、ギャップ、やりがい - 中途社員の転職理由と比較視点を加える
例:前職と比べて良かった点、企業に感じる魅力や安心感
社員のリアルな言葉を通じて、自社で働くことの具体的なメリットを伝えましょう。
④ 魅力が「発信内容と実態」で一致しているか?
伝えている内容と実際の職場環境や社風が乖離していると、入社後のギャップや企業イメージの低下につながります。
- メッセージと行動に一貫性があるか?
- 社員もその魅力を日常的に感じているか?
- 魅力を裏付けるエピソードや具体的な体験談があるか?
企業が「良い」と思っている魅力が、そのまま候補者に響くとは限りません。だからこそ、「誰に伝えるのか」「何が刺さるのか」を常に意識し、外部の視点やリアルな声を取り入れることが、魅力の「自己満足化」を防ぐための鍵です。
「企業の魅力」を言語化する3ステップ
前の項目でもお伝えしたように、魅力の言語化は「良いところ」を列挙することではありません。企業の魅力は、社員の声や日々の行動、組織の文化の中にあります。そのため、魅力を見つけて候補者に伝わるように「具体性」と「戦略性」を持たせ、整理・表現することが重要です。
企業の魅力の定義づけの部分で、「自社らしさ・外部視点・言語化して整理する」ことをお伝えしました。それに加えて、企業の魅力を言語化する上で大切なことは、目的・ターゲットを明確にすることです。
「誰に向けて魅力を言語化するのか?」「何を目的にして言語化しているのか?」を明らかにすることが重要になります。この2つが曖昧な場合、言葉もぼやけてしまいます。たとえば以下のように、誰に向けて、何を目的にしているのかを具体化していきましょう。
例:
誰に向けているのか→「20代で成長意欲の高い人材に、裁量と挑戦機会が多い環境であることを伝えたい」
目的→成長意欲の高い若手の応募を増やすこと
さらに、企業内で実践できる魅力を見つける方法を3ステップで紹介します。
Step1|活躍社員を起点に魅力を洗い出す
活躍している社員の背景や価値観を深堀りすることで、企業の魅力が自然と浮き彫りになります。企業の魅力を見つける上で、「実際に活躍している社員」を起点にする方法は、最も信頼性が高く実践的です。
実際に成果を出している社員には、企業の価値観や文化とフィットしている共通点があり、そこには自社らしさ=企業の魅力が詰まっています。
活躍している社員を見極めるためには、活躍の基準や定義があるとわかりやすくなります。
例えば、
- 成果の達成、質と量ともに高い成果を出している
- チームや部署など、組織の目標達成に貢献している
- 自ら課題を見つけて動き、自律的に学び成長している
- 理念や指針に共感し、自社らしさを社内外に体現する行動をしている
- 企業や組織内外で円滑なコミュニケーションを図り、情報共有や意見交換を活発に行っている。
活躍社員は企業や組織によって異なる場合もあります。そのため、自社の組織文化や求める人材像を明確にしたうえで活躍社員を決めていくことが大切です。
Step2|社内ヒアリングで“らしさ”を抽出する
企業の魅力や「自社らしさ」を言語化する際に効果的なのが、社内ヒアリングの活用です。
実際に現場で働いている社員の声を集めることで、経営層や人事だけでは見落としがちなリアルで共感性の高い魅力を引き出すことができます。
ここでは、社内ヒアリングを通じて企業の「らしさ」を抽出する具体的なステップをご紹介します。
①ヒアリング対象を意図的に分ける
さまざまな立場・年代の社員に話を聞くことで、多角的な視点から共通する価値観や文化が見えてきます。
| 対象者 | 抽出視点 |
| 若手 | 入社理由、ギャップ |
| 中堅 | 成長環境、文化、リーダー像 |
| ベテラン | 歴史、変化、価値観 |
| 経営層 | ビジョン・未来像 |
②価値観や日常が浮かび上がる質問設計
抽象的な質問ではなく、実体験に基づく具体的なエピソードを引き出せる質問が効果的です。
効果的な質問例(感情・行動・背景を引き出す)
- 「最近、会社らしいなと感じた出来事は?」
- 「入社して驚いた“文化的な習慣”はありますか?」
- 「会社で“いいな”と思う瞬間は?そう感じた理由は?」
- 「前職と比べて、この会社でよかったと思える点は?」
- 「これまでで一番成長を実感できた経験は?」
避けたい質問(抽象的すぎて曖昧になりがち)
- 「会社の魅力はなんですか?」
- 「働きやすいと感じるのはどんなところですか?」
ポイントは、「いつ・どこで・なぜそう思ったか」といった行動と感情をセットで引き出すことです。
③共通するキーワードや価値観を整理する
ヒアリング内容を以下のようにキーワード単位で整理・可視化します
- 頻出する言葉や表現(例:「挑戦」「フラット」「任される」など)
- 共通する行動パターンやエピソード
- 他社にはない自社独特の文化や価値観
この段階では、“良い話”を並べるのではなく、自社らしさを裏付ける共通項を見極めることが大切です。
④抽出した「らしさ」を社員に検証してもらう
整理した魅力やキーワードを社内にフィードバックし、社員自身に「本当にそう思うか?」を確認します。
- 「この言葉は自分たちに合っているか?」
- 「実際に日常で体現できているか?」
- 「他社と比較しても自社らしいと言えるか?」
社内で共感・納得を得られた言葉こそが、外部にも伝わる本物の魅力になります。
社内ヒアリングは、企業の内側から見える魅力を言語化するための強力なツールです。
制度や理念だけでなく、日々の何気ない出来事や社員の実体験からこそ、企業のリアルな「らしさ」が出てきます。
採用に活かす魅力づくりの第一歩として、ぜひ「社内の声」を丁寧に聞くヒアリングを実践してみてください。
Step3|競合と比較して「相対的な強み」を見つける
競合と比較して自社の「強み」を明らかにすることは、採用ブランディングや応募者への説得力のある訴求につながります。
相対的に自社と競合他社を比較する方法として「ポジショニングマップ」というものがあります。ポジショニングマップとは、2つの評価軸で自社と競合他社を可視化するフレームワークです。これを採用領域で活用すると、次のような利点があります。
① 相対的な強みが明確になる
- 自社の「特徴的なポジション(立ち位置)」が見える
- 競合が多い中で差別化ポイントを発見しやすくなる
② 採用メッセージに一貫性が生まれる
- どんな人材に何を訴求すべきかが明確になり、 メッセージの軸がブレなくなる
- 求人票、面接、スカウト文などのトーンを統一できる
③ 社内の共通認識が作れる
- 採用チーム・現場メンバーとの間で、「うちの強みは何か?」の共通言語ができる
- 上司や経営層への説明・提案材料としても有効
④ 候補者に“選ばれる理由”を伝えやすくなる
- 他社と比較検討する候補者に対して、「だからこの会社が自分に合う」と納得してもらえる
続いて、実際に採用に使用できるポジショニングマップを4つ紹介します。
① 【自由軸型ポジショニングマップ】
任意の2軸(例:「裁量の大きさ」×「働きやすさ」)で自社と競合を比較
メリット:
- 最も採用で使いやすい
- ターゲット人材の重視ポイントと、自社の特徴をかけ合わせて設定できる
例:
横軸:裁量の大きさ(少 ←→ 多)
縦軸:働きやすさ(しっかり ←→ 柔軟)
② 【3C分析 × ポジショニング】
自社(Company)、競合(Competitor)、候補者(Customer)の3者視点で整理
メリット:
- 「候補者のニーズ」と「競合にない強み」の交差点を探せる
- ポジショニングマップに変換すると、訴求軸が見つけやすい
③ 【SWOT分析 × マッピング】
自社の強み・弱み(Strength/Weakness)と、外部環境(機会/脅威)を分析し、ポジションを定義
メリット:
- 自社の優位性を言語化しやすくなる
- 強みをポジショニングマップの軸に転換することも可能
④ 【VRIO分析 × 差別化整理】
自社の経営資源が「価値(Value)、希少性(Rarity)、模倣困難性(Imitability)、組織(Organization)」を満たすかを評価
メリット:
- どの強みが“競合にはない優位性”になりうるかを判断できる
- 採用ブランディングの「競合優位性」の根拠づけに有効
ポジショニングマップは採用戦略の起点となります。「伝える前に、位置を定める」ために、ポジショニングマップは非常に有効です。
- 採用ブランディングにおける訴求ポイントの明確化
- 他社と比較した差別化メッセージの発見
- 採用チーム内での共通認識の形成
- 候補者への納得感ある説明・共感の創出
上記4つのことを意識して戦略を立てていきましょう。
魅力を伝えるコンテンツへの落とし込み方
これまで企業の魅力を言語化してきたとしても、それをただまとめただけでは候補者の心には届きません。大切なのは、その魅力を「誰に・どこで・どう伝えるか」を考え、伝え方を工夫することです。
候補者は複数のチャネル(媒体・SNS・面接など)を通じて企業を見ています。だからこそ、どのチャネルでも一貫性を持ちながら、それぞれに合った伝え方をすることが必要です。以下では、主な発信チャネルごとの役割や表現のポイントをご紹介します。
求人票で魅力を伝えるには?ありがちなNG表現と改善例
求人票は、候補者が最初に企業に触れる重要な接点です。しかし、「どこにでもある表現」や「抽象的な言葉」では、候補者の心には届きません。
求人媒体の役割は候補者との最初の接点をつくることです。ポイントは、候補者に興味をもってもらう“きっかけ”を作ることです。限られたスペースの中で魅力を端的に伝える必要があります。
掲載するべき内容例:
- 他社との違いが分かる強み・特徴
- 「働くことで得られるメリット」を明確に
- 社員の声や実績を数字で見せる
また、採用力の高い企業は、求人票で次の3つを徹底しています
- 具体性がある
- 自社ならではの独自性がある
- 読み手(候補者)視点でメリットが伝わる
以下に、よくあるNG表現と改善ポイントを具体例とともに紹介します。
①抽象表現では伝わらない:「具体的な職場の様子」を描く
NG例:
- 風通しの良い職場です
- アットホームな雰囲気です
改善例:
- 「月1回の全社ミーティングで、若手から経営層まで意見交換を実施」
- 「社内カフェスペースで、部署を超えたランチ会や交流が日常的に行われています」
②法律で義務付けられている内容は“魅力”にならない
NG例:
- 社会保険完備
- 交通費支給
改善例:
- 「週2日のリモート勤務・副業OKなど、柔軟な働き方を制度化」
- 「年間30万円までの研修・セミナー費用を会社が全額負担」
③感覚的な言葉ではなく、「数字」や「事例」で裏付ける
NG例:
- やりがいのある仕事です
- 成長できる環境です
改善例:
- 「新卒入社1年目で商品企画に抜擢され、ヒット商品を開発した社員も」
- 「社員の7割が20代。入社2年でチームリーダーを任された事例もあります」
④誰にでも当てはまる理想像ではなく、「実在の人物像」で惹きつける
NG例:
- 「主体性があり、コミュニケーション力のある社員が活躍」
改善例:
- 「元アパレルスタッフの社員が、未経験から3カ月で営業目標達成。今では後輩育成も担当しています」
- 「挑戦する姿勢を評価する風土があり、提案から実行まで任されている社員も居ます」
⑤待遇面は「実績・制度」で信頼性を
NG例:
- 高収入可能!
- 頑張り次第で稼げます!
改善例:
- 「未経験スタートの平均月収32万円(2024年度実績)」
- 「インセンティブはチーム評価+個人実績で還元。昨年度は全体の8割が支給対象でした」
| チェック項目 | 確認ポイント |
| 具体性があるか | 数字・制度・実例で構成されているのか |
| 独自性があるか | 他社にも言える内容ではないか |
| 候補者視点になっているか | 入社することで何が得られるかが明確か |
| 信頼性があるのか | 誇張やあいまいな表現は使っていないか |
求人票は単なる募集要項ではありません。企業の魅力を端的に伝える採用ブランディングの第一歩です。
表現を少し工夫するだけで、読み手の印象は大きく変わります。自社のらしさや実態が伝わる求人票を作ることで、ミスマッチを防ぎ、共感を生む採用につながります。
スカウト文・採用サイト・面接で伝えるべきこと
①スカウト文
スカウト文は候補者と企業の出会いの段階となり、候補者が興味を引くような文章を書くと効果的です。この段階では、候補者はまだ企業のことを知らないため、他社と比較される前に「ちょっと気になる」と思ってもらえるかが鍵です。
伝える内容の役割:
- 「なぜあなたに声をかけたのか」: パーソナルな特別感を感じてもらうことができる
- 「企業の魅力」:短くても惹かれる”自社らしさ”を伝える
- 「アクションの提示」: カジュアル面談を行いませんか?など、次のステップへのアクションを促す
ポイント:
「あなたに送っている」ということが伝わるような特別感を出すことが大切です。また、次のステップを提示する際は負担を感じさせないように「カジュアルに」「一度お話してみませんか?」など気軽さを強調することで、候補者のハードルが低くなります。
② 採用サイト
採用サイトは企業の想いやストーリーを深く伝えるところであり、候補者の理解と共感を得ることがポイントとなります。興味を持った候補者は「この企業ってどんなところ?」と調べ始めます。ここで企業の理念や価値観を伝えることで応募意欲を高めることができます。
伝える内容の役割:
- 「理念・価値観・歴史」: 企業の背景に共感してもらえる
- 「働く人・職場の雰囲気」:自分が馴染めるのかの判断材料にしてもらえる
- 「キャリアパスや制度」: 自分にとっての将来性を想像しやすくする
ポイント:
仕事内容やキャリアパスは特徴やなぜやるのかを具体的に書くことで候補者からの共感を得ることができます。また、写真や動画を活用することでより企業の雰囲気やイメージが掴みやすくなります。
③ 面接
面接は「候補者から志望者になる」ための重要な転換部分です。候補者とリアルに向き合い入社意欲を高めることが大切です。また、一方的に情報を与えるだけでなく、双方でコミュニケーションをとり「ここで働きたい」と思ってもらうことを意識しましょう。
伝える内容の役割:
- 「ネットに載っていないリアルな情報」:面接でしか得られない特別感を感じてもらう
- 「人やチームの雰囲気」:実際に働くイメージが湧くような情報を伝える
- 「不安の先回り解消」: よくある質問に先回りして応える
ポイント:
双方向の会話で候補者の理解と納得感を深め、「ここで働きたい」と思える体験を提供しましょう。また、候補者に合わせて柔軟に話す内容を変えることで圧迫感や不安を与えることなくコミュニケーションをとることができます。
実際に「会社の魅力」を言語化して改善につながった事例
「事業内容が伝わりづらい」「社員の雰囲気が見えない」「面接まで進んでも、候補者と噛み合わない」
そんな採用の悩みを抱える企業は少なくありません。特に、知名度が高くない企業や、事業が複雑・専門的な業種では、応募者に自社の魅力や実態が十分に伝わらず、ミスマッチにつながることもあります。
そうした課題を抱えていた企業が、「事業内容の言語化」「社員のリアルな声の活用」に取り組み改善した事例を紹介します。
IT系企業|事業内容の言語化で母集団の質が向上
「何をしている企業か分からない」と言われていた状況から脱却した改善事例を紹介します。
事例:Fintech系IT企業
課題:創業初期、社名やロゴから事業内容が想起しにくく、
・「お金の会社?」
・「何のサービスをしているのかよくわからない」
と認知されにくい状態が続いていた。
改善ステップ
① ストーリー設計の再構築(自社の「存在意義」から言語化)
- 自社のミッションに立ち返り、単なる家計簿アプリではなく、「バックオフィス支援を通じた中小企業支援」という軸を明確にした。
② サービスのカテゴライズを見直し
- 単一プロダクト(家計簿アプリ)のイメージから、「BtoB向けSaaSサービス群を展開するFintech企業」へ。
- それぞれのサービスに明確な役割・ネーミングをつけ、公式サイトや採用ページで用途と対象を明確化する。
③ 採用広報における言語・図解の見直し
- 「何をしている会社か分からない」を防ぐため、企業説明資料(いわゆる採用ピッチ資料)を刷新。
- ビジネスモデルを図式化し、「どんな価値を誰に提供しているか」を一目で伝わる構成に。
④ 社名だけでなく「タグライン」を併用
- 採用や登壇、展示会で自社と事業内容や強みがすぐ伝わるよう、
「社名+説明文」を常にセットで発信。
成果:
- 採用候補者や取引先の理解度が高まり、面談時の「何をしてる会社?」という質問が減少。
- SaaS企業としての認知が急上昇し、SaaS業界でのポジショニング確立。
- スタートアップ界隈で「ピッチ資料が参考になる企業」として認知拡大。
製造業|社員の声を活用した採用コンテンツで志望度が向上
「人の魅力」を社員インタビューやメッセージ動画で表現し、内定辞退が減少した例
事例:製造業向けERPの開発会社
課題:業務内容が堅そう・地味そうと見られ、「どんな人が働いているのか見えない」状態で、内定後も不安を抱く学生が多く、辞退者が一定数発生していた
改善策:
① 「人の魅力」特化のインタビューページを設置
- 年齢・経歴・性格が異なる複数名の社員にインタビューし、「なぜこの企業に?」「入社前と後のギャップ」など感情が伝わる話題に絞って構成
- 単なる「仕事内容紹介」ではなく、価値観や成長の実感にフォーカス
② 動画メッセージで「人柄・雰囲気」を見せた
- 内定者向けに配信する動画を、「会社紹介」から「人の温度感が伝わる内容」に変更
- 先輩社員がざっくばらんに話すオフ寄りの雰囲気
- マネージャーが素の言葉で応援メッセージ
- 形式ばった動画ではなく、スマホ撮影+字幕編集で「素朴さ」を出した
③ 「人」を軸にした採用イベントの開催
- 技術職や営業職の若手社員との座談会イベントを実施
- 一方的な説明でなく、候補者の不安や本音を受け止める時間を設けた
成果:
- 内定者からの感想:「堅そうな企業だと思っていたけど、人が親しみやすかった」
- 動画を見て「人に惹かれて入社を決めた」という声が複数出た
- 内定辞退率が前年より20%以上改善(特に技術職の学生に効果が大きかった)
中小企業|競合比較で“らしさ”を発見し、候補者とのミスマッチ解消
「待遇や知名度では勝てない」企業が、独自の文化・働き方にフォーカスして成功した事例を紹介します。
事例:IT系中小企業
背景と課題:
- 従業員数30名程度の中小企業(クラウドサービス・業務効率化支援)
- 給与水準は大手IT企業に劣り、社名も知名度が低かった
- 「待遇・ブランドで勝てない中でどう採用するか」が課題
独自の打ち手:「働き方の透明化 × 自律文化の発信」
① 全社員フルリモート・フルフレックスを早期導入(2011年〜)
- コアタイムなし、出社義務なし、全国どこでも勤務OK
- 「企業にいる時間」ではなく「成果」と「自己管理能力」を重視
② “自律”を軸にした文化を発信
- 「自由に働ける企業」ではなく、「自律できる人が集まる企業」
- 社員インタビューやブログで、自由と責任のバランスをリアルに紹介
- カルチャーを採用基準とし、共感しない応募者はあえて選ばない姿勢
③ 給与・制度ではなく“価値観の共鳴”をアピール
- 「働くこと=自己実現の手段」という考えを軸にし、
志向性の合う人材にだけ深く刺さるメッセージを発信
成果:
- 大手企業の内定を辞退して入社する人も出現
- 働き方を見て「ここで働きたい」と応募が増加
- 離職率が大幅に低下し、高定着・高生産性チームが実現
まとめ|魅力づけは「伝え方」より「設計と整理」が先
これまでの内容をまとめると、採用活動における魅力の伝え方の設計と整理は、
「ターゲットを明確にする、自社の魅力を自社らしさを含めて言語化する、採用段階ごとに伝える内容を決めること」が大切になります。
採用における魅力づけというと、「どんな言葉で伝えるか」「どんな媒体で発信するか」といった“伝え方”に注目が集まりがちです。もちろんそれも大切ですが、本当に効果的な魅力発信を行うには、その前段階である「何を」「誰に」「どのように伝えるか」という魅力の設計と情報の整理が不可欠です。
魅力が曖昧なままでは、どんなに言葉を工夫しても候補者には響きません。逆に、しっかりと自社の強みや価値を整理し、ターゲットに合わせて設計された内容であれば、シンプルな言葉でも十分に伝わります。
採用成功のカギは、表現テクニックよりもまず、「伝える内容そのもの」をいかに見つけ出し、整えるかにあります。
明日からできる3ステップ
明日からできる採用改善ステップを3つ紹介します。
①求人情報を見直す:具体的内容であるか、どんな人に向いているのかなど魅力が伝わりやすい文章か確認する
②面接でリアルな情報を伝える:質問に答えるだけになっていないか、ネットに載っていない情報を伝えているのかチェックする
③現場と魅力を再確認する:社員インタビューを実施して採用サイトや面接の話材に活用する、より説得力を持たせる内容にする
よくある質問とつまずきポイント
採用活動において、候補者の方をはじめ、現場や経営層など、さまざまな立場からの質問があります。
以下に、よくあるご質問をカテゴリごとに整理しました。
①候補者からよくある質問
| カテゴリ | 主な質問例 |
| 仕事内容 | ・具体的にどんな業務を担当するのか? ・1日の仕事の流れは? |
| キャリア・成長 | ・キャリアパスはどうなっているか? ・評価や昇進の基準は? |
| 働く人 | ・どんな人が多いのか? ・上司やチームメンバーの雰囲気は? |
| 職場環境 | ・残業はどのくらいか? ・リモート勤務は可能か?・服装や働き方の自由度は? |
| 福利厚生 | ・福利厚生は何があるか? ・産休・育休は取りやすいか? |
| 社風・文化 | ・どんなカルチャーか? ・中途社員はなじめるか? |
| 入社後の支援 | ・研修制度は? ・困ったときの相談先は? |
| 選考・評価 | ・面接で重視されるポイントは? ・選考結果はいつ頃出る? |
②経営陣・現場社員から採用担当への質問
| カテゴリ | 主な質問例 |
| 採用ニーズ | ・どんな人材がほしいのか明確になっているか? ・今のチームに足りていないスキルは? |
| 選考基準 | ・どんな観点で評価するのか? ・面接で何を見てほしい? |
| 採用活動の内容 | ・どこに求人を出しているのか? ・スカウト文や求人票はどんな内容? |
| 現場の負担 | ・面接や説明会の準備って大変? ・どこまで関与すればいいの? |
③経営・人事担当者が自問するべき
| カテゴリ | 主な質問例 |
| 採用目的の明確化 | ・なぜこのポジションで採用が必要なのか? ・採用が会社全体にどう貢献するか? |
| 魅力設計 | ・自社の魅力は何か?他社と何が違うか? ・候補者に刺さるように伝えられているか? |
| 求人の精度 | ・求人票はターゲットに合っているか? ・抽象的な表現ばかりになっていないか? |
| 選考体験 | ・候補者にとって「丁寧で信頼できる対応」になっているか? |
| 内定辞退対策 | ・候補者の不安を事前に聞けているか? ・オファー時に納得感ある提案ができているか? |
採用改善を進める際、多くの企業が現場(現場社員・現場マネージャー)との連携に課題を感じます。現場は候補者にとって「一緒に働く未来の仲間」であり、採用の質・成功に直結しますが、以下のような「つまずきポイント」がよく見られます。
① 採用の目的や背景が現場に共有されていない
- 「なんでこのタイミングでこのポジション?」が分からない:目的や期待値が不明なまま面接に臨むと、質問がズレたり熱量に差が出る
改善ポイント:
最初に「採用の背景」と「この人が入ると現場がどう良くなるか」を共有する
②面接準備や対応が「片手間」になっている
- 面接官が候補者情報を読んでおらず、場当たり的な質問ばかり
- 忙しさを理由に、面接が「ただの確認作業」に
改善ポイント:
- 事前に5分で読める「面接官向けシート(候補者概要+確認したい観点)」を共有
- 面接官研修 or フィードバック機会を1度でも設けると大きく改善
③採用は人事の仕事、という意識が強い
- 採用協力が「業務外」という認識があり、受け身になりがち
- 自分たちのチームに人が来るにもかかわらず、関心が薄い
改善ポイント:
- 採用が「チームにいい人が入るための共同プロジェクト」であると伝える
- 採用成功事例を現場にフィードバックし、協力の意義を見える化する
本コラムの内容を参考に「自社の魅力」を整理し、適切な伝え方をすることで、「候補者から選ばれる企業」を目指しましょう。
この記事の監修者:
1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。