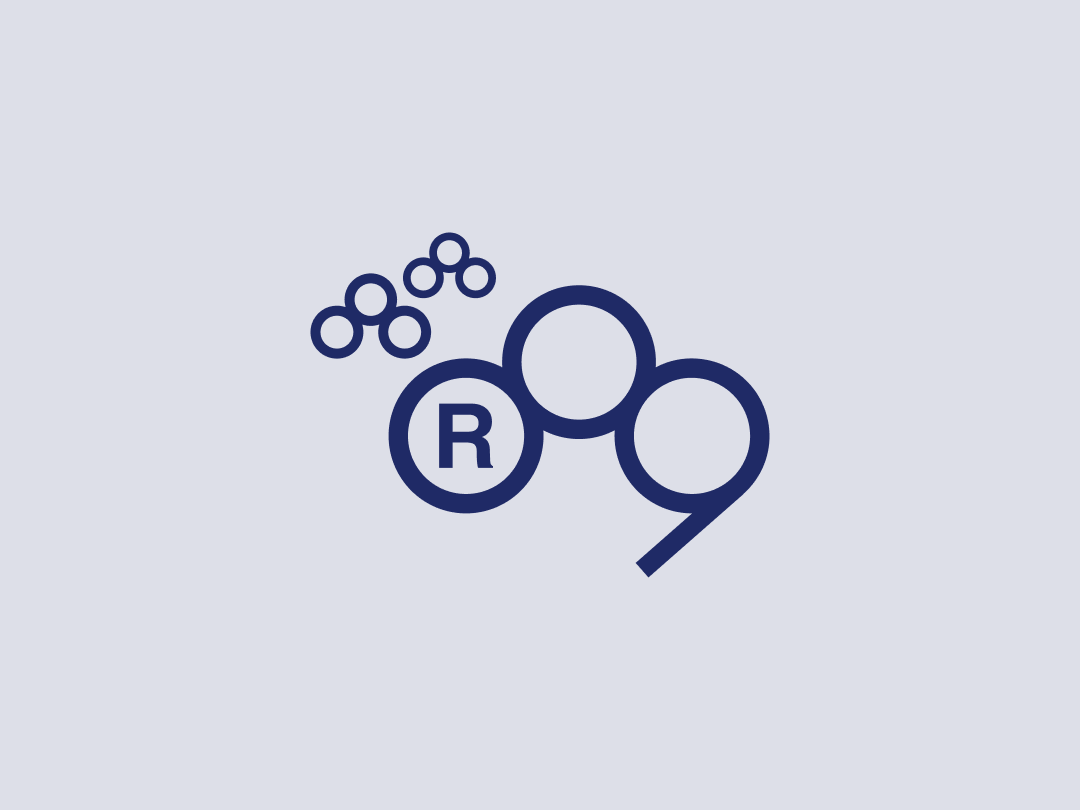新卒採用で心をガッと掴む座談会|答え方のポイント、質問例など徹底解説
公開日: 2025年09月05日
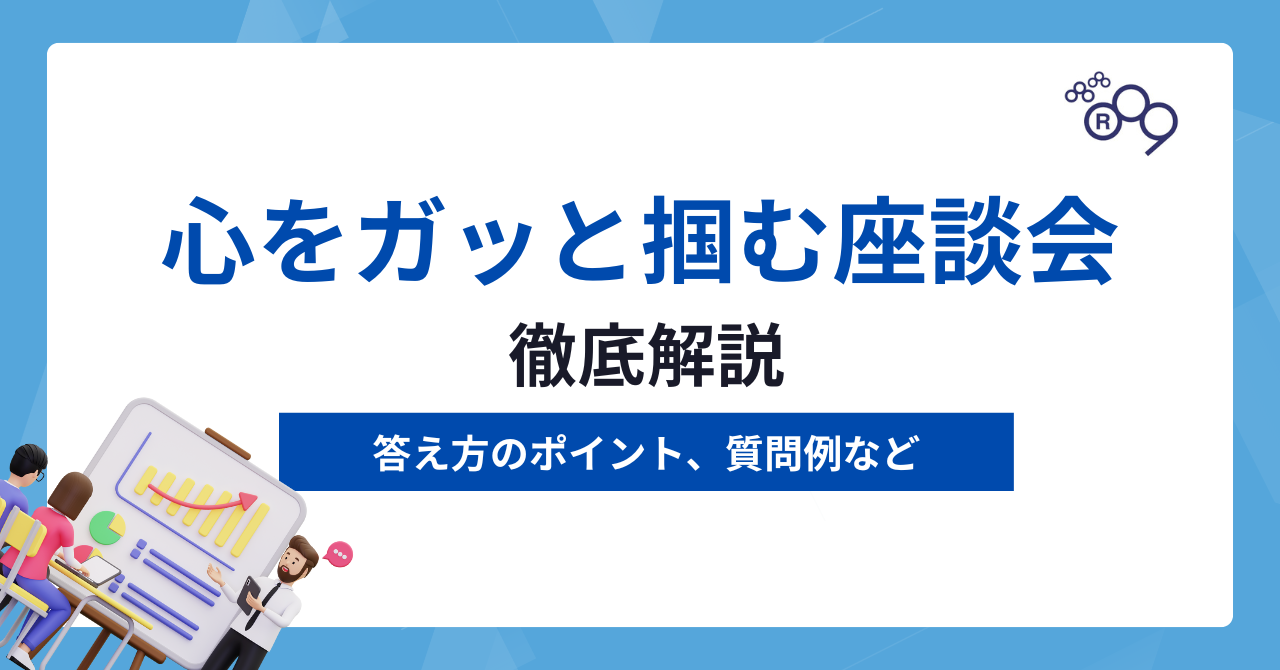
「せっかく座談会を開いても、学生の反応がいまいち…」
そんな悩みを抱える採用担当者は少なくありません。
採用座談会は、企業のリアルな魅力や“人の雰囲気”を直接学生に伝えられる、数少ない直接接点の場。うまく活用できれば、志望度の向上・辞退防止・エンゲージメント強化に直結する、強力な打ち手です。
しかし現実には、「社員が一方的に話して終わる」「制度説明ばかりで学生が飽きている」「選考になかなか繋がらない」といったもったいない失敗が多く見られます。
この記事では、学生の心をガッと掴み、志望度を一気に高める座談会の設計ノウハウを、豊富なデータ・具体例とともに徹底解説します。
「話す内容」だけでなく、「雰囲気づくり」「答え方のポイント」「学生が知りたい質問例」まで網羅してご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
そもそも採用における「座談会」とは?
まずは、採用における「座談会」とは何かについて解説していきます。
採用活動における座談会の役割と位置づけ
採用座談会とは、選考フローの一環またはプレイベントとして実施される、「社員と学生がざっくばらんに話す場」です。企業説明会や面接とは異なり、評価や合否には直接関係せず、学生が企業や社員に対して「リアルな情報」「人となり」「カルチャー」を感じられることが最大の目的です。
企業側にとっては、自社の魅力を言語化しにくい「雰囲気」や「人柄」を伝える貴重な場。一方、学生にとっては「志望企業と自分の相性を見極める」手がかりになるため、採用広報・歩留まり改善・辞退防止といった文脈で導入されることが増えています。
座談会は有効?データから見る学生の本音
実際に就活生にとって、座談会は有効なのでしょうか。マイナビが公表した「2025年卒 内定者意識調査」から紐解いていきましょう。
【図21】入社意欲の高まる企業PR(複数回答)
・福利厚生の充実:72.5%
・待遇(給与・賞与など)の良さ:64.8%
・ワークライフバランスの良さ:61.9%
・社風や雰囲気の良さ:58.1%
この結果からわかるのは、「福利厚生」や「待遇」などの条件面に加え、企業の「空気感」や「人」に強く惹かれる学生が多いということです。
これらの情報は、ホームページや会社説明会の資料だけではなかなか伝わりません。だからこそ、現場社員の口から実体験ベースで語る場としての座談会が、非常に有効なのです。
「残業は、実際どれくらい?」
「福利厚生って、実際に使えてる?」
「有休って取りやすい?」
「同期や上司との関係ってどう?」
「入社してみて、どう感じた?ギャップは?」
また、同調査によると、入社予定先企業を選択した際のポイントとして、「先輩社員(OB・OG)の印象が良かった」という回答が35.3%にも上りました。
このように、「社員と接点を持てたこと」が意思決定に大きく影響している今、座談会のようにカジュアルな場で“社員の人となり”を伝える機会は、採用成果に直結すると言えます。
特に、以下のようなポイントを「社員の言葉」で具体的に伝えられると、学生の志望度・安心感は一気に高まります。
| 伝えたい内容 | 伝え方の例(座談会での実体験) |
| 福利厚生の活用実態 | 「週に1回はランチインタビュー制度を利用し、無料でランチ食べてます」 |
| 社風・雰囲気 | 「Slackで役職関係なく雑談してるくらい、風通し良いです」 |
| キャリアのギャップ | 「最初は不安だったけど、配属後に3ヶ月メンターがついてくれました」 |
| 働き方の柔軟性 | 「フルリモートOKなので、悪天候の日は家で働いてます」 |
これらは、HPやパンフレットでは決して伝えきれない要素です。座談会こそがそれを伝えられる場として、今ますます重要視されていくでしょう。
よくある採用座談会の失敗パターン
採用座談会は、うまく設計すれば志望度アップ・辞退防止などに直結する有効施策です。しかし、運営方法を間違えると、逆効果になることさえあるのがこの施策の難しさ。
ここでは、人事・学生両方から「よくある失敗」をピックアップし、その背景と改善ポイントを紹介します。
失敗例①:社員ばかり話し、学生が発言しにくい雰囲気に
「社員が一方的に話して終わってしまった」
「質問を促されても、何を聞けばいいかわからない…」
学生は「聞く」立場で参加することが多いため、場の空気が硬いと発言しにくくなります。特にオンライン開催では、表情や空気感が伝わりにくいため、静まり返ってしまうケースも頻出です。
改善策:
・社員側からの「逆質問(例:〇〇さんはどう思いますか?)」を入れる
・匿名チャットや投票ツールを活用し、間接的な発言機会をつくる
・アイスブレイクや“発言しなくてもOK”の前置きで緊張をほぐす
失敗例②:話す内容がワンパターンで響かない
「やたら制度の説明が多い」
「不自然に良いところばかり推してくる」
「HPに載ってることをなぞるだけだった」
せっかくの座談会でも、説明会と同じような内容に終始してしまっては意味がありません。学生が期待しているのは、「リアルな体験談」や「ちょっとした本音」です。
改善策:
・「最初の頃に戸惑ったこと」「正直ギャップだったこと」など、ネガティブ→ポジティブの構成を意識
・話題を「学生が聞きたがること」から逆算する(後述のトークテーマを参照)
失敗例③:誰を出しても学生の反応が変わらない
「結局、座談会に誰が出ても同じような印象に…」
「“優等生的”な社員ばかりで、リアリティがなかった」
優秀でロジカルな社員ほど、情報の整理や説明が得意ですが、それが「学生目線」とズレることも珍しくありません。学生が印象に残るのは、「自分もこうなれそう」と思えるような共感軸のある社員です。
改善策:
・年次が近い社員(1〜3年目)や“挫折経験がある社員”を積極的に選出
・異なるタイプの社員を組み合わせ、異なる視点で答える
・学生の属性に合わせて社員をアサイン(理系向け/女子学生向けなど)
失敗例④:目的が曖昧で“やっただけ”になってしまう
「とりあえず開催したけど、成果が見えなかった」
「どんな学生が来たか、何も残っていない…」
目的設計が曖昧だと、座談会は“ただのイベント”で終わってしまいます。母集団形成・志望度アップ・選考誘導など、目的に応じた設計・データ取得・フォローが必須です。
改善策:
・学生のアンケート設計とKPI(例:選考参加率、満足度)を事前に定める
・次回選考につなげる導線(その場で日程提示、QRコードで申し込みなど)を用意
・社内でも“採用成果に直結する施策”として共有・評価されるよう工夫
これらの失敗例は、決して特殊なケースではなく、よくある“もったいない”パターンです。次章では、これらの反省点を踏まえて、「学生の心を掴む座談会をどう設計するか」の具体的なポイントを解説します。
学生の心をガッと掴む座談会のポイント
ここからは、座談会で学生の心を強くつかむポイントについて解説します。
① 話しやすい場を整える
採用座談会の成果は、話す内容だけでなく「空気の良さ」も重要です。学生が心を開き、自分ごととして企業をイメージできるかどうかは、最初の10分で決まります。
以下に、効果的な雰囲気づくりのポイントを紹介します。
社員の自己開示から始める
学生が緊張して話しにくいのは当然のこと。そこでまず、社員側が「自分の弱み」や「本音」を開示することが大切です。
例:「実は、入社当初は“この会社で本当にやっていけるのかな…”って不安しかなかったんですよ」
このような自己開示は、「あ、ここでは本音で話していいんだ」と学生に感じさせる強力なメッセージになります。
司会・進行の工夫で堅苦しさを払拭する
座談会が「説明会の延長」になってしまうと、学生も社員も構えてしまいます。進行役は以下のような工夫を取り入れましょう。
| 工夫 | 内容 |
| アイスブレイク導入 | 簡単な会話から開始 |
| 口調をカジュアルに | 「〜です」より「〜なんですよね」の方が柔らかい |
| 発言を強要しない | 「無理に発言しなければと思わなくても大丈夫ですよ」と伝える |
| 小グループ制 | 5〜6人単位に分けて親密感を生む(特にオンライン) |
堅苦しさを取り除くことで、学生の内面からの発言を引き出す場を整えます。
② 学生の「知りたい」に対しリアルに答える
「質問に答える」というと一見当たり前に思えますが、実際にはうまくできていない企業も多くあります。
座談会では、学生が本当に知りたいことに、どこまでリアルに・誠実に応えられるかが、満足度と志望度を左右します。
実態を包み隠さずに伝える
座談会の目的は、「うちの会社、良いでしょ?」と盛って一方的にアピールすることではありません。むしろ、リアルな実態や本音を包み隠さず伝えることが、学生の信頼を得る近道になります。
たとえば、こんなやりとりは印象に残りやすいものです。
Q:「残業って正直どうなんですか?」
△「部署によりますね」「あまりありません」
〇「私はだいたい毎日1時間くらいですね。月末はちょっと忙しいですが、週に1回は早めに帰れる日もあります」
Q:「入社後のギャップはありましたか?」
△「特にないです」
〇「最初は想像以上にスピード感があって、正直焦りました。でも、半年くらいでやっとペースをつかめた感じです」
こうした話は、学生にとって“想像できる未来”となり、志望意欲にもつながります。
うまくいった話よりも、最初のつまずきやギャップをどう乗り越えたかの方が、ずっと心に残るのです。
聞きづらい質問は、企業側から先回りして伝える
座談会はカジュアルな場でありつつも、学生にとっては「もしかしたら選考に影響するかも」と緊張している場でもあります。
そのため、以下のような質問は関心があってもなかなか聞けないケースが多いです:
- 残業ってどれくらいあるのか?
- 有休はちゃんと取れているのか?
「待遇ばかり気にしてると思われたくない」という心理があるからこそ、企業側から“よく聞かれるので先にお伝えすると…”という形で切り出すのが効果的です。
ネガティブな内容は、「正直に」+「ポジティブとセット」で伝える
完璧な企業は存在しません。ときには、学生からの質問が自社の弱みや課題に触れるものであることもあります。
そんなときに大切なのは、ごまかさず、誠実に、そして前向きな言葉で伝えることです。
「繁忙期はどうしても業務が集中します。ただ、業務分担の工夫や、休みをずらして取るなど、少しずつ改善されてきています」
曖昧な返答や取り繕いは、短期的には好印象でも、入社後のギャップや離職リスクを高める結果になりかねません。正直さとポジティブな着地の両立ができると、学生に「信頼できる会社だ」と感じてもらいつつ、意欲を高めることができます。
③志望意欲を「あと一歩」押し上げる
座談会は、企業を知ってもらう場であると同時に、学生に「ここで働いてみたい」と思ってもらう最後のひと押しの場でもあります。
1章・2章で紹介したように、「話しやすい雰囲気」と「知りたいことへのリアルな回答」が整っていれば、学生の中には既に好感や関心が芽生えているはずです。
しかし、志望度を「興味がある」→「本気で選びたい」に引き上げるには、もう一段階、工夫が必要です。
登壇者を適切に選定する
学生が「この会社、なんかいいかも」と感じるかどうかは、誰が話すかに大きく左右されます。
座談会で登壇する社員を選ぶ際は、単に優秀なロールモデルを揃えるだけでなく、「学生が共感できる要素」を意識した選定が重要です。
以下のようなポイントを意識しましょう。
・年次が近い社員(1~3年目)の選定:就活当時の記憶や悩みが新鮮で、学生の視点に近い話ができる
・挫折や迷いの経験を話せる社員の選定:単なる成功体験だけでなく、乗り越えたプロセスが刺さる
・人柄や雰囲気にバリエーションを持たせた選定:ロジカルなタイプ、感情豊かなタイプ、自然体なタイプなど、複数名を登壇させると共感の幅が広がる
・学生の属性に寄せた選定:理系・文系、女子学生向けなど、母集団に合わせた社員を選ぶと、解像度が高まる
学生自身に言語化してもらう
座談会の終盤で、「気づき」や「印象に残ったこと」を言葉にしてもらうと、学生自身の中で「惹かれている理由」が整理され、意思決定の一歩手前まで進みます。
- 「今日の話の中で、印象に残った言葉はありますか?」
- 「入社後のイメージ、少し湧いてきましたか?」
このように、軽く投げかけるだけでも効果的です。ここでの発言は選考や内定承諾に対する意欲にもつながってきます。
次の一歩につながる導線を必ず用意する
せっかく座談会で志望度が高まっても、「良い話が聞けた」で終わってしまっては意味がありません。
「気持ちが動いた瞬間に、行動へつなげる」ための導線が重要です。
・座談会後に選考案内を送る
・QRコードでカジュアル面談の申し込みへつなげる
・Slack・LINEなどで接点継続のコミュニケーションを設計する
このように、単発で終わらせず、継続的な関わりを提示しておくことで、志望度は行動につながります。
学生が本当に知りたい具体的な質問リスト
学生が知りたい質問を、下記にまとめました。
事前に回答を準備する際や、企業側からテーマを振る際にご活用ください。
入社前後・働き方に関すること
・入社して最初に取り組んだ仕事は?
・社会人1ヶ月目って、正直どんな感じ?
・入社前に「やっておいてよかった」と思うことは?
・1日のスケジュールは?(時間感も含めて)
・ひとり立ちするまでに、どれくらい時間がかかった?
大変だったこと・乗り越えた経験
・入社して一番しんどかった瞬間は?どうやって乗り越えた?
・最初に「つまずいた」エピソードは?
・成長を感じられた出来事は?
・モチベーションが下がったとき、どうしてる?
・今でも悩んでいることってある?
人間関係・職場の空気
・上司との関係性は?距離感・相談しやすさは?
・同期はどんな人たち?
・チームの雰囲気は?
・飲み会や社内イベントの頻度・参加率は?
・フィードバックや評価の伝えられ方は?
働き方・ライフスタイル
・実際、残業はどれくらい?
・有休は取りやすい?
・リモート/出社のバランスは?柔軟にできる?
・休日はどんなふうに過ごしてる?オンオフの切り替え方は?
・社会人になって、プライベートの変化は?
会社・人のカルチャーに関すること
・どんな人が活躍してる?共通点は?
・この会社ならではの特徴は?
・ギャップは?
・長く働きたいと思える理由は?
・社内で「あの人みたいになりたい」と思う人は?
まとめ
いかがでしたか?
採用座談会は、ただ情報を伝えるだけの場ではなく、学生の不安を安心に変え、志望度を高める重要な場です。
- 自己開示を大切にした雰囲気づくり
- 学生が知りたいことに対して、正直に・リアルに答える
このような小さな工夫の積み重ねが、選考参加率や内定承諾率といった成果にもつながります。ぜひ今回ご紹介した内容を参考に、貴社らしい魅力が伝わる座談会を設計してみてください。
この記事の監修者:
1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。