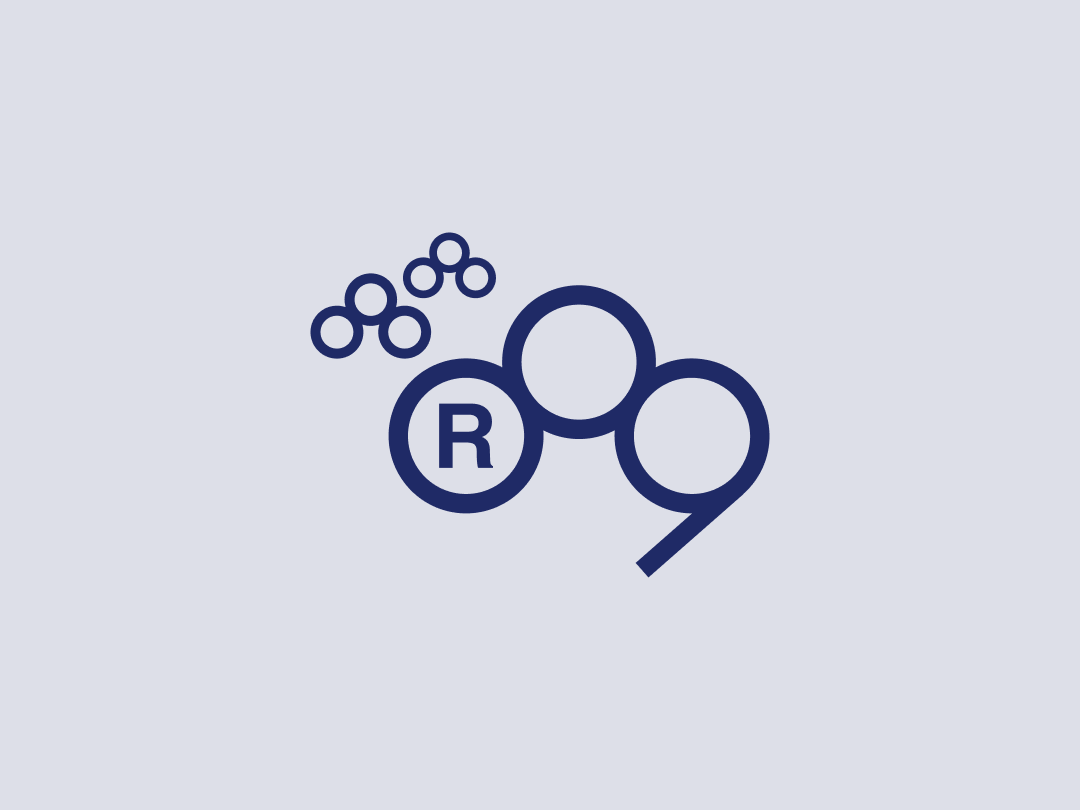【実務解説】採用KPIの指標例と設定手順
公開日: 2025年05月21日

多くの人事担当者は、「採用活動の効果をどう測定し改善すればよいか」に頭を悩ませています。採用を成功させるには、勘や経験だけでなく、データに基づく指標(KPI)を設定し、進捗を管理することが重要です。
本記事では 「採用KPI」 をテーマに、具体的な項目例や設定方法、運用するうえでの注意点について実務に役立つ形で解説します。
採用KPIとは何か
採用KPI(Key Performance Indicator)とは、採用活動のパフォーマンスを示す重要指標のことです。最終目標である「必要な人材の採用(入社)」に向けて、各プロセスの進捗を定量的に測定する中間指標を指します。
営業で訪問件数や商談件数をKPIとするように、採用でも「応募者数」「面接通過率」など各段階の数値目標を設定します。これらのKPIを追うことで、最終的な採用目標の達成可能性やボトルネックを把握できます。
KPIはあくまで採用目標達成に向けたプロセス指標であり、「その目標を達成するためには何件の応募が必要か」「面接を何件実施すべきか」といった具体的な行動量や進捗を測る基準となります。適切なKPIの設定とモニタリングによって、採用活動の改善ポイントを早期に発見し、効果的な改善施策につなげることができます。
採用KPIの具体的な指標例
採用プロセスの各段階で設定できる主なKPI指標にはどのようなものがあるでしょうか。以下によく用いられる採用KPIの例を挙げます。
応募数(エントリー数)
採用募集への応募者の人数です。採用目標を達成するためにまず重要となるKPIで、応募者が増えれば採用の母集団(候補者プール)が拡大します。
ただし応募数は多ければ良いわけではなく、有効応募率(応募者のうち自社が求める要件を満たす人の割合)にも注目する必要があります。応募者が多くてもターゲット外ばかりでは目標達成は難しいためです。この割合が高いほど、採用ターゲットに対して効果的にアプローチできていることを意味します。
応募数を増やす施策と同時に、質の高い応募者を集める工夫も大切です。
書類選考通過率
エントリーした応募者のうち、書類選考(履歴書・職務経歴書審査)を通過した人の割合です。計算式は「書類選考通過者数 ÷ 応募者数 × 100」で算出されます。
この指標により、母集団の質や選考基準の適切さが見えてきます。通過率が低すぎる場合、母集団の質が低いか、選考基準が厳しすぎる可能性があります。
面接通過率
面接を受けた候補者のうち、次の選考ステップに進めた人の割合です。一次面接通過率・最終面接通過率など選考段階ごとに設定します。例えば一次面接通過率=「一次面接合格者数 ÷ 一次面接実施人数 × 100」のように算出します。
面接通過率は採用プロセスのボトルネックを知る手がかりになります。特定の面接ステージで通過率が極端に低ければ、その段階で選考基準の見直しや面接手法の改善が必要かもしれません。
内定承諾率
内定を出した候補者のうち、実際に承諾(入社)した人の割合です。計算式は「承諾者数 ÷ 内定通知者数 × 100」で算出されます。
この割合は内定辞退率の裏返しの指標となります。承諾率が低い場合、オファー面談後のフォロー体制や提示条件の見直しなど、内定辞退を防ぐ対策が必要です。内定承諾率を高めることが計画通りの人員確保に直結します。
上記の4つ以外にも、内定数(出した内定の件数)や入社率(応募から入社まで至った割合)、採用コスト(採用単価)や採用リードタイム(採用に要する日数)など、会社のニーズに応じたKPI指標があります。自社の採用課題に照らして有用な指標を選びましょう。
自社の採用目標に合ったKPIの設定手順
自社の採用目標を達成するために、どのように適切なKPIを設定すればよいでしょうか。ポイントは「量」と「質」のバランスを考慮しつつ、現状の課題を分析し、過去データを活用して現実的な目標値を定めることです。以下にKPI設定の基本ステップを示します。
1. 採用目標の明確化
はじめに採用活動全体のゴールを明確に設定します。誰を何名、いつまでに採用するのかという目標(例:「半年以内に即戦力の営業担当を3名採用」)を具体的な数値と期限で定めましょう。
この採用目標が定まっていないと、適切なKPIを設定できません。採用目標の内容によって採用計画や必要なプロセスも変わるため、まずはゴールをはっきりさせることが重要です。
2. 採用フローの洗い出しと課題分析
次に、その目標を達成するために必要な採用フローを整理します。一般的には「母集団形成(募集)→書類選考→面接(複数回)→内定→入社」というフローですが、自社に合わせて詳細なフローや採用チャネルを洗い出してください。
各段階で過去にどれくらいの歩留まり率(通過率)があったか、どの段階にボトルネック(課題)があるかをデータで確認します。
例えば「応募は集まるが書類通過率が低い」「内定は出せているが承諾率が低い」など、現状の課題を把握しましょう。自社の過去の採用データを分析することで、特に注力すべきKPIが見えてきます。
3. KPI目標値の算出と設定
実際に採用フローの各段階において必要な数値目標(KPI)を算出します。逆算の発想で「採用目標達成に必要なプロセス数」を割り出すイメージです。
例えば採用目標が「〇ヶ月で○名入社」なら、過去の通過率を参考に「◯名の入社には内定何件必要か」「その内定数を得るには何人の一次面接が必要か」「応募は何件必要か」といった計算を行います。こうしたプロセス数値をツリー状に紐付けたものが「KPIツリー」と呼ばれます。
計算には自社の過去の歩留まり率(各選考ステップの通過割合)を活用すると現実的な目標を立てやすくなります。例えば、前年度の実績で「書類選考通過率50%、一次面接通過率40%、内定承諾率50%」であれば、最終的に2名入社するには約20名の応募が必要というイメージです(書類選考通過10名、一次面接通過4名、内定承諾2名)。
自社の採用チャネルごとの特性も考慮し、無理のないKPI数値を設定しましょう。ポイントは、目標値が高すぎても低すぎても効果が薄れるため、「達成可能かつ挑戦的な水準」を見極めることです。
4. 重要KPIの選定
設定した指標の中から自社の採用成功に特に重要なKPIを見極めます。すべての数値を追いかけるのではなく、自社の方針や課題に直結する指標にフォーカスしましょう。
例えば「まずは応募母集団を増やすことが急務」であれば応募数を最重要KPIに据える、「質重視の採用をしたい」場合は書類通過率や有効応募率に重点を置く、といったイメージです。
過去データ分析で判明したボトルネック(例:内定辞退の多さ)があれば、その改善につながるKPI(内定承諾率など)を主要管理指標に据えるのも有効です。
以上のステップを経て、自社の採用戦略に合致したKPIを設定します。設定時には単に数値を決めるだけでなく、各KPIに達成期限を設ける(例:「〇月までに応募△件」)ことで行動計画に落とし込みやすくなる点も意識しておきましょう。
KPIの運用方法や注意点
KPIを設定したら、それを運用(モニタリングと改善)していくフェーズに入ります。限られたリソースで採用を進めるには、設定したKPIを「生きた指標」として活用することが肝心です。以下、KPI運用のポイントと注意点を解説します。
定期的なモニタリングでPDCAを回す
採用KPIは設定して終わりではなく、定期的に数値を把握して改善を継続する(PDCAサイクル)ことが重要です。
理想は月次ベースで進捗をチェックし、計画との差異を分析して対策を講じることです。実績が目標に届いていない場合は、その原因を各KPIの数値から定量的に突き止め、具体的な改善アクションを実行しましょう。
例えば「応募数は足りているが内定辞退率が高い」ことがわかれば、内定後のフォロー体制を強化するといった対策が考えられます。
このようにデータに基づき施策を検証・改善するサイクルを回すことで、採用成功の確率を高めることができます。進捗管理にはExcelや専用システムで「KPI管理シート」を作成し、数値を可視化・共有することも有効です。
状況に応じたKPI計画の見直し
採用市況の変化や計画との大幅な乖離が生じた場合、KPI自体を見直すことも検討します。
設定時には適切と思われた目標値でも、運用中に「想定より応募単価が高騰し予算内で応募数を確保できない」など状況が変わることがあります。その際は、単に施策面の修正だけでなくKPI目標値やスケジュール自体の調整を行ったほうが現実的な場合もあります。
ただし、目標未達が見えたからといって安易に数値目標を下方修正するのは避けましょう。「なぜ達成が難しいのか」を関係者で議論し、必要であれば採用計画全体を見直すくらいの視点で検討しましょう。
KPIはあくまで目標達成のための手段であり、目的そのものではないことを忘れずに、状況に応じて計画を柔軟にアップデートすることが大切です。
KPI数値への過度な執着に注意
KPIは手段であって目的ではないという原則を常に意識しましょう。数値目標の達成自体が目的化してしまうと、本来の採用の質や組織にもたらす効果がおろそかになるリスクがあります。
例えば「KPIの応募数を達成するため」に応募要件を緩和しすぎて不適切な候補者まで大量に集めてしまったり、内定目標を優先するあまり採用基準を下げて質を犠牲にしてしまうのは本末転倒です。また数字ばかりを追いすぎることで、新しい採用チャネルの開拓や柔軟な発想が阻害される恐れもあります。
KPI達成に一喜一憂するのではなく、「最終的に望ましい人材を採用する」という本来のゴールを見失わないようにすることが重要です。
まとめ
以上、採用KPIの基本から設定・運用上のポイントまで解説しました。
採用KPIを適切に活用すれば、限られたリソースでも効率的かつ効果的な採用活動が可能になります。自社の状況に合った指標を選び、定期的なモニタリングと改善を行うことで、採用の質とスピードを着実に向上させていきましょう。各指標の数値を参考に、課題をチームで共有し、適切な採用戦略で貴社の成長に必要な人材を獲得していってください。
この記事の監修者:
1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。