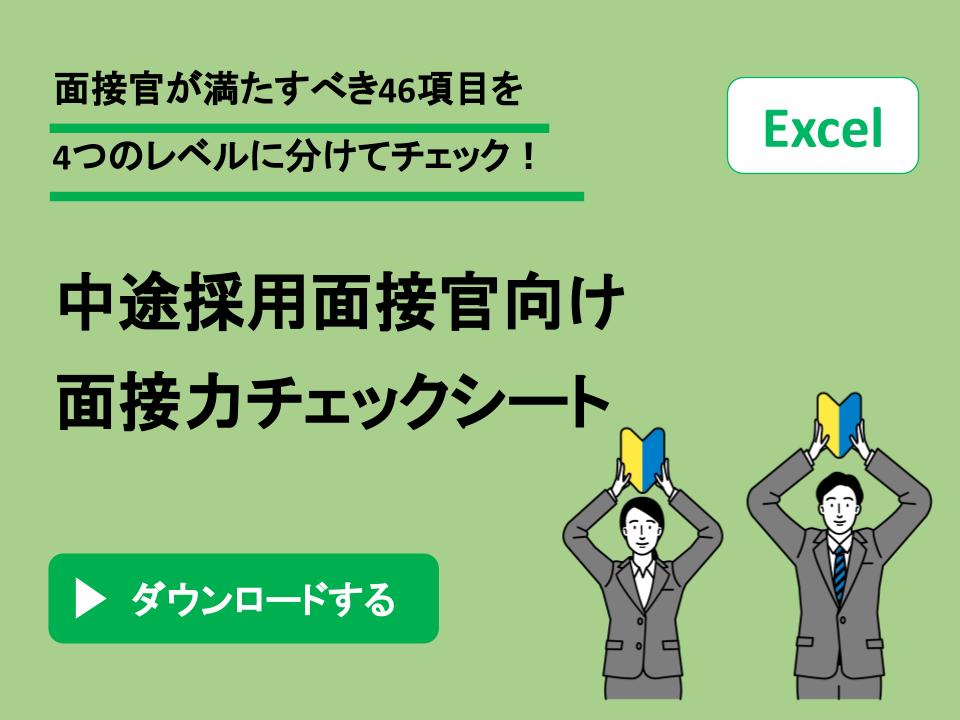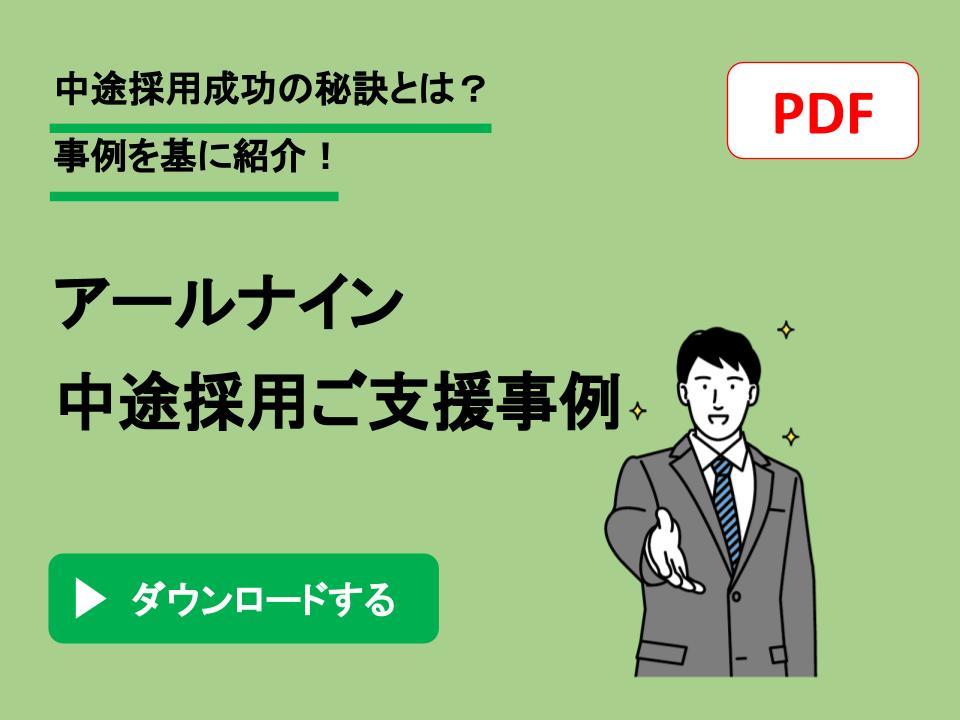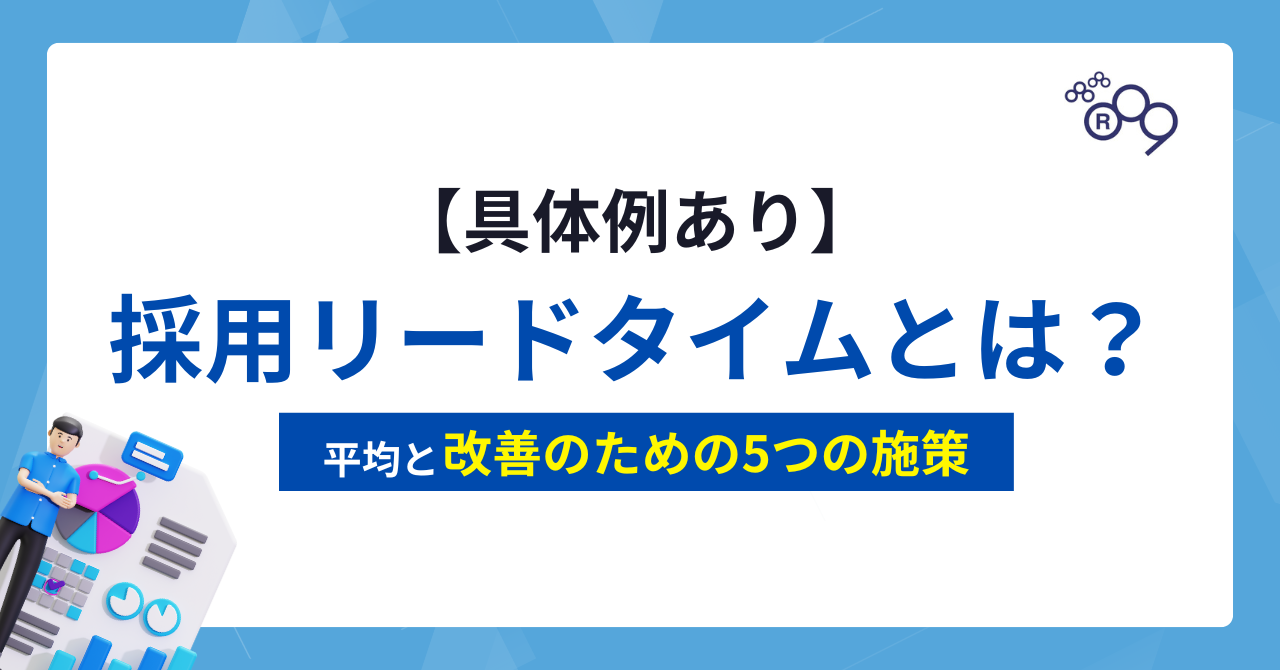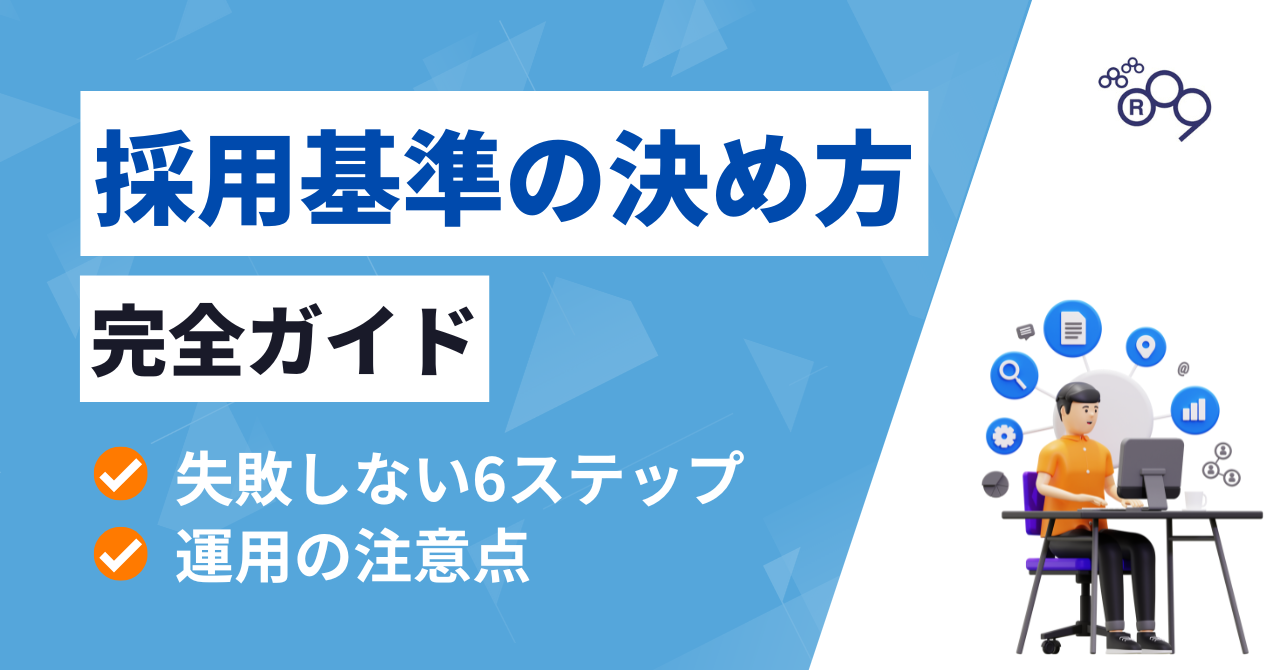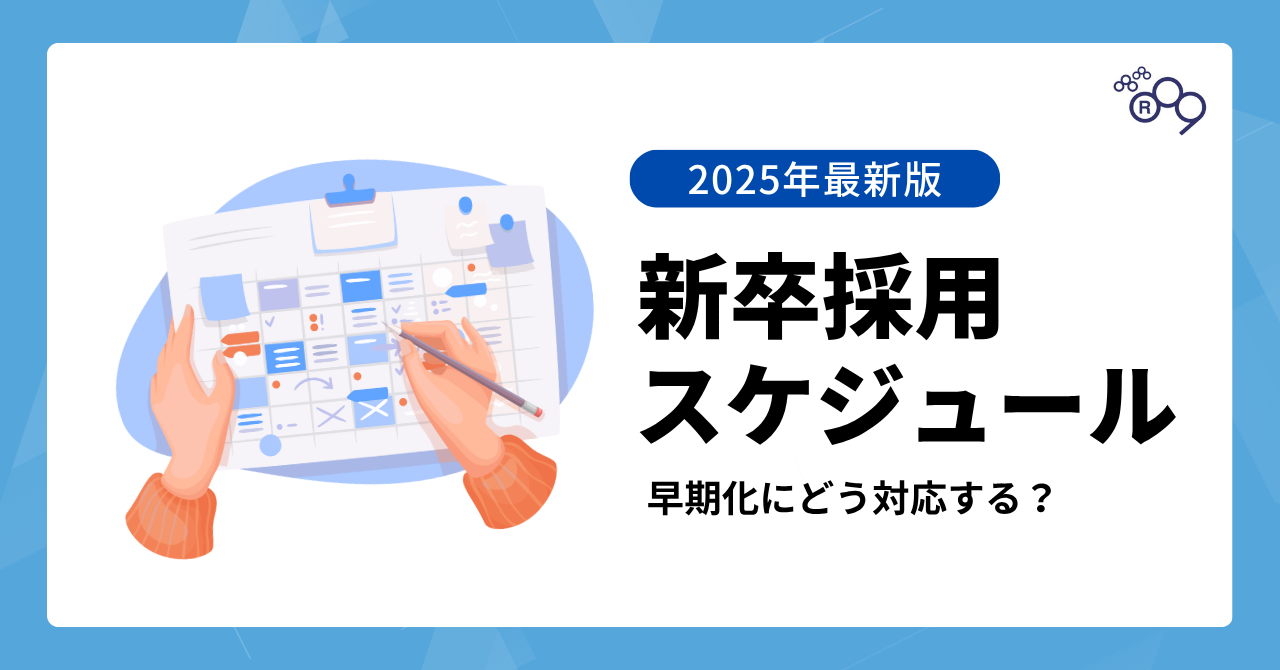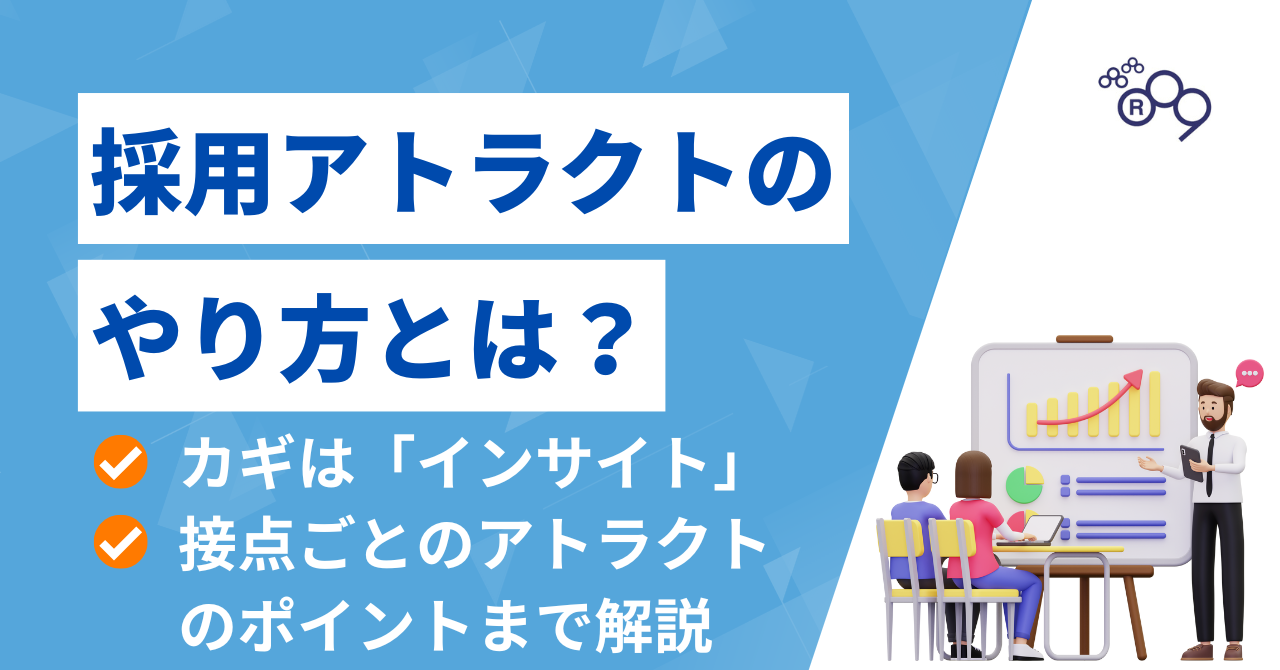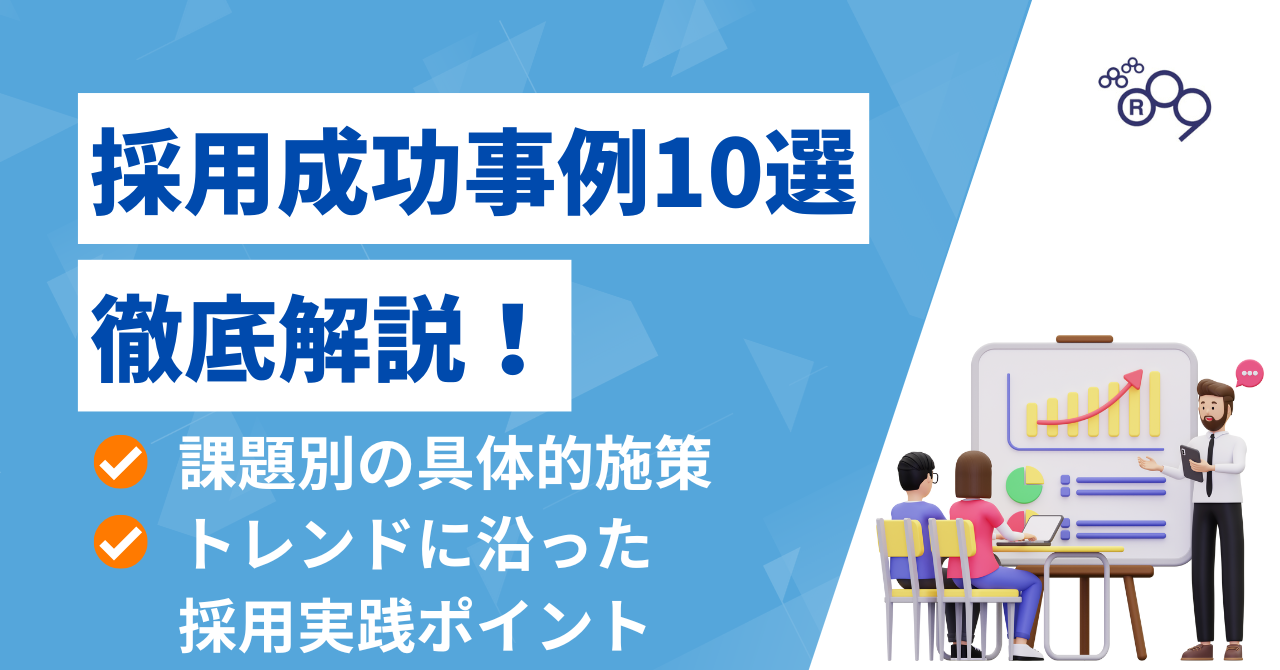中途採用の面接官の心得と役割とは | 事前準備や進め方、質問項目を徹底解説します
公開日: 2022年02月22日 | 最終更新日: 2025年03月27日

新たな人材を獲得するための手段である、中途採用。中途採用は新卒採用とは異なり、時期を限定せずに人材を獲得できる方法です。
新たな人材と出会える絶好の機会になりますが、面接後に辞退の申し出を受けるケースもあります。辞退される理由には、応募者が面接官に対して抱く印象が大きく影響していることがあります。
つまり、中途採用の面接では、面接官が合否を判断するだけでなく、逆に面接官も応募者から1人のビジネスパーソンとして好ましい人かどうか判断されているのです。このような理由から、中途採用面接官は応募者に対し、常に真摯に対応する必要があります。
今回の記事では中途採用の面接官の心得について紹介します。また、面接の質問項目や注意点も解説します。この記事を読み終わった採用担当者は面接官としての心得を理解し、求める人材を獲得できるようになるでしょう。
【関連資料】「中途エンジニア採用を成功させる5つのポイント」はこちら!
【関連資料】「【中途採用】採用CX 完全マニュアル」はこちら!
中途採用での面接官の役割
中途採用が実施される会社では、選考の工程で面接を導入するケースが多いでしょう。面接時での面接官は、以下のような役割を担っています。
- 応募者が自社に合う人材か見極める
- 自社に合った人材を入社に導く
ここでは、中途採用での面接官の役割を解説します。
役割1. 応募者が自社に合う人材か見極める
1つ目の役割は、応募者が自社に合う人材かどうか見極めることです。面接官は面接を通して、応募者の本質を見抜きます。
例えば、1対1の面接ではコミュニケーション能力や考え方など書類ではわからない部分を引き出します。また、入社後の目標を問い、どのような答えを出すのか試すことができるでしょう。応募者の自社に対する思いもわかり、入社への本気度が把握できるはずです。
このように、面接官は採用試験を通して、応募者が自社に合った人材なのか慎重に見極める大事な役割を担っています。応募者が提出した履歴書や職務経歴書以外の、面接でしか得られない情報を引き出してください。
役割2. 会社に合った人材を入社へ導く
2つ目の役割は、自社に合った人材を入社へ導くことです。面接官は応募者の本質を見抜き採用するだけではなく、自社へスムーズに入社してもらうために適切な対応を行う役割があります。
例えば、入社前の連絡方法や入社後のスケジュールなどが明確になっていない場合、応募者が不安や疑問を抱き、辞退を申し出ることがあるでしょう。また、入社後の早期退職につながる可能性もあるため、事前に応募者の不安や疑問を取り除くことが大切です。優秀な人材が他社に流れてしまわないように真摯な対応を取りましょう。
中途採用の面接官の心得
中途採用で面接官を任された場合、やみくもに取り組んではいけません。面接官は応募者の合否を判断するだけではなく、以下のような心得を持つ必要があります。
- 会社の顔として面接に臨む
- 会社にマッチする人材を探す
- 応募者が落ち着ける雰囲気を作る
ここでは中途採用の面接官の心得を項目ごとに紹介します。
心得1. 会社の顔として面接に臨む
1つ目の心得は会社の顔として面接に臨むことです。応募者にとって、面接官は企業を詳しく知るための貴重な情報源になるからです。
例えば、面接の際に面接官が会社を紹介する場合、応募者にとって面接官から話される内容が会社の本音だと受け止めるでしょう。また、面接官の態度や言葉遣いが良くない場合は会社全体のイメージが悪くなります。応募者は面接の最中に興味を失い、会社へ入社する意志が弱くなる可能性があるでしょう。
面接官は会社の顔として、責任感を持った発言や態度を取りましょう。応募者は、面接官や会社の雰囲気を他社と比較しています。面接官は応募者が同じ会社で働きたいと感じるような人物を目指し、ビジネスマナーや相応しい考え方を身につけましょう。
心得2. 会社にマッチする人材を探す
2つ目の心得は会社にマッチする人材を探すことです。中途採用の応募者は年齢や経験が統一されていないため、さまざまな方がいます。また、履歴書や職務経歴書に記載されていない魅力を持った人材がいる可能性もあります。
例えば、同じ年齢の応募者が複数人受験した場合、人によって経験や考え方が異なります。さらに、同じ業種を経験していたとしても仕事への取り組み方が違うケースもあるでしょう。
そのため、面接官は面接中に自社のやり方と合うのか見極めなければいけません。入社後、他の社員と連携が取れるのか、コミュニケーション能力についても判断しながら、会社にマッチする人材を見つけましょう。
心得3. 応募者が落ち着ける雰囲気を作る
3つ目の心得は応募者が落ち着ける雰囲気を作ることです。多くの応募者は面接の独特な雰囲気に緊張するからです。
例えば、自社の会議室で面接を行う場合、応募者の中には慣れない状況で緊張のあまり、思うように話せない方がいるでしょう。面接官は、応募者の緊張をほぐすために世間話を行ったり、会話中に相槌を打ったりすることをおすすめします。
応募者が落ち着きを取り戻したところで、本格的な面接を行いましょう。面接は独特な雰囲気が漂うため、状況によって空気を一新する必要があります。面接官は、応募者の本質が引き出せる環境作りを心掛けましょう。
【導入事例】説明会と1,500件の一次面接を代行し、工数を大幅削減!
【導入事例】面接官トレーニングでSNSでの悪口がなくなった!
中途採用の面接官が面接までにすべき3つの準備
続いて、中途採用の面接官が面接までにすべき準備について解説いたします。充実した採用面接を行うためには、入念な準備が必要です。
それでは順番に解説していきます。
1. 自社が求める人材の定義を再確認する
採用面接は「自社が求める人材を獲得する」ことが目的です。
その目的を達成するためには、自社が求める人材がどのような人物であるかをしっかりと頭に入れておくことが必要です。
求める人材を再確認することで、求職者に確認するべき事項や、的確な質問も見えてきます。
採用活動を行うにあたり設定した「採用ペルソナ」を面接までに必ず確認するようにしましょう。
2. 採用面接のロールプレイングを行う
採用面接を初めて行う際は、どんな段取りで進めたらいいか、どんな質問をしたらいいかに戸惑い、円滑に面接を進められないものです。
そのため、事前に上司や他の人事担当者と一緒にロールプレイングをすることをお勧めします。
ロールプレイングで面接の段取りや質疑応答を経験しておくと、気持ちの余裕を持って面接に臨むことができるようになります。
また、ロールプレイングを経験することで、現在の自分の課題も見えてくるため、不足している部分を面接までに補うこともできます。
採用面接を初めて行う際は、ロールプレイングを数回行っておきましょう。
3. 自社についての理解を深めておく
採用面接に臨む前に、面接官は自社についての理解を深めておくようにしましょう。
中途採用の面接官は、求職者から見れば会社の顔として映ります。
求職者から自社のことを聞かれた際、面接官が即答できなかったり、自信がなさそうに回答していたら、求職者は「この会社は大丈夫かな」と不安に思うでしょう。
下記のような内容は、最低限自信を持って回答できるように準備しておきましょう。
・自社の事業内容
・自社の業績
・自社の課題
・自社のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)
逆に上記のような内容に自信を持って回答し、求職者に納得感を持ってもらえるよう伝えることができれば、求職者が自社に入社してくれる可能性も高まります。
会社の顔として自信を持った回答ができるよう、自社についての理解を深めておきましょう。
中途採用面接の基本的な流れ

中途採用の面接が行われる場合は、事前に順序を決めなければいけません。面接官は順序に沿った上で、限られた時間で進めていきます。以下が、中途採用面接の基本的な流れです。
- アイスブレイク
- 会社の紹介
- 質疑応答①(採用担当者から応募者へ)
- 質疑応答②(応募者から採用担当者へ)
- 事務的な確認
ここでは、中途採用面接の基本的な流れを項目ごとに紹介します。
順番1. アイスブレイク
1番目はアイスブレイクを行います。アイスブレイクは、参加者の緊張をほぐすために行われる手段です。応募者の中には緊張のあまり、通常の会話ができない方がいます。そこで、面接前にアイクブレイクを行いリラックスしてもらいます。
例えば、面接の前に天気や気候、身近なニュースなどの雑談をします。応募者は難しく考える必要がなく、自然に会話が行えます。面接官は面接と関係する話題を避け、場の雰囲気を和らげましょう。アイクブレイクの時間は5分を目安に行ってください。
仮に時間が長過ぎると、双方に緊張感がなくなり有意義な面接ができません。双方が程よい緊張感を持ちながら、面接を迎えましょう。
順番2. 会社の紹介
2番目は会社の紹介を行います。応募者はパンフレット・求人票・公式HPから会社の情報を収集していますが、全てを理解しているわけではありません。また、応募者が情報収集できる内容は限られているため、会社の良い部分が伝わっていないこともあるでしょう。
例えば、職場内の雰囲気や仕事の流れは現場で働いている社員に聞かなければ、具体的な内容を把握できません。応募者は具体的な内容を聞くことで、入社後の働くイメージがつきやすくなるはずです。面接官は応募者に会社の詳細を詳しく伝え、より興味を持ってもらいましょう。
順番3. 質疑応答①(面接官から応募者へ)
3番目は面接官から応募者へ質問を行います。面接官は事前に応募者から受け取った履歴書や職務経歴書を確認し、質問事項を絞ります。
例えば、転職回数が複数回ある場合は各職場を退職した理由を尋ねます。また、退職した理由次第でより具体的に質問するケースもあるでしょう。ただし、応募者によって深堀されたくない方もいるため、質問の仕方については注意する必要があります。
面接官は応募者の気になる点について、双方が会話する形で行いましょう。会話の中から応募者の本質やマナーなど多角的な視点で評価してください。
順番4. 質疑応答②(応募者から面接官へ)
4番目は応募者から面接官へ質問を行います。応募者は面接を通して、疑問や不安を抱く部分が出てくるからです。例えば、応募者の中には仕事の具体的な手順や自らが任される業務を詳しく知りたい方がいます。また、福利厚生面で明確にしておきたい方もいるはずです。
面接官は応募者の質問に対し、真摯に答えるようにしましょう。真摯に答える姿勢が応募者に良いイメージを与え、自社への志望度が高くなる可能性があります。説明する際は分かりやすくかつ丁寧に答え、理解を深めてもらいましょう。
順番5. 事務的な確認
5番目は事務的な確認を行います。面接が終わった後に、合否が決定する日数や連絡方法を確認します。また、面接官から応募者へ伝えるべき事項がある場合は、この時に行ってください。
面接後、今後の流れについて双方が把握していないと、トラブルに発展する可能性があります。面接官は、事前に応募者と共有する情報を確認し具体的に伝えましょう。仮に口頭で伝えることに不安がある場合はメールに詳細を記入し、応募者に送るといいでしょう。トラブルを未然に防ぎながら、スムーズな採用活動を行いましょう。
中途採用での主な質問項目
中途採用の面接では、面接官が応募者にさまざまな質問を行います。質問内容は面接官によって異なるため、明確な決まりはありません。以下に、中途採用面接での主な質問項目を挙げています。
- 前職の退職理由と転職理由
- 自己PR・自己紹介
- 過去の実績
ここでは、中途採用面接での主な質問項目を3つほど紹介します。
質問項目1. 前職の退職理由と転職理由
質問項目の1つ目は、前職の退職理由と転職理由を問うことです。なぜなら、転職したとしても応募者の抱えている問題が解決しないケースがあるからです。また、転職理由を知ることで転職への意欲の度合いが判断できるでしょう。
例えば、人間関係が上手くいかずに前職を退職した場合、転職先でも同じ問題を抱える可能性があります。また、転職者本人が悩んでしまい、早期退職につながるリスクがあるでしょう。面接官は応募者の退職理由を聞き、入社後に問題が起きないように対策を取る必要があります。
質問項目2. 自己PR・自己紹介
質問項目の2つ目は自己PR・自己紹介について尋ねることです。なぜなら、応募者の人柄を確認することで自社に合っている人材なのか判断できる要素になるからです。また、自社への志望度を確かめることができます。
例えば、過去の経験や得意な分野などを聞き、自社の業務に活かすことができるかどうか見極めることができます。また、コミュニケーション能力についても確認することが可能です。面接官は、応募者の自己PR・自己紹介からどのような人材なのか把握しましょう。
質問項目3. 過去の実績
質問項目の3つ目は過去の実績を問うことです。なぜなら、応募者がどのような仕事を行ってきたのか把握し、入社後に任せる業務を決められるからです。
例えば、過去に携わった仕事を把握することで、今後立ち上げるプロジェクトを任すことが可能です。さらに、過去の経験を活かして新たな業務に率先して取り組んでくれることにも期待ができます。応募者の過去の実績を確認し、入社後に担当する業務を決めましょう。
中途採用の面接官が注意すべきポイント
続いて、中途採用の面接官になったら備えておきたい心得について解説していきます。
行動は全てマインドから生まれます。中途採用の面接官として的確な動きができるよう、まずは必要な心得をしっかりと備えておくようにしましょう。
それでは、順番に解説していきます。
1. 会社を代表しているという意識を持つ
中途採用の面接官は、求職者には会社の顔として映ります。
求職者は通常、面接を受ける企業の他の人物と接することはないため、面接官=企業として認識します。
そのため、面接官の言動を見て一緒に働くイメージを浮かべます。
面接官の服装、髪型など清潔感があるかどうかも大きなポイントです。
服装、言葉遣い、気配りなどを含め、面接官である自分が企業の顔として見られるということを認識しましょう。
2. 採用面接は求職者の本心を引き出す場であることを理解する
採用面接は、求職者の本心を引き出す場です。
悪い例として、面接官が威圧的な雰囲気を出したり、求職者へ横柄な態度をとってしまう企業があります。
これでは、求職者が本心を語ることはできません。
求職者の緊張がほぐれ、リラックスして話せるよう下記のような工夫をしていきましょう。
・アイスブレイクの時間を設ける
・相槌をしながら話を聞く
・面接スペースを窓の見える部屋にする
・面接スペースに観葉植物を置く
求職者がどうしたらリラックスして話せるか考え、面接の場作りをしていきましょう。
3. 雇用関係は企業と求職者でイーブンであることを理解する
雇用関係を結ぶうえで、企業と求職者はイーブンであることを理解しておきましょう。
面接官の中には、企業側だけが求職者を選定しているという誤った認識を持ち、横柄な態度で面接をしてしまう人もいます。
雇用関係は、「自社で仕事をして欲しい」という企業側の要望と、「自分を雇用して欲しい」という求職者の要望がマッチして成立します。
そこに優劣はないため、「雇ってやる」「働いてやる」と考えるのは至極間違った捉え方です。
企業は確かな基準で選定するとともに、求職者に企業を選んでもらう努力もしなければなりません。
横柄な気持ちは捨て、求職者に選ばれるために、という意識を持って面接に臨むようにしましょう。
4. 幅広い分野のキャッチアップを心がける
中途採用の面接官は、面接で様々な求職者とコミュニケーションを取ることになります。
そのため、自社の業種や職種だけではなく、他業種、他職種の情報も普段からキャッチアップすることが必要です。
相手のバックボーンを少しでも理解できると、面接の会話も円滑に進めることができます。
相手がその思考や行動に至った背景を少しでも多く理解できるよう、普段から視野を広げ情報のキャッチアップをしていきましょう。
5. 一方的なコミュニケーションではなく対話を意識する
面接は求職者の本心を確かめる場ですが、面接官が一方的に質問や話をしてばかりではよくありません。
面接官と求職者の双方が対話をし、双方向のコミュニケーションを取ることが大事です。
そのためには、相手が喋りやすくなるようにしっかりと話を聞く姿勢を持つことも大事です。
また、予め用意した質問をするだけではなく、自然な会話の流れとして、会話から生まれる疑問について聞いていくことも大切です。
面接といえど対話というコミュニケーションに変わりありません。
「傾聴」の姿勢を大事に、しっかりと人と人とのコミュニケーションをとっていきましょう。
6. 相手への伝わりやすさを重視する
面接官は質問をしたり、受け答えをする際には、相手への伝わりやすさを意識しましょう。
社内用語、業界用語、横文字の言葉など相手が分かりづらい言葉は避け、中学生でもわかるような言葉で説明ができるといいでしょう。
また、抽象的な表現は避け、具体的な内容で話すことも心がけましょう。
抽象的な質問では求職者は回答しづらく、面接官側も欲しい回答を得ることはできません。
面接は知識を披露しマウントをとる場ではありません。
相手への伝わりやすさを意識して、言葉のチョイスを行っていきましょう。
7. 面接時は自分に働いているバイアスを意識する
面接は最初の5分で合否を決め、残りの時間はその合否判断を決定づけるために質問をしているという説があります。
例えば、最初の5分間で不合格と判断した場合、残りの時間は「不合格」というバイアスを持って質問をしてしまうということです。これは逆も然りです。
これでは、求職者の良い部分を見落としてしまったり、深堀りすべき内容を逃してしまうことに繋がります。
面接中は自分の印象とは、あえて逆の角度で質問をしてみることも必要です。
自分に働いているバイアスを意識し、意図的にフラットに戻せるようコントロールしていきましょう。
8. 求職者へ自社を選んでくれた感謝を持つ
面接を行うということは、求職者が数ある企業から自社を選定して応募をしてくれたということです。
まずは、自社を選んでもらったことに対して感謝を伝えることが大切です。
感謝の気持ちを持って、来社する求職者を迎え入れましょう。
下記のような細かな部分でも感謝を表現することはできます。
・求職者が戸惑うことがないよう面接会場までの案内を伝える
・気持ちよく挨拶をする
・来社した際は飲み物を用意しておく
・業務の説明を丁寧に話す
・質疑応答の時間を設ける
このような心配りは、求職者が持つ自社に対する印象にも大きく影響します。
求職者に自社で働きたいと思ってもらうためにも、感謝の気持ちを持ち、細かな気配りをした対応を心がけましょう。
9. 最後まで企業の顔であることを忘れずに対応する
面接官は求職者との面接が終わり、見送りが完了するまで気を抜かないようにしましょう。
面接で求職者と打ち解けた際、または求職者の不採用を決めた際など、気持ちが緩んでしまうことがあります。
たとえ(仮令)面接で不採用となったとしても、どこかでその求職者と縁がある、場合によってはお客様になる可能性があります。
最後に与える印象は、求職者に大きく残るものです。
面接の合否がいずれの場合も、良い企業だと思ってもらえる様、最後まで気を抜かずに会社の顔として対応するようにしましょう。
10. 面接での禁止事項を頭に入れておく
面接を行う際、面接官が聞いてはいけない内容、行ってはいけない行動もあります。
代表されるものとして、下記のような内容について話すことが禁じられています。
・性別に関して
・年齢に関して
・容姿に関して
・宗教に関して
・政治に関して
・出生地に関して
・出産や育児に関して
これらは就職差別にあたる可能性があることを理解しておきましょう。
また、モラルや印象の面からも、下記のような行動はとらないように注意しましょう。
・あくび
・腕くみ
・睨みつける
・他社を悪く言う
・背もたれによりかかる
・求職者を圧迫すること
・求職者へ興味がないことをアピールする
このような内容は採用活動のルールとして禁止されている事項であり、自社の品位を落とすことでもあります。
これらの禁止事項を行わないよう、十分に注意していきましょう。
11. 応募者が不快に感じる態度を取らない
応募者が不快に感じる態度を取らないことです。なぜなら、応募者の志望度が低くなってしまい、内定を出しても辞退する可能性があるからです。
例えば、面接中にあくびや背もたれに寄りかかるなどの態度を取ると、相手に良い印象を与えません。また、険しい表情や腕組みを行うこともイメージが良くありません。
応募者は、会社の顔である面接官の態度から会社のイメージを形成します。。そのため、面接官の態度次第で優秀な人材を確保できるのかが左右されるでしょう。
12. 書類やメモに集中しない
書類やメモに集中しないことです。なぜなら、面接官が応募者に対して関心が無いと誤解されかねないからです。
例えば、面接官が目線を外したまま質問を続けた場合、応募者は自分に関心が無いのだと感じるでしょう。また、目の前の人間ではなく書類でしか判断しないのかと不快な気持ちを抱くこともあり得ます。面接官は書類やメモに集中し過ぎないように気をつけてください。応募者本人の入社への熱意を感じるために、目を合わせながら面接を行いましょう。
13. デリカシーの無い質問を避ける
デリカシーの無い質問を避けることです。なぜなら、就職差別やハラスメントにつながるリスクがあるからです。
例えば、面接の段階で家族の職業や収入など詳しく聞きすぎると就職差別につながる恐れがあります。さらに、恋愛や容姿に関する質問を行うとハラスメントになる可能性があるでしょう。面接では採用の有無を判断する質問事項以外に関して、極力避けることをおすすめします。
まとめ
本記事では、中途採用の面接官の心得について紹介しました。また、主な質問項目や3つの注意点にも触れています。面接官は会社の顔として、ビジネスマナーや言葉遣いに気をつけましょう。
さらに、応募者が好感を持てるように真摯な対応を取ってください。中途採用はさまざまな方が応募してくるため、各応募者の本質を引き出し自社に合う人材を見つけましょう。
この記事の監修者:
1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。