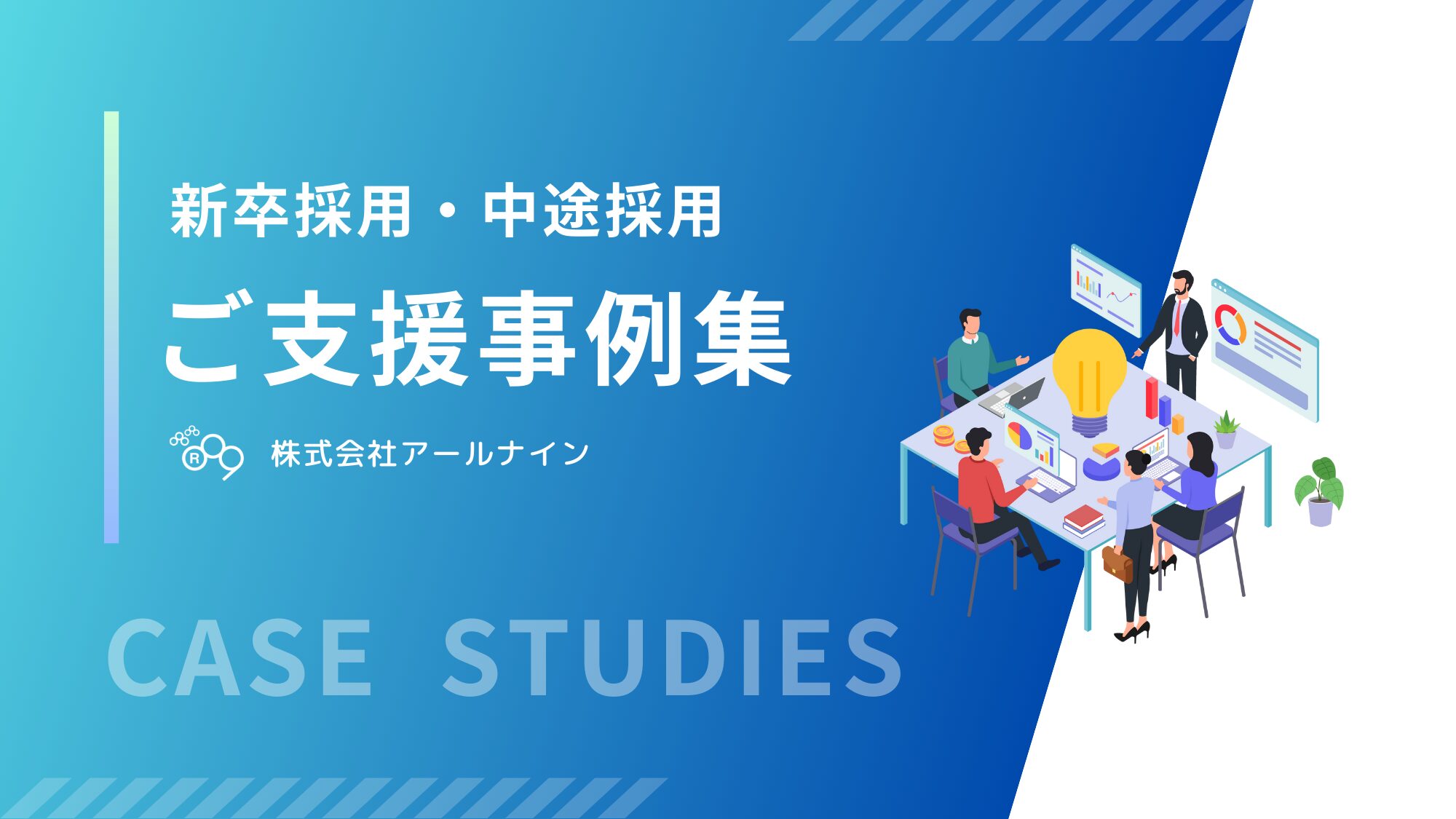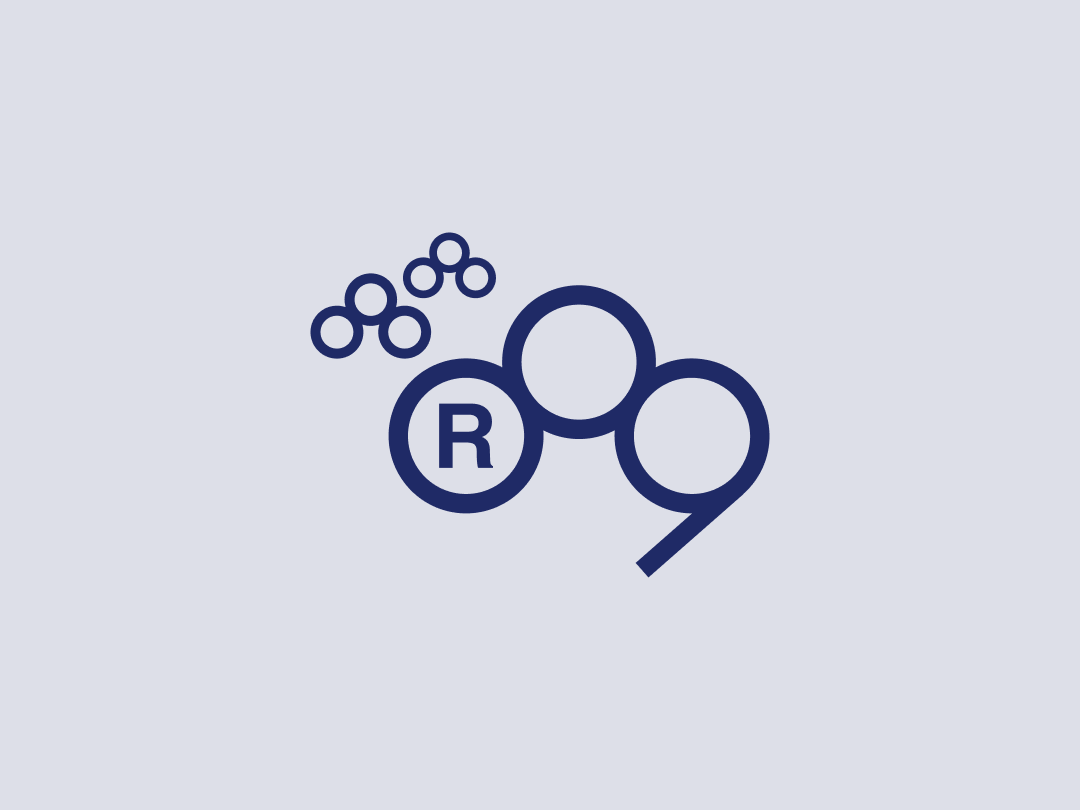採用のコツ7選|仕組みで変える採用活動の実践ガイド
公開日: 2025年04月30日 | 最終更新日: 2025年05月20日
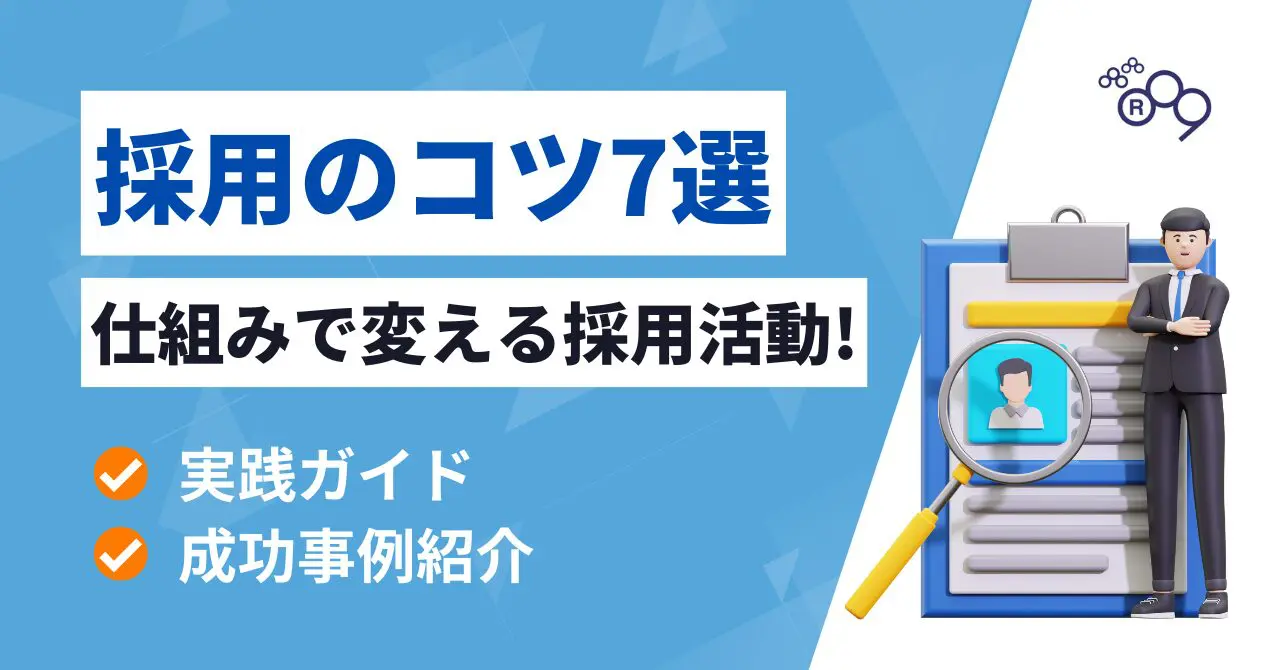
採用の成果は、「やり方」よりも「考え方」で決まります。属人化や場当たり対応になりがちな採用業務を、構造から見直すだけで、応募数もマッチ度も変わってきます。
本記事では、770社以上の採用を支援してきたアールナインの現場知見をもとに、採用活動を改善する「7つのコツ」と「5つの実行ステップ」を、実務者目線で整理しました。
「求人は出しているけど応募が来ない」「いい人から辞退されてしまう」そんなお悩みを持つ人事・経営者の方に向けて、感覚に頼らない、再現性のある“仕組み採用”のヒントをお届けします。
採用がうまくいかない企業に共通する課題とは?

採用が「うまくいかない」と感じる企業には、実は共通した“構造的な落とし穴”があります。
特に中小企業やスタートアップでは、担当者の勘や経験に頼った“なんとなく採用”が続いてしまい、応募が来ない、辞退される、定着しない…というループに陥りがちです。
以下では、よくある課題を3つに整理して紹介します。
1. 採用の目的・ターゲットが曖昧
「急に退職者が出たから採用したい」「営業を増やさないといけない」
こんなふうに採用が“目的”ではなく“手段”として始まってしまうケースはよくあります。
「誰を採るべきなのか」「なぜ今その人が必要なのか」
これが曖昧だと、求人票も評価基準もブレてしまい、ミスマッチや辞退につながります。
2. 属人化していて、ノウハウがたまらない
面接官によって質問が違う、合否判断が「なんとなくの印象」
こうした属人的な採用は、担当者が変わるたびに“ゼロからのスタート”になりやすく、再現性がありません。
評価観点や質問内容、対応の仕方を言語化・テンプレート化していくことで、質の高い選考体験が“設計”できるようになります。
3. 振り返りや改善の仕組みがない
「とりあえず終わった」「人が採用できたからOK」
これでは、次の採用活動に活かせる学びがたまりません。
・どこで歩留まりが発生していたか
・どのチャネルが効果的だったか
・なぜ辞退されたのか
こうしたデータを定点でチェックし、改善していくサイクルが、採用の“再現性”を生みます。
採用のコツ7選|“なんとなく採用”から抜け出すために

採用活動がうまくいかないとき、ありがちなのが「とにかく求人を出してみる」「面接してみてから考える」といった感覚頼みの進め方です。でも、採用の成果を左右するのは、実は“始める前の設計”にあります。ここでは、採用支援の現場を通じて見えてきた「採用成功の鉄板ルール」を7つのコツとして整理しました。
1. 採用の目的とターゲットを明確にする
採用は、「誰でもいい」では始まりません。
なぜそのポジションが必要なのか?どんな課題を解決したいのか?から逆算することが大切です。
- 目的が「人が辞めたから」だけになっていませんか?
- ターゲット像を“年齢・性別”ではなく、“価値観・スタンス”で描いていますか?
このプロセスを省略することは、採用のミスマッチを招く大きな要因となり得ます。
現場とのすり合わせ、できていますか? 実際に活躍している人を見れば、「どんな人がフィットするか」のヒントが隠れています。
2. 採用計画は“なんとなく”ではなく、戦略的に立てる
「今月◯人採用する」だけが計画ではありません。
誰を、いつまでに、どの手段で採用するのかを、事業フェーズとリンクさせて考える必要があります。
- 優先順位はどのポジションですか?
- 採用チャネルに偏りはありませんか?
- 年間スケジュール、立てていますか?
採用は経営とセットで考えるもの。 現場や経営層とのすり合わせが、戦略設計のカギです。
3. 求人票は“求職者視点”で設計する
求人票は企業からのラブレター。でも、一方通行ののラブレターになっていないでしょうか。
「当社はアットホームな職場です」では伝わりません。
求職者が知りたいのは、自分がここで働くイメージが持てるかどうかです。
- 1日の流れ
- チームの雰囲気
- キャリアの可能性
こうした具体性が、心を動かす言葉になります。 求人票は「企業の言いたいこと」ではなく、「求職者に伝わる言葉」で設計することが大切です。
4. 選考フローはスピードと一貫性が命
面接連絡が1週間後。評価の基準が面接官ごとに違う。
こうしたズレに、候補者は敏感に反応します。
- 連絡は翌営業日が理想
- 質問や評価軸はテンプレート化
- 最終面接では「未来の話」を
温度が高いうちに、次のステップへ。 スピードと丁寧さは、両立できます。
5. 面接官こそ、採用の成否を分ける
求人票で興味を持ってもらえても、面接で「なんか違った」と思われたら終わりです。
最後に印象を決めるのは、面接官のふるまいです。
- 圧迫感や上から目線はSNSで広まります
- 面接官トレーニングは定期的に実施していますか?
面接官は会社の顔。 誰が話すかで、企業の魅力は180度変わります。
6. 内定後フォローは“入社までの設計図”で
せっかく内定を出しても、放置したら辞退されます。
候補者にとっての「空白期間」は、不安そのものです。
- カジュアルなフォロー面談
- 入社までのスケジュール共有
- 配属予定メンバーとの顔合わせ
内定者フォローは、言うなれば「恋人期間」。定期的な連絡や細やかな配慮が、入社への安心感につながります。
7. 採用活動は振り返りと改善が命
「うまくいかなかったな」で終わらせていませんか?
- 書類通過率、面接辞退率、ちゃんと見ていますか?
- 面接官のコメントは残っていますか?
- 辞退理由は分析できていますか?
採用は感覚ではなく、データと仕組みで改善するもの。次に活かすことで、再現性のある採用体制が育ちます。
続いて、「どこから始めればいいかわからない」という方のために、採用改善を実行に移す5つのステップをご紹介します。
採用チャネルの選び方|目的別に“ハマる手段”を見極めよう
求人手法は、「とりあえず有名な媒体に出す」「紹介会社を使う」では成果につながりません。重要なのは、“何のために採用するのか”という目的に応じて、チャネル(手段)を戦略的に選ぶことです。
以下のように、目的に応じて有効なチャネルは変わってきます。
採用目的別|おすすめのチャネルマップ
媒体は単体で使うより、複数チャネルを目的別に使い分ける“設計力”が成果を分けます。
| 採用の目的 | おすすめのチャネル |
| 母集団形成を増やす | 求人広告・媒体 |
| 即戦力を採用したい | エージェント・ダイレクトリクルーティング(DR) |
| 採用単価を抑えたい | リファラル・自社HP |
| ブランディングも強化したい | note・SNS・ピッチ資料 |
1. 母集団形成を増やしたい
おすすめ:求人広告・求人媒体
幅広い求職者にアプローチできるため、「まずは数を確保したい」場面に有効です。ただし掲載内容次第で結果が大きく変わるため、ターゲットに刺さる表現・条件設計が重要です。
2. 即戦力を採用したい
おすすめ:人材紹介(エージェント)・ダイレクトリクルーティング(DR)
経験・スキルが明確な人材をピンポイントで採用したい場合に最適です。 自社に合う人材かどうかの“見極め精度”と“スカウト文面の工夫”が成功のカギです。
3. 採用単価を抑えたい
おすすめ:リファラル採用・自社採用サイト(HP)
コストをかけずに質の高い応募を得たいときは、社員の紹介や自社ページの活用が有効です。特にリファラルはカルチャーフィットしやすく、定着率も高い傾向があります。
4. 採用ブランディングも強化したい
おすすめ:note・SNS・ピッチ資料
「会社の想い」や「働く人のリアル」を発信することで、長期的な認知・共感を醸成できます。短期的な成果というより、“選ばれる企業”づくりの土台になります。
チャネルは単体で使うより、“目的に応じて組み合わせる”ことで成果が上がります。
採用活動を改善する具体的なアクションプラン
「コツや手法はわかったけれど、具体的に何から手をつければいいか分からない」そんな方に向けて、採用活動を“感覚”から“構造”へと変える5つのステップを紹介します。
属人化しがちな採用業務を、誰がやっても再現できる体制に整えるための“仕組み化の道筋”です。
ステップ1:目的を言語化する
採用のスタート地点は、「なぜこの人材が必要なのか」を明確にすることです。
営業組織の商談化率を上げたい、新規事業を動かしたい――そんな経営や事業課題から逆算して、採用目的を言語化しましょう。
- 配属先のマネージャーにヒアリングしてターゲット像をすり合わせる
- 経営層と採用目的を共有し、全社で「採用の方向性」を持つ
ステップ2:戦略と計画を設計する
「誰を・いつ・どんな手段で採用するか」を、感覚ではなく設計に落とし込みます。
- 採用ターゲットごとに「チャネル×アプローチ」のマトリクスを作る
- 年間カレンダーを「募集期/選考期/振り返り期」に分けて設計
- 応募数、通過率、辞退率などのKPIを定めて月次で共有する
ステップ3:候補者体験を設計する
選考は「企業が見る場」であると同時に、「企業が見られる場」でもあります。
“応募者がどんな体験をするか”の視点で設計すると、離脱や辞退が減ります。
- 求人票には「1日の流れ」「チーム構成」「柔軟な働き方」などを記載
- 各選考で「何を評価するか」「どんな会話をするか」を明確にする
- 採用説明資料に社員のリアルな声を取り入れる
ステップ4:内定後の関係性を設計する
内定から入社までの時間は、“採用活動のクライマックス”とも言えるフェーズ。
この間の体験が、承諾にも定着にも影響します。
- 入社までのスケジュールと手続きの流れを一覧化して共有
- カジュアル面談や配属先との顔合わせを取り入れる
- 非公式の接点(LINEやSlackなど)で関係性を深める
ステップ5:改善サイクルを仕組み化する
やりっぱなしの採用では、いつまでも同じ課題を繰り返してしまいます。
定期的な振り返りとナレッジの蓄積が、再現性を生み出します。
- 月次で応募数・通過率・辞退理由などを定点で振り返る
- 面接後に「良かった点・改善点」を面接官全員で共有
- 求人票や質問リスト、選考評価基準などをナレッジベースに蓄積
「採用がうまくいかない」と感じている方は、まずは小さな改善から始めてみてください。具体的なアクションを実施することで、属人的な「感覚採用」から抜け出し、安定した成果を生む再現性のある採用体制が構築できます。
現場から学ぶ:採用が変わった企業に共通すること
採用支援の現場では、「やり方をガラッと変えた」よりも、「考え方を少しずつ構造化した」企業の方が、着実に成果を出しています。ここでは、アールナインが支援してきた企業の中から、特に印象的だった3つの改善ストーリーをご紹介します。
1. “活躍する人”の定義を見直したことで、ミスマッチ採用が激減
業界(従業員規模)
メディア関連(50〜100名)
課題
「自分の意見を発信できるタイプが合う」と考え、自己主張が強い候補者を積極的に採用していたが、入社後すぐにカルチャーギャップで離職するケースが続出。特に社長交代後の数年間で、離職率は1割→4割に急上昇。
取り組み
- 全社員に適性検査を実施し、「実際に活躍している人材像」を客観的に分析
- 管理職層との対話から、「調整力があり、協働できる人」の方が社風にフィットするという仮説が浮上
- ターゲット像を「発信力」から「共創力」重視に変更し、面接評価軸を見直し
結果
採用ペルソナの刷新により、応募数は維持しつつ、定着率が大幅改善(離職率5分の1に減少)。配属後の定着・活躍にも手ごたえあり。
2. 面接設計を“属人化”から“仕組み化”へ変えて、辞退率が激減
業界(従業員規模)
製造業(5,000名以上)
課題
新卒採用を全国で展開していたが、年間3,500件以上の1次面接を人事部が直接対応。準備や移動の負荷が大きく、候補者への対応が雑になり、辞退率が30%を超えていた。
取り組み
- 面接代行により、事前設計したマニュアルと評価表を活用して1次面接を外部化
学生の志向性に合わせた質問設計・言葉のトーンなどをすり合わせ - 面接ごとに“伝えるべき訴求ポイント”を整理し、印象のバラつきを防止
結果:
辞退率は30%→8%に改善。学生からの「話しやすかった」「企業理解が深まった」というポジティブな声も増加し、面接官の育成負荷も軽減された。
3. 面接官トレーニングで、候補者の信頼とブランドイメージが回復
業界(従業員規模)
IT・ソフトウェア開発(3,000名以上)
課題
一部の面接官の「高圧的」「上から目線」な振る舞いが、SNSで悪評として拡散。採用広報に注力していたにもかかわらず、内定辞退率が増加。
取り組み
- 面接官100名に対して、トレーニングを4回に分けて実施(評価観点・伝え方・態度など)
- 模擬面接&フィードバックにより、表情やリアクションの癖を可視化
- 評価基準・選考意図の統一でブレを解消
結果
面接の質が大きく改善し、「面接が好印象だった」「しっかり見てくれた」といった声が多数寄せられるように。内定承諾率も安定化し、採用ブランディングの再構築にもつながった。
採用の“よくある悩み”に答えます|実務Q&A
実務の現場では、仕組みや考え方は理解できても、「結局どう進めれば?」と手が止まる瞬間があります。ここでは、採用支援の現場でよく聞かれる質問とそのヒントをまとめました。
Q1. 応募者の“人間性”って、面接でどう見極めればいい?
A. 一貫した質問設計と、価値観に踏み込む対話がカギです。
「どんな時にやりがいを感じますか?」「誰かと意見が食い違ったとき、どんなふうに対応していますか?」といった問いから、その人の判断基準やスタンスが見えてきます。
ヒント
- “行動”ではなく“思考”を問う質問を入れる
- 表情やエピソードの具体性に注目する
- 面接ごとに質問を固定化して、比較しやすくする
Q2. 経歴やスキルが本物か、どうやって確かめる?
A. 「できること」ではなく「やってきたこと」で確認します。
「〇〇の経験があります」だけでは不十分。「どんな場面で?どう工夫した?結果どうだった?」と掘り下げると、実態が見えてきます。
ヒント
- STAR法(Situation/Task/Action/Result)で深掘る
- スキルより、再現性と学びの姿勢に注目
- 同じ内容を複数の面接官で確認して整合性を見る
Q3. 自社に“合いそうかどうか”って、どう判断すれば?
A. 自社のカルチャーを言語化しておくことが第一歩です。
たとえば「スピードより正確さ重視」「個人よりチームで成果を出す」など、自社の価値観を軸に質問・評価を組み立てましょう。
ヒント
- ハイパフォーマーに共通する行動特性をリストアップ
- カルチャーに合う/合わないを事前にチームですり合わせ
- 面接時に「当社で大切にしていること」に共感しているかを確認
Q4. なかなか基準を満たす人が現れないのはなぜ?
A. ターゲット設定が狭すぎる、または理想が高すぎる可能性があります。
「すべての条件を満たす完璧な人材」を求めるのではなく、「現状の組織にフィットし、成長の余地がある人材」を迎え入れる視点が、より実効性の高い採用につながります
ヒント
- 「must要件」「want要件」に分けて行う
- 育成前提で“ポテンシャル採用”を検討
- 「早く採用」より「育てやすい人材を採用する」視点に切り替える
Q5. 応募者の条件要求が多くて、対応しきれない…
A. まずは“譲れない軸”を明確にし、柔軟に伝えることが大切です。
すべてに応えようとせず、「ここは応えられます」「ここは難しい」と対話を設計することで、むしろ信頼を得ることができます。
ヒント
- 応募者の要望が多い理由(不安・前職の失敗)を読み取る
- 勤務条件だけでなく、“働きやすさの工夫”を伝える
- 条件を交渉でなく“すり合わせ”として捉えると関係性が築きやすい
まとめ|“感覚採用”から卒業し、構造で成果を出す
「採用活動は、“やり方”だけでなく“考え方”を変えることで、大きく変化します。属人化・場当たり・思いつきの採用から、構造と仕組みに基づいた採用へ。本記事では、アールナインの支援現場で見えてきた「採用のコツ7選」と「改善の5ステップ」をご紹介しました。
採用のコツ7選(再確認)
- 採用の目的とターゲットを明確にする
- 採用計画は“なんとなく”ではなく、戦略的に立てる
- 求人票は“求職者視点”で設計する
- 選考フローはスピードと一貫性が命
- 面接官こそ、採用の成否を分ける
- 内定後フォローは“入社までの設計図”で
- 採用活動は振り返りと改善が命
成果を変えるのは「感覚」ではなく「構造」
採用は、企業の“入り口”をつくる最重要活動です。小さな工夫と仕組みの積み重ねが、応募者との信頼を育て、定着・活躍につながります。
まずは、「何を目的に」「どんな人を」「どのように採るか」を、チームで言語化するところから始めてみてください。
▶ 採用活動の見直しをご検討中の方へ
当社では、採用の設計・運用から、求人票や面接フローの見直し、代行業務までトータルでご支援しています。 「何から手をつければいいか分からない」というご相談も歓迎です。まずはお気軽にご相談ください。
この記事の監修者:
1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。