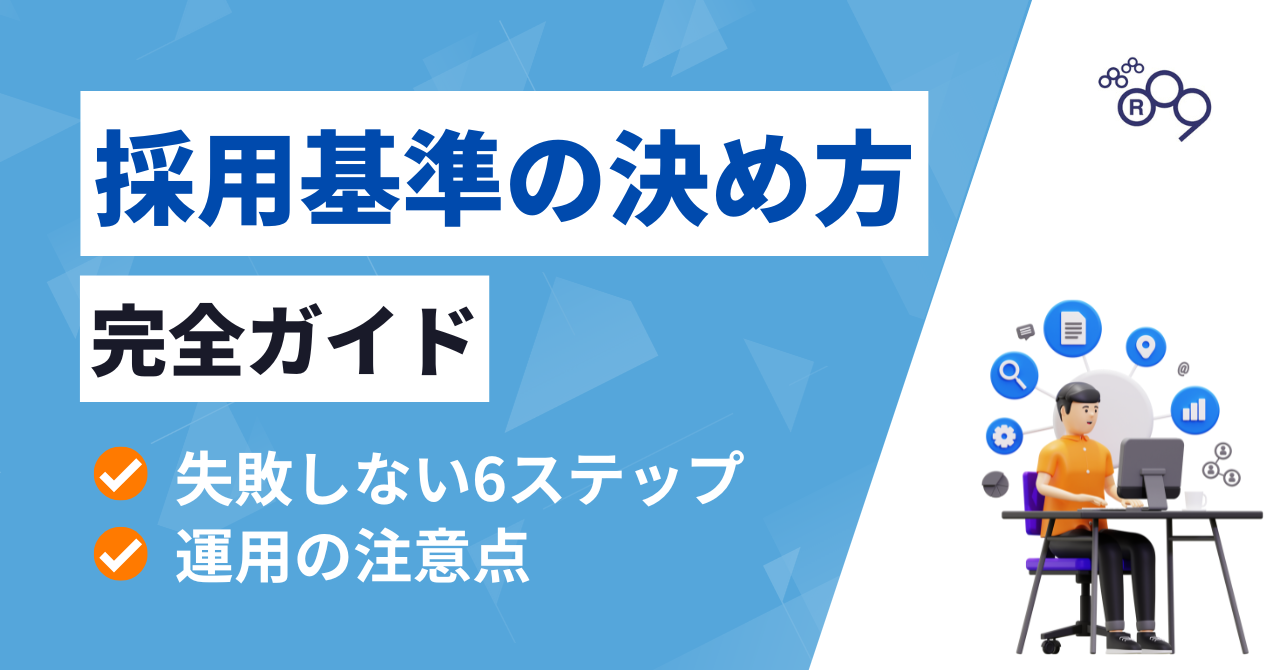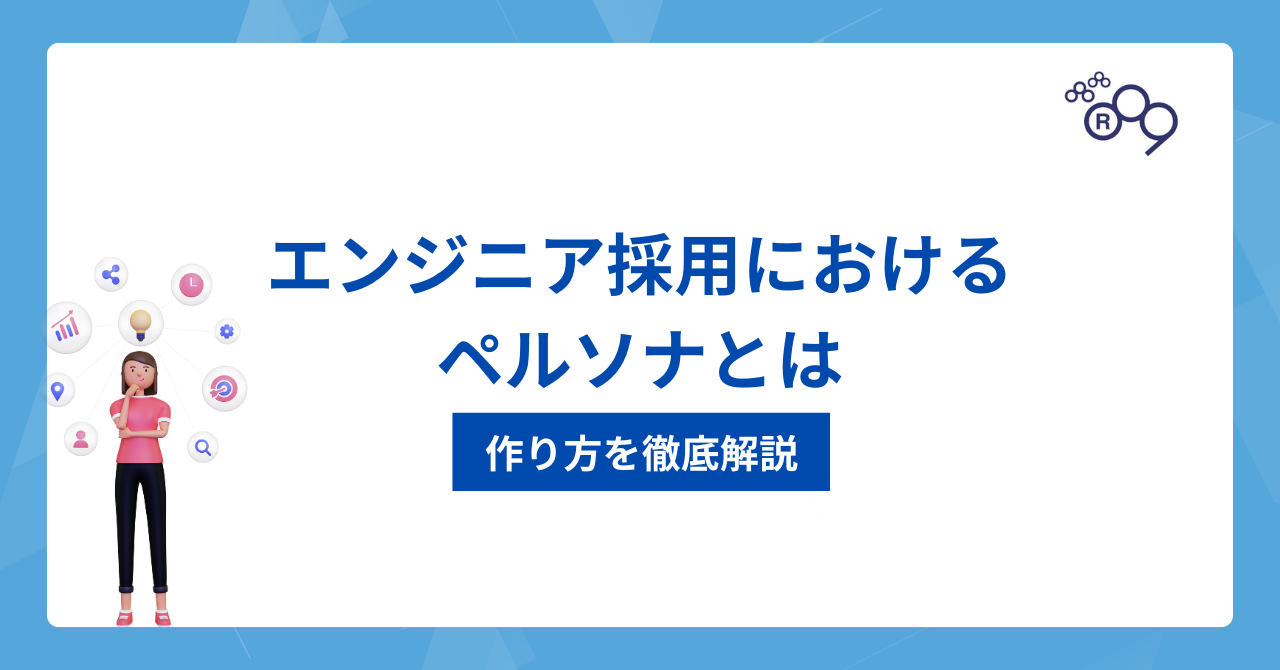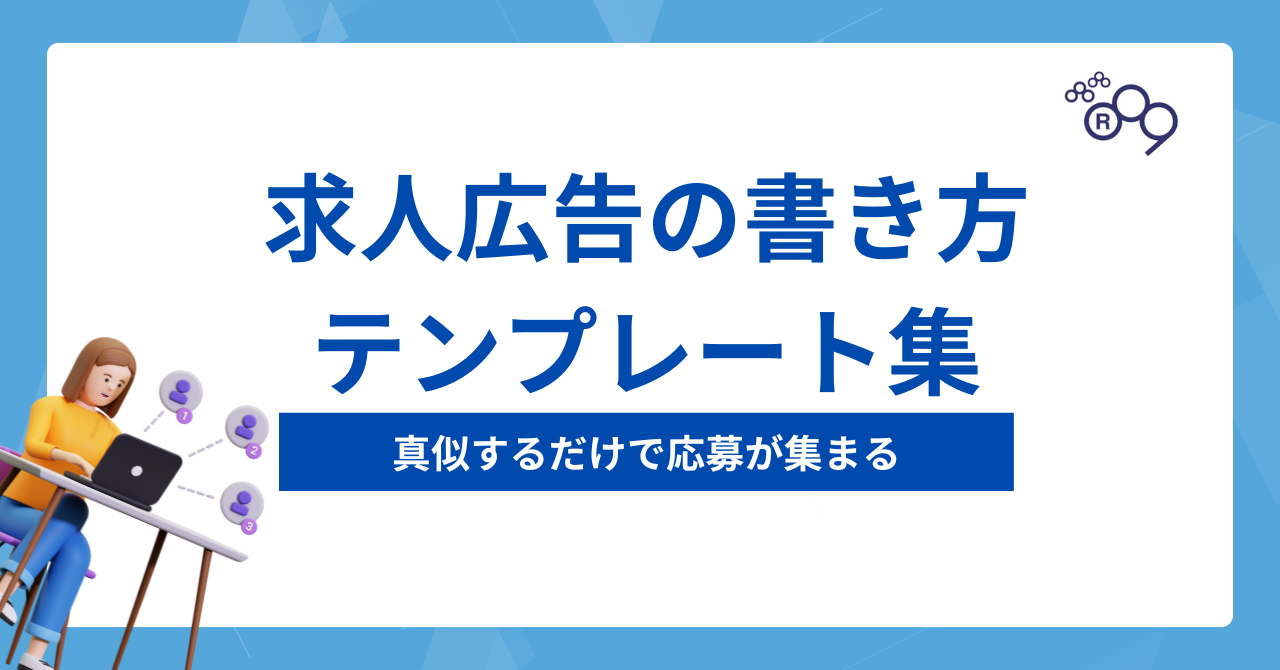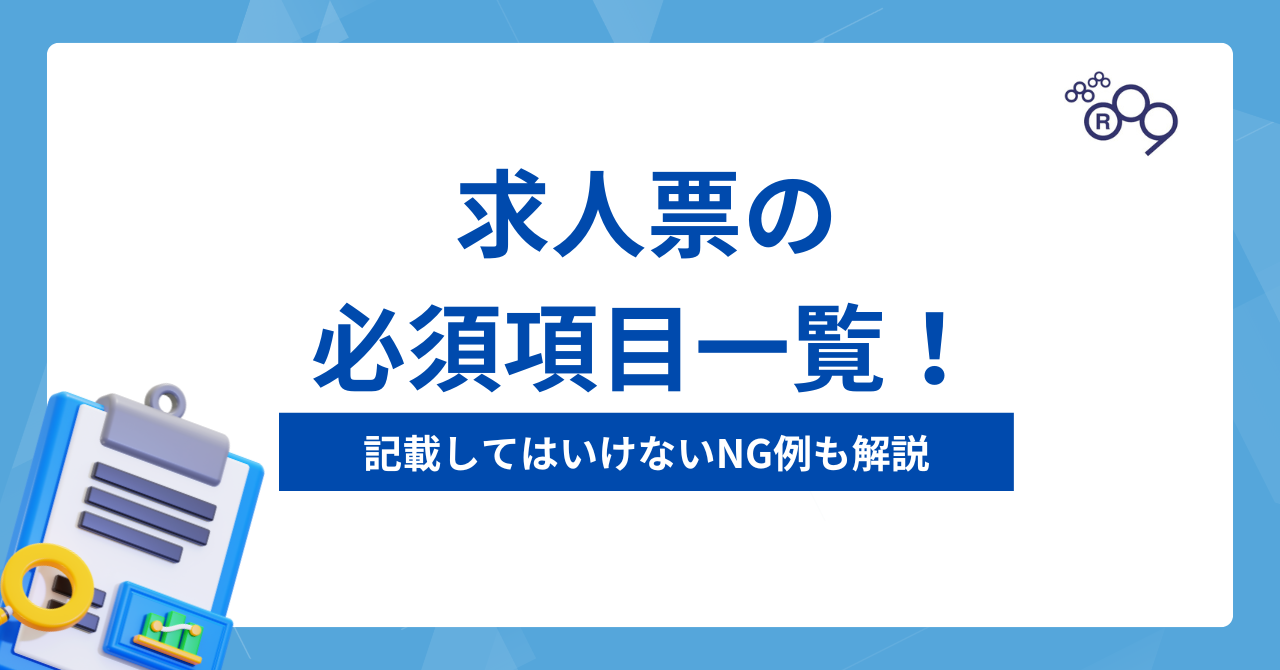採用ミスマッチの正体とは|現場を巻き込み防止する4つの具体策
公開日: 2025年08月05日
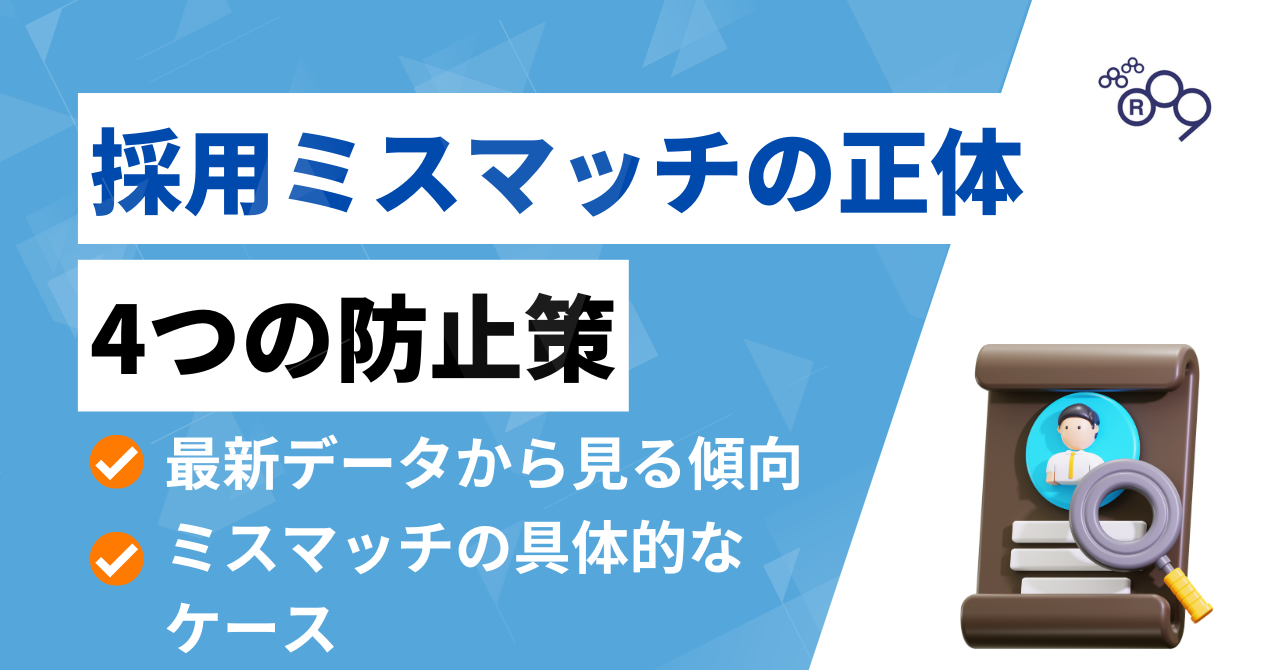
「実績もあって、面接の印象も良かったのに、活躍しない」
「早期離職が続いている」
そんな“採用ミスマッチ”に頭を悩ませていませんか?
スキルも経歴も十分なはずなのに、なぜうまくいかないのか。その背景には、価値観やスタンス、カルチャーとのズレという“見えにくいギャップ”が潜んでいます。
本記事では、採用ミスマッチの定義から、よくある具体例、さらに今日から実践できる防止策までを、実務目線でわかりやすく解説します。
- 採用後に「やっぱり違った…」を防ぎたい
- 面接で“自社に合う人”を正確に見極めたい
そんな方は、ぜひ最後まで読んでください。
「採用ミスマッチ」とは?
そもそも、採用ミスマッチとはどういったものなのでしょうか。
採用ミスマッチとは、「期待と実態のズレ」
採用ミスマッチとは、企業が期待していた人物像と、実際に入社した人材の特性・スキル・姿勢がかけ離れている状態を指し、多くの企業で問題になっています。
たとえば、以下のようなケースは典型的な“カルチャー&スキルミスマッチ”です。
- 自主性を期待していたのに、指示待ち姿勢が強く、全く動けない
- 即戦力として採用したが、基本的な業務理解やITスキルに乏しく教育コストばかりかかる
- チームで連携して動く文化なのに、極端に個人プレー志向で周囲と噛み合わない
- 「共感してます」と言っていたのに、価値観やスタンスが明らかにズレていて社内に不満を撒き散らす
こうしたズレは、面接時に見抜けなかったことへの後悔に繋がりやすく、現場や経営層から「人事の目利きが甘い」「どうしてこんな人間を採用したのか」と責められるきっかけにもなりかねません。
企業で実際に発生している、採用ミスマッチの現状
2024年に株式会社PRIZMAが実施した「求職者と人事採用担当者に関する調査」によると、
人事・採用担当者の87%が「採用ミスマッチを経験した」と回答しています。
また、20〜30代の新卒・中途入社の求職者側に対して、
「入社後に“想定と違う”と感じたことがあったか?」と尋ねた結果がこちらです:
- かなりあった:16.1%
- 少なからずあった:60.2%
- なかった:23.7%
つまり、実に76%以上が“何らかのギャップ”を感じていることが明らかになっています。
さらに、「具体的にどのような点でギャップを感じたか?」という質問に対する上位3つの回答は以下の通りです:
- 事業内容が思っていたものと違った(31.6%)
- 職場の雰囲気・人間関係があまり良くなかった(25.9%)
- 思っていたキャリアやスキルが身につかなかった(21.7%)
このように、条件面だけでなく、価値観・職場文化・成長機会など“目に見えにくい部分”でのミスマッチが多発しているのが現状です。
採用成功=スキル・条件マッチだけでは成立しない時代。
「カルチャー・期待・成長観」まで含めた総合的なマッチングが問われています。
引用元:株式会社PRIZMA「求職者と人事採用担当者に関する調査」(2024年)
https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper63
採用ミスマッチの具体的なケース
採用ミスマッチは、単に「合わなかったね」で済まされる話ではありません。多くの企業で起きているのは、“一見よさそうな人材”を採用したのに、いざ入社してみると期待とのギャップが大きかったというケースです。この章では、具体的なミスマッチの例を紹介します。
例①:中途営業職 ― スキルはあるがカルチャーが合わない
採用背景:
営業経験が豊富な人材を採用。前職ではトップセールスとして活躍しており、選考中は「個人ではなく、チームで成果を出す文化に共感している」と話していた。
入社後の状況:
たしかに営業としての実績はあるものの、過去のやり方に固執し、チームメンバーへのダメ出しや否定的な発言が目立った。
自分の手法を押し付けようとする姿勢に、周囲の士気は低下。
共有や協働を重視する文化にも馴染めず、チーム内には不満が噴出。
最終的には馴染むことができず、半年で退職に至った。
採用時の課題:
面接では「実績」や「論理的な受け答え」ばかりに注目し、「カルチャーに共感します」という言葉を鵜呑みにしてしまった。結果として、「個人主義的な価値観」や「前職の成功体験に強く依存する傾向」に気づけなかった。
例②:新卒エンジニア職 ― 学力は優秀、でも主体性ゼロ
採用背景:
超難関大学出身で、技術試験も高得点。「まさかうちのようなベンチャーに来てくれるとは」と期待が高まり、大きな戦力になると確信して採用。
入社後の状況:
与えられた作業はこなすものの、自ら課題を見つけたり、提案・実行したりする主体性が見られない。
マニュアルや研修が整っていない環境に戸惑い、自主的に学びにいく姿勢にも欠けていた。
指示待ちの傾向が強く、ベンチャー特有の“自走力”が求められる環境には適応しきれなかった。
採用時の課題:
面接では「地頭の良さ」や「知識量」にばかり目を向け、肝心の行動特性や成長意欲を見極めきれなかった。
インターンやアルバイト経験についても深掘りが甘く、当時どのように動いていたかを確認し損ねた。
採用ミスマッチを防ぐために企業ができること
採用ミスマッチは、「見極めの甘さ」や「候補者とのすれ違い」によって生まれます。
つまり、「この人で本当に良いのか?」を見抜く力と、「うちのリアルはこうです」と正しく伝える力の両方が問われます。
ここでは、今日から実践できる具体策を4つご紹介します。
① 自社にマッチした「価値観」を言語化
採用ミスマッチの多くは、「スキルはあるのに活躍しない」「いい人材だと思ったのに馴染めない」といった、“スタンス”や“価値観”のズレから起こります。
これは、多くの企業で「業務に必要なスキルや経験」は明文化されていても、「自社にフィットする行動特性や価値観」が曖昧なまま選考されていることが主な原因です。
- 前職ではトップセールス → チームでの共有ができず孤立
- 学歴・スキルは十分 → 受け身すぎて自走できない
- 人当たりが良く、印象も◎ → 変化の激しい環境に疲弊して早期離職
いずれも「スキル基準は満たしているが、価値観が合っていない」ことが共通しています。
そのため、要件を見直す際は、“自社で活躍できる人材は、どのような価値観を持っているのか”といったカルチャー面も必ず定義しましょう。その際、人事部門だけで完結せず、現場や経営層と認識をすり合わせることが必須です。
- 決まりきったやり方に固執せず、変化を楽しめる
- 「まずやってみる」姿勢がある
- チームで成果を出すことにやりがいを感じる
このように、自社にマッチする「価値観」を言語化しましょう。
② 採用基準を面接へ落とし込み、見極める
次に、上記で定めた要件を満たしているか、面接で見極めていく必要があります。
面接を誰が担当しても同じ基準で評価できる状態に整えるため、質問項目や評価基準をあらかじめテンプレート化しておきましょう。
たとえば、以下のような「過去の行動事実」に基づいた質問リストを用意しておくと、抽象的な回答に流されずに済みます。
「これまでに自ら改善した業務には、どんなものがありましたか?」
「チーム内で意見がぶつかった経験はありますか?そのとき、どう対処しましたか?」
「工夫した点はなんですか?その際、なぜその工夫をとろうとしましたか?」
こうした質問によって、行動の裏側に潜む価値観を見極め、「自社の求めるスタンス・価値観と合っているか」が見えてきます。
また、面接官同士のすり合わせと評価観点の明確化も欠かせません。具体的には以下のような取り組みが効果的です。
- ロールプレイや模擬面接で、評価基準のブレを確認
- 評価シートを使いながら、「なぜこの点数にしたのか」をすり合わせる
- 観点(例:主体性・課題解決力)ごとにコメント欄を設け、事実と所感に分けて記録
- 評価後にFBを共有し、「次回はこう掘り下げよう」といった改善意識を持つ
「主観でなんとなく○」ではなく、「○と評価した根拠は何か?」まで言語化する文化を育て、現場面接官が同じ目線で価値観を見極める仕組みをつくりましょう。
③ 接点の“量”と“質”を高める
候補者の「価値観」や「スタンス」は、短時間の面接だけで見極めるのが難しいものです。
だからこそ、“面接以外”の形でも複数回接点を持ち、さまざまな角度・視点から候補者を知る機会を設けることがミスマッチ防止に直結します。
接点の量を増やす:複数回の接点設計
・社員座談会(現場メンバーとの雑談形式)
・選考前のフォロー面談(志望度や不安点の確認)
・内定後のオファー面談(入社後の期待値すり合わせ)
こうした“場”を複数用意することで、候補者自身も徐々に本音で話せるようになり、お互いにとっての理解精度が高まります。
接点の質を高める:カジュアル面談の活用
特におすすめなのが、「カジュアル面談」です。
選考前の段階で、お互いを深く知るために実施するもので、評価の場ではなく“対話の場”として設けます。面接よりも前だからこそ、飾りすぎていない候補者の素の姿を見極めやすい場です。
ポイントは、企業側も飾らずに「リアル」を伝えること。
・魅力や強みだけでなく、実際に大変なことや課題も伝える
・候補者の働き方や価値観に関する質問を丁寧に行う
・「どういう時にやりがいを感じるか」「どんな職場環境がストレスになるか」など、深堀りする
こうした本音ベースの対話を通じて、入社後のギャップを未然に防ぐことができます。同時に、候補者からの信頼を得られ、内定辞退の防止にもつながります。
④ 採用後のオンボーディング設計
どれだけ面接を丁寧に設計しても、ミスマッチの“ゼロ化”は現実的には困難です。だからこそ、採用後のフォロー体制=オンボーディングが、定着と活躍への鍵を握ります。
せっかく採用した人材が「なんか違ったかも」と感じて離職する前に、早期にギャップをキャッチし、支援する仕組みが必要です。
・入社1ヶ月間は、週1回の1on1を実施する
→ 不安や違和感をこまめにキャッチ。ちょっとした誤解やモヤモヤが離職に直結する前に対処できる
・メンター制度を導入する
→ 年齢や社歴の近い先輩社員が「質問しやすい」「相談できる存在」として伴走することで、孤立を防げる
この際、下記のような質問を投げかけましょう。
- 「入社前に抱いていた期待と、実際に働いてみてどうだったか?」
- 「不安や不満に感じていることはあるか?」
- 「これからどんなことを学び、どんな貢献をしたいと考えているか?」
これにより、本人が気づかないズレを言語化し、配属・業務内容・教育方針の軌道修正にも活かすことができます。
まとめ
本記事では、採用におけるミスマッチの具体例やその対策について解説しました。いかがでしたか?
- スキルや経験だけで判断していないか?
- 自社に合う価値観やスタンスを言語化できているか?
こうした問いに向き合い、「どうすれば“お互いに納得できる採用”になるか」を真剣に考えることが、採用成功への第一歩です。
特に、人数もリソースも限られた中小・ベンチャー企業にとっては、「採ったけど活躍しない」「すぐに辞めてしまう」という事態が、事業に与える影響は極めて大きいもの。
だからこそ、採用のミスマッチを防ぎ、自社で活躍してもらえるかが、これからの企業成長を左右します。
この記事の監修者:
1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。