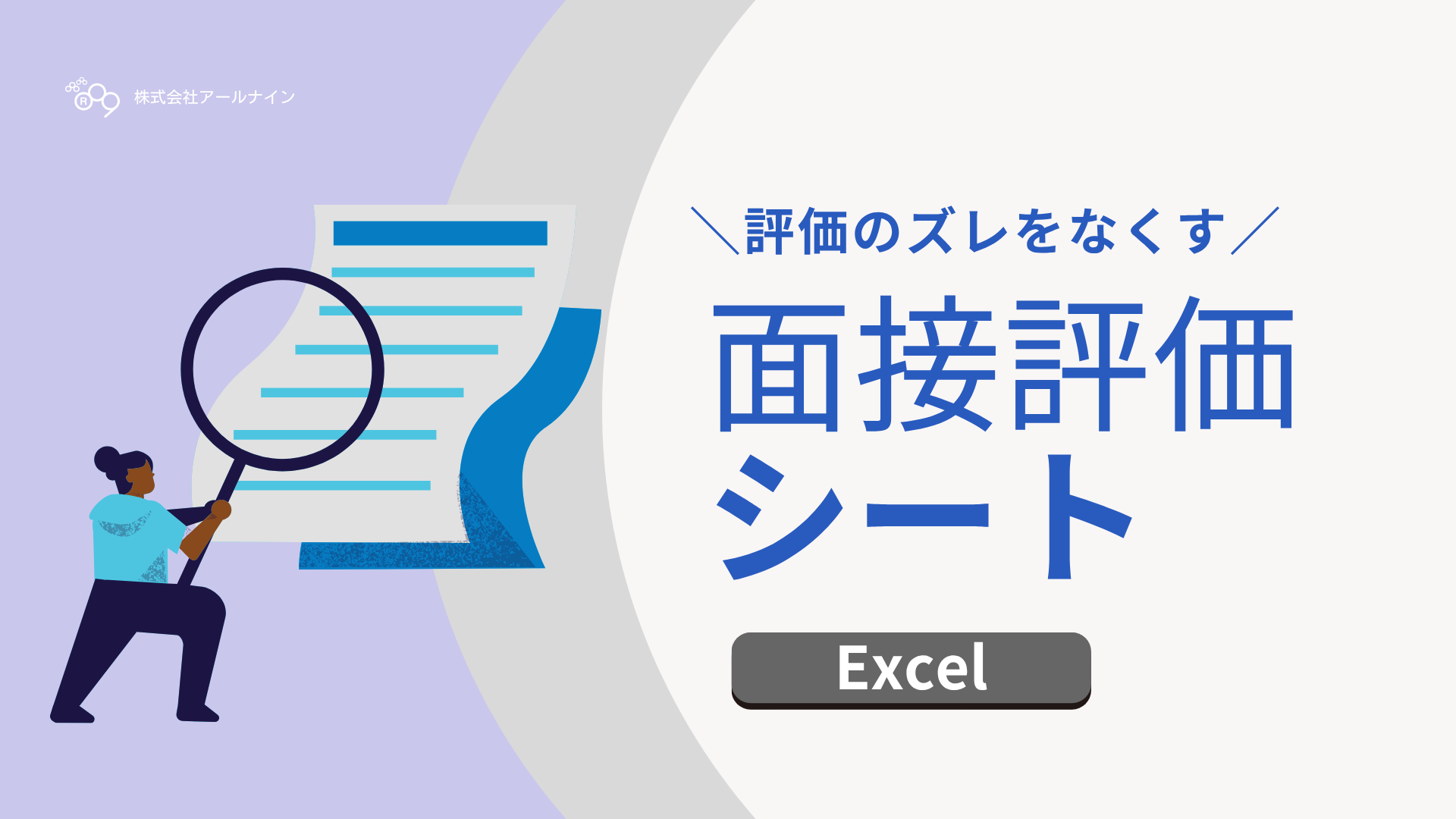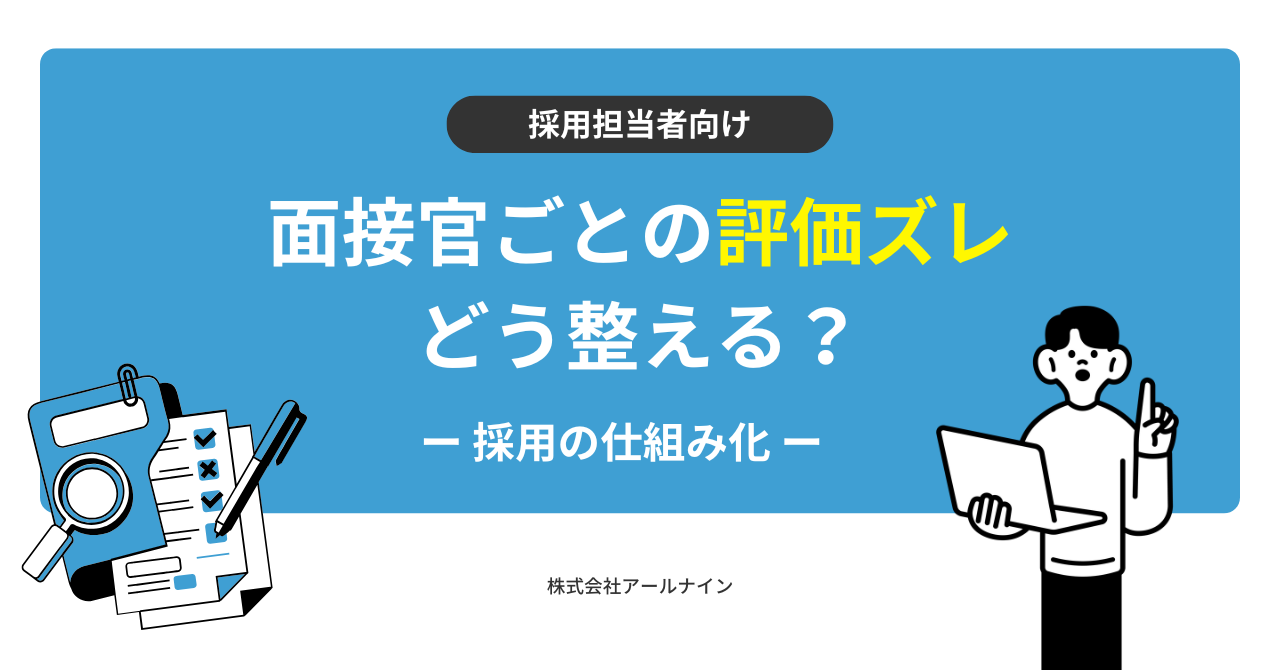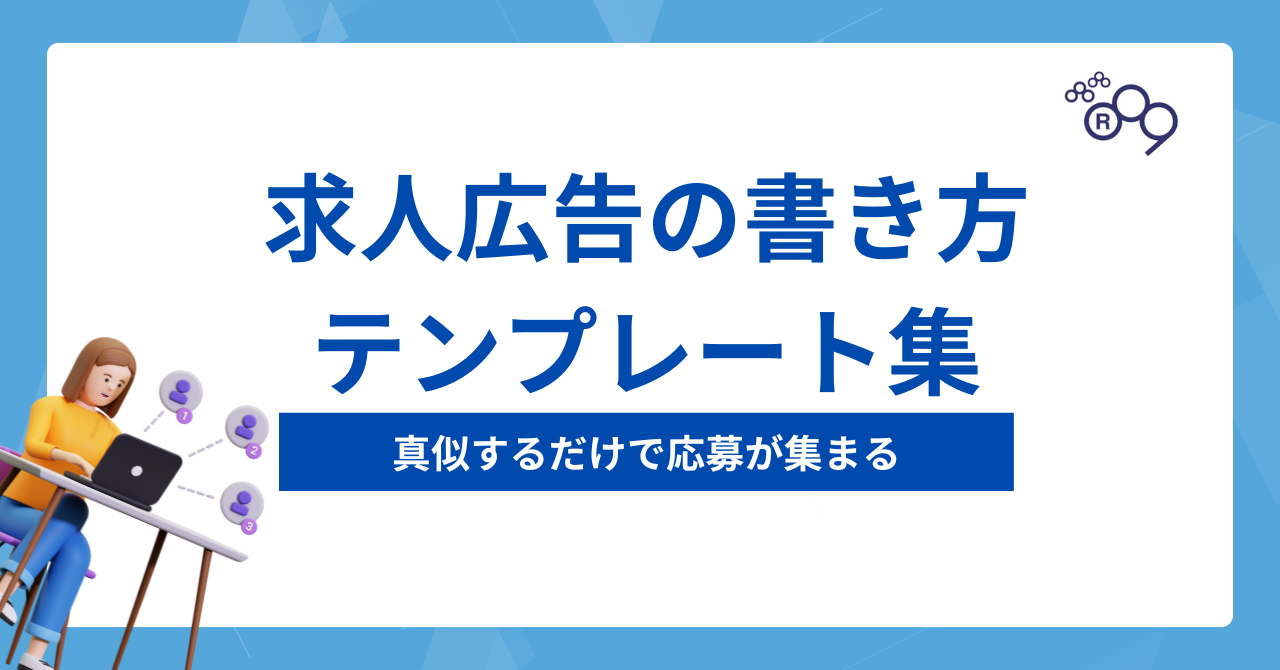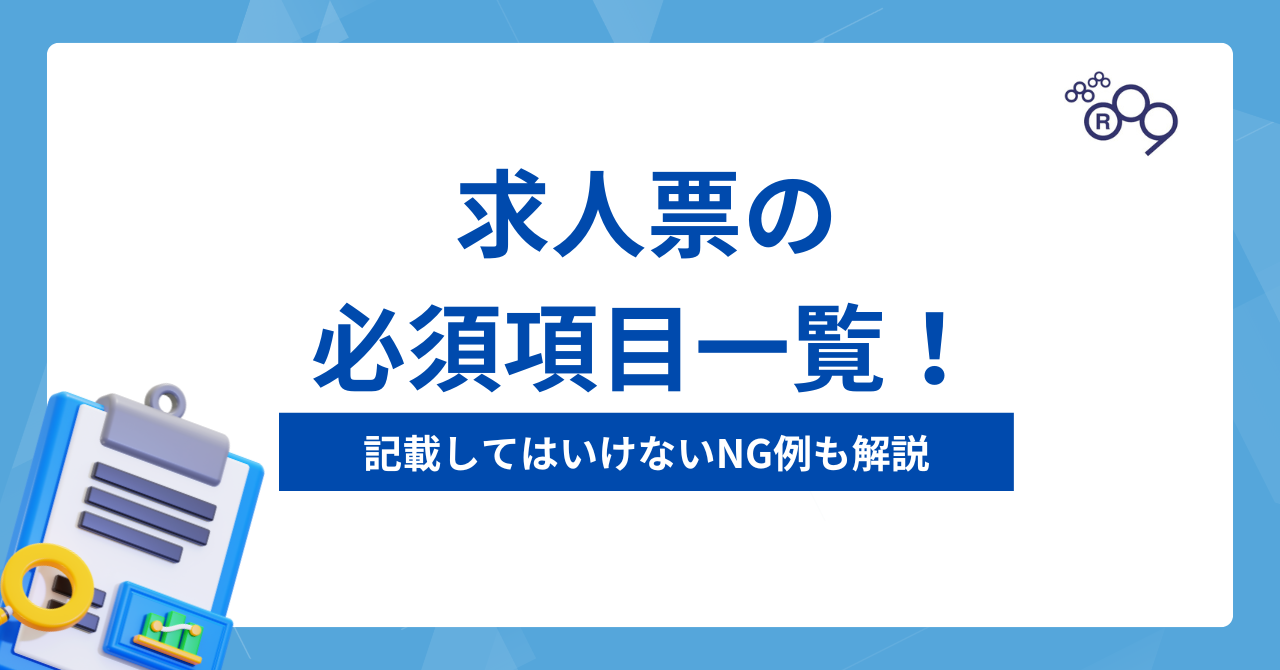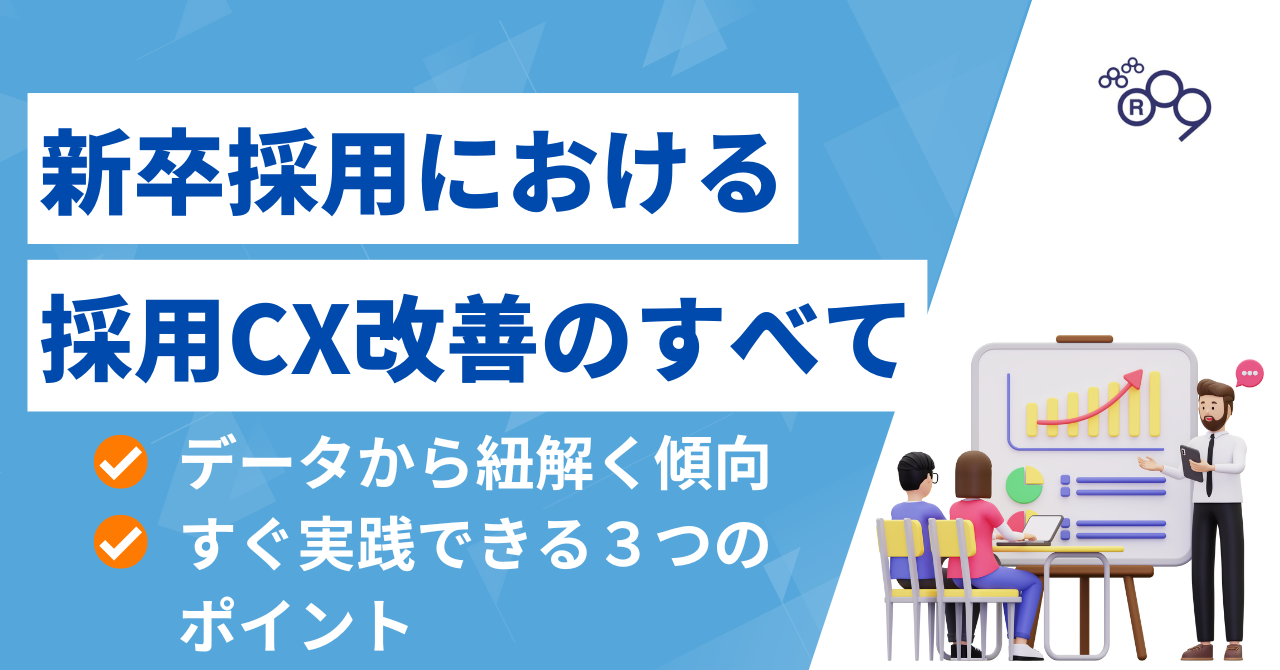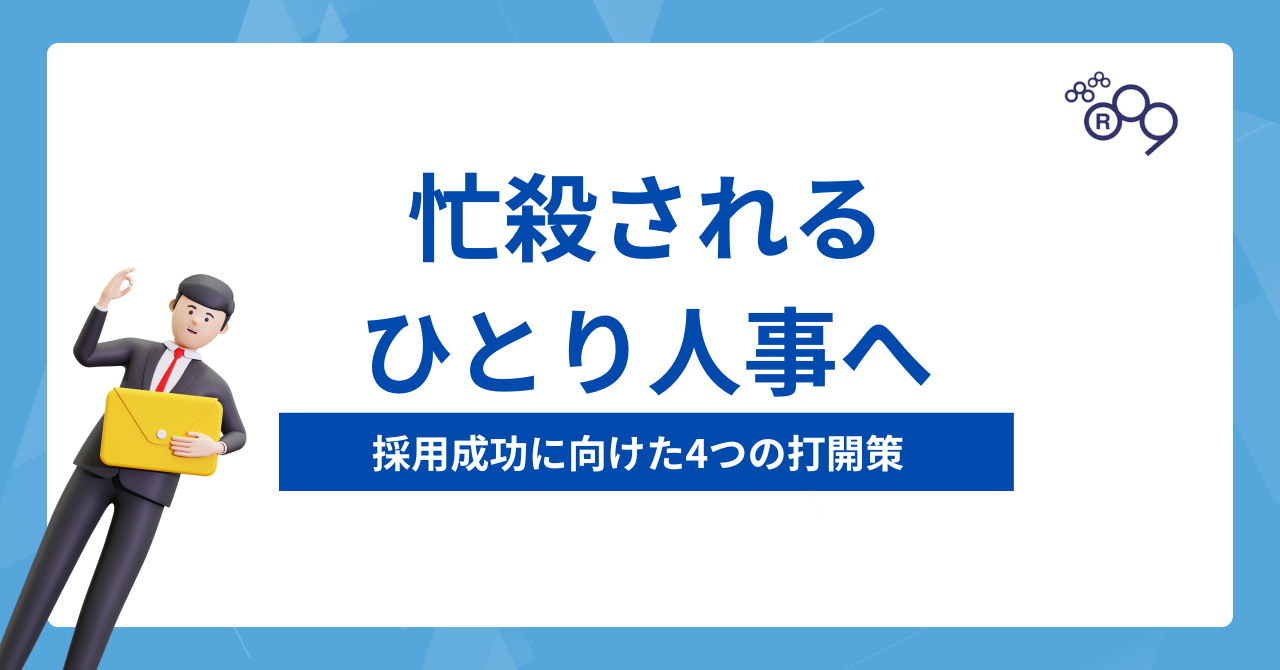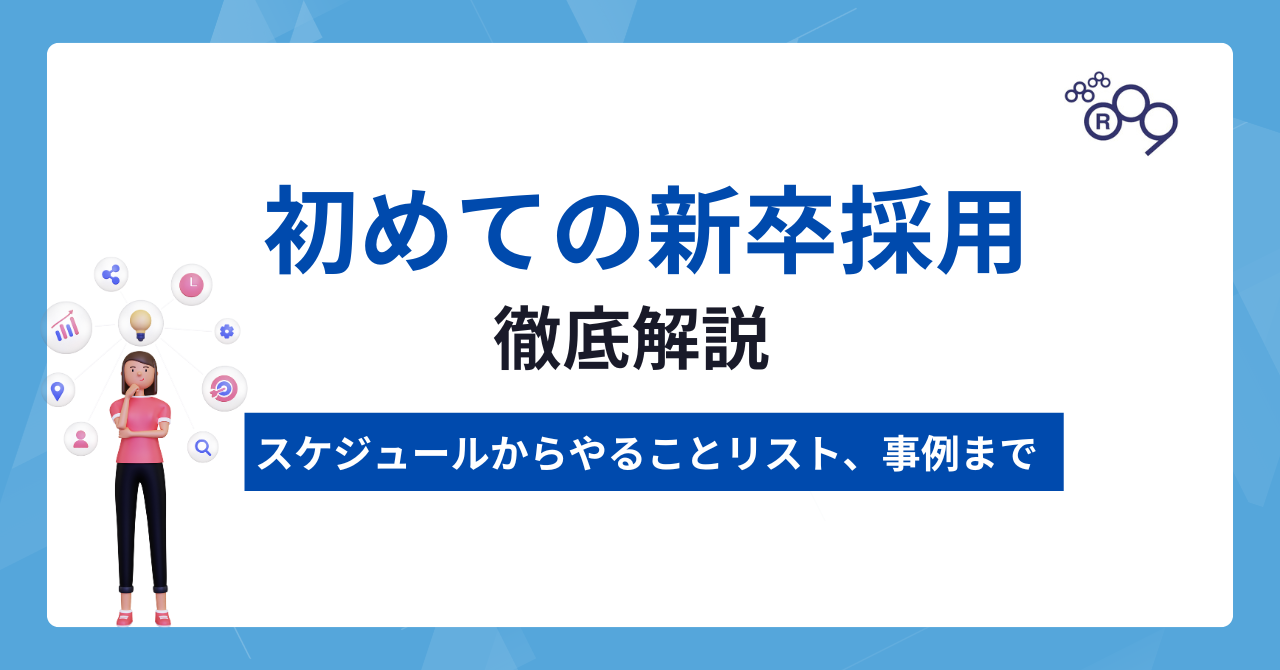【無料テンプレート付き】面接評価シートの作り方|評価基準と質問例つき
公開日: 2021年07月27日 | 最終更新日: 2025年08月07日

今回の記事は「面接評価シート」についての解説です。
採用面接での評価基準にブレがあり、会社方針の軸に沿った採用ができていない。採用面接での印象が良かったので採用したが、入社後に期待するパフォーマンスが見られない。
採用活動に携わる方であれば、そのような経験はありませんでしょうか。
採用面接では、その場の空気感ではなく、明確な基準に沿って採用可否を判断しなければいけません。基準に沿った判断ができなければ、自社が求める人物を獲得できる確率は大幅に下がります。
今回ご紹介する「面接評価シート」はどのような能力を重視するか、各能力に対してどのような基準で判断するのかを可視化することで、面接のブレをなくし、採用活動の成功率をあげる重要なツールです。
面接評価シートは採用活動の軸作りをするツールです。正しい知識を理解し、採用活動に活用していきましょう。
面接評価シートとは
面接評価シートとは、採用面接で”評価する項目”と”各項目の評価基準”を可視化したものです。採用面接で重視して評価すべき項目をまとめ、採用面接を補助し、記録をするためのツールです。
採用担当者が面接で感じた良い・悪いという主観的な印象だけで判断しては、採用活動のクオリティを安定させることはできません。属人的な判断では採用担当者が変わるたびに、採用傾向が大きく変わってしまいます。
面接評価シートを導入することで、下記5つのメリットを享受できます。
- 面接の記録を残すことで評価の振り返りを行い、次回の採用面接に活かせる
- 「主観に基づく評価」から脱却し、応募者を客観的に評価できる
- 面接進行がスムーズになり、質問のブレ・漏れが減る
- 合否の根拠が「見える化」され、社内での説明・振り返りがしやすくなる
- 面接の記録が“資産”となり、育成・配属・次回採用に活かせる
面接評価シートの具体的な作り方【7ステップ】
ここからは、面接評価シートの具体的な作り方を、7ステップに分けて徹底解説していきます。
1. 自社の「求める人物像(ペルソナ)」を明確にする
まずは「どんな人が自社で活躍しているか」を言語化しましょう。
やることは次の3つです。
- 【ステップ1】:過去に活躍している社員を3~5名ピックアップ
- 【ステップ2】:その社員の共通点(行動パターン、考え方、仕事姿勢)をメモ
- 【ステップ3】:以下の軸で整理する
- 属性:年齢、性別、学歴・職歴など
- スキル:専門知識、経験、技術
- 行動特性(コンピテンシー):主体性、スピード感、巻き込み力など
- 価値観:顧客志向、成果へのこだわり、誠実さ など
- 【ステップ4】:「具体的な一人の架空人物=ペルソナ」としてプロファイルを起こす
完成形として、以下のように具体的な1人の架空人物に落とし込みます。
・年齢:33歳
・性別:男性
・家族構成:妻1人、娘1人(2歳)
・所得:650万円
・学歴:早稲田の付属高校~早稲田大学
・職歴:大手転職エージェント→スタートアップの人事コンサル
・業種:toB 向けに無形商材を提供
・職種:営業・マネージャー
・地域:東京
・チーム人数:5名程度
・ライフスタイル:子育てにも力を入れたい。柔軟な働き方をしつつチャレンジしたい。
・パーソナリティ:人当たりが良く、誰とでも分け隔てなく接する。
・仕事で大事にしていること:チームで成果を出す。自由度が高い。新しいことに挑戦できる。
・行動特性:失注理由をチームで振り返る場を自発的に設け、改善施策を実行
2. 必要な評価項目を洗い出す(MUST/WANT/NEGATIVEで分類)
「ペルソナに必要な要素」から評価項目を出していきます。
【ステップ1】:キーワードを洗い出す
- 例:行動力、論理的思考力、対人スキル、改善提案力、向上心…など
【ステップ2】:それぞれを3つに分類
- MUST(絶対必要):これがないと活躍できない
- WANT(あると望ましい):あれば伸び代や応用力が高い
- NEGATIVE(不要):自社文化に合わない特性
評価項目は多くても10項目以内に絞るのが現実的。面接時間内で判断できる数にすること。
3. 各評価項目の「基準・定義・配点」を言語化する
ここまでで評価項目が出そろったら、次にやるのは「何をもって高評価とするか?」の基準づくりです。これを曖昧にしておくと、面接官ごとに基準がバラバラになり、主観評価に逆戻りしてしまいます。
【ステップ1】:5段階評価で統一する
すべての評価項目について、1〜5点の5段階で採点できるようにします。
数字だけではなく、各スコアに具体的な状態像(行動例)を持たせるのがポイントです。
【ステップ2】:1〜5点の評価基準を定義する
たとえば「行動力」の評価を設計する場合、以下のように粒度を揃えて書き出します。
| スコア | 「行動力」の評価について |
| 5点 | リスクをとってでも、課題解決のために自ら動き、周囲を巻き込んで成果を出した経験がある |
| 4点 | 自ら課題を見つけ、関係者を巻き込みながら改善提案・行動に移した経験がある |
| 3点 | 与えられた業務を、指示がなくても計画的に完遂している |
| 2点 | 指示を受けてからであれば、粛々と業務を進められる |
| 1点 | 指示を出さないと動けない、もしくは指示があっても行動が遅い |
このように、面接官同士でブレようのない定義にしておくことが、再現性ある選考の第一歩です。
【ステップ3】:記入フォーマットに落とし込む
評価基準を定義したら、ExcelやNotion、Googleスプレッドシートなどで一覧化しておきましょう。
また、各評価項目に「コメント記入欄」も必ず設けてください。
- どんなエピソードを聞いてこのスコアをつけたか、事実+所感
- 他の評価者に共有すべき懸念
といった定性的な情報もセットで残すことで、あとから振り返ったときの精度が段違いに上がります。
4. 評価項目ごとの「質問例」を用意する
どれだけ立派な評価項目や基準をつくっても、「何を聞いてそれを判断するか」が設計されていなければ、面接はうまく回りません。
ありがちなのが、評価項目と質問がつながっていないケースです。たとえば「主体性を見たい」と思っているのに、エピソードを聞いても主体性があるのかないのか分からない。これでは評価軸と面接内容が乖離してしまいます。
【ステップ1】:各評価項目に2〜3個の質問例を用意する
ここでは例として「主体性」と「論理的思考力」の質問例を紹介します。
● 主体性
- 最近、自ら提案して始めた取り組みはありますか?それはなぜですか?
- 誰かに言われたわけではなく、自分で動いた経験を教えてください。その背景は?
- 目標を達成するために、周囲を巻き込んで工夫したことはありますか?
● 論理的思考力
- 問題に直面した際、どのように解決策を導き、実行しましたか?
- 過去に「納得感ある提案」をした経験はありますか?どうやって構成・整理しましたか?
- 上司や顧客を説得する際、どんな順番・観点で話を組み立てましたか?
「評価項目 × 質問例」は、テンプレートとして1セットにしておくことで、面接官全員の“質問の質”を揃えることができます。
【ステップ2】:STAR面接フレームワークで質問設計の精度を高める
質問例をつくる際は、単発の聞き方で終わらず、STAR面接(状況→課題→行動→結果)で掘り下げられる構造にしておくとベターです。
たとえば:
「◯◯の課題に対して、どんなアクションをとりましたか?」
→ そのときの組織の状況は?
→ なぜそれが課題だと考えましたか?
→ どんな選択肢があって、なぜその行動を選びましたか?
→ 結果はどうなりましたか?今後同じ状況になったら、どうしますか?
この流れを意識すると、表面的な「やったこと紹介」ではなく、思考のプロセスや再現可能性まで評価できるようになります。
5. 合否のラインを決める
評価項目や点数を記録していても、「何点なら合格なのか」という合否ラインが明確でなければ、迷いが生じます。
評価にブレや属人性を持ち込まないためには、事前に「数値基準」と「不合格基準」をルールとして明文化しておくことが不可欠です。
【ステップ1】:合格ラインを点数で定義する
面接評価シートには、通常「5段階 × 7項目=35点満点」などの構成が多いです。
この場合、
- 合格基準:25点以上(全体の7割)
- ボーダーライン:22〜24点
- 不合格基準:21点以下
のように、合否判断のベースラインを定めておきましょう。
「ボーダー層については役員面接・最終面接に回して深掘りする」などの扱い方もルール化しておくと、面接官の判断が迷わず済みます。
【ステップ2】:足切りライン(失点基準)も設ける
総合点だけでなく、「この項目が◯点以下なら不合格」といった“足切り基準”も設けましょう。特に、「合計点では合格だが、能力が偏りすぎている」といったケースも発生しがちです。
たとえば、以下のような設計です:
- 2点以下の項目が2つ以上ある場合は問答無用で不合格
- 「顧客志向」「誠実性」のいずれかが2点以下なら不採用(自社の根幹価値観として重視しているため)
これにより、「総合点は良いけど、この人を採るべきか?」という不安が残るケースでも、ロジカルに判断できます。
もちろん、最終判断は役員面接や現場マネージャーの裁量に委ねる部分も出てきます。
しかし、「合否の大前提はこの基準に沿っている」という共通認識とスクリーニングルールがあるだけで、全体の判断精度が格段に上がるのです。
また、評価シートにこれらの合否基準を記載しておけば、面接官の心理的負荷も軽減されます。
6. 面接官への事前共有・すり合わせ(トレーニング含む)
どれだけ評価シートを精緻に設計しても、それを使う面接官に正しく意図が伝わらなければ、評価の精度は上がりません。
むしろ、「なんとなくで5点」「良い人だったから高得点」という“属人的な運用”がはびこってしまえば、シートを作った意味がなくなります。
そこで重要なのが、面接官への事前共有と「すり合わせの場」の設計です。
【ステップ1】:まずはスライド資料で共通理解をつくる
最初にやるべきは、評価シートの「目的」「背景」「活用方法」をしっかり伝える場づくりです。
面接官向けに以下のようなスライドを用意しましょう:
- なぜ今、面接評価シートが必要なのか(背景・課題感)
- どんな基準で、どのように評価していくのか(具体例付き)
- 質問例と評価項目の紐づけ
- 合否判断ルールの解説(ボーダーや足切りライン)
ポイントは「運用する側の視点」で、“負担にならない・活用しやすい”と感じてもらえる説明を心がけることです。
【ステップ2】:ロールプレイで実践トレーニングを行う
説明だけでは、実際の運用ではうまくいきません。ここでは、過去の候補者の履歴書・職務経歴書を使って模擬面接を行いましょう。
面接官役・評価者役・観察者の3者に分かれてロールプレイすることで、
- どこで評価が分かれるか
- どの質問で情報が引き出しにくいか
- 評価基準が曖昧な項目がどこにあるか
など、実践でのズレや課題が見えてきます。
【ステップ3】:面接後の“点数すり合わせ”を言語化する
面接を実施したら、必ず「なぜこの点数にしたか?」を言語化して共有する場を設けましょう。
たとえば:
- 「行動力は5点とした理由は?どの発言・エピソードからそう判断した?」
- 「Aさんは2点つけたけど、Bさんは4点だった。その差はどこ?」
このプロセスを繰り返すことで、評価の共通言語が組織内に蓄積されていきます。
面接官によって「見るポイント」や「点数のつけ方」がバラついていては、せっかくの評価シートも意味をなしません。
だからこそ、運用前の共有と、面接後の振り返りプロセスをセットで設計することが重要です。
7. 実践を通してPDCAを回す
評価シートは、「作って終わり」「導入して満足」で終わるものではありません。実際に使ってみて初めて、「どこが使いにくかったか」「本当に見極められたか」といった課題や改善点が見えてきます。ここからが本当の運用フェーズの始まりです。
【ステップ1】:面接後すぐの「振り返り」を設ける
面接が終わったら、できるだけその日のうちに10分ほど、評価者同士で振り返りをしましょう。
- 「マニュアルにある質問で、エピソードの深堀が実践できたか?」
- 「点数の基準が曖昧で、判断に迷う箇所はなかったか?」
といったポイントを会話するだけでも、評価精度は大きく変わります。
面接直後は情報の鮮度が高いため、習慣化するのがおすすめです。
【ステップ2】:月次/四半期単位で「レビューの場」を設ける
一定期間評価シートを使ったら、人事と現場メンバー合同でレビュー会を開きましょう。
見るべき観点は以下のようなものです。
- 評価項目は実際の活躍人材とズレていないか?
- 面接で使いづらい項目や、判断に迷った評価基準はなかったか?
- 質問と評価の紐づけがあいまいになっていないか?
- 合否判断ルールは妥当だったか?ブレは起きなかったか?
こうした確認を通じて、評価シートの精度は高まります。
【ステップ3】:採用以外にも“活用”を広げる
一定期間シートが現場に定着してきたら、それを採用以外の場面でも活用できるように展開しましょう。
- オンボーディング設計に活用:入社前の評価内容をもとに「初期3ヶ月の育成目標」を設計
- 配属判断の材料として:どんな強み・志向があるかを配属会議で共有
- 昇格・評価面談のベースに:面接時から一貫した評価軸で成長の可視化が可能に
評価シートを上手く活用できれば、組織全体で価値観を共有できる資産になります。
面接評価シートで取り入れるべき評価項目例
面接評価シートを作成するにあたり、まず、どういった能力を重視するかを考えていきます。
自社が求める人物には、どのような能力要素を持っていて欲しいかを具体化していく作業です。
以下のような能力要素を参考にし、自社が求める人物に必要な能力を組み立てていきましょう。
【能力・技術面】
- 知識
- 論理的思考力
- 問題解決力
- 分析力
- 理解力
- 判断力
- 表現力
- クリエイティビティ
- コミュニケーション能力
【行動面】
- リーダーシップ
- 協調性
- 積極性
- 主体性
- 責任感
- 向上心
- ストレス耐性
上記以外に「社会人基礎力」を軸にして必要な要素を考えてみるのも良いでしょう。
「社会人基礎力」とは、2006年に経済産業省が提唱した「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」のことです。
「社会人基礎力」は下記3つの能力とさらに要素へ分類した12の能力要素からなります。
①「前に踏み出す力」
- 主体性
- 働きかけ力
- 実行力
②「考え抜く力」
- 課題発見力
- 計画力
- 想像力
③「チームで働く力」
- 発信力
- 傾聴力
- 柔軟性
- 状況把握力
- 規律性
- ストレスコントロール力
【出典】経済産業省「社会人基礎力」(https://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/)
面接評価シートを活用するうえでの5つの注意点
面接評価シートの導入にあたって、気をつけなければならない注意点もいくつかあります。ここでは面接評価シートの導入に関する注意点を解説いたします。
面接評価シートの導入にあたっての注意点としては下記があげられます。
- 自社の人材の要件と面接評価シートの項目が連動していない
- 評価項目の数が多すぎる
- 評価項目の定義や基準が曖昧
- 他社のサンプルをそのまま使ってしまっている
- 面接評価シートの運用が目的化している
1.自社の人材の要件と面接評価シートの項目が連動していない
まず、失敗事例として多いのは、面接評価シートの評価項目が「自社の求める人物像」であるかを判断するのに適した項目になっていないというケースです。
学歴、年齢などの世間一般で重要視されがちな項目を、自社の必要要件であるかの判断なしに評価項目として入れてしまっている場合は、あらためて項目の見直しが必要です。
大事なのは、世間一般のハイスペック人材に合わせることではなく、自社の求める人物像の要素から面接評価シートを作成していくことです。
2.評価項目の数が多すぎる
面接評価シートを作るうえで、評価項目の数が多すぎてしまうのも問題です。評価項目が多すぎると、面接中に面接評価シートの項目を埋めながら進行することが困難になります。
また、そもそも評価項目が多すぎるということは、重要な要素に絞りきれていない可能性が高いです。全ての理想を満たした人材を見つけることは、事実上かなり難しいです。
そのため、求める能力要素に優先順位をつけ、優先して求める項目をピックアップし面接評価シートを作る必要があります。
各能力を「MUST(必須)」「WANT(あると望ましい)」「NEGATIVE(不要)」で判断していくようにしましょう。
3.評価項目の定義や基準が曖昧
採用面接評価シート運用の失敗例として、各評価項目の定義や基準が曖昧であるということも多いです。
評価項目の定義や基準が曖昧であると、採用担当者、現場責任者、人事、経営陣の間で認識のズレが生じることになります。
例えば、「主体性」という評価項目に対して、どのような事例で主体性が見られたか、評価をつける際の尺度はどのような基準で判断するのかを明確化していかないと共通の認識を持つことは難しくなります。
評価項目の定義や基準は、しっかりと定義を言語化し、協議しながら共通認識を深める必要があります。
4.他社のサンプルをそのまま使ってしまっている
稀に、他社で出している面接評価シートをそのまま使用している企業を見ることがありますが、それでは面接評価シートとしての意味を成しません。
ここまでの内容で説明したように、面接評価シートは自社の求める人物像にあわせて作成していく必要があります。他社の面接評価シートをそのまま使っても、自社の求める人物を獲得できるはずがありません。
面接評価シートの型を0から作成するのは労力がかかりますので、フォーマットや枠自体を参考にすることは推奨しますが、必ず最後には自社用にカスタマイズしていきましょう。
5.面接評価シートの運用が目的化している
前項でも少し説明しましたが、面接評価シートの運用は、あくまで採用活動のクオリティをあげるための手段です。
採用活動の質を高め、自社が求める人物を獲得することこそが目的です。
面接評価シートを埋めることばかりに注意をとられ、実際の求職者との対話がおろそかになっては、自社が求める人物であるかの適正を十分に判断することはできません。
あくまで、補助ツールであるという認識をしっかりと持つようにしましょう。
まとめ
面接評価シートは単なるチェックリストではありません。
“この人をなぜ採るのか”を言語化し、組織として納得できる採用判断を行うためのツールです。
属人的な判断や場の空気に左右されず、候補者の本質を見極めるためには、
「どんな人物を採りたいのか」→「そのために何をどう聞くか」→「どう評価するか」を一本の線でつなぐ必要があります。
本記事で紹介した7ステップを実行すれば、評価項目と質問がリンクし、現場と人事が共通言語で語れる評価シートができあがります。ぜひ実践してみてください。
以下リンクより、弊社作成の面接評価シートのテンプレートをダウンロードいただけます。自社の方針に沿ったカスタマイズを加えてぜひご活用ください。
この記事の監修者:
1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。