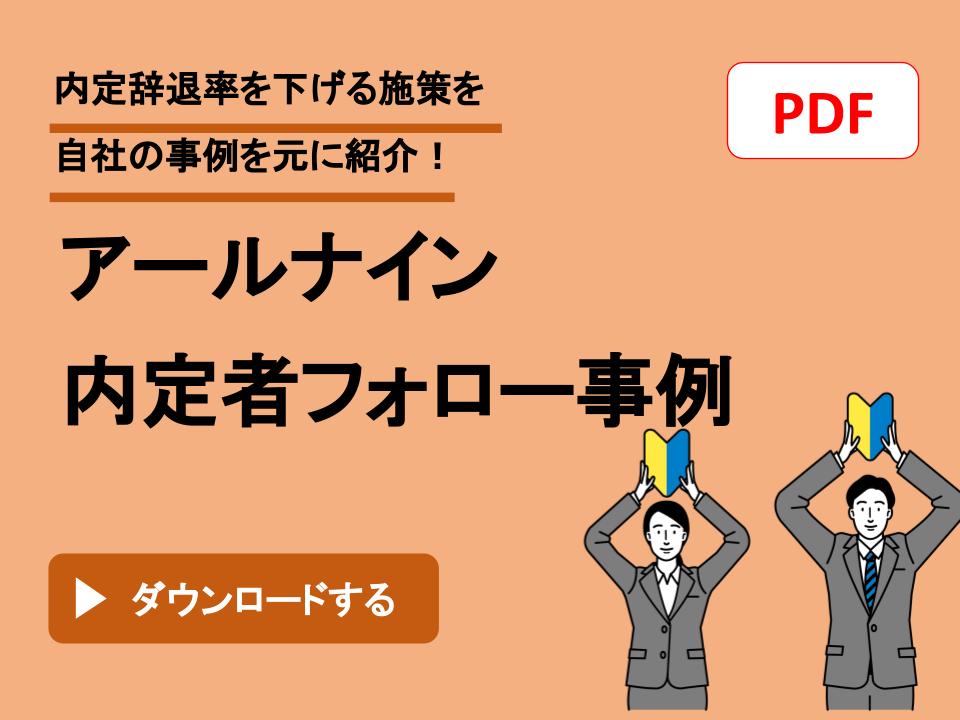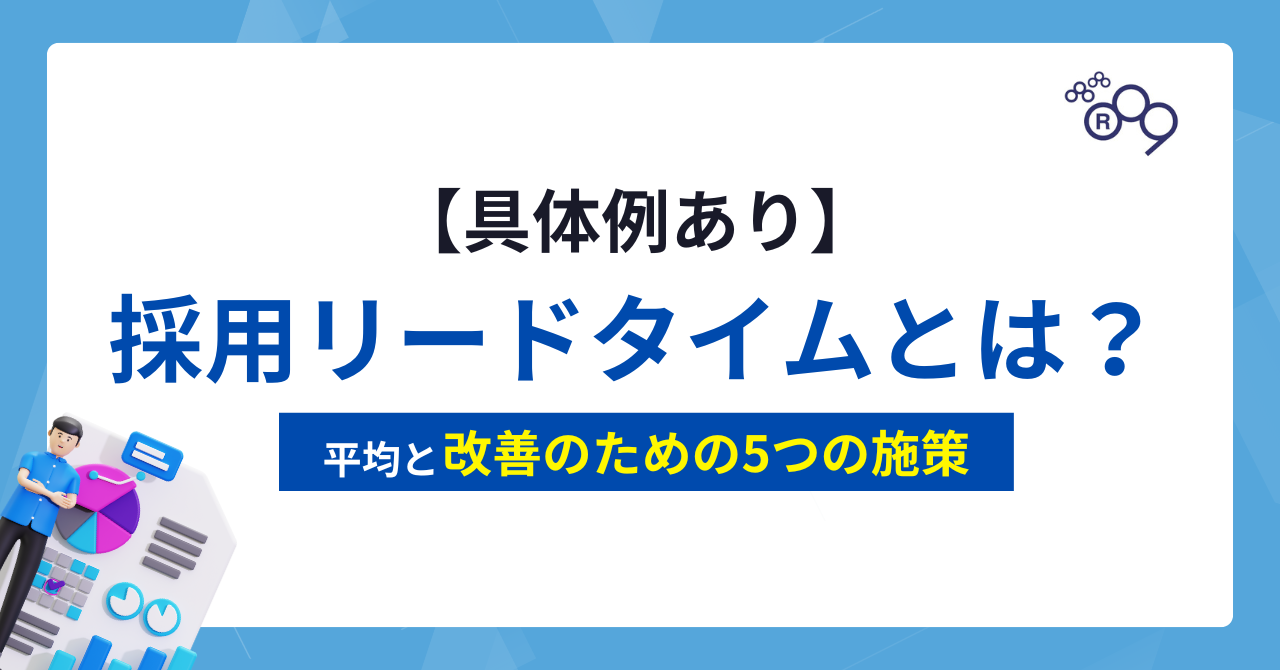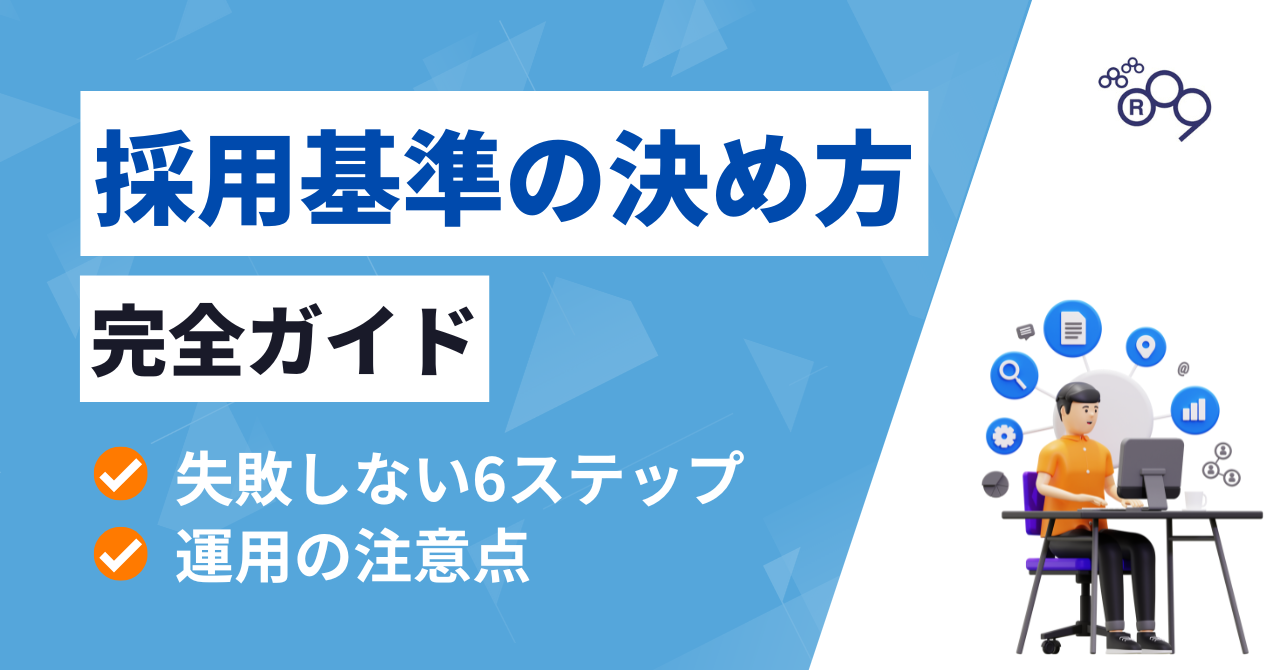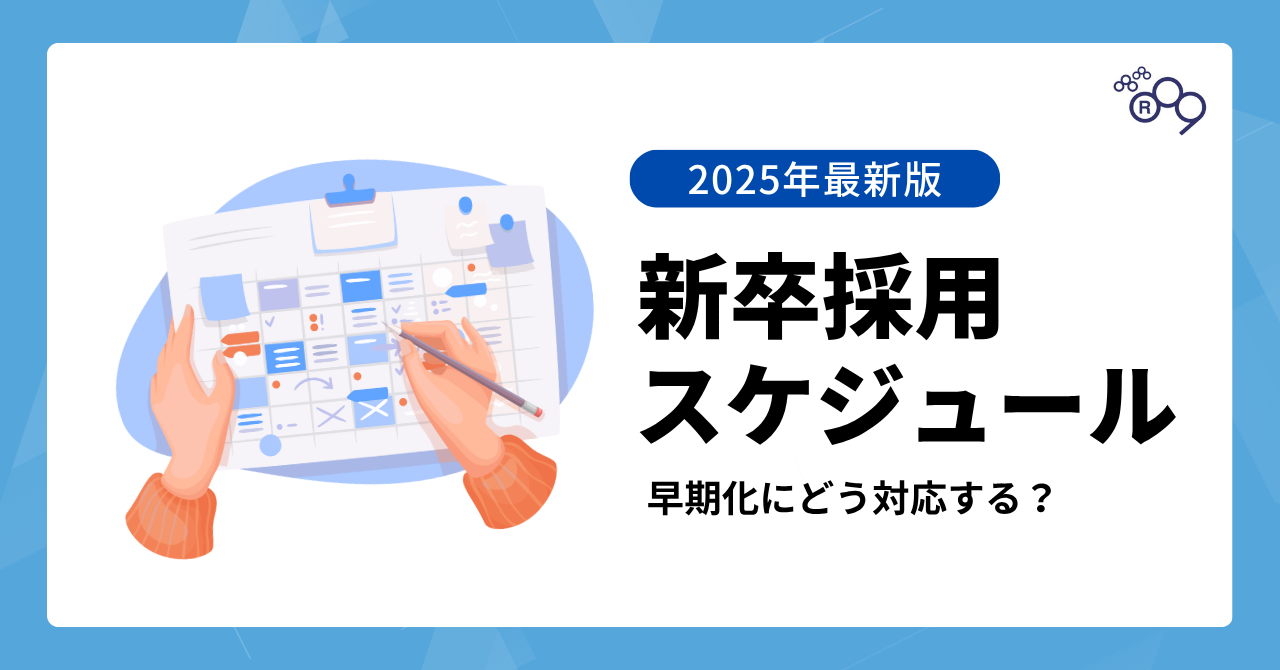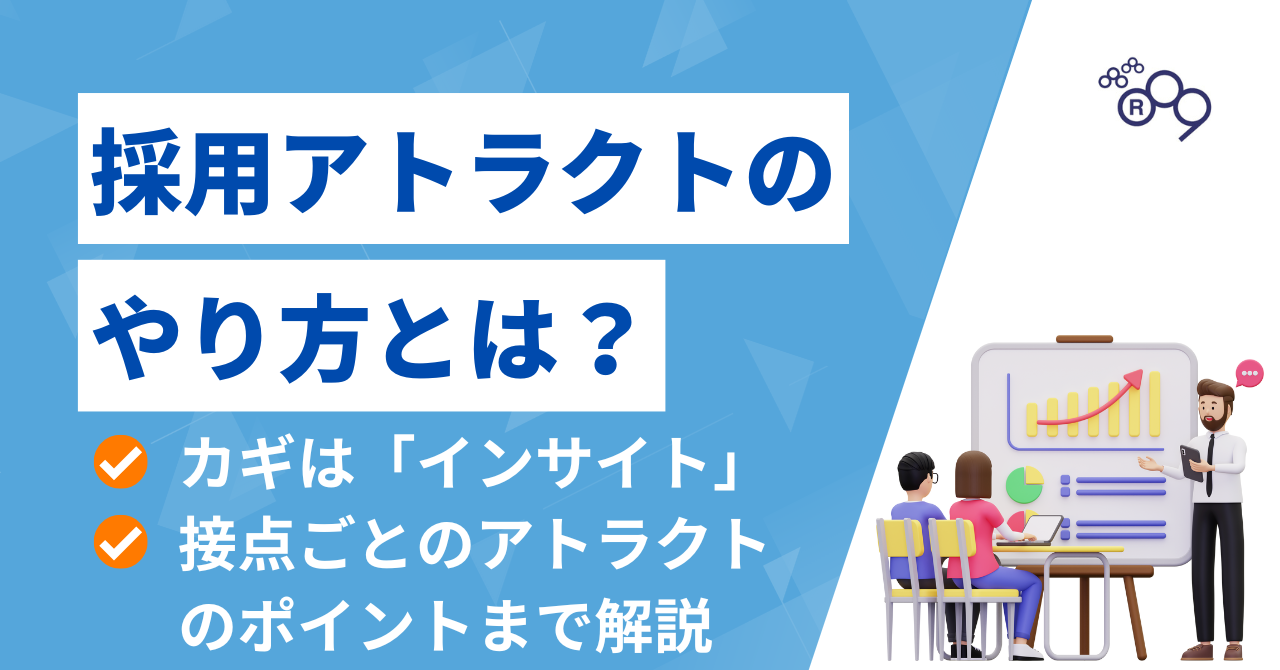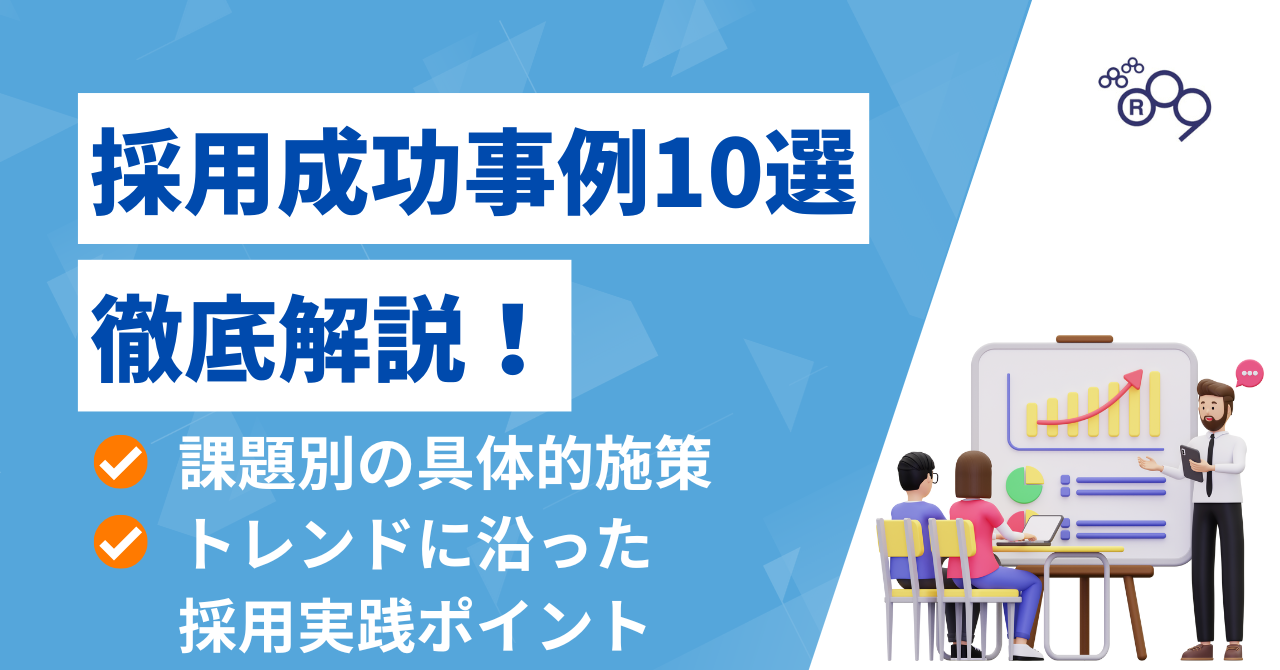内定者フォローの施策例13選|フォローのポイントや学生の実際の声も紹介
公開日: 2021年08月31日 | 最終更新日: 2025年04月30日

- 苦労して採用しても内定辞退が発生している
- 内定辞退を防ぐための内定者フォロー強化を実施したい
- 内定者の満足度が高いフォロー事例が知りたい
こんな悩みを抱えていませんか?
採用通知後から入社までの期間は、内定者が不安や悩みを抱えやすい時期です。
その間、企業側から何も連絡がなければ、内定を辞退して他社へ行ってしまう候補者も増えるでしょう。
無事に入社に導き活躍してもらうためにも、内定者の不安を払拭する内定者フォローが必要となります。
本記事では、内定者フォローの目的やポイント、学生の実際の声やフォロー施策を紹介します。
なぜ内定者フォローが重要なのか
続く学生側の売り手市場
昨今、内定者フォローはより重要度を増しています。
理由は「売り手市場」が続いているからです。
リクルートワークス研究所の調査によると、大卒求人倍率は
2022年卒:1.50倍
2023年卒:1.58倍
2024年卒:1.71倍
と、年々上昇傾向にあり、その水準がコロナ以前まで戻っているという結果が出ています。
また、株式会社リクルートの就職みらい研究所の調査によると、2024年卒の学生の内定辞退率は64.3%。過半数の学生が内定辞退を経験していることがわかりました。(2024年卒 12月1日時点)
直近3年の内定辞退率を比較してみると、
2021年卒:60.9%
2022年卒:62.4%
2023年卒:64.6%
2024年卒:64.3%
と学生の内定辞退率は年々増加傾向にあることがわかります。
さらに、学生の内定取得企業数も年々増加傾向にあり、2社以上の内定を取得している学生は
23卒:40.2%
24卒:45.5%
25卒:48.8%
となっております。2人に1人の学生が複数の内定を保有しているようです。
このような学生側の売り手市場では、学生の入社意思がとても価値の高いものになります。
求職者に選ばれる企業であるためにも、求職者の心をつかむ内定者フォローは必須であるといえるでしょう。
参考:株式会社リクルート『就職みらい研究所』、リクルートワークス研究所
内定者フォローの3つの目的
次に、内定者フォローの目的について整理していきましょう。
内定者フォローを行う理由として、大きく下記3つの理由があります。
①内定辞退の防止
②就業前の準備
③入社後、早期退職の防止
①内定辞退の防止
1つ目の目的は内定辞退の防止です。
せっかく獲得した内定者に辞退されてしまうと、その方の採用に要した時間・コストが無駄になってしまいます。人員計画にも大幅な支障が生まれてしまいます。
そのため内定辞退を防止する動きが大切です。
内定辞退防止の一番のポイントは、”内定者の不安を取り除くこと”です。
就職活動中、内定者は内定獲得に向けて必死に取り組みますが、内定をもらい一安心できた後、本当にこの企業に就職して良いのかを考え始めます。
家族からの何気ない一言などで、自分の選択が正しいのか不安が生じることも多くあります。
適切に内定者の不安を払拭するフォローを行うことで内定辞退の防止に繋がります。
関連記事:【新卒】内定承諾後の辞退を防ぐポイント | 調査で分かった本音の辞退理由とは
②就業前の準備
内定者の中には、入社したら一日でも早く活躍したいと思っているモチベーションの高い人材も多くいます。
内定者のモチベーションを維持するためにも、内定者フォローを活かして入社時から良いスタートを切れるよう準備期間を設けることも必要です。
業務に関する専門分野の知識はもちろん、ビジネスパーソンとしてのマインドを持ってもらえるようなフォロー企画を考えると良いでしょう。
就業前の事前準備をすることで、前述した不安を解消することにも繋がります。
また、後述する入社後の早期退職を防止することにもつながります。
入社後、新入社員として少しでも良いスタートを切れるよう、準備ができる環境を提供してあげましょう。
③入社後の早期退職の防止
内定者フォローをする理由の3つめは、「入社後の早期退職の防止」があげられます。
新入社員は、入社後3年以内に3割が退職すると言われています。
原因は様々ですが、代表されるものとして「入社後のギャップ」があげられます。
内定をもらう前と、実際に入社して業務をしてみた後で、業務の内容、職場環境がイメージと違ったと感じる内定者も少なくありません。
そのため、入社前に業務の内容、一緒に働く社員、キャリアステップなどをできるだけ具体的に説明してあげることが必要です。
モチベーションの高い社員を育成することで、企業のパフォーマンスはあがります。
このように、内定者フォローは入社後のパフォーマンスや離職率にも影響する重要な施策といえます。
内定者の実際の声5選
次に、多くの企業の内定者フォロー面談を代行してきたアールナインが、実際に内定者から引き出した本音を抜粋して解説いたします。
1.同期社員と上手く協働できるか不安
内定者の中には、同期社員と協働することに不安を感じる方もいます。
同期社員はライバルでもあり、1番身近な仲間でもあります。
「同期社員にはどのような人がいるのか?」「自分は同期のレベルについていけるか?」など、同期社員との協働に対しての不安を取り除く対策が求められます。
内定者同士の交流の機会を求める声も多くありました。
2.先輩社員や上司と上手く協働できるか不安
社内の人間関係として、先輩社員や上司との協働に不安を感じる声もあります。
「もしもパワハラ上司の部署に配属されてしまったら…」「業務を教わる先輩が怖い人だったら…」など、内定者の中には、上司を含む既存社員に対して不安を抱いている場合もあるでしょう。
既存社員との交流の機会を作るなど、不安を払拭できる機会を設けましょう。
3.入社後仕事についていけるか不安
大学で学んだことやアルバイトで経験してきたことと入社後の実際の業務内容が異なるため、仕事についていけるか不安に思う方は多いです。
研修でフォローできることを伝えたり、新卒入社の先輩社員から話を聞くことで不安払拭をすることが重要になります。
4.自分が成長していけるか不安
入社後の自分の成長に不安を感じる内定者の方もいます。
多くの新卒社員は「これから知識やスキルを身につけ、成長していこう」という強い意欲を持っています。反面、「自分が入社する会社で成長していけるか…」「会社が期待する成長に応えられるか…」という不安も同時に抱えることがあるようです。
先輩社員との座談会などの機会を作り、不安を払拭できるようフォローしていきましょう。
5.実際に働く時に選考時のイメージとギャップがないか不安
選考時に社風や働き方に共感して内定を決めたはいいものの、実際に働き始めたらイメージとのギャップがあるんじゃないかと不安に思う学生は多いようです。
選考ではどうしてもいい部分ばかり伝えてしまったり、脚色を加えてしまう場合もあると思います。
面接時の魅力訴求方法を見直すことも重要ですが、内定から入社にかけてそのギャップを埋めていくことも重要です。
内定者フォローを企画する際の大事な7つのポイント
続いて内定者フォローには様々な施策がありますが、企画する際のポイントについて解説いたします。
①内定者の不安な気持ちに寄り添い、安心させてあげる
②企業との絆を深める
③企業理念や価値観を浸透させる
④社員とのコミュニケーション機会を作る
⑤活躍している社員との交流機会をつくる
⑥SNSを活用して社内の情報をオープンにする
⑦定期的に連絡を入れる
①内定者の不安な気持ちに寄り添い、安心させてあげる
内定者フォローで最も重要なポイントは「学生の不安は何か」「その不安をどう取り除くか」を考え抜くことです。
社会人経験のない学生は、入社にあたって様々な不安でいっぱいです。学生の気持ちを正確に汲み取って、それを解消していくことが出来れば、内定者の心を惹きつけ、内定辞退を防ぐことが出来ます。
【導入事例】内定者サーベイツール【PEPS】で入社に対するエンゲージメントを向上!
②働くイメージを持ってもらう
内定者フォローは、内定者に「この会社で働きたい」と思ってもらえるよう、企業と内定者のエンゲージメントを深める機会でもあります。
内定者インターンや内定者研修として実際の業務に携わってもらうのも有効です。
選考中は見れなかったものを見せ、伝えられなかったことを伝えましょう。
③企業理念や価値観を浸透させる
企業へのエンゲージメントを深めるためには、会社の向かう方向性や価値観を伝えていく必要があります。
企業が持つ理念や価値観を、内定者フォローを通して浸透していけるように工夫しましょう。
④社員とコミュニケーションを取る機会を作る
内定者は、自分が働く会社の先輩達がどのような人であるか気になっています。
働いている社員とのコミュニケーションの機会を作ることで、先程解説したポイントでもある「働くイメージを持ってもらうこと」もできます。
⑤活躍している社員との交流機会をつくる
働いている社員との交流をする際、トップで活躍している社員との交流も作ると良いでしょう。
活躍している社員と関わることで、内定者の目指すべきものが見え、モチベーションも高まります。
⑥SNSを活用して社内の情報をオープンにする
会社の雰囲気を知ることは、自分がその会社で働くイメージにも繋がります。
昨今、多くの企業がSNSを活用して、社内の様子を発信しています。オープンに社内の情報を発信していくことも、内定者が働くイメージを深めるために必要です。
⑦定期的に連絡を入れる
内定者フォローは、一度の企画を行って終わりではありません。内定者と定期的に連絡をとることが重要です。
しばらく連絡がこないと、内定者は放っておかれている、必要とされていないと認識してしまいます。
定期的に連絡をとり、内定者とのコニュニケーションを深めていきましょう。
【導入事例】内定者フォロー代行とリクルーティング代行により学生からの信頼を獲得!
内定辞退を防ぐ内定者フォロー事例14選
最後に内定者フォローの事例について解説していきます。
下記を参考にして、自社の目的に沿った方法を検討していきましょう。
①先輩社員との座談会
内定者と既存社員でざっくばらんに喋ることができる機会は必要です。
仕事のやりがいや社員の人となりなど、お互い直接話すことで見えてくるものがあるでしょう。学生はどんな人と働くのか不安でいっぱいです。入社時に知り合いの先輩社員がいることは心強く、安心材料にもなります。
また、学生に提供する情報に偏りが出ないよう、できるだけさまざまな職種、ポジションの現場社員に協力してもらうための仕組みづくりを考えましょう。
実際に働く社員の声を聞く場を作ることで、ロールモデルの創出やモチベーション向上にも繋がります。
特に若手社員と交流を持ってもらうことは、どのように仕事をするのか、どのような課題を乗り越えればよいのかなど入社直後のイメージを具体化する効果が期待できます。
②内定者懇親会
内定者同士の親睦を深めることは内定辞退防止に繋がります。
良好な人間関係ができることで、入社後の働いている姿をポジティブに想像しやすくなるのです。
懇親会のような形で、学生同士がコミュニケーションをとる機会を作ってあげましょう。
【導入事例】内定者フォロー代行とリクルーティング代行により学生からの信頼を獲得!
③職場見学
内定者は実際に自分がどのような環境で働くのか気になっています。
実際に職場を見学する機会を作ってあげ、入社後にその場所で働くイメージを具体化させましょう。
内容は、工場や施設など入社後に働く予定の職場内を見て回ることと、面談による説明や質疑応答が基本です。同時に、その職場ならではの魅力を伝えてあげると更に効果的です。
特に会社の雰囲気は最もよく見られるポイントです。
雰囲気の良い印象を与えると、見学者は安心した気持ちで過ごすことができ、会社に好感が持てるでしょう。
④内定式
内定式を行う意味合いの一つとして、内定者の気持ちの切り替えという狙いがあります。
内定したという実感を持たせ気を引き締めさせるとともに、入社を歓迎していることを伝える貴重な機会となります。
社長から経営理念やビジョンを直接聞くことで、企業への理解を深めることが期待できます。また、励ましの言葉を聞くことにより、自分への期待を感じられ、モチベーションを高める効果も期待できます。
学生が今後の流れを把握できるようスケジュールもこの場で伝え、入社までの道のりを具体的に示しましょう。
⑤社内イベントへの参加
企業によっては、入社前に社内イベントを行っているところもあります。
レクリエーション要素を入れたイベントを行うことによって、既存社員、内定者同士の繋がりを深めることができます。
例えば、協力しながらチームで行うオンラインクイズ大会を開催している企業もあり、参加者同士の相互理解を深める効果が期待できます。
また、チームビルディングを目的とした運動会やバーベキューなども事例として多くあります。
⑥自社の採用活動に関わらせる
内定者の後輩にあたる代の採用活動に関わらせることも有効です。
実際に学生との面談をしてもらうことによって、内定者は自社の良いところを探したり、自分が入社の決め手になったことを何度も言語化することができます。
企業と選考を受ける候補者という立場から、一緒に後輩を採用しようとする立場に変わることで会社への帰属意識、先輩としての意識が芽生えます。
内定者が面談を行った学生が選考を進んでくれれば、やりがいも生まれるでしょう。
⑦社内報の送付
職場の雰囲気や自社の考え方、内定式の様子などを社内報として発信します。
定期的に企業トップのメッセージや最新情報をキャッチアップしたり、職場の雰囲気を知ることができたりします。自然と学生から社会人へのマインドチェンジを促すことができます。
内定者インターンの一環として、学生にこれらの社内報制作のアシスタントをしてもらうのも非常にお勧めです。
社内報制作の打ち合わせのため、定期的に内定者と連絡・接触が発生し、囲い込み効果が期待できるほか、入社前に現役社員を取材することによって、社内に溶け込みやすくなるなどの副次的な効果もあります。
⑧内定者研修(業界理解研修、ビジネスマナー研修)
入社後、良いスタートができるよう事前に必要な研修を行っていくことをお勧めします。
モチベーションの高い内定者は、入社までの期間を活用し準備をしたいと考えています。業界理解研修・ビジネスマナー研修などは人気であり、多くの事例があります。
実際に入社後にどのようなスキルが求められているのか、各現場のニーズをきちんと把握し、入社後に活かせるような研修を企画しましょう。
また、労務的な点も注意が必要になります。内定者はまだ雇用契約を結んでいないため、研修への参加を強要することはできません。
また、参加が義務と捉えられたり、一定時間集合する必要がある場合は、賃金の支払いなどが必要になることがあります。
詳しいことは専門家に確認しながら、内定者にきちんと合意を得たうえで、十分に注意をしながら内定者研修を行いましょう。
アールナインでは内定者研修の代行も行っております
⑨グループワーク
グループワークでは、プレゼンテーションや共同作業、ゲームなどを行います。
基本的にはいくつかのグループに分かれて作業を行い、メンバーなどとコミュニケーションを取ることで、内定者同士がコミュニケーションを取る機会を設けられます。
また、グループワークにアイスブレイクを取り入れれば、さらに緊張をほぐせることが期待できます。
グループワークのネタはさまざまで、なかにはオンラインで実施できるものもあります。
論理的思考力を見つけてもらいたい場合には、グループ内で議論し、答えを導き出すネタを取り入れましょう。
物事の要点をまとめてわかりやすく伝えたり、全体の意見を引き出すために発言の少ない人に声をかけたりすることで、仕事で活用できるコミュニケーションについても学べるでしょう。
グループワークのファシリテーションに課題がある企業様には、ファシリテーターの代行という支援も行っております。
⑩内定者インターン
業務内容、会社の雰囲気を理解してもらうことが出来ます。
説明会や面接などを通して伝えていると思いますが、他者から話を聞くのと実際に自分で体験するのとでは理解度が異なります。実務を通してしか分からない魅力を肌で感じてもらうことが出来るのがインターンシップを実施するメリットといえます。
また、先輩社員と共に働くことで交流を深め、帰属意識を高める効果があります。居心地の良い場所だと思ってもらえるよう、積極的にコミュニケーションを図りましょう。
副次的な効果として、選考時には分からなかった内定者の適性を知ることもできます。内定者が実際に仕事をしている様子や、周囲の人とのコミュニケーションの取り方を見ることができるためです。
そのような情報から、配属場所やOJTトレーナーの割り当てを調整することができ、入社後の早期活躍にも繋がります。
株式会社アールナインでは、自社の内定者にインターン生として入社まで働いてもらっています。詳しくはこちらの資料をご覧ください。
⑪内定者によるイベントの企画
社内イベントを内定者に企画してもらうという事例もあります。
グループワークとはまた違う形で結束を強められるでしょう。主体性も強まり、会場の予約やスケジューリングといった社会人スキルも身につけられます。
ただし、内定者に丸投げしてしまわないよう、人事や運営チームがサポートする姿勢は忘れないようにしてください。
⑫フォロー面談
内定者と直接話し合う場を設けます。入社後のミスマッチを防ぐためのすりあわせや、内定者の不安・疑問の解消に努め、入社意欲を向上させ囲い込む効果があります。
定期的に顔を合わせることで、身近に相談できる相手がいるという安心感が生まれ、帰属意識が高まるという効果もあります。
また、仕事への意欲や性格、希望する部署および業務、どのようなキャリアを積み上げたいのかなども見えてくるため、入社後の定着・育成にも繋がるでしょう。
この際、「なんとか自社に入社してほしい」という気持ちを前面に出すのではなく、あくまでもフラットに相談に乗るように心がけることがポイントです。
「自分を入社させるために大げさに言っているのではないか」という風に警戒されてしまうと、せっかくのフォロー面談で本音を引き出せません。一人の社会人の先輩として学生の不安や疑問に真摯に向き合い、安心できる環境を作ってあげましょう。
アールナインでは、第三者という中立な立場から内定者の本音を引き出す「内定者フォロー面談代行」サービスも提供しております。
⑬メンター制度の導入
人事担当者とは別に、メンターとして各学生に先輩社員を配置し、業務のことからプライベートのことまで、気軽に話せる状態を作ってあげましょう。
そうして心強い味方を社内に作ることで安心感が生まれ、会社への帰属意識も強まります。
学生のタイプを採用段階で見極め、年齢やバックグラインドまで考慮し、適したメンターを配置しましょう。
⑭内定者フォローツールの導入
内定者フォローツールとは、内定者と企業、または内定者同士のコミュニケーションを促すためのサービスや、内定者のモチベーションを把握できるツールです。
内定者フォローツールには主に4つの種類があります。自社の業務特性や内定者フォローの課題と照らし合わせて、自社に合ったツールを活用しましょう。
- 採用管理と内定者フォローを一貫して行えるツール
- コミュニケーションに強みを持つツール
- eラーニングなど学習教材に強みを持つツール
- 内定者の分析に強みを持つツール
※内定者フォローツールについて、くわしくはこちらの記事をご覧ください。
内定者フォローツールおすすめ5選!リアルとセットで行うのが吉
内定者フォローに役立つおすすめサービス5選
ここまで、内定者フォローのポイントや実際の施策を紹介してきました。
それぞれの施策に直接役立つサービスや、併用するとさらに効果を高めるサービスがございますので、いくつか抜粋して紹介させていただきます。
1.エアリーフレッシャーズクラウド
EDGE株式会社が提供するエアリーフレッシャーズクラウドは内定者とのコミュニケーション促進をフォローしてくれる内定者フォローツールです。
タイムライン型のコミュニケーション機能やおしらせ機能は内定者も使いやすいデザインになっています。また、フォローアップステータス機能では、個別にフォローが必要な学生をお知らせしてくれるので、個別対応も迅速に行うことができます。
研修教材の提供や提出物管理機能も搭載されているため、内定者の課題の管理も簡単に行えます。
特徴
- 既読管理機能、リマインド機能で複雑な連絡業務を効率化できる
- 個別にフォローが必要な内定者を知らせてくれる
- タイムライン形式のデザインでやり取りがしやすい
2.MOCHICA
株式会社ネオキャリアが提供するMOCHICAはLINEと連携して面談の日程調整やメッセージのやり取りを行う、採用候補者のフォローサービスです。従来のメールや電話に比べて、LINEでのやり取りで候補者との距離を”もっとちかく”にするためのコミュニケーションに特化したツールです。
候補者のメールの返信率が低い、やり取りに時間がかかるといった悩みを抱えている企業におすすめです。
特徴
- LINEと連携して候補者とスムーズな連絡が可能
- ダッシュボードで候補者の採用進捗が可視化できる
- 採用から内定後までの連絡手段を一元化できる
3.サイバックスUniv.
リスクモンスター株式会社が提供するサイバックスUniv.は4000種類のオンライン研修を低額で受けられる、内定者のスキルアップに特化した内定者フォローツールです。
eラーニングだけでなく、Webセミナーなど豊富な研修が定額で受講し放題というお得なサービス内容です。階層別・職種別の研修プログラムも充実しているため、自社に合った最適なコンテンツを選ぶことができます。
特徴
- eラーニングを含む豊富な研修が定額で受講できる
- 内定者の研修の受講状況を一元管理できる
4.PEPS
月に1回、内定者に対して20問程度のサーベイを配信。独自の集計ロジックにより辞退リスクを独自のスコアで算出し、内定者のコンディションを可視化。
フォローが必要な内定者を検知します。 また、内定者に対して確認すべき項目も明確になるので従来のコンディションチェックでありがちな「サーベイの結果が分かっても、その後どうアクションをとって良いか分からない」という状態を防ぎます。
特徴
- アンケートによって内定者のコンディションを把握できる
- 独自の集計ロジックで内定者のコンディションを可視化できる
- 現在の気持ちだけではなく気持ちの変化も可視化
5.株式会社アールナイン「内定者フォロー代行サービス」
これまでに約630の企業の採用を支援してきたアールナインの採用プロフェッショナルが、内定者フォロー面談や内定者研修を代行し、内定辞退を防ぎます。
フォロー面談では第三者の立場から内定者の本音をヒアリングすることで、入社前に抱えている不安の払拭や入社に向けての意欲醸成を行います。
内定者研修では企業様の目的に応じて幅広い研修コンテンツを用意しております。0からコンテンツを企画することも可能です。
特徴
- 第三者の立場から、企業には言いづらい内定者の本音を引き出せる
- 企業に合わせた研修コンテンツをカスタマイズ作成
- 時間のかかる業務を代行することで人事の工数を削減し、コア業務に専念できる
最後に
ここまで、
- なぜ内定者フォローが重要なのか
- 内定者フォローの目的
- 内定者の実際の声
- 内定者フォローのポイント
- 内定者フォロー施策
- 内定者フォローに役立つおすすめツール
それぞれについて解説してきました。
様々な施策を紹介してきましたが、最も重要なのはひとりひとりの内定者と向き合い、不安を取り除きながら入社まで導くことです。
入社してから活躍する社員を増やすためにも、適切な内定者フォローを行いましょう。
とはいえ、人事担当者の時間は限られており、内定者ひとりひとりに時間を割くことは難しい場合もあるでしょう。
その際は弊社の内定者フォローサービスでお力添えできる部分があるかと思いますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
また、株式会社アールナインは、これまでの600社を超える採用実績の中での知識・ノウハウの蓄積に加え、内定者パルスサーベイツール「PEPS」で収集したデータをもとに内定者フォローを自社でも行っています。23卒の内定辞退率(内定出し→入社)は12人中8人の33%という結果になりました。
株式会社リクルートの調査では、2023年12月時点での内定辞退率は64.3%とされていることから、効果的な内定者フォローを実施できていることがわかると思います。
以下の資料では、内定者が持つ悩みとそれに対応した施策を、アールナインでの事例をもとにご紹介しています。無料でお気軽にDL出来ますので、是非ご一読ください。
この記事の監修者:
1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。