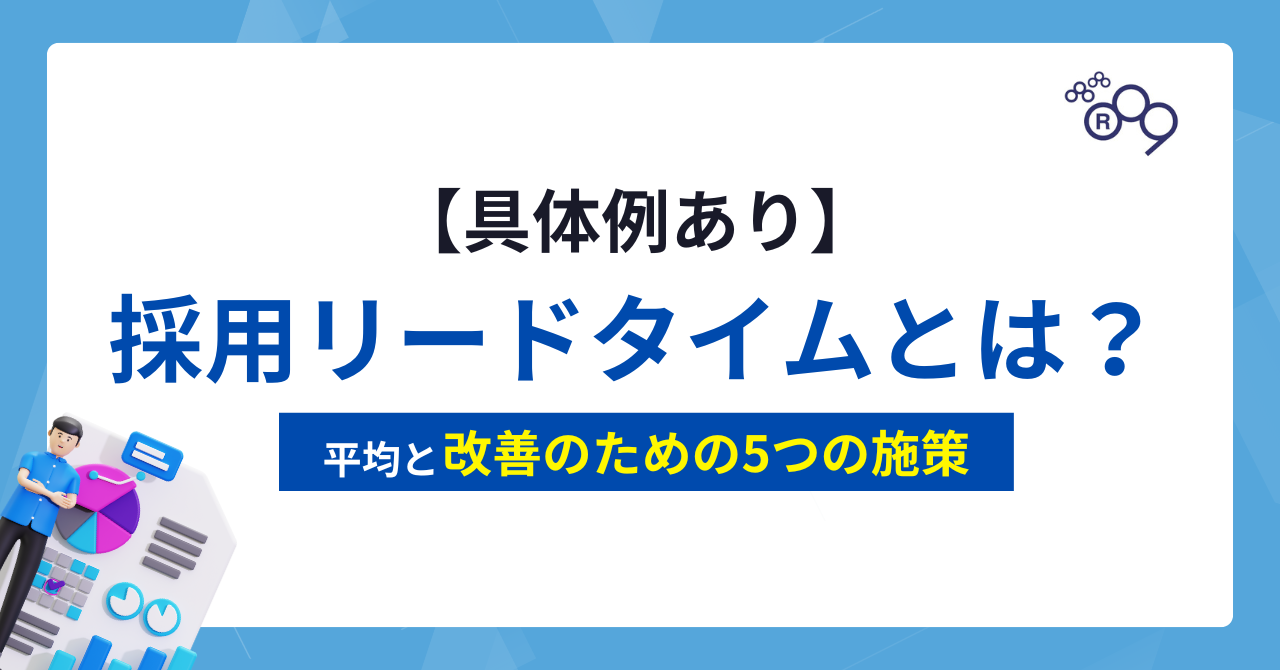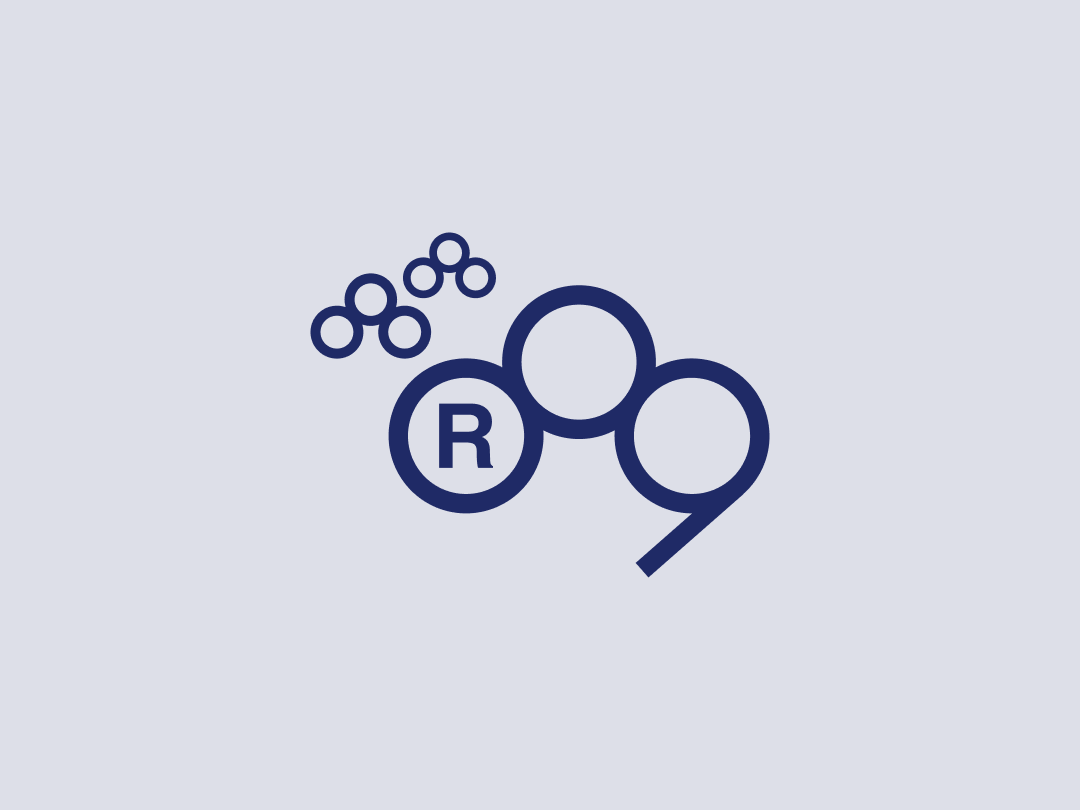リファラル採用とは?制度設計から社内浸透までを5ステップで徹底解説
公開日: 2025年08月05日
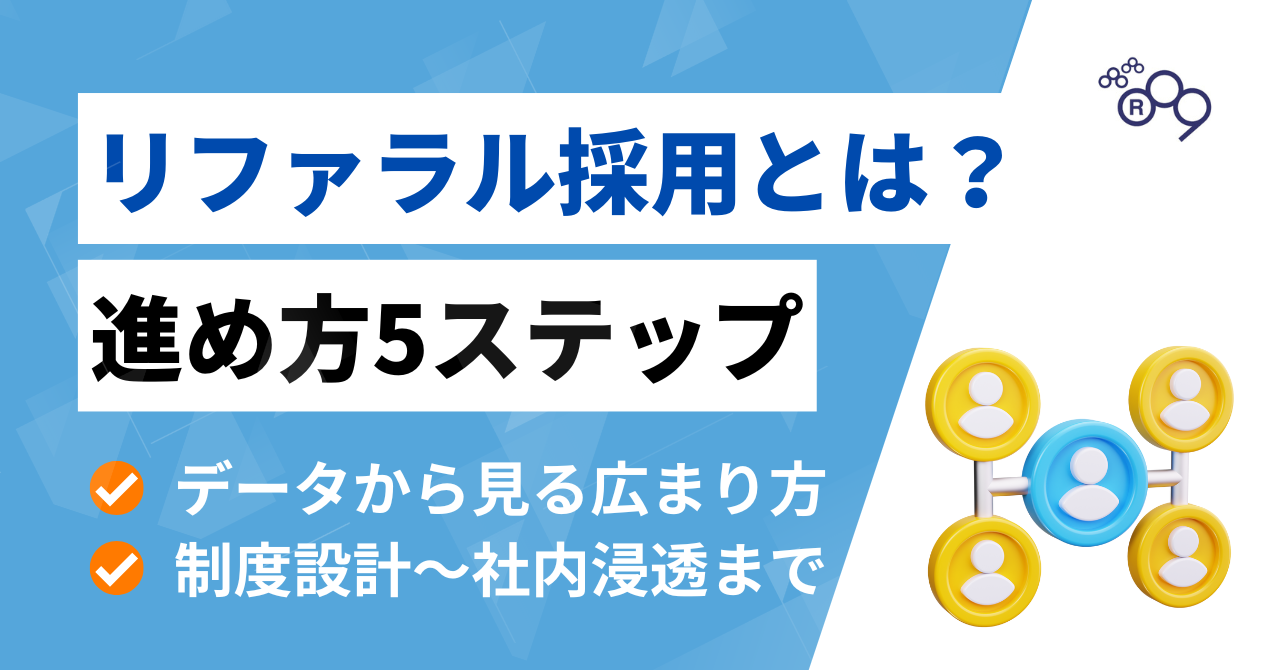
「リファラル採用がいいと聞くけど、制度の作り方・浸透のさせ方がわからない」
「報酬を用意しても、誰も紹介してくれない」
こうした悩みを抱える人事担当者は少なくありません。
この記事では、リファラル採用の基本から、制度設計・運用・浸透・改善までを、すべて“手を動かせるレベル”で徹底解説していきます。
多くの企業が取り組んでいる「リファラル採用」とは?
リファラル採用とは、社員が信頼できる知人を紹介し、その人物を通常の選考を経て採用する制度です。
求人広告や人材紹介などの外部チャネルに頼らず、社内のつながり(ネットワーク)を活用して、ミスマッチの少ない人材を効率よく採用できるのが特徴です。
紹介される候補者は、すでにその企業で働いている社員と関係性があるため、仕事内容や職場の雰囲気に対する理解が深く、入社後のギャップが少ない傾向があります。
その結果、カルチャーフィットしやすく、定着率も高い採用手法として、多くの企業で注目されています。
50%以上の企業が導入済み。データから見る、リファラル採用の広がり
近年、リファラル採用を導入する企業は急速に増えています。
株式会社矢野経済研究所の「リファラル採用・アルムナイ採用支援サービス市場に関する調査(2025)」によると、「リファラル採用の実施経験がある」との回答比率は50.1%と過半数を占めました。
さらに、同調査における「リファラル採用・アルムナイ採用支援サービス市場規模の推移・予測」によると、2024年度の市場規模は前年度比169.0%の50億7,000万円に拡大する見込みとされています。
引用元:株式会社矢野経済研究所の「リファラル採用・アルムナイ採用支援サービス市場に関する調査(2025)」
https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3732
このように、単なる一時的なトレンドではなく、今後ますますメジャーな採用手法として定着していくと考えられます。実際に、弊社アールナインでもリファラル採用による複数名の採用実績があります。
社員の紹介を通じて、カルチャーフィットする人材を効率的に採用できるため、特に採用専任者が少ないフェーズの企業にとって、強力なチャネルになってきています。
リファラル採用と縁故採用の違い
「社員の知り合いを採用する」と聞いて、縁故採用(いわゆる“コネ入社”)と混同する方も少なくありません。
しかし、リファラル採用と縁故採用では、目的もプロセスも評価基準も大きく異なります。
| 項目 | リファラル採用 | 縁故採用 |
| 推薦の経路 | 社員による紹介 | 血縁・地縁・特別な人脈など |
| 選考プロセス | 通常の選考と同じ | 面接・選考が省略されるケースも |
| 評価基準 | スキル・カルチャー適合・実力重視 | 関係性重視・評価の甘さも |
| 採用の公平性 | 他の応募者と同等に扱う | 社内・社外から不公平に見られやすい |
「紹介されたから採用される」というわけではなく、あくまで“応募のきっかけが紹介である”というだけで、選考自体は通常と同様に行われます。
「紹介して落としたら気まずいのでは?」という不安の声もありますが、あらかじめ評価基準と伝達方法を整備しておけば、紹介者との関係が悪化するリスクは最小限に抑えられます。
リファラル採用のメリットとは?
リファラル採用は、単なる“つながり採用”ではなく、採用手法のひとつとして制度的に設計・運用するからこそ、大きなメリットを発揮します。
ここでは、企業側・社員側それぞれの視点から得られる主な利点を紹介します。
企業側のメリット|コスト削減・文化適合・スピード感
採用コストを抑えやすい
求人広告や人材紹介に比べて、成果に応じた報酬型で設計できるため、初期投資や固定費が抑えやすいのが特徴です。人材紹介に月60万円を支払っていた企業が、リファラル報酬を10〜20万円に設定することで、年間コストを半減させたケースもあります。
カルチャーフィットしやすい人材が集まる
紹介者を介して応募するため、候補者は事前に社内文化や仕事の実態をある程度理解しているケースが多く、入社後のギャップや早期離職が起こりにくい傾向があります。
採用スピードが上がりやすい
紹介者との事前コミュニケーションがある分、選考フローがスムーズに進みやすく、内定までのリードタイムを短縮できるという利点もあります。
紹介者側・社員のメリット|信頼できる人と働ける満足感
信頼できる人と仕事ができる
紹介した相手と同じチームで働けることは、業務上の連携のしやすさや安心感につながり、働きやすさの向上にも貢献します。
組織への貢献が可視化される
適切な報酬制度や社内表彰と組み合わせることで、「採用活動への貢献」が具体的な成果として評価されやすくなります。これは社員のモチベーションにも良い影響を与える要素のひとつです。
このように、リファラル採用は「コストを抑えつつ、定着率の高い採用を実現する手段」として多くの企業に活用されている制度です。
リファラル採用のデメリットとは?よくある失敗例も解説
ここまでリファラル採用の良い面を紹介しましたが、制度設計や運用次第では、うまく機能しなかったり、思わぬリスクや摩擦を生むケースもあります。
この章では、リファラル採用のデメリットや、導入現場で実際に起きがちな失敗パターンについて整理していきます。
デメリット①:紹介者・候補者間の「気まずさ」や心理的負担
もっともよく挙げられるのが、紹介した人が不採用になった場合の気まずさです。
紹介者は「信頼しているから紹介した」のに、それが断られることで自尊心を傷つけられたように感じることがあります。
一方で、人事側も「断りにくい」「配慮が必要」といった心理的ハードルが高まり、選考の透明性が揺らぐ場面も。
失敗例:
面接官が「紹介者の手前、なるべく不採用にしたくない」という意識から、本来落とすべき候補者を採用してしまい、早期離職につながった。
デメリット②:同質化による多様性の低下
リファラルは、社員のネットワークを活かす分、似たような価値観・経歴の人が集まりやすいという傾向があります。
これは短期的にはカルチャーフィットしやすい一方で、組織の多様性や新しい視点の欠如を招くリスクも無視できません。
失敗例:
組織が紹介された人だけで固まり、新卒や他チャネルからの入社者が馴染めずに孤立してしまった。
デメリット③:制度運用の設計と浸透に想像以上の工数がかかる
ただ「誰か紹介して」と声をかけるだけでは、社員は動かず、紹介も集まりません。制度を適切に機能させるには、想像以上に多くの整備と社内連携が必要になります。
- 報酬のタイミング・金額・支給条件などの細かい設計
→「入社時?定着後?全員同じ?部門によって変える?」など、決めることが山積み - 紹介してよい範囲の線引き(親族・恋人・業務委託など)
→ グレーにすると、後からトラブルや“モヤモヤ”が生まれがち - 社内への制度浸透・周知活動
→ 告知だけでは動かない。説明会やマネージャー巻き込みが必要になる - 選考フローへのスムーズな接続
→ 現場の協力、優先度調整、書類確認のルール化など、意外と摩擦が多い部分
リファラル採用は、こうした見えにくい落とし穴があります。だからこそ、制度として丁寧に設計・運用し、社員の心理にも寄り添った仕組みにする必要があります。
リファラル採用を活用しやすい企業の特徴
ここまで説明してきたリファラル採用のメリット・デメリットを踏まえたうえで、リファラル採用を活用しやすい企業の特徴を2つほど紹介しましょう。
従業員満足度(ES)が高い企業
リファラル採用は、従業員の紹介を前提としているので、従業員満足度(ES)が高い企業でないと制度が成り立ちません。紹介者自身が会社や仕事に満足していないと、他の人に紹介しようという気が起きないからです。
ですから、ESやエンゲージメントの高い企業であれば制度活用はスムーズに進むといえるでしょう。
スタートアップ・ベンチャー企業
リファラル採用は1つ目の特徴に当てはまる大手企業で導入が進んでいますが、採用にかけられる予算が少ないスタートアップやベンチャー企業が導入するのにも向いています。
リファラル採用は前述した通り、紹介をしてくれた従業員への成功報酬制がとられているため、大きな費用はかかりません。紹介者の人脈活用が前提のため、広告や採用媒体を利用して採用市場で競争する必要がなく、採用コストを中長期的に抑えることができます。
ただし、それぞれの従業員が紹介できる人数には限度があります。従業員が少ない会社の場合、「リファラル採用のみを行うのは難しい」ということを覚えておきましょう。
リファラル採用制度の設計~浸透のさせ方|具体例を交え、5ステップで徹底解説
「リファラル採用が良いのは分かった。でも、実際にどうやって制度を作ればいいのか分からない」
そう感じて検索してきた方も多いのではないでしょうか。
ここでは、制度設計に必要なステップを「そのまま社内で使えるレベル」で具体的に解説します。
採用専任がいない企業や、制度運用が初めての人事担当者でも、実務で手を動かせる内容になっています。
【ステップ⓪】求める人材や採用基準の明確化
通常の採用と同様に、採用ミスマッチを防止するために、「求める人材」や「採用基準」を明確化し、従業員に共有しておきましょう。
従業員のなかには、紹介したいと思う人材がいても、「はたして会社に合う人材なのか」、「紹介しても採用に至らないのではないか」などの不安を抱えて紹介を躊躇することもあります。しかし、あらかじめ「求める人材像」が明らかであれば、紹介ハードルも下がるはずです。
逆に、人材像が明確でなければ紹介数ばかりが増え、採用業務に負担がのしかかります。ミスマッチを起こさないためにも、人材像の明確化は必須でしょう。
【ステップ①】紹介者・紹介対象者の定義
リファラル制度で最も見落とされがちなのが、「紹介する側・される側のルールを決めないまま走り出す」ことです。
このステップが曖昧だと、後から「恋人はOK?親は?」「業務委託って紹介対象?」といった“制度に対する不信感”が生まれやすくなります。
—
▼ 紹介できる人(紹介者)
– 正社員:〇
– 契約社員・アルバイト・インターン:〇
– 業務委託社員:△(関与範囲に応じて判断)
—
▼ 紹介される人(紹介対象者)
– 一般の友人・知人:〇
– アルムナイ(元社員):〇
– 恋人・配偶者・同居人:〇(申告必須)
– 三親等以内の親族:〇(申告必須)
– 現在業務委託として関与している人物:△(利益相反の観点で要検討)
—
「申告必須」にする理由は、“選考の公平性”や“部署間の利害関係”に配慮するためです。 明文化されていれば、社員も安心して紹介しやすくなります。
【ステップ②】報酬(インセンティブ)の設計
報酬(インセンティブ)は、リファラル制度を実際に動かすにあたり、非常に重要です。 制度を導入しても紹介が集まらない最大の理由は、「紹介のインセンティブが弱い」ことだからです。
金額やタイミングは、以下のような観点で設計するのが一般的です。
| 観点 | 設計の考え方 |
| 採用難易度 | エンジニア・専門職など、採用が難しい職種ほど報酬を高くする(例:20万円など) |
| 採用コスト対比 | 人材紹介費(例:60〜100万円)の50〜70%を報酬上限の目安にする企業も |
具体例:
| ポジション | 金額 | タイミング |
| エンジニア職 | 20万円 | 入社3ヶ月後 |
| セールス/コーポレート職 | 10万円 | 入社3ヶ月後 |
| アルバイト | 2万円 | 入社1ヶ月後 |
制度的な話だと、紹介者が退職済みの場合は、支給対象外になることが多いですが、中には推薦時点で在籍していれば例外とする企業も。このように、報酬の設計をきっちり定めることで、紹介者が安心して+意欲的に動ける状態を作りましょう。
【ステップ③】選考フローの設計とルール整備
リファラル採用の選考で最も多い失敗は、「信頼できる社員の紹介だから、大丈夫だろう」「不合格にすると気まずくなりそう」といった思考から、本来の基準を歪めてしまうことです。
制度を正しく機能させるには、「通常選考と同じ基準で進めつつ、紹介者・候補者双方への丁寧な配慮」を両立させる設計が必要です。
選考フロー例:
紹介フォーム入力 → 推薦コメントを添えて書類選考 → 通常フローで1次・2次面接 → 合否決定 → 結果を候補者に通知 → 紹介者にも結果を簡潔に共有 など
この際のポイントは、以下の3点です。
推薦者コメントの記入欄を設ける
紹介フォームやATSに、「この人を推薦した理由(200字程度)」などのコメント欄を設けます。これにより、単なる数合わせではなく、紹介者の視点や職務理解が反映された推薦になるため、選考側も評価の前提が整いやすくなります。
例:Googleフォームに記載例を表示
「〇〇さんとは前職で3年間同じチームで働いており、特に自走力と業務スピードに強みがあります。弊社のエンジニア組織にもマッチすると感じて推薦しました。」
面接スピードを担保する「優先枠」の設計
選考スピードはリファラル成功の鍵です。通常選考と同じ基準で進めつつも、「紹介枠の面接は週に2枠以上、優先的に調整できる」体制を設けましょう。
特に現場都合で時間が取りづらい職種では、人事側が間に入って即日調整するフローも効果的です。
不合格時の紹介者フォロー
リファラル制度を社内に定着させるうえで、見落とされがちなのが「不合格時の紹介者対応」です。紹介者からすれば、時間と信頼を使って候補者に声をかけ、会社の魅力を伝え、選考にまでつなげています。それにもかかわらず、不合格のため報酬が出なかったり、そもそも合否の連絡すら一切なかったりすると、「もう紹介したくない」とモチベーションが下がってしまうのは当然です。
だからこそ、候補者本人への連絡とは別に、紹介者にも結果を伝える運用を必須化します。あくまで紹介者は採用チームの一員です。「選考の内情」を伝える必要はありませんが、「結果がどうなったのか」「協力してくれたことがちゃんと評価されているか」の2点を押さえて伝えることで、制度に対する信頼は大きく変わります。
ーーーー
紹介者への連絡例:
〇〇さん
先日は□□さんをご紹介いただき、ありがとうございました。
書類・面接ともに慎重に検討を重ねましたが、今回はポジションとの適合や他候補との比較を踏まえ、見送りの判断となりました。
ご本人へはすでに人事よりご連絡済みです。
改めて、ご紹介という形で採用活動にご協力いただけたこと、心より感謝申し上げます。
もし今後、〇〇さんのご縁の中で「一緒に働きたい」と思える方がいらっしゃれば、ぜひまたお力添えいただけますと幸いです。
ーーー
このように、選考内容には触れず、「ポジションとの適合」や「比較の結果」という形で納得感を持たせる言い回しを用いるのがポイントです。紹介してくれた事実そのものに感謝を伝え、次のアクションを促す一言を添えることで、制度への信頼と紹介意欲を維持しやすくなります。
【ステップ④】社内への告知と制度の浸透
どれだけ制度を丁寧に設計しても、「知られていない制度」は、存在しないのと同じです。
「誰も紹介してくれない」という課題の多くは、報酬やフローではなく、社内への告知不足に起因しています。
- SlackやTeamsに専用チャンネルを設置し、紹介用フォームを常時ピン留め
- 月初などに定期リマインドを投稿し、報酬アップキャンペーンと組み合わせることで注意喚起を強化
- 人事説明会・部門MTGで5分枠を確保し、制度の背景と意義を伝える
- マネージャー経由でメンバーへ声がけ:「このポジション、紹介できそうな方いませんか?」
- 紹介から採用につながった事例は、朝会や社内報で簡単に共有
└ 「●●さんの紹介で、○○職に●●さんが入社されました!」 - ランキング制度や、紹介数に応じた特別報酬などで意欲向上
このように、「継続的な告知→浸透→成果を賞賛」の流れを継続的に設計することが、制度を形骸化させず、「紹介したくなる空気」を社内に育てます。 制度そのものだけでなく、それを伝え続ける仕組みまで含めて設計する視点を持ちましょう。
【ステップ⑤】KPI管理・運用改善
制度を「作って終わり」にしないためには、ちゃんと動いているかを確認できる指標(KPI)と、改善サイクルをあらかじめ設計しておくことが重要です。
ポイントとして、KPIは選考プロセス全体で設計しましょう。単に「何件紹介が来たか」だけを追っていても、制度がうまくいっているかどうかは判断できません。リファラル採用では、“紹介~入社・定着”までの各フェーズに分けてKPIを設計するのがポイントです。
| フェーズ | KPI指標 | 見るべき観点・活用ポイント |
| 紹介発生 | 紹介件数 | 月別推移や部門別の偏りを確認。「制度がちゃんと使われているか」を可視化 |
| 書類選考 | 通過率(通過数 ÷ 紹介数) | 通過率が低ければ、紹介対象の定義や事前の期待値すり合わせに課題があるかも |
| 面接〜最終 | 面接通過率・辞退率 | どこで辞退されているか?選考設計や連絡スピードなど運用面の改善に活かせる |
| 内定・辞退 | 内定率・内定辞退率 | 条件・ポジション・クロージング手法などの見直し判断に使える指標 |
| 入社・定着 | 入社率・定着率(3ヶ月・6ヶ月) | 制度が成果に結びついているか?定着率が悪ければ選考・紹介経路の精度見直しを |
KPIを集計 → 分析 → 改善アクションを繰り返します。よくある課題と改善アクションは、下記です。
- 紹介件数が少ない → 告知頻度・チャンネルを見直す/報酬アップキャンペーンを検討
- 通過率が低い → 「どんな人を紹介してほしいか」のメッセージを再整理して発信
- 内定辞退が多い → スピードや条件面のクロージング力を強化
- 定着率が悪い → 紹介時の情報伝達や選考フィードバックの質を見直す
四半期ごと・半期ごとに集計し、経営陣・部門責任者と共有するレポート体制を整えましょう。良い制度をつくるだけでなく、動かし続ける仕組みをつくることこそが、リファラル採用を成功に導きます。
まとめ
リファラル採用には、採用コストの削減やカルチャーフィットした人材の獲得、定着率の向上といった大きなメリットがあり、人事リソースが限られている中小・ベンチャー企業にもおすすめの採用手法です。
一方で、「制度を設計して、実際に回す」ための運用の工数や、社員への周知・巻き込みの難しさといった壁も存在します。
だからこそ、「ただ制度を作る」だけではなく、誰が紹介できて、誰を紹介してよいかの定義/報酬の明確化/社内への伝え方/KPIによる改善運用など、制度と運用をセットで考えていくことが、成果を出す鍵になります。まずは小さな一歩から実践していきましょう。
株式会社アールナインでは、15年770社以上の採用支援実績をもとに、採用戦略の立案から、媒体運用・スカウト・面接調整までを一気通貫で支援する採用代行サービス「人事ライト」を提供しています。採用にお悩みの方や、「何から始めればいいかわからない」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事の監修者:
1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。