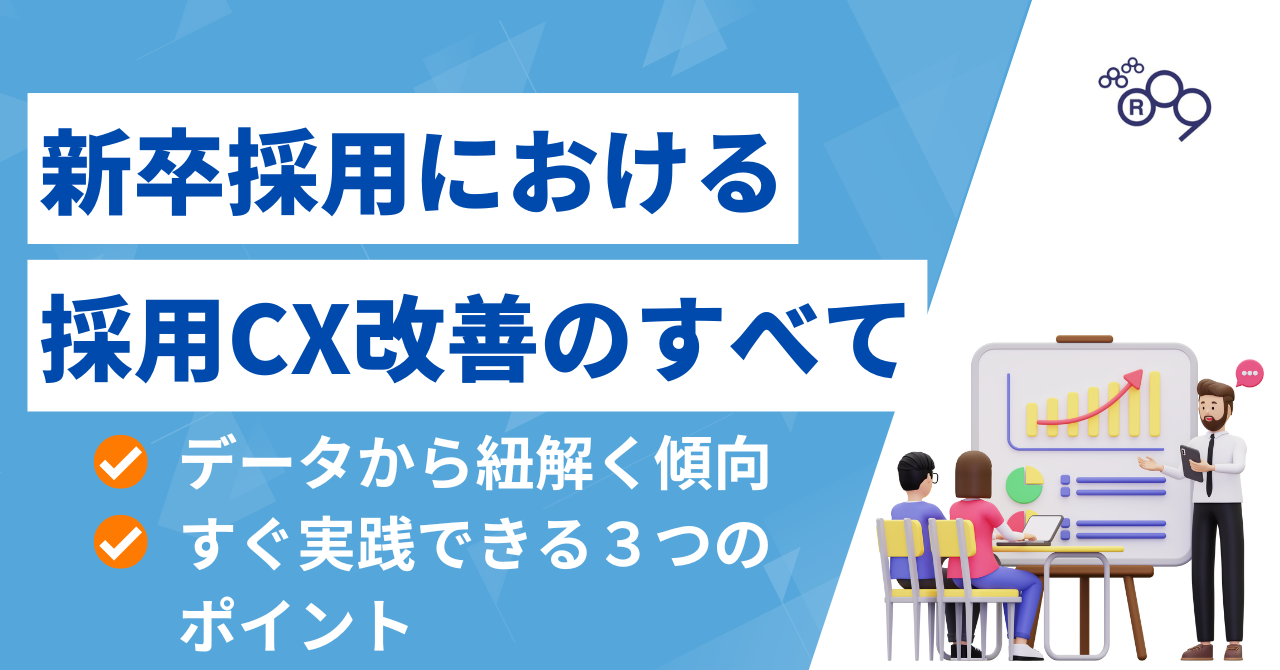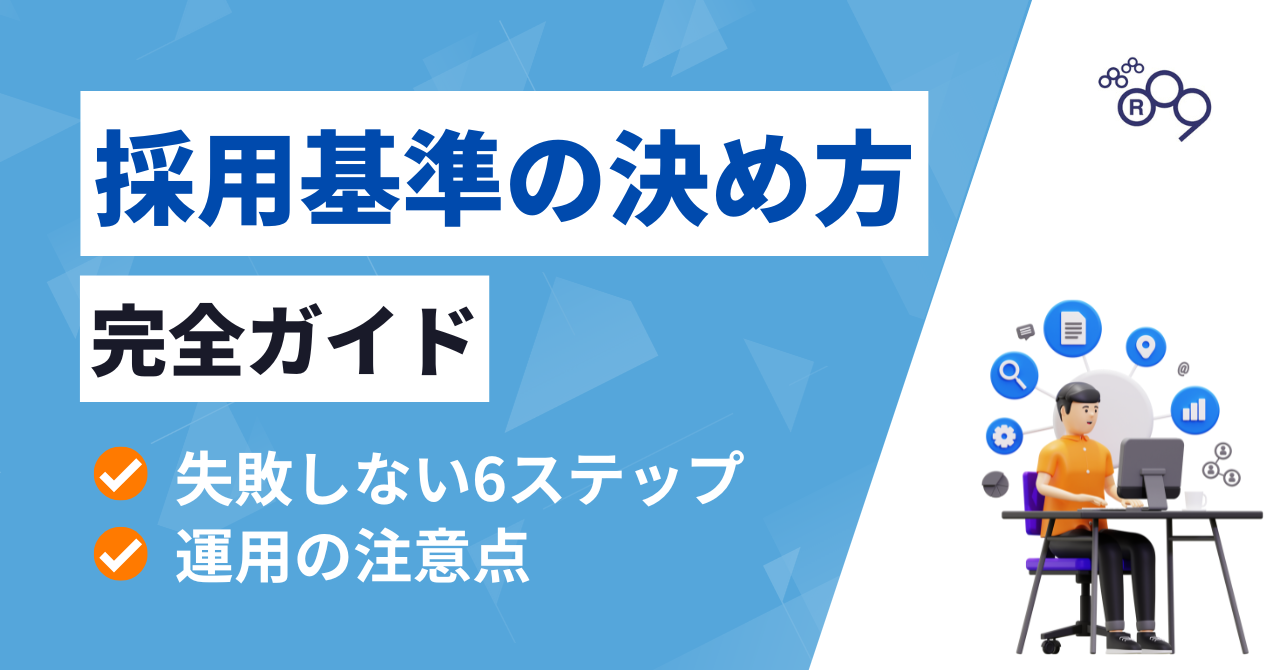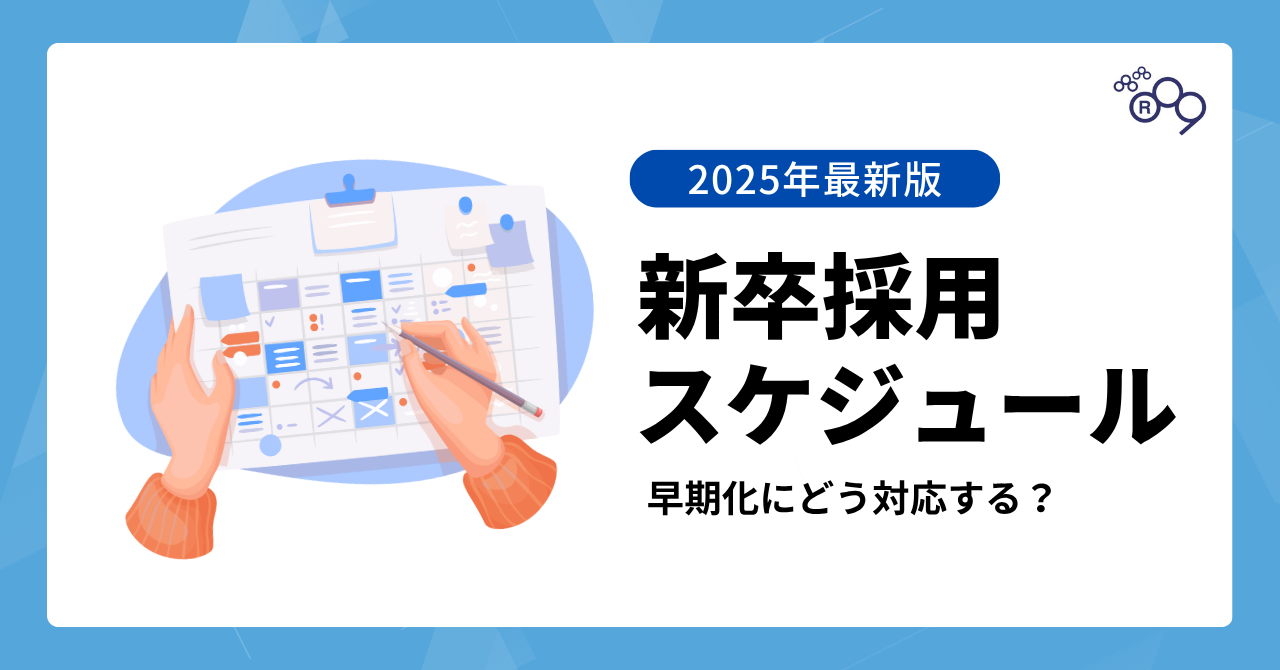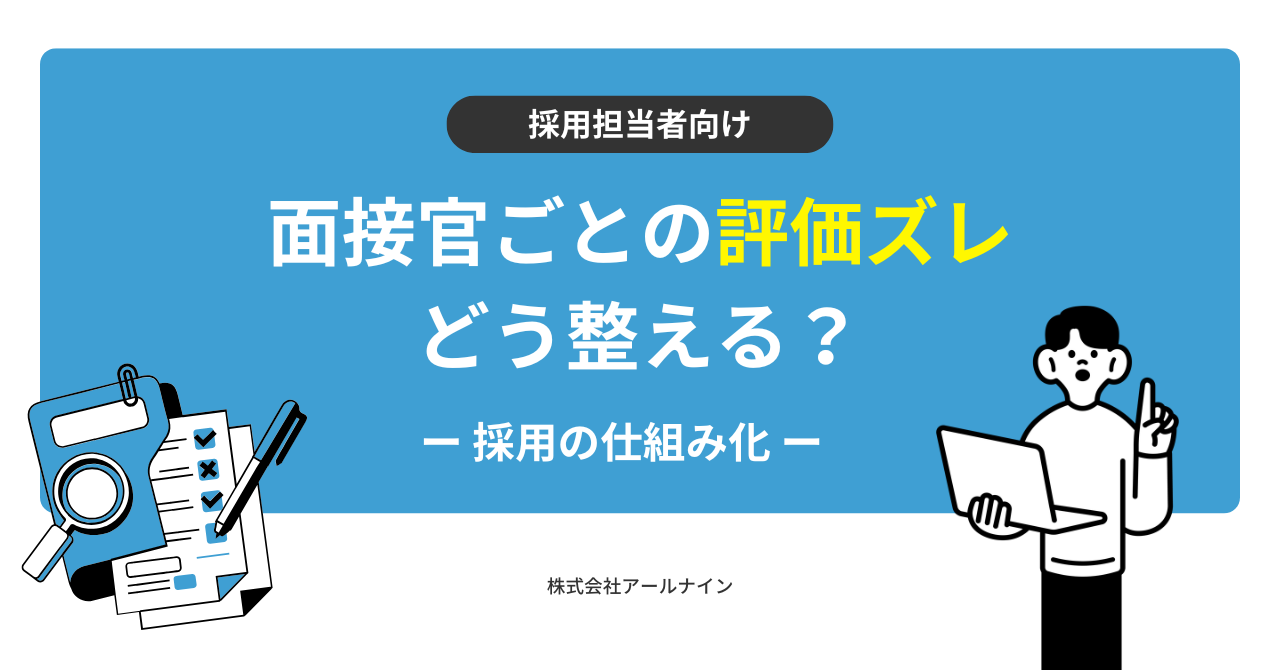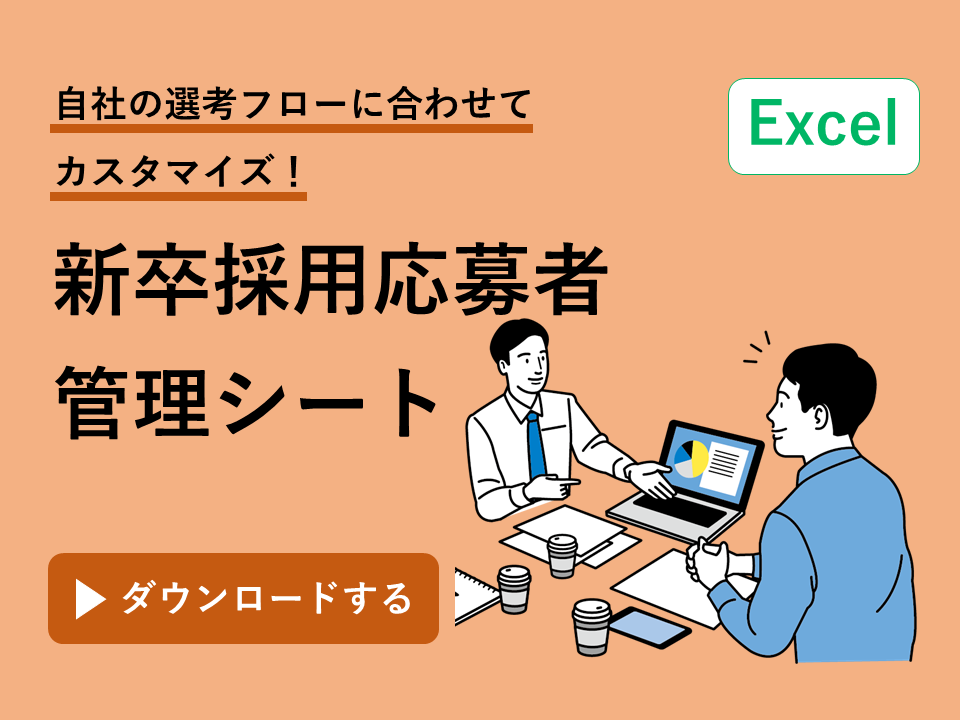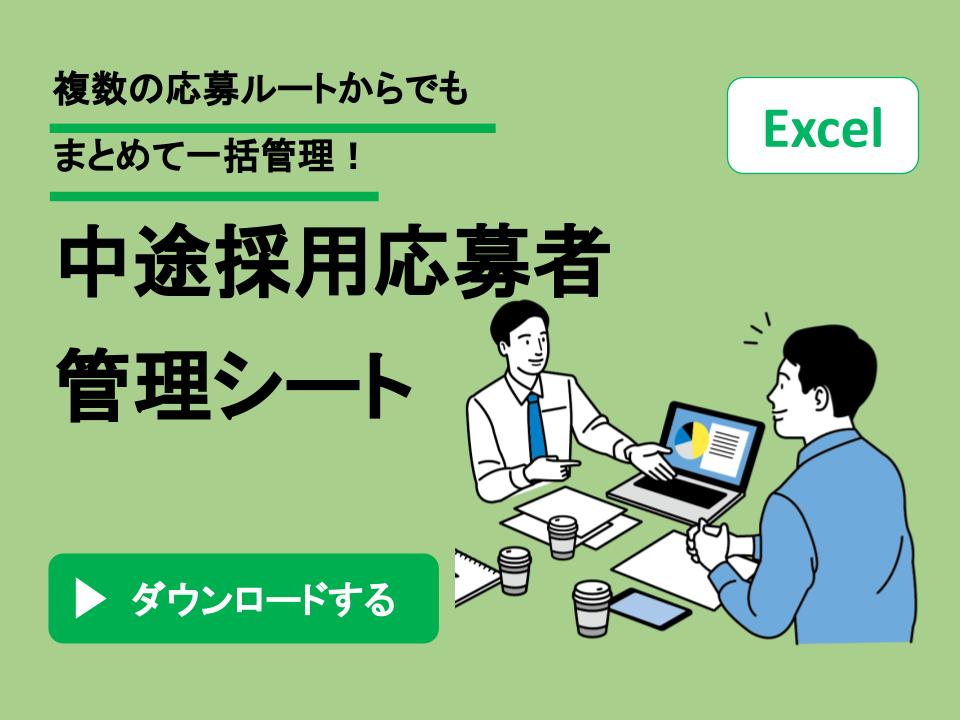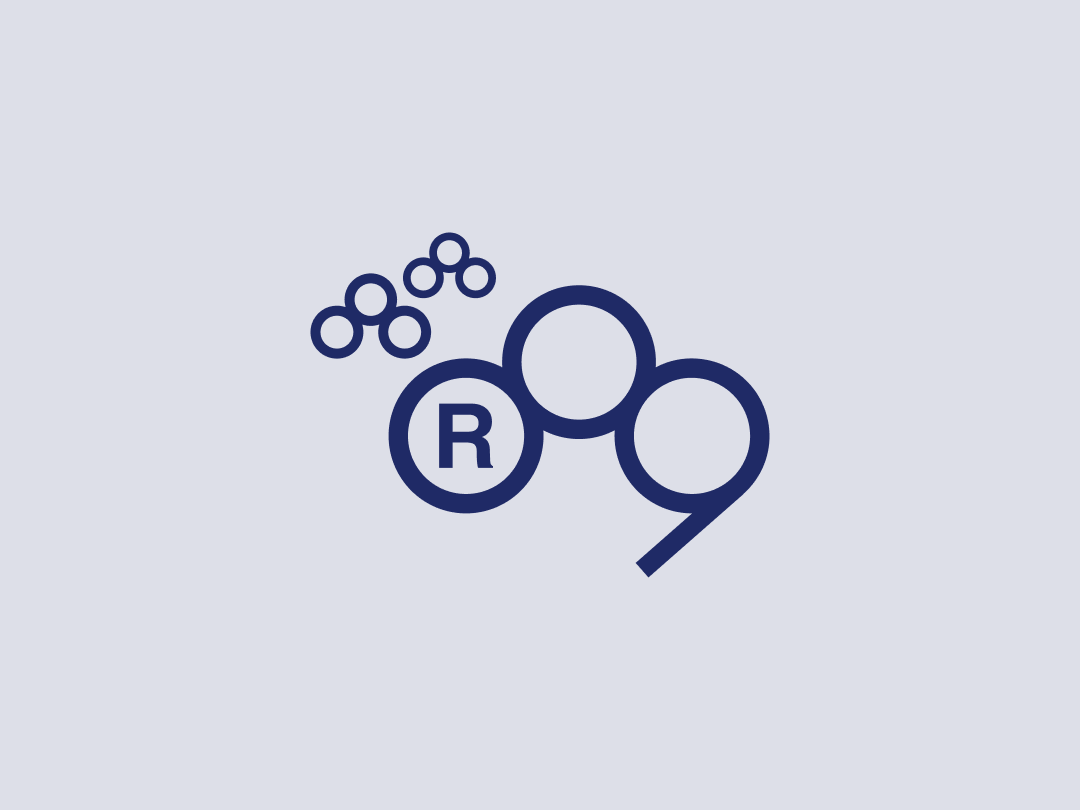採用計画の立て方|採用CX視点で“選ばれる企業”になるための6ステップ
公開日: 2020年11月24日 | 最終更新日: 2025年11月11日

採用が「企業が人を選ぶ」時代から、「候補者に選ばれる」時代へと変わる中、これまでのような“社内都合の採用計画”では成果につながらないケースが増えています。
特に今は、選考を通じて企業への印象が形づくられる「採用CX(候補者体験)」の重要性が高まっており、計画段階からこの視点を取り入れることが、採用成功の前提となっています。
本記事では、採用活動を構造的に設計し、候補者体験の向上を軸に設計していく「採用CX起点の採用計画」の立て方を、6つのステップに分けて分かりやすく解説します。
新卒・中途を問わず、“選ばれる企業”になるための実践的なヒントとして、ぜひご活用ください。
読みやすいPDF版はこちら↓
採用計画を立てる前に押さえるべき3つの視点
採用活動の成否を分けるのは、「計画をどれだけ丁寧に設計できたか」にかかっています。特に現在のような“選ばれる採用”が求められる環境下では、ただ人数やスケジュールを決めるだけの計画では機能しません。候補者視点をふまえた“体験設計”としての採用計画が求められます。
そのためには、以下の3つの視点を事前に整理することが重要です。
① 採用市場・競合の動向を把握する
採用計画を立てるうえでまず必要なのは、「自社を取り巻く外部環境」の把握です。
たとえば、新卒採用であれば学生の就活動向や内定保有率、中途採用であれば求職者の動きや採用競合の求人内容など、市場環境によって採用の難易度は大きく変わります。
自社にとっての「競合」とは、必ずしも同業種に限りません。学生や求職者が比較・検討している企業群(=比較検討の土俵)を見極め、採用ターゲットと重なる他社の訴求内容・採用プロセスを把握しておくことが、採用計画の精度に直結します。
② 自社の採用活動を振り返る
過去の採用活動におけるデータや実感を振り返ることも、計画設計には不可欠です。
特に、以下のような点を整理しておくと、次回の採用計画に活かせます:
- 各工程の歩留まり(例:面接辞退率、内定辞退率、内定承諾率など)
- 歩留まり向上に貢献した接点の特徴(例:座談会の印象が良かった、現場社員との接点が承諾率に効いた 等)
- 選考中の学生・候補者の「志望理由」や「辞退理由」
こうしたデータの蓄積があれば、定量的に改善余地のある接点やメッセージ設計を見直すことができます。
③ 採用活動の全体像とKPIを定義する
採用は“点”ではなく“線”の設計です。
特に採用CX(候補者体験)の視点を取り入れる場合、「どのような体験が、どのフェーズで、どのように印象形成されるのか」を見える化しておく必要があります。
そのうえで、下記のようなKPIを設定すると、接点設計が具体的になります。
- 各接点ごとの到達率・歩留まり(例:説明会参加率→面接移行率)
- 内定出しをする人数
- 内定辞退率の上限目安
採用CX起点で考える「選ばれる採用計画」6ステップ
従来の採用計画は、「どの時期に、何人を、どの手法で採用するか」という社内都合の計画が中心でした。しかし、候補者が企業を“選ぶ側”に回っている今、求められるのは“体験価値を設計する採用計画”です。
その設計思想として取り入れたいのが、採用CX(Candidate Experience:候補者体験)という考え方です。
採用CXとは、候補者が企業と接触してから内定・入社に至るまでのすべてのプロセスにおける「体験の質」を指します。
たとえば、スカウトメールを受け取ったときの印象、説明会での情報の伝わり方、面接時の雰囲気、社員との対話内容、内定後のフォローなど、候補者はあらゆる接点を通じて「この会社に入りたいかどうか」を判断しています。
そしてその判断は、合理性だけではなく「感情」に強く影響されます。
だからこそ、採用計画の段階から、候補者がどう感じるか・どう惹かれていくかを意識した“体験設計”が求められるのです。
特に、行動経済学で知られる「ザイオンス効果(単純接触効果)」に着目し、接点の質と回数を戦略的に組み込むことは、承諾率や志望度に大きく影響します。
以下では、採用CXを軸にした採用計画の6つのステップを紹介します。
Step 1:採用の目的と方針を明確にする(=採用の“なぜ”を言語化)
まず取り組むべきは、「なぜ採用するのか」という目的を、経営戦略・組織課題と結びつけて明確にすることです。
例:
- 新規事業立ち上げに伴う人材補強
- 若手層の定着率向上を目的とした新卒採用
- 組織カルチャーをアップデートするための採用
この“採用の背景と目的”を言語化しておくことは、社内連携・社外発信の両面で軸になります。
Step 2:採用ターゲット(ペルソナ)と候補者体験を描く
誰を採用したいのか――というターゲット設定は、採用CXにおいて「どんな体験が響くのか」を考える基盤になります。
たとえば、
- 安定志向の学生なら、社内制度・福利厚生への安心感
- 成長意欲の高い転職者なら、裁量やキャリアステップの提示
といったように、ペルソナごとに“刺さる体験”は異なります。候補者が自社に惹かれていく「感情の変化のストーリー」を描くことで、採用活動全体のCX設計が可能になります。
Step 3:候補者接点を設計する(ザイオンス効果に基づく「6接点設計」)
「人は繰り返し接するものに好感を抱きやすい」というザイオンス効果(単純接触効果)の観点からも、接点数の設計は非常に重要です。
アールナインが実際に採用のご支援を行う中で、「全体で6回以上の接点があると、5回以下に比べて内定承諾率がかなり向上する」ことが分かりました。
例:6接点モデル
- 初回面談(カジュアル面談)
- 1次面接
- リクルーター面談
- 2次面接
- 社員面談
- 最終面接
「自社を深く知ってもらう」「感情的納得を積み重ねる」接点をどこにどれだけ設けるか。それを事前に設計することが、候補者の志望度や内定承諾率を高める鍵となります。
Step 4:採用プロセスと選考基準を設計する(見極めと訴求の両立)
選考とは「見極める場」であると同時に、「選ばれる場」でもあります。
見極め重視のあまり硬直的な面接ばかりでは、候補者は“選定されている感覚”を持ち、離脱してしまうこともあります。
一方で、訴求ばかりに偏ると、「自分のことを見てくれていない」と感じてしまいます。
そこで重要なのが、「どのフェーズで何を評価し、何を伝えるか」のすり合わせです。
- 1次面接:カルチャーマッチの見極めと訴求
- 2次面接:スキル・ポテンシャルの見極めと、自社でそれをどう活かせるかの訴求
- 最終面接:志向性と覚悟の見極め、社内でどう活躍してほしいか伝える など
プロセス全体を通じて、「評価基準 × 訴求ポイント」が設計されているかが鍵となります。
Step 5:採用スケジュールと媒体戦略を設計する(チャネル別の接点強化)
採用成功は「スケジュール設計」にかかっています。
特に、新卒であれば“採用解禁日”にとらわれすぎない早期接点の設計が鍵です。中途であれば“応募〜初回接触までのリードタイム短縮”が成否を分けます。
また、媒体戦略についても、「接点の1つとしてどう活かすか」の視点が必要です。
- ナビサイト:初期認知の導線設計
- スカウト:文章に込めた想いと初動スピード
- 自社採用ページ:印象形成・ブランドイメージ
- SNS:情報接触の“軽い”接点づくり
どの媒体で、どのような役割を担わせるかまでを含めて、計画の中で設計しておくことが重要です。
Step 6:社内体制・評価体制を整える(チームでつくる採用CX)
どれほど設計が良くても、社内体制が整っていなければ計画は実行に移されません。
特にCXの質に直結するのが、面接官や現場社員の関与と質です。
- 評価基準の統一(面接官ごとにバラつかない)
- 面接クオリティの担保(圧迫面接・尋問感がない、聞く姿勢がある)
- 社内全体の目的理解(何のための採用か)
採用担当者だけでなく、現場や経営層を巻き込んだ“チーム設計”が、計画の実行力と候補者体験の質を担保します。
新卒・中途での採用計画の共通点と相違点
採用計画においては、「新卒」と「中途」で採用市場の前提も、候補者の行動も異なります。そのため、手法やスケジュールに違いが出るのは当然ですが、だからといって別々のロジックで設計する必要があるわけではありません。
むしろ、採用CXという共通の視点で捉えることで、“新卒・中途の違い”を押さえつつも、一貫した計画設計が可能になります。
共通点:どちらにも必要な5つの設計要素
- 採用目的の明確化
事業課題や組織の未来像と結びつけて、採用の“Why”を明確にすること。 - ペルソナと訴求軸の設計
求める人物像を定義し(WHO)、その人が惹かれる体験や情報を設計すること(WHAT)。 - 接点数の設計(6接点以上)
ザイオンス効果に基づき、印象形成に必要な“接触回数”を逆算すること(HOW)。 - 見極めと訴求のバランス設計
評価だけでなく、候補者が“ここで働きたい”と思える接点を盛り込むこと。 - 社内体制とプロセスの可視化
評価基準やスケジュール、社内の巻き込み体制まで見える化して共有すること。
これらの考え方は、採用対象が新卒であっても中途であっても、共通して必要です。
相違点:対応すべき違いと設計時のポイント
新卒採用における前提と対応ポイント
| 観点 | 新卒採用の特徴 | 計画時の留意点 |
| スケジュール | 固定化・年次制 | 早期接点(夏・秋インターン)を戦略的に設計 |
| 比較対象 | 同期企業・ナビ上の他社 | 事業競合だけでなく「採用競合」を見極める |
| 意思決定軸 | 直感・人・成長環境 | 採用CXを軸にした設計が重要 |
| 認知経路 | 多様化(ナビ、ダイレクト、SNS等) | 多様なチャネルを前提に初期接点設計を行う |
中途採用における前提と対応ポイント
| 観点 | 中途採用の特徴 | 計画時の留意点 |
| スケジュール | 通年/流動的 | スピード感を持った選考フロー設計が必須 |
| 比較対象 | 前職・年収・働き方 | 訴求軸の設計に「条件」だけでなく「納得感」が必要 |
| 意思決定軸 | 再現性・確実性・未来像 | 長期的なキャリアパスと定着支援の可視化が効果的 |
| 認知経路 | エージェント・スカウト | エージェントとの関係構築と連携が重要 |
一貫性を持たせるために
新卒も中途も、「どのように自社に惹かれていくか」という“候補者体験の設計”という意味では本質は同じです。
違いを理解した上で、軸となる採用方針やCX設計の視点を共有し、同じ戦略思想の中で、それぞれに最適化されたプロセスを組むことが、採用の“再現性”と“質の担保”につながります。
採用計画を「机上論」で終わらせないために
どれだけ入念に設計した採用計画であっても、「実行されない」「現場と乖離している」「数値の進捗しか見ない」――そんな状態では、採用の成果にはつながりません。
採用計画を“実行できるもの”として機能させるためには、運用フェーズで押さえるべき視点と仕組みがあります。
計画を“現場”で運用できるようにする
採用活動は人事だけでは完結しません。面接官・現場社員・経営層との連携があって初めて、計画が実行に移されます。
そのため、以下のような「巻き込みの設計」が不可欠です。
- 採用目的・ターゲット・CX設計を社内で共有する
- 面接官向けに評価基準や伝えるべき訴求内容を整理する
- 採用に関わる社員が“なぜこの採用が必要か”を理解している
策定された計画を現場が理解し、具体的な行動に落とし込めるかどうかが、計画の成否を左右します。
進捗と質の両方をモニタリングする
採用計画の多くは「面接何人」「内定何名」といった数値目標に偏りがちです。
しかし、採用の質を担保するためには、「歩留まり」や「体験」の視点を加えたモニタリングが必要です。
- 接点ごとの歩留まり(例:説明会→面接移行率、1次→最終面接通過率)
- 面接満足度や辞退理由など、CXに関わる定性的なデータ
- エージェントや媒体ごとの母集団傾向と歩留まりの差
こうしたデータをもとに、計画と実際の乖離を早期に発見し、適宜改善できる運用体制を整えておくことがポイントです。
振り返りと“次回”に繋がる仕組みを設ける
採用活動は単発で終わるものではなく、必ず次の採用に繋がります。
だからこそ、採用活動後には必ず「振り返り」と「知見の言語化」が必要です。
- 成果の要因(うまくいった理由、苦戦した要因)
- 候補者から見た印象(選ばれた理由/辞退された理由)
- 今回の設計・運用で“再現したい要素”と“見直すべき要素”
これらをテンプレート化し、ナレッジとして社内で共有・蓄積していくことで、採用計画は“都度つくり直すもの”ではなく、再現性のある仕組みへと育てていく資産になります。
採用計画は「立てたこと」に意味があるのではなく、それを「実行・改善し続けられるかどうか」が問われます。
机上論にとどまらず、実行され、成果につながる採用計画を目指すことが、採用成功の近道です。
まとめ:“選ばれる企業”になるための第一歩としての採用計画
採用計画は、単なる「採用人数の目標」や「スケジュールの確認」ではありません。
本来は、企業がどのような人と出会い、どのような体験を通じて関係を深め、共に働く未来をつくっていくか――そのための“設計図”です。
今の時代、企業が候補者を見極めるだけでは採用は成立しません。
候補者からも「この企業と働きたい」と選ばれる存在であるために、採用CXという視点を採用計画に取り入れることがますます重要になっています。
そのために必要なのは、
- 採用の目的や背景を明確にすること
- ターゲットとなる人材と、その心を動かす体験を描くこと
- ザイオンス効果を踏まえた“接点設計”を行うこと
- プロセスの中で「見極め」と「魅力づけ」を両立させること
- 組織として実行できる運用体制を整えること
こうした観点を踏まえて設計された採用計画は、企業の“採用力”を高めるだけでなく、組織そのものの魅力や働く価値を見つめ直す機会にもなります。採用は、企業と人の未来をつくる行為です。
“選ばれる企業”への第一歩として、体験を設計する採用計画を、ぜひ自社の採用戦略の中心に据えてみてください。
この記事の監修者:
1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。