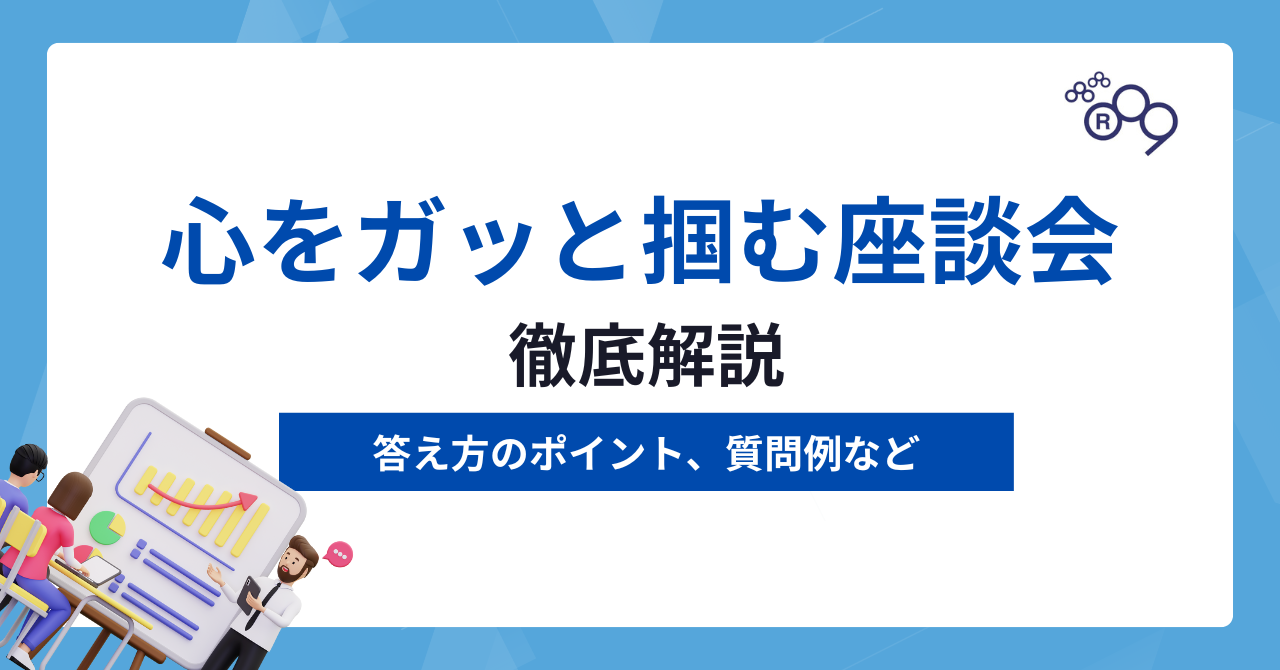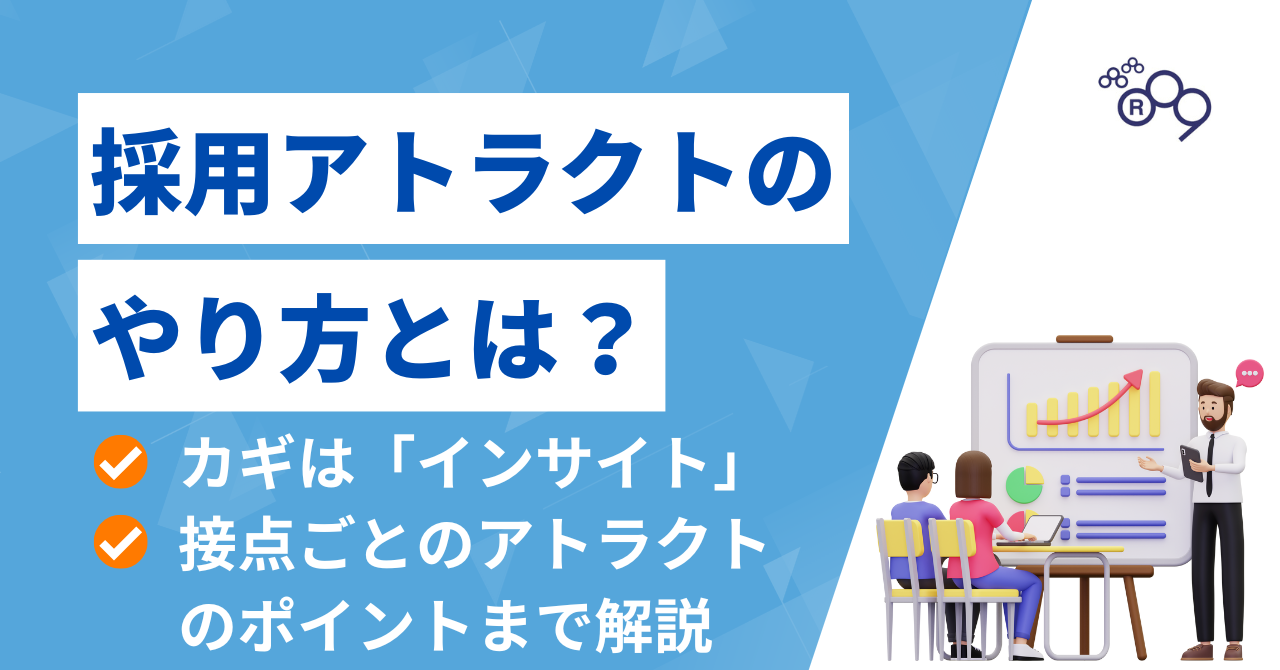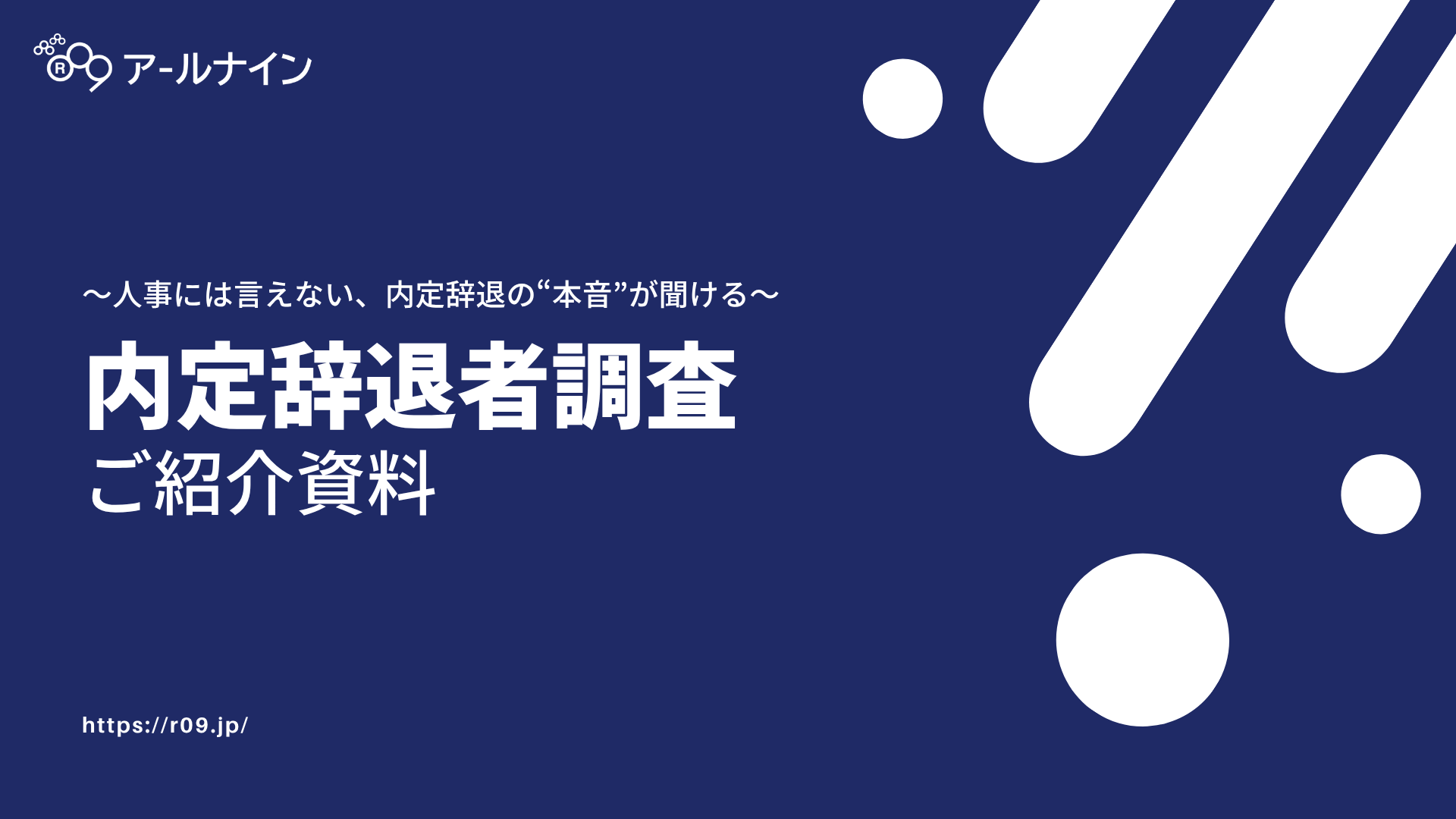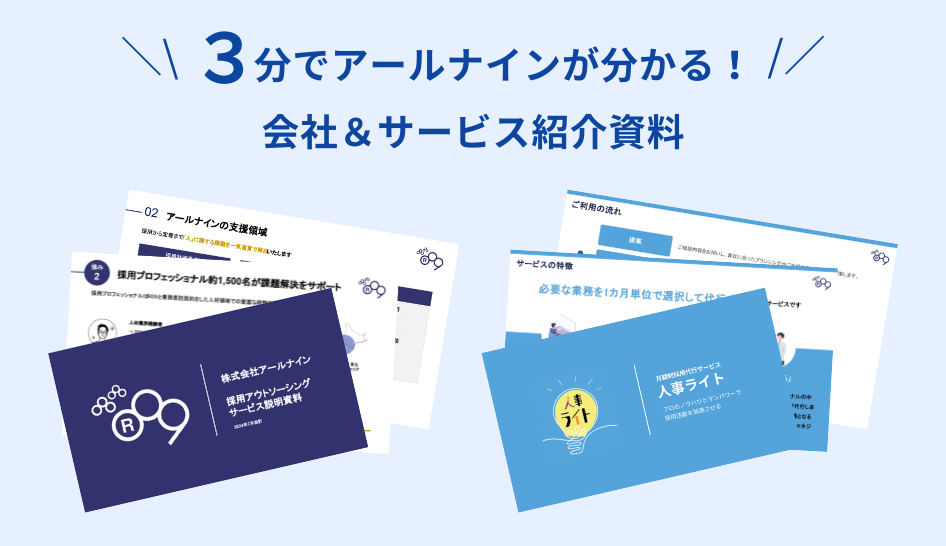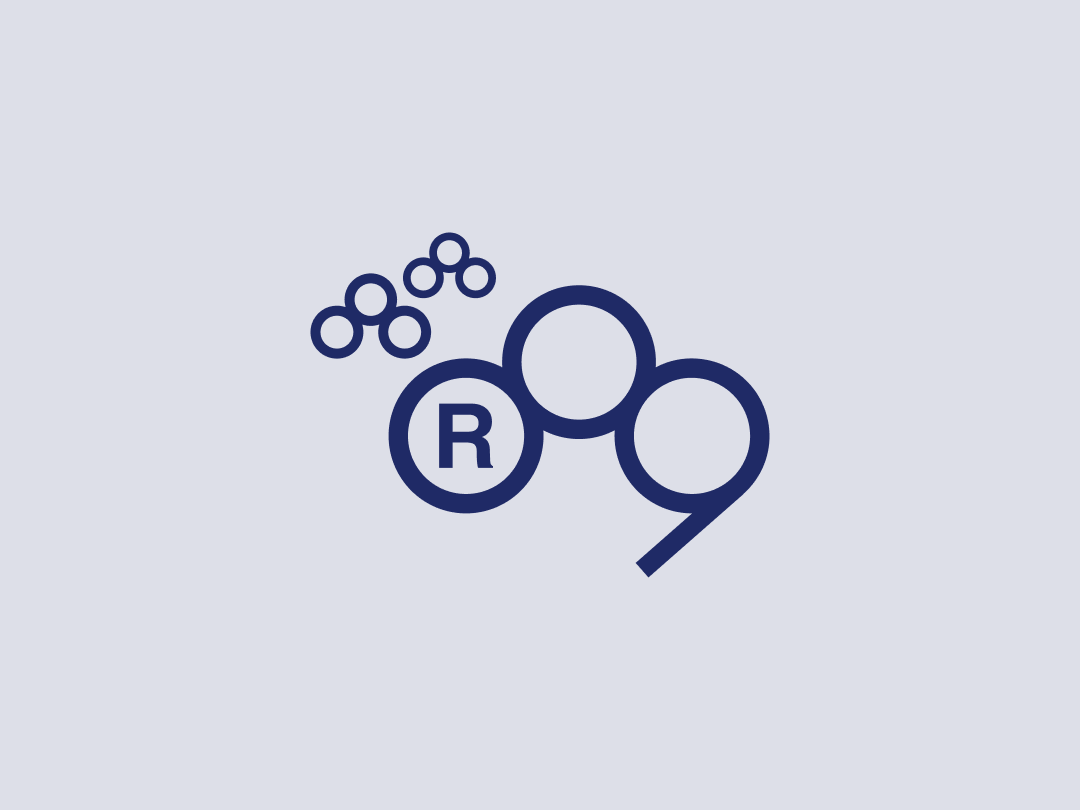新卒採用における採用CX改善|売り手市場を勝ち抜くポイントを解説
公開日: 2025年11月11日
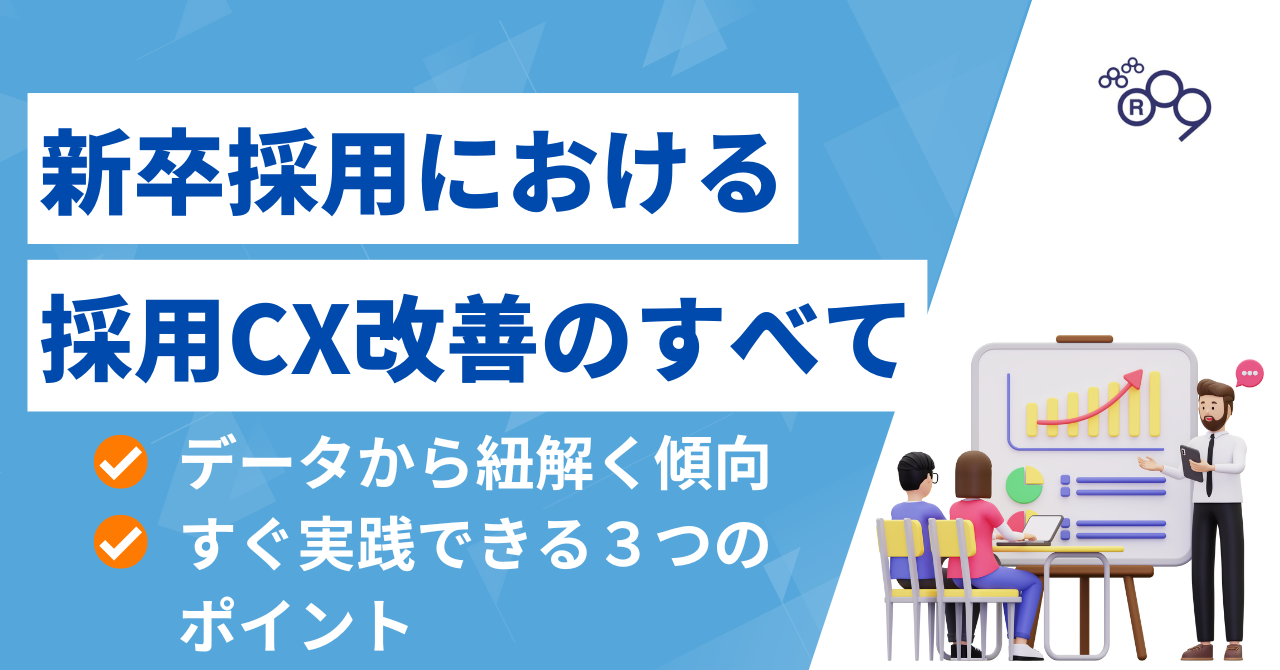
売り手市場が続く今、大量の母集団を集めることは難しくなってきています。採用成功のカギを握るのは「歩留まり率を高めること=採用CX(候補者体験)の改善」です。
本記事では、採用CXの基本と注目される背景、改善の具体策、さらに実際の企業事例をご紹介します。学生から「選ばれる採用」を実現したい方はぜひ参考にしてください。
採用CXとは?
採用CX(Candidate Experience/候補者体験)とは、学生が企業の採用プロセスを通じて得る体験全体を指します。説明会、面接、内定後フォローといった一つひとつの接点が、学生の感情や満足度に直結します。
新卒採用データから紐解く、採用CXが注目される理由
近年、日本の新卒採用市場では「採用CX」が急速に注目されています。その背景にあるのは、売り手市場の激化です。
そもそも採用成果は 母集団数 × 歩留まり率 で決まります。母集団が100人、歩留まり率が1%であれば、採用できるのは1人だけ。採用成功の道筋は「①母集団を十分に集める」「②歩留まり率を高める」の2つしかありません。しかし近年は、母集団を集めること自体が難しくなっています。
リクルートワークス研究所「ワークス大卒求人倍率調査(2026年卒)」によると、大卒求人倍率は以下のように推移しています。
- 2022年卒:1.50倍
- 2023年卒:1.58倍
- 2024年卒:1.71倍
- 2025年卒:1.75倍
- 2026年卒:1.66倍
2026年卒は前年に比べて0.09ポイント低下したものの、水準自体は依然として高く、学生1人あたり1.6社以上の求人が存在する状況で、売り手市場が続いていることが分かります。
引用:リクルートワークス研究所:「ワークス大卒求人倍率調査(2026年卒)」
特に認知度が低い中小企業の場合、大手のように大量の母集団を集めることは難しいです。そこで、母集団を無理に増やすのではなく、「歩留まり率」を高める戦略です。そして、その鍵を握るのが採用CXなのです。
リクルートマネジメントソリューションズの「2025年新卒採用 大学生の就職活動に関する調査」によると、「就職活動中の志望度向上に特に影響が大きかったこと」の項目の中に、採用体験によるものが多く含まれています。

引用:リクルートマネジメントソリューションズ:2025年新卒採用 大学生の就職活動に関する調査
すなわち、採用CXは「歩留まりを高め、選ばれる企業になるための最重要戦略」と言えるでしょう。
【具体例つき】採用CX改善で新卒採用を成功させる3つのポイント
ここからは、採用CXを高める3つのポイントを紹介していきます。
1. 接点回数を確保する
学生との接点は「量」がカギです。
ザイオンス効果(単純接触効果)
心理学でいうザイオンス効果(単純接触効果)により、人は繰り返し接触するほど印象や好感度が高まり、関心も強まる傾向があります。
ある企業の分析では、接点が5回以下の学生と6回以上の学生とで、内定承諾率に2倍以上の差が出たという結果もあります。
つまり、説明会や面接だけでなく、面談・座談会・メールフォローといった「非選考の接点」をどう設計するかが、志望度を左右します。
サンクコスト効果
また、学生が投下した労力が意思決定を後押しするサンクコスト効果も働きます。
「この企業に時間をかけたからこそ、ここに入りたい」という心理です。
接点の間隔は2〜3週間に1度を目安に、面接やグループワークの合間にカジュアル面談やリクルーター面談を挟むと、志望度の低下を防ぎやすくなります。
単に回数を増やすのではなく、「一貫したストーリーで学生と関わる」ことが重要です。
2. 接点ごとの質を高める
接点の“数”だけでは、学生の心は動きません。重要なのは、一つひとつの接点で「この会社に惹かれる理由」をつくること。
同じ時間でも、伝え方次第で学生の印象は大きく変わります。
スカウトメールでは「WHY YOU」を含んだ個別メッセージを
最初の接点ほど、個別性が効きます。「なぜあなたに声をかけたのか」を明確に伝える“WHY YOU”の一文を添えることで、返信率は確実に上がります。
たとえば「○○さんのゼミでの研究内容を拝見し、当社の新規プロジェクトと重なる部分がありご連絡しました」といった、相手に合わせた一言が効果的です。
会社説明会では社員の「リアルな声」を伝える
スライドで会社概要を説明するだけでは響きません。実際の社員が「なぜ入社を決めたか」「入社後に感じたギャップ」「リアルな実情」を語る方が、はるかに信頼されます。
また、強みだけでなく課題も率直に話しましょう。「誠実な会社」という印象を与えられるだけでなく、入社後のイメージもクリアにさせられます。
さらに、最後の15分を座談会形式に変えるだけでも、学生の理解度と志望度は大きく高まります。
カジュアル面談は「相互理解」をベースに、価値観に合わせた魅力訴求を
カジュアル面談を導入し、適切に実施することで、接点の質を高めることができます。
カジュアル面談は選考ではなく、相互理解の場として設計することが重要です。学生のこれまでの取り組みや価値観、将来像を丁寧に聞き出し、それに合わせて自社の情報を伝えましょう。
たとえば「成長環境を重視している学生」には、挑戦できる制度や若手の活躍事例を中心に伝えるなど、価値観に沿った伝え方を意識しましょう。
また、面談で得た情報は今後の選考でも活用できる貴重なデータです。学生理解の深さが、次の面接やクロージングの質を左右します。
面接は「選ぶ」だけでなく「選ばれる」視点を大切に
面接は「見極める場」であると同時に、「学生に選ばれる場」でもあります。逆質問では、学生の質問の裏にある価値観をくみ取り、それに沿って企業の魅力を伝えましょう。
たとえば「成長できる環境がありますか?」という質問には、制度の説明だけでなく、実際に成長した社員の具体例を添えると効果的です。
また、現場面接官や役員が面接に不慣れな場合、その対応差が候補者体験を大きく左右します。事前の面接官トレーニングで、質問の仕方や評価基準を統一し、候補者体験の質を担保しましょう。
接点の“質”は、学生が感じる信頼と安心を積み上げるプロセスです。
1回ごとの接点を「体験設計」として見直すことが、結果的に内定承諾率を最も押し上げます。
3. 候補者の声を改善に活かす
採用CXを磨くには、候補者がどう感じているかを知ることが重要です。
説明会・面接・内定フォローなど、各接点の後に短いアンケートを取りましょう。
- 印象・満足度
- 改善してほしいこと
- 志望度の変化(上がった/変わらない/下がった)
これをもとに、定期的に「辞退理由トップ3」や「高評価のポイント」を社内共有します。
内定辞退者の声は特に貴重なので、外部(第三者)経由でヒアリング「内定辞退者調査」も選択肢に上がります。
こうして得た声を下記に活かすことで、自然とCXが磨かれていきます
- 説明会スライドの改善
- 面接官トレーニングのテーマ設定
- フォロー施策の見直し
1人でも「また会いたい」と思ってくれる候補者が増えれば、それが採用力の底上げにつながります。
採用CX改善事例:東阪企画株式会社
東阪企画株式会社(テレビ番組制作/従業員数約50名)では、学生にしっかり向き合える採用体制づくりを目指し、採用CX改善に取り組みました。
スカウトでは、どんな学生にスカウトメールを送るのか、どんなメッセージを届けるのかを考えるために、まずは「自分たちがどんな人材を求めているのか」を社内で言語化。そのうえで、学生一人ひとりに合わせた個別のメッセージを作成することで、「選ばれる」確率が高まりました。
さらに、カジュアル面談の実施や、面接官研修を通じて面接という接点を学生にとって魅力的な体験に変え内定承諾率の向上につながりました。
これらの取り組みにより、学生の満足度が高まり「選ばれる採用」へと変化。結果として、従来は出会えなかったような人材からの内定承諾も得られ、今でも最前線で活躍するなど、本質的な採用成功につながりました。
まとめ
売り手市場が続く新卒採用において、採用CXは「歩留まりを高め、学生に選ばれるための最重要戦略」です。
接点の量と質を工夫し、候補者の声を改善に活かすことで、内定承諾率や定着率を着実に向上させることができます。
「うちの採用でも取り入れたい」「まずは何から改善すればいいか知りたい」という方は、ぜひアールナインまでお気軽にご相談ください。800社以上の支援実績をもとに、貴社に合った採用CX戦略をご提案いたします。
この記事の監修者:
1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。