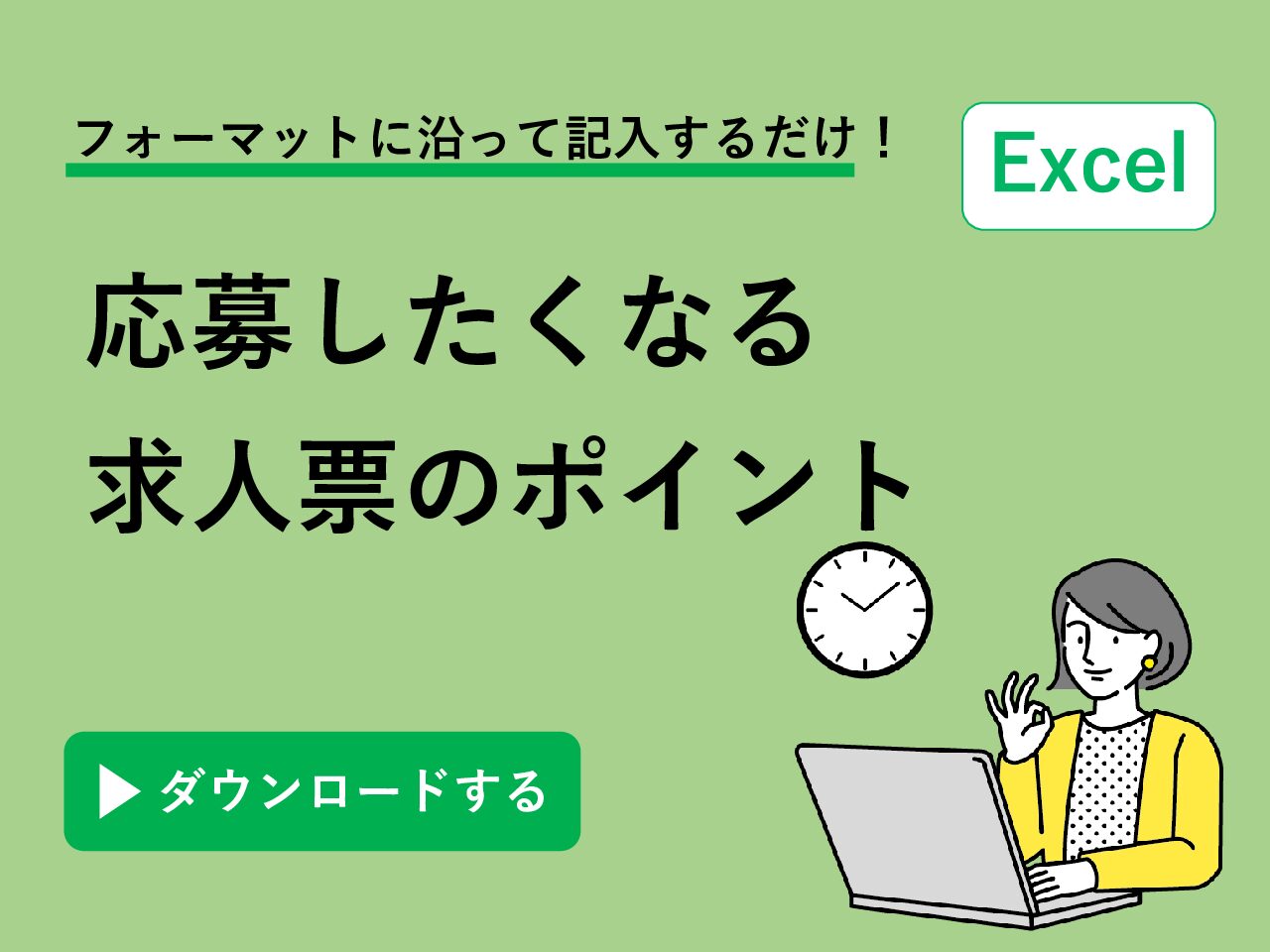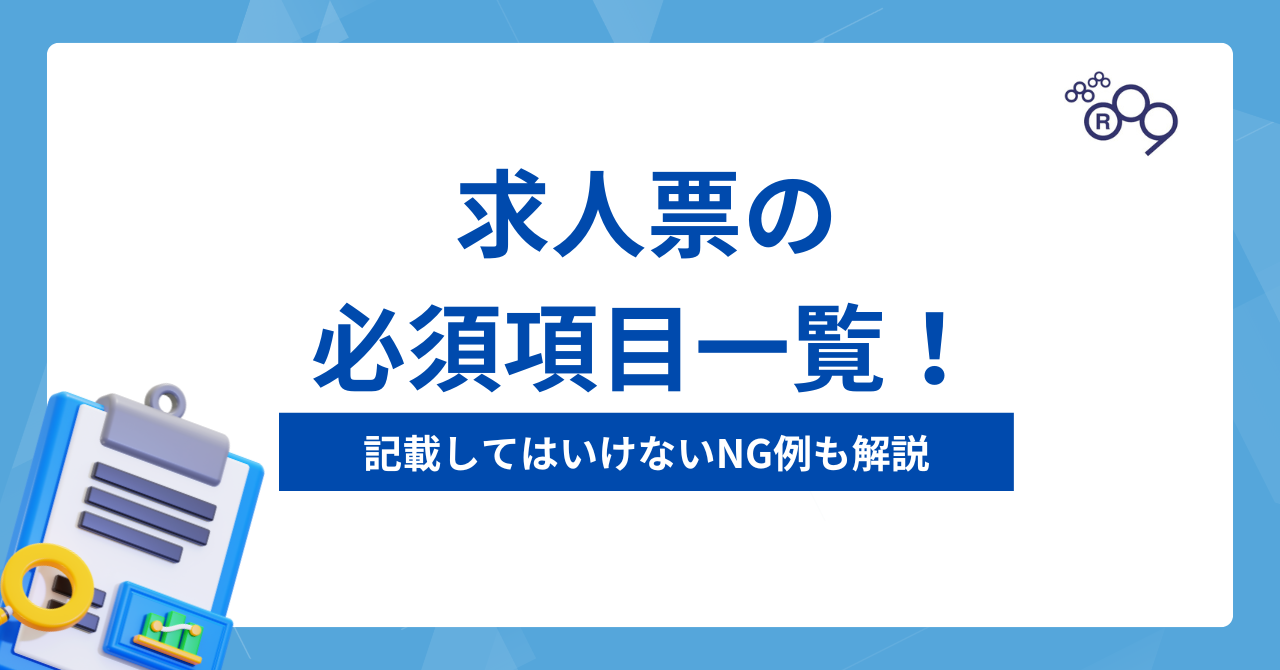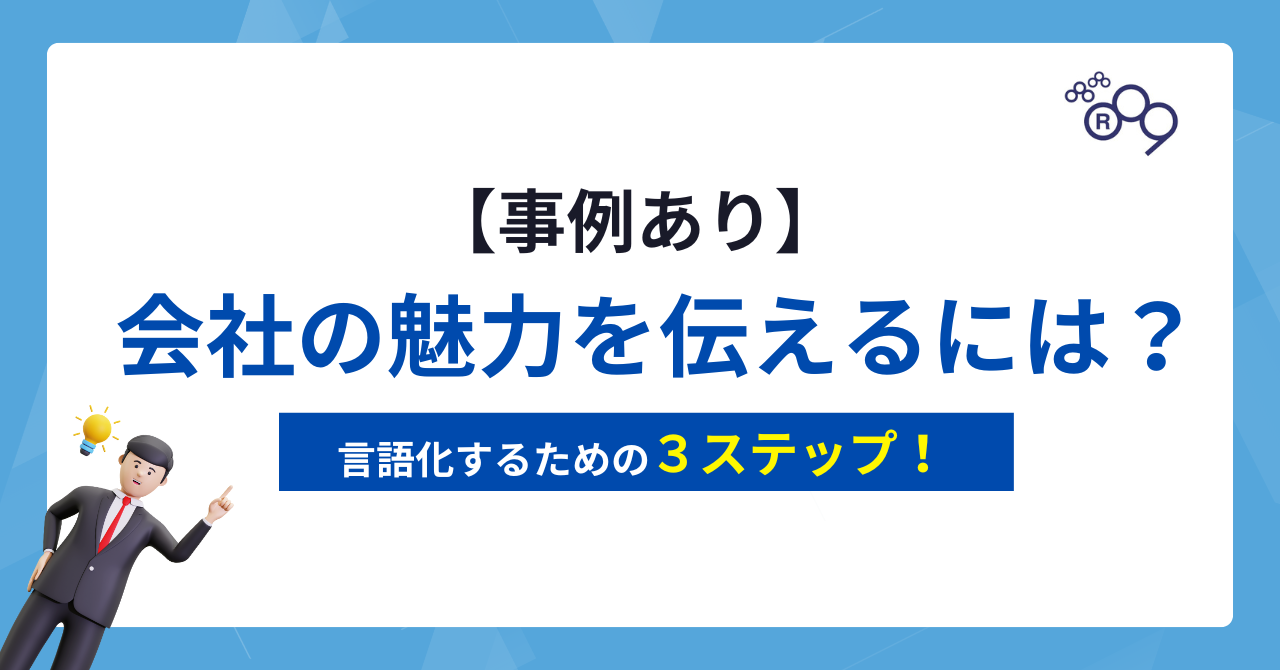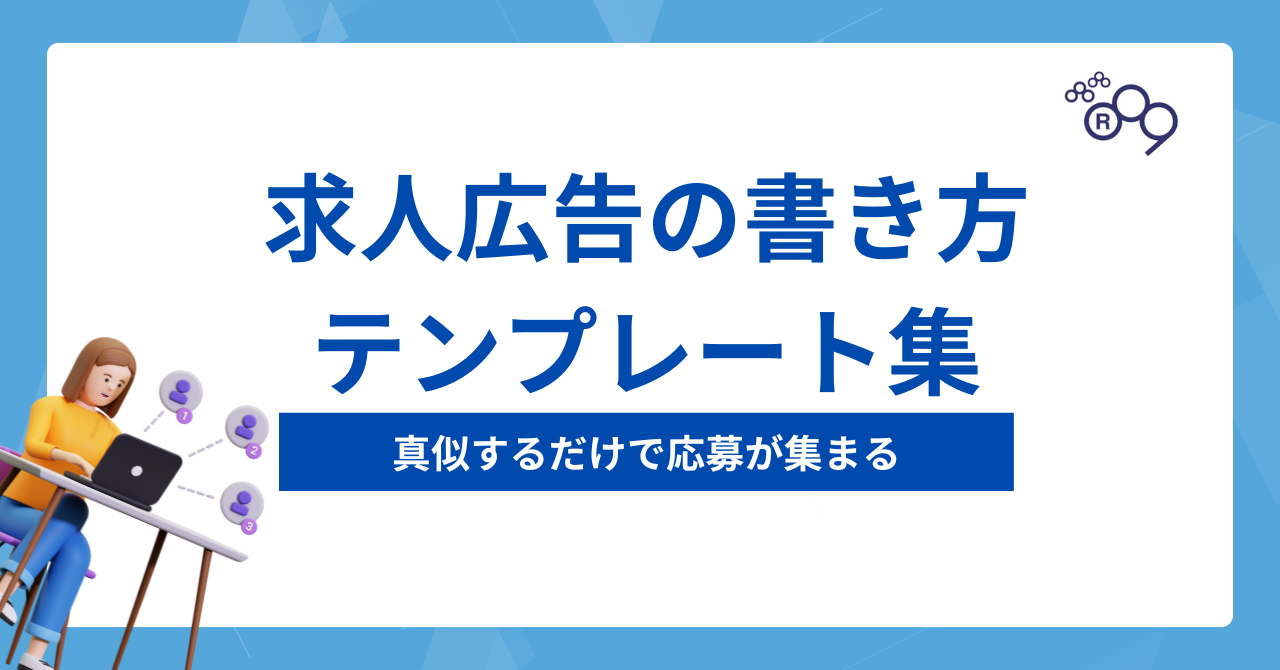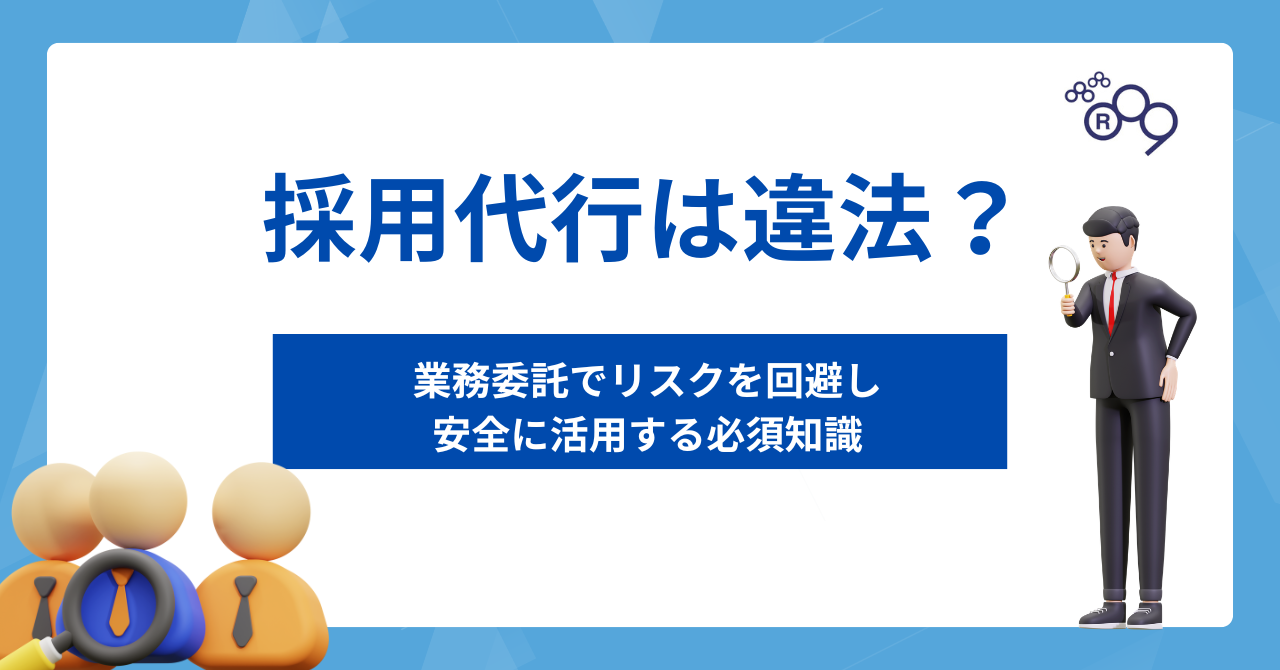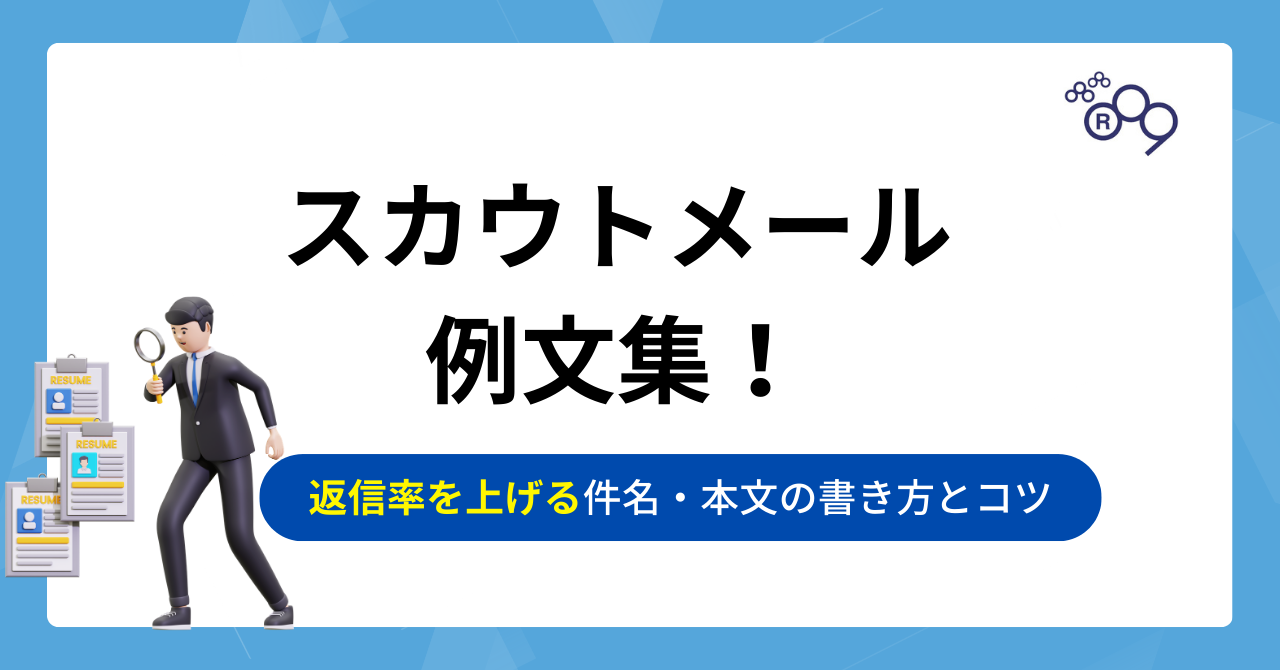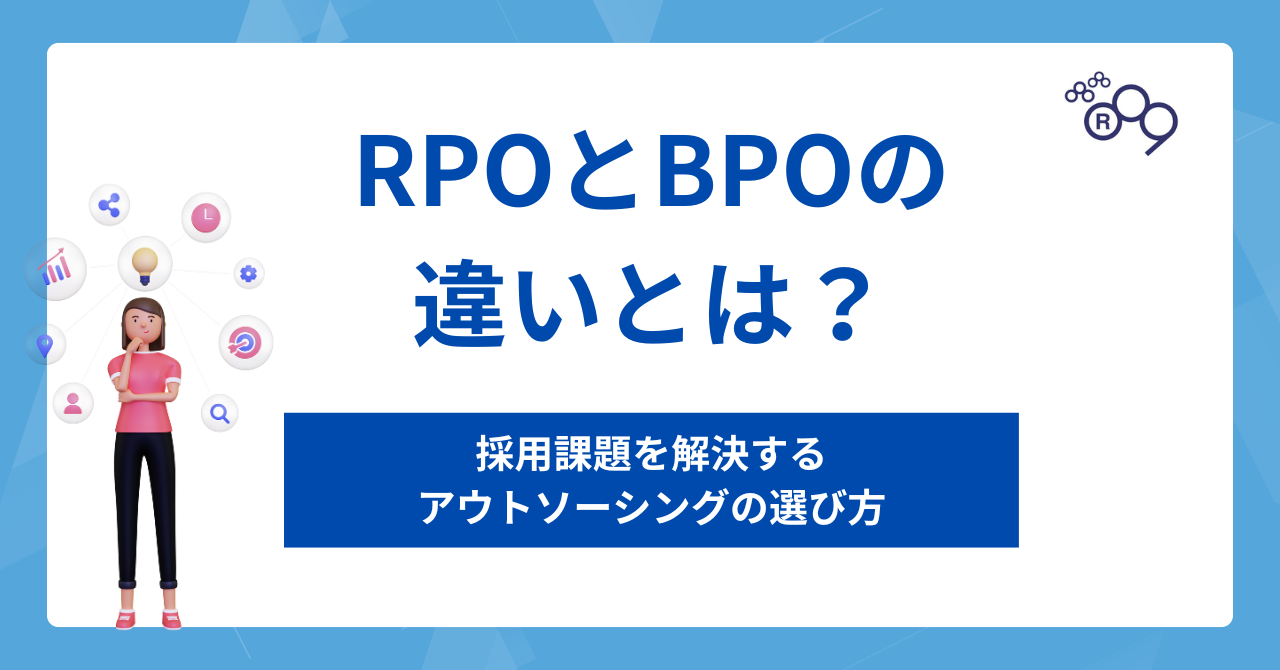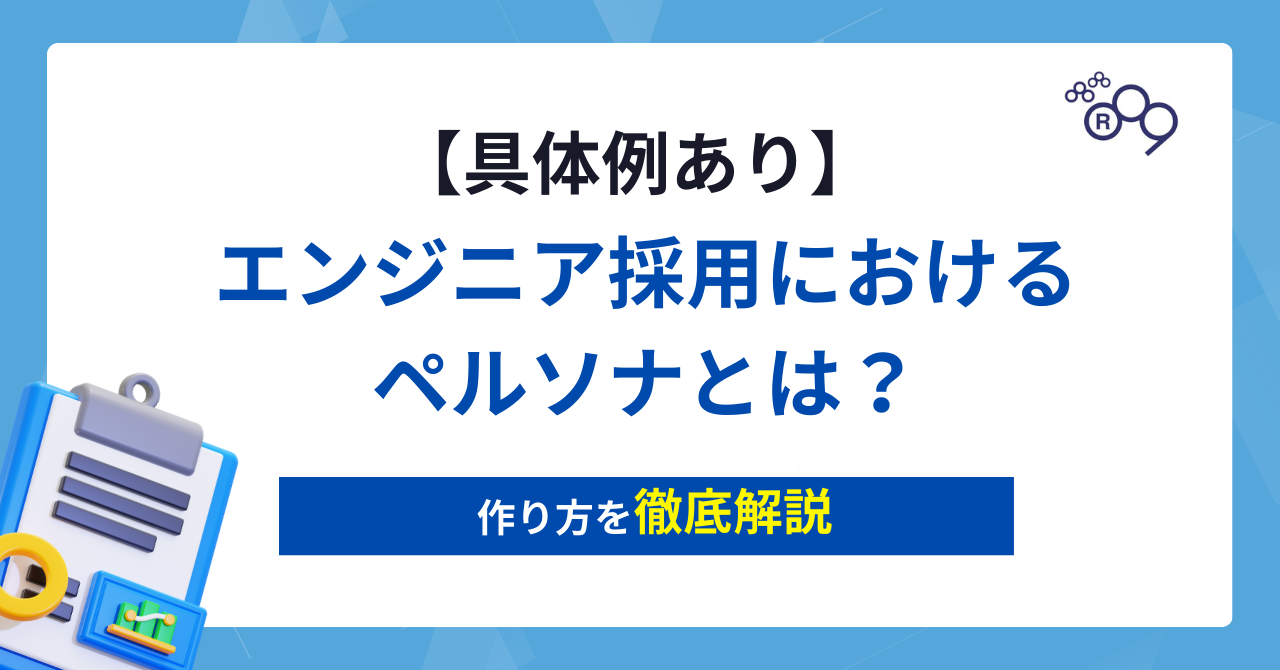求人票の年齢制限はどう書けばOK?原則NGの理由や例外、効果的な書き方
公開日: 2025年11月13日 | 最終更新日: 2025年11月17日

現在、求人票で年齢を限定して募集することは法律で原則禁止されています。
しかし、業種や職種によっては「若手を採りたい」「一定の経験を持つ層に絞りたい」と感じる場面もあるでしょう。
本記事では、求人票に年齢制限を設ける際の注意点や、法律で認められた例外事由、そして違反せずにターゲット層へアプローチする書き方をわかりやすく解説します。
採用効果を高めながら、法令にもきちんと沿った求人票づくりのポイントを押さえましょう。
年齢制限が禁止されている理由
求人票で「35歳以下」「20代限定」などの表記を見かけることがありますが、現在は原則として年齢による制限を設けて募集することは禁止されています。
この規制は、単なるルールではなく「すべての人が平等に職業選択の機会を得られる社会をつくる」ために定められたものです。ここでは、年齢制限が禁止されている背景と、審査でNGになる理由、そして年齢制限を設けないことによるメリットを解説します。
雇用対策法で年齢制限が原則禁止されている
求人票における年齢制限の禁止は、「改正雇用対策法(平成19年施行)」に基づいています。
この法律により、企業は募集・採用時に年齢を理由として応募を制限してはならないと定められました。
つまり、「35歳以下」「若年層限定」などの文言を求人票に記載することは、基本的に違法行為にあたります。
また、この法改正の背景には、「中高年が転職しにくい社会構造の是正」や「年齢にかかわらず能力で評価される雇用の促進」があります。
年齢条件で応募を制限することは、求職者の機会を不当に奪うことになるため、国としても厳しく規制されているのです。
求人媒体・ハローワークの審査でNGになる理由
法律に加えて、ハローワークやIndeedなどの求人媒体も独自の審査基準を設けています。
その目的は、差別的な表現を排除し、求人情報の公平性を保つことにあります。
たとえば、ハローワークの審査では以下のような表現が指摘・修正の対象になります。
- 「20代が中心」「若手限定」など、年齢層を限定する表現
- 「男性活躍中」「女性歓迎」など、性別を前提とした表現
媒体ごとに細かな基準は異なりますが、共通して求められているのは「年齢・性別を理由に応募機会を狭めない」ことです。
審査を通すためには、採用目的を正しく伝える文脈で表現することが求められます。
年齢制限を設けないことで得られる3つのメリット
年齢制限を設けずに募集を行うことで、実は採用面にも多くのメリットがあります。
- 幅広い応募者の確保
年齢条件を設けないことで、経験豊富な人材や多様な経歴の応募が増えます。 - ダイバーシティ推進の評価
年齢・性別などにとらわれない採用は、企業ブランド向上にもつながります。 - 労働局への指摘・掲載停止リスクの回避
不適切な表現を避けることで、媒体審査落ちや行政指導のリスクを防げます。
つまり、「年齢制限をなくすこと」は単なる法令遵守にとどまらず、採用力を高める手段でもあるのです。
年齢制限が認められる例外事由と正しい書き方
求人票での年齢制限は原則として禁止ですが、特定の条件を満たす場合のみ「例外的に」記載が認められています。
これは「労働施策総合推進法施行規則(旧・雇用対策法施行規則)」に定められた6つの例外事由に基づくもので、いずれの場合も「例外事由の号数」と「その理由」を明記する必要があります。
以下では、それぞれの事由の内容・条件・書き方を具体的に整理します。
例外事由1号/定年を上限とした募集
定年年齢が決まっており、期間の定めのない労働契約(正社員採用など)である場合は、この例外に該当します。
ただし、有期雇用契約(契約社員・パートなど)や、定年以外の理由による上限設定は対象外です。
求人票には、例外事由の号数と理由を添えて記載しましょう。
記載例:「定年60歳のため、60歳未満の方を募集(例外事由1号)」
例外事由2号/労働基準法などで年齢制限がある募集
労働基準法や関連法令で特定年齢層の就業が禁止されている職種は、法に基づいて年齢制限を設けることが可能です。
代表的なものは、警備業(18歳未満不可)や深夜業務(18歳未満不可)などです。
こちらも、例外事由の号数と理由を添えて記載します。
記載例:「法令により18歳以上の方を募集(例外事由2号)」
例外事由3号イ/長期キャリア形成を目的とした若手限定募集
長期的なキャリア育成を目的とした募集で、若年層を対象に正社員として採用する場合に限り、年齢制限を設定できます。
適用には以下の2条件が必要です。
- 職業経験を問わないこと
- 新卒者と同等の処遇であること(教育・育成・配置の観点)
この規定は「新卒一括採用の仕組みから漏れた若手求職者」への配慮として設けられたものです。
記載例:「35歳未満の方(例外事由3号イ/長期キャリア形成のため)」
例外事由3号ロ/技能などの継承を目的とした特定年齢・職種募集
社内での技能やノウハウの継承を目的とし、年齢構成に偏りがある場合に該当します。
適用には以下の2条件を満たす必要があります。
- 対象年齢層が30〜49歳の範囲内で5〜10歳幅であること
- 該当層の人数が上下の年齢層の1/2以下であること
技術伝承を目的とするため、年齢条件は狭く設定されるのが一般的です。
記載例:「技能継承のため、35〜40歳の方を募集(例外事由3号ロ)」
例外事由3号ハ/芸術・芸能分野における特定年齢の募集
俳優・モデル・子役など、表現上どうしても特定年齢が求められる職種の場合に該当します。
「役柄上、特定年齢層が必要である」ことを明示すれば問題ありません。
記載例:「舞台の配役上、20代の方を想定(例外事由3号ハ)」
例外事由3号ニ/60歳以上の高齢者、その他特定の年齢層限定募集
国の雇用施策上、以下の年齢層を対象とする場合は年齢制限が認められます。
- 60歳以上
- 33歳以上55歳未満(就職氷河期世代)
- 60歳以上65歳未満(特定求職者雇用開発助成金の対象者)
これらはいずれも「雇用促進」を目的とした年齢設定のため、例外として扱われます。
記載例:「60歳以上の方を積極的に採用(例外事由3号ニ)」
参考:厚生労働省『年齢にかかわりない募集・採用を行うための指針(職発第0425001号)』
年齢制限のある求人募集の効果的な書き方
年齢制限を設けた求人募集は、記載の仕方や訴求の方向性によって効果が大きく変わります。
ここでは、「若手採用」と「経験者募集」を例に、実務で使える効果的な書き方を解説します。
【若手採用】年齢制限の効果的な書き方
若手採用を目的とする場合は、例外事由3号イ(長期キャリア形成)を適用するのが一般的です。一方で、例外事由に該当しない場合は、“若手が活躍している事実”を伝える表現が有効です。
例としては、以下のような言い回しが適しています。
- 「入社2年でリーダーに昇格した社員も」
- 「平均年齢27歳のチーム」
- 「未経験から営業マネージャーを目指せるキャリア制度あり」
これらは虚偽でなく事実をベースにした表現であり、年齢制限には当たりません。
「若手が活躍できる環境」をリアルに伝えることで、応募者の納得感と定着率向上にもつながります。
【経験者募集】年齢制限の効果的な書き方
例外事由3号イ(長期キャリア形成)を用いる場合、原則として「経験者限定」とすることはできません。
なぜなら、「職業経験不問」が適用条件に含まれているためです。
しかし、実務上は「若手×経験者」を求めたいケースも少なくありません。その場合は、直接“経験者募集”と書かずに、経験者が魅力を感じる環境・制度を訴求する方法が効果的です。
たとえば次のような表現です。
- 「最新の製造機器を導入しています」
- 「スキルに応じた昇給・評価制度を整えています」
- 「ベテラン社員がチームを支える体制があります」
このように環境・制度・チーム構成をアピールすることで、年齢や経験の直接的な限定を避けながら、実質的にターゲット層へ訴求できます。
年齢制限が本当に必要かを見直す
最後に、「そもそも年齢制限が必要か」を再確認してみましょう。
応募が多すぎて選考に時間がかかる場合などは年齢制限が有効ですが、条件を増やしすぎると応募数は減少します。
特に人材不足が進む現在では、年齢や経験よりも意欲やカルチャーフィットを重視した採用が成果につながるケースも増えています。
年齢制限を検討する前に、以下のような視点で見直してみるのも有効です。
- 年齢に関係なく活躍できる職場づくりができているか
- 教育・サポート体制を整えれば、対象層を広げられないか
柔軟な採用方針をもつことが、結果的に応募母数の増加とミスマッチ防止につながります。
年齢制限の有無に関わらず、応募を増やす求人票の書き方のコツ
年齢制限を設けなくても、求人票の設計次第でターゲット層に刺さる原稿を作ることは可能です。
ここでは、応募数とマッチ度を高めるための5つの基本ポイントを紹介します。
求めるターゲットを明確にする
まずは「どんな人に応募してほしいか」を社内で明確にしましょう。
性別や年齢は公に書けませんが、以下のような要素は整理しておくべきです。
- 必要なスキルや資格(例:法人営業経験/Excelでの資料作成)
- 経験値や志向性(例:自走できるタイプ/チームで成果を出した経験)
- 転職回数やキャリア志向の目安
これらをMUST(必須条件)とWANT(歓迎条件)に分けて記載することで、求職者にも伝わりやすくなります。
2. ターゲットに刺さる自社の強みをアピールする
求職者は複数の求人を比較して読むため、他社との違いを明確に示すことが重要です。
訴求の切り口としては次の3点が効果的です。
- 事業の魅力(例:業界でのポジション・事業の将来性)
- 環境の魅力(例:有休取得率・残業時間・産育休実績)
- 仕事の魅力(例:裁量の大きさ・顧客との距離感・柔軟な働き方)
求職者は「長く働けるか」「自分に合うか」といった不安を抱いています。
そのため、会社の強みを“見える化”して不安を払拭することが応募促進につながります。
3. 内容をできるだけ具体的に書く
仕事内容が曖昧だと、応募者は「自分に合うか」が判断できず応募をためらいます。
求人票では以下のような具体的な表現を意識しましょう。
- 数字を入れる(例:月10件の訪問、Slackでの連携が中心)
- 一日の流れや仕事の進め方を描く
- 「何を」「どう」する仕事かを明確に伝える
求職者が“自分にもできそう”と思える表現が、応募意欲を引き出すポイントです。
4. 誰にでもわかりやすい言葉を使う
専門用語や社内用語は避け、初めて読む人でも理解できる表現にしましょう。
- 長文は短く区切り、1文1メッセージにする
- 略語・横文字はできるだけ言い換える
- 「第三者が読んでも誤解しないか」を確認する
公開前に複数人でチェックすると、客観的な改善がしやすくなります。
5. 写真や動画を使って雰囲気を伝える
テキストだけでは伝わりにくい「人の魅力」「社内の空気感」は、ビジュアルを活用して補いましょう。
- オフィスや職場の写真
- 働く社員の表情やコメント
- 短いインタビュー動画
完璧な演出は不要です。少し不器用でも“リアルで温かい”雰囲気が伝わるコンテンツの方が、応募者の共感を得やすくなります。
まとめ
いかがでしたか?
求人票で年齢制限を設ける際は、法律で定められた「例外事由」に該当するかどうかを確認することが何よりも重要です。むやみに「35歳以下」「20代限定」と記載してしまうと、違法リスクにつながるおそれがあるため、要注意です。
また、若手層にアプローチしたい場合は、「キャリア形成」「成長環境」「求める人物像」「働く雰囲気」といった要素を具体的に伝えることが効果的です。
年齢そのものではなく、“若手が活躍できる環境”を言葉と事実で表現しましょう。
この記事の監修者:
1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。