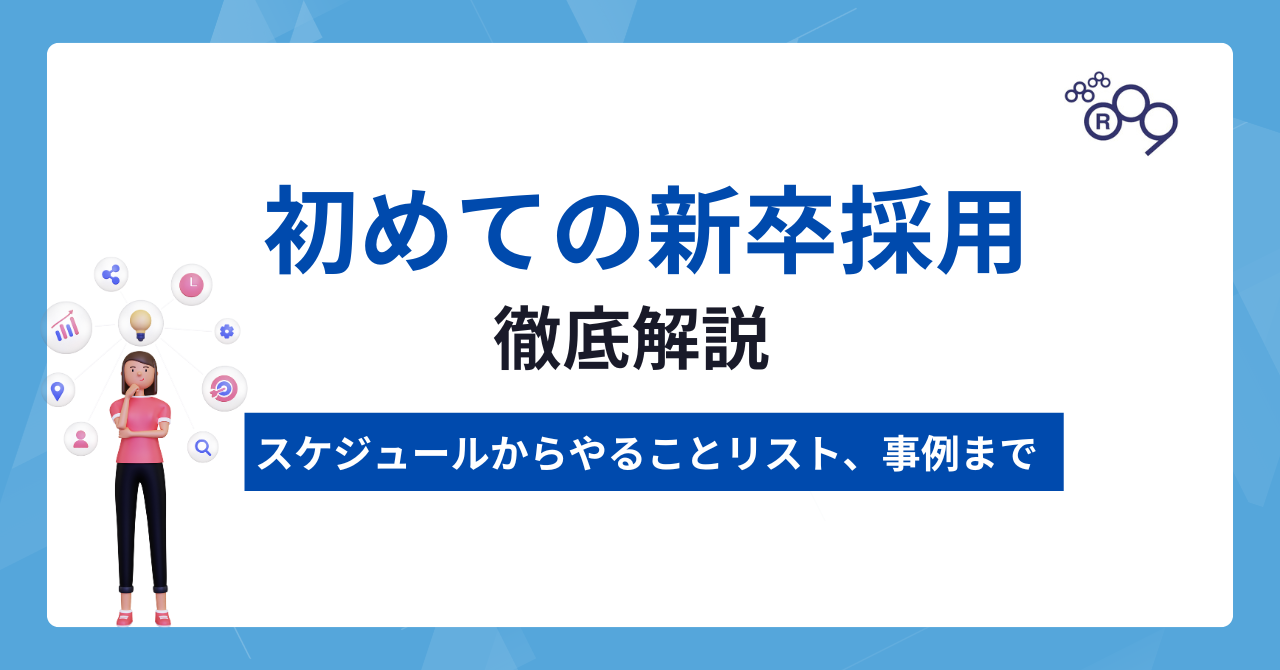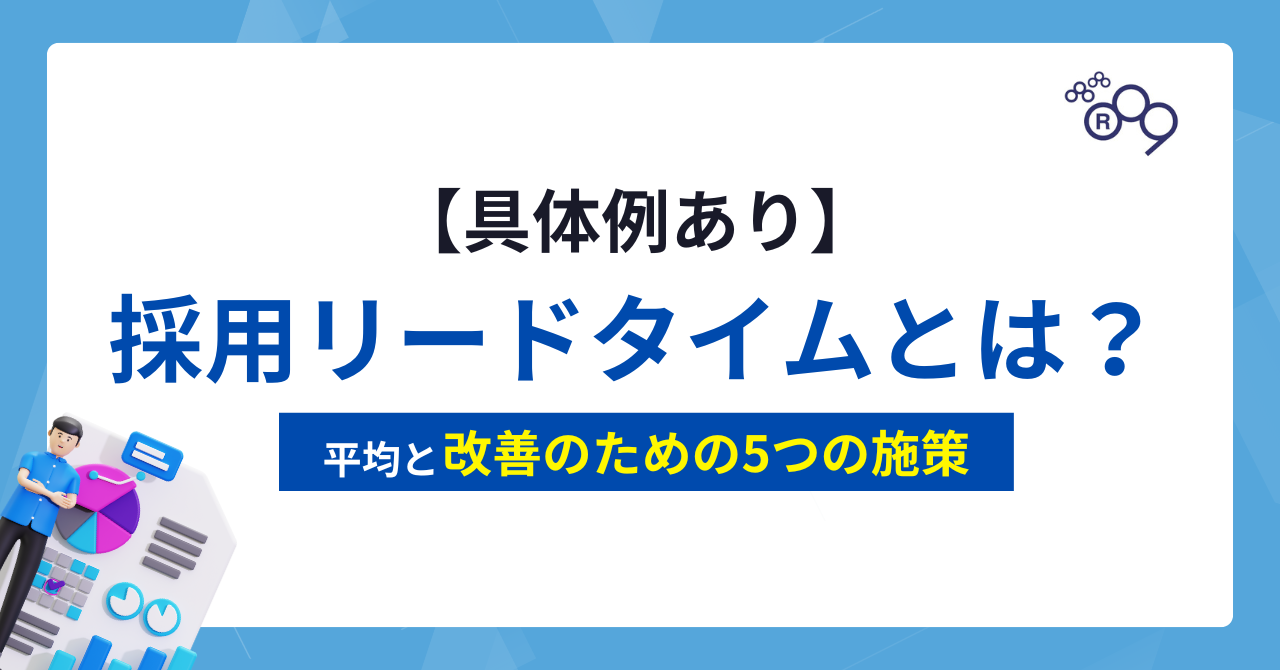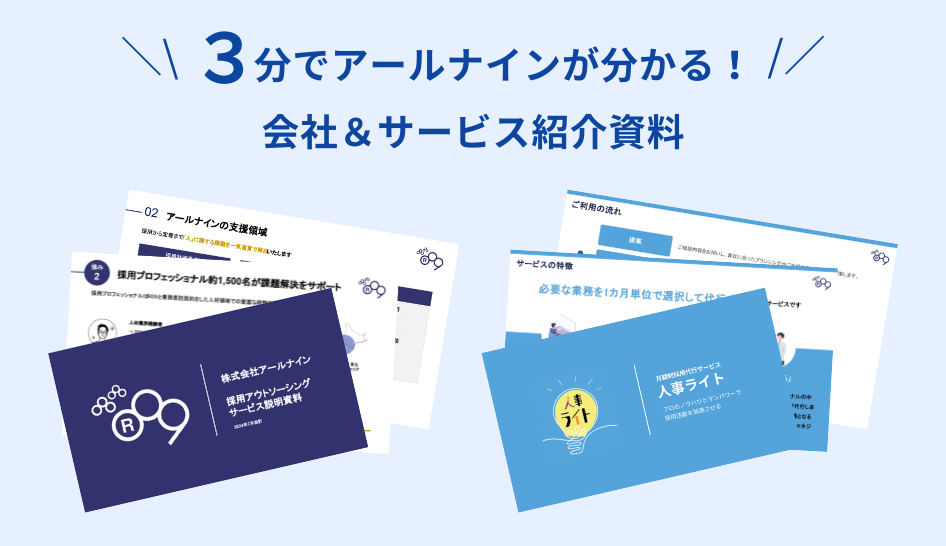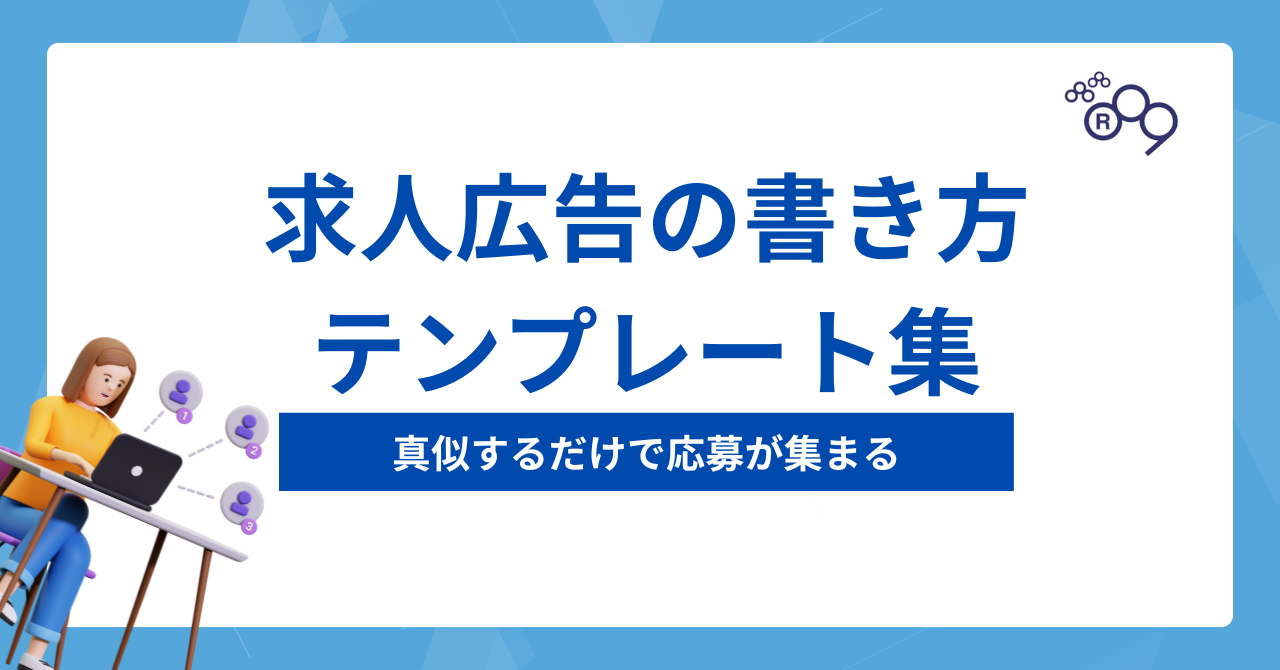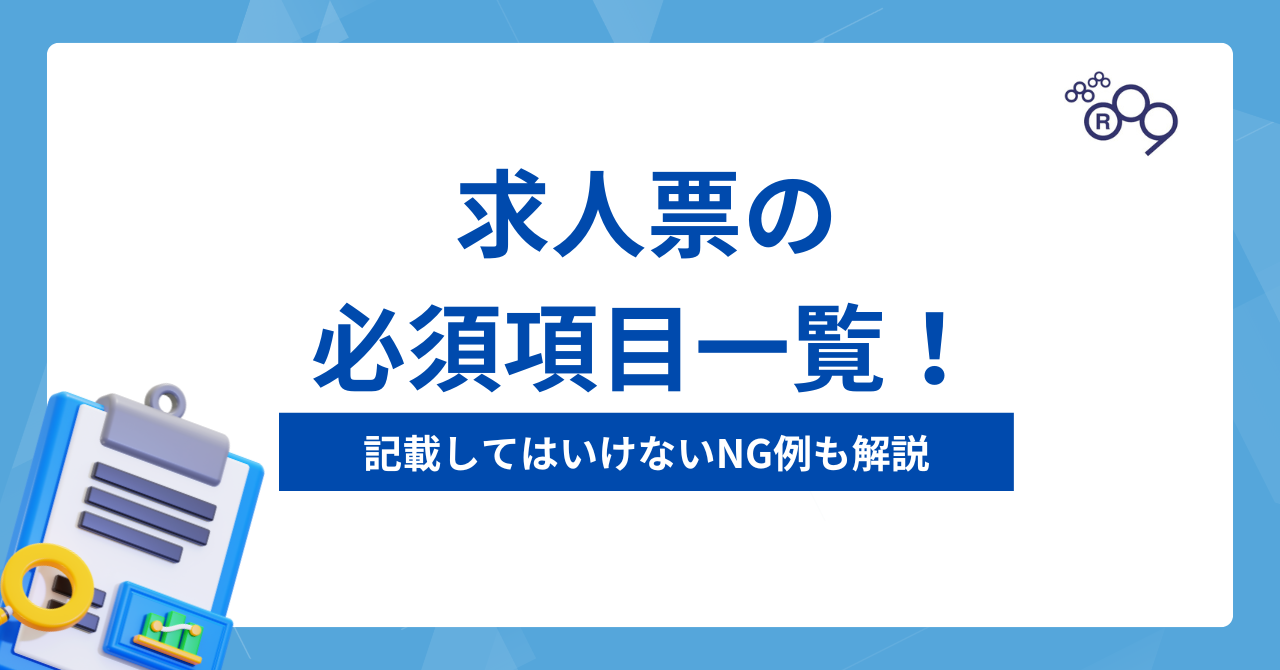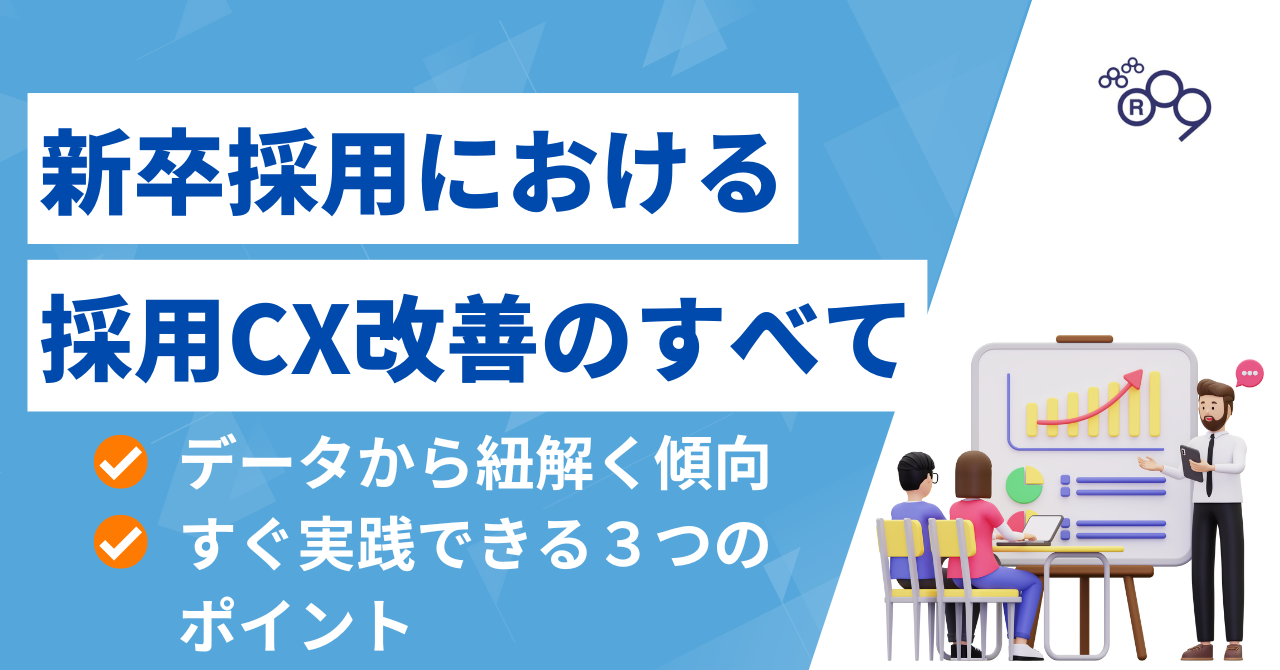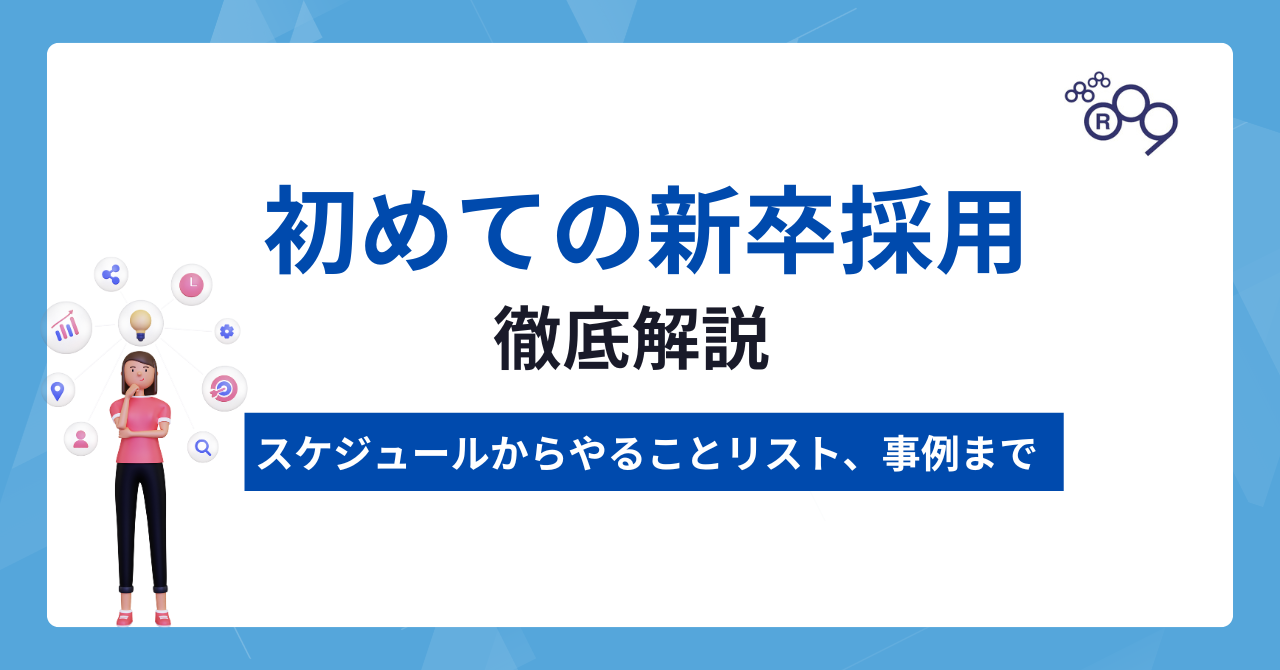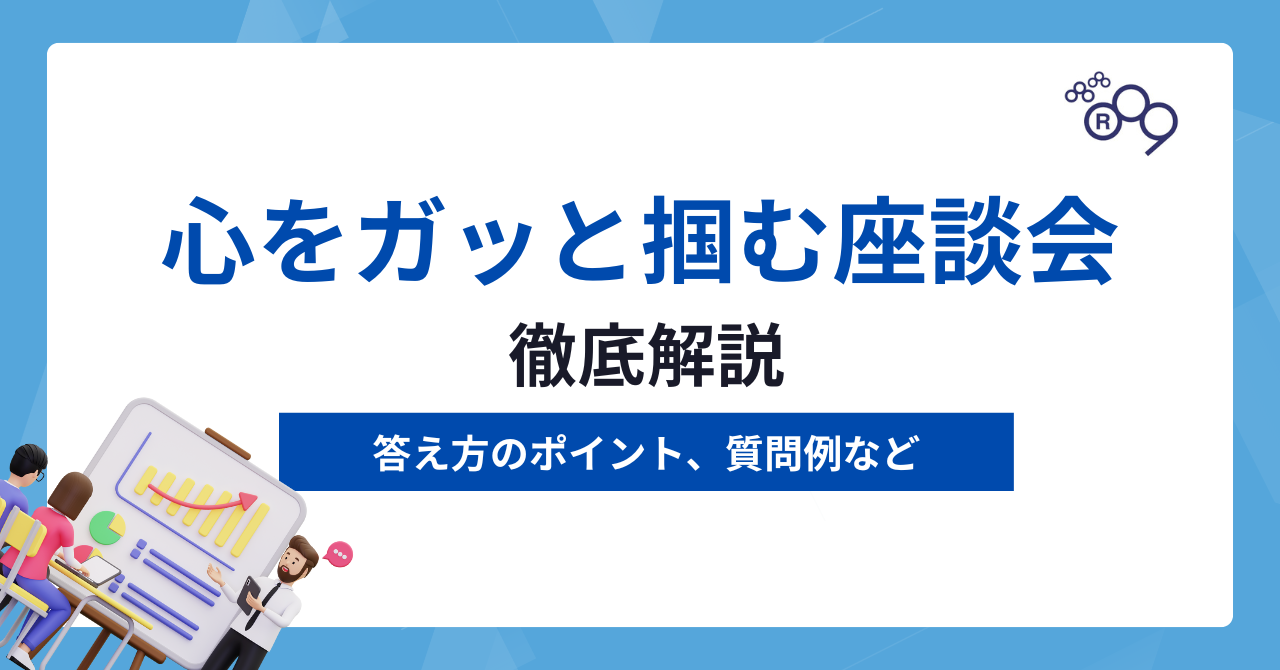忙殺されるひとり人事へ|採用成功に向けた4つの打開策
公開日: 2025年11月11日
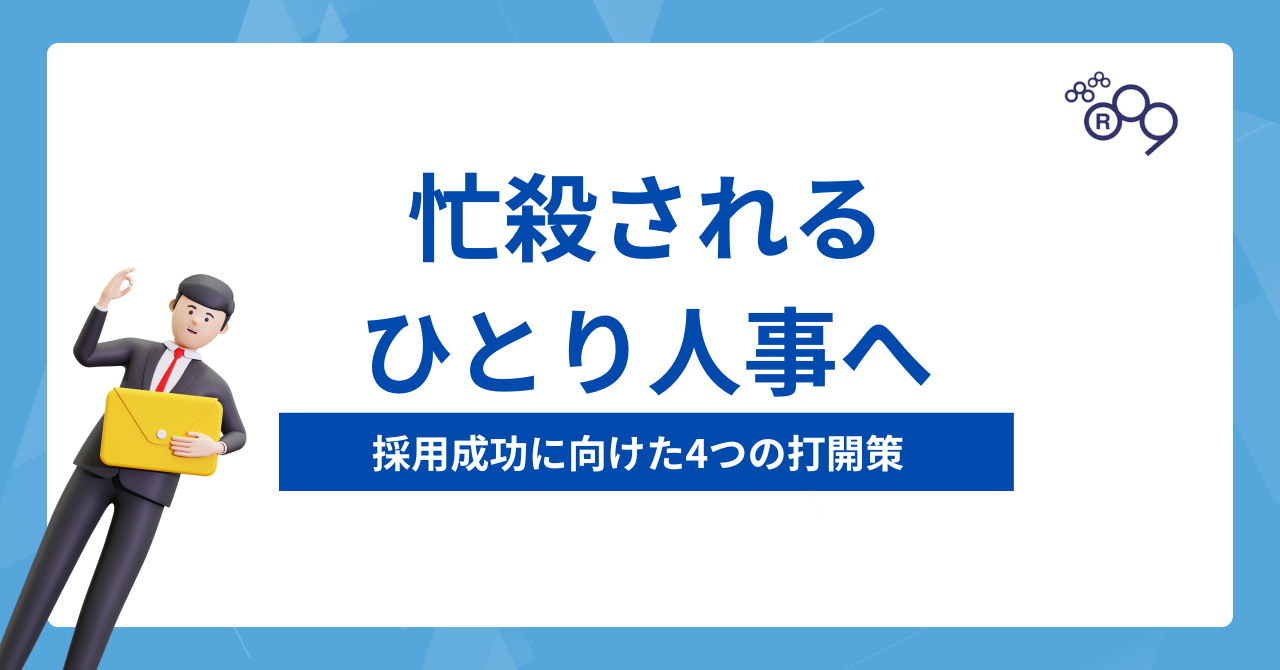
ひとり人事とは、採用・労務・総務など幅広い人事業務をひとりで担う担当者のことです。
近年はスタートアップや中小企業の増加に伴い、この「ひとり人事」という立場で働く人も少なくありません。
特に拡大期や新卒採用を始めるタイミングでは、日々のタスクに追われて「採用をどう進めればいいのか」「成果を出せるのか」と悩むことも多いでしょう。
そこで本記事では、限られたリソースの中でも採用を成功させるための具体的な打開策を4つ解説します。
ひとり人事が抱える採用の悩み
採用専任を置けず、人事業務を一人で担う「ひとり人事」。
特に中小企業や成長途上のベンチャーでは、採用・労務・育成など複数領域を兼任しており、採用活動のPDCAを十分に回せない課題を抱えるケースが多く見られます。
ここでは、採用現場で頻出する3つの課題を整理します。
母集団形成に苦戦
ひとり人事にとって、最初の壁は「応募数の確保」です。
スカウト送付、エージェント対応、求人媒体の運用など、母集団形成に関わる業務はすべて同時並行で発生します。
結果として、“手を動かすこと”が目的化し、効果検証や改善まで手が回らない状況に陥りがちです。
典型的な課題として、以下のような事象が挙げられます。
- スカウト文面がテンプレ化し、返信率が伸びない
- エージェントとの連携が後手に回る
- 求人原稿や媒体分析が更新されず、効果が鈍化する
この状態が続くと、「とりあえず現行施策を回す」だけの採用運用に固定化され、
新しいチャネルや訴求改善に着手できない。結果として、応募数・質ともに頭打ちになります。
採用の質を高める改善に手が回らない
応募は一定数あるものの、「マッチしない」「辞退が続く」「早期離職が発生する」など、採用の質的課題を抱えるケースも多く見られます。
本来は、
- 採用要件の再定義
- 求人票・スカウト文の訴求改善
- 面接官評価の標準化
- 候補者体験(CX)の向上
といった改善サイクルを回す必要があります。
しかし、オペレーションに追われる環境下では、これらが常に“後回し”になります。
結果、「数を追う採用」から抜け出せない構造が続き、
採用効率や定着率の改善が進まないという悪循環が発生します。
候補者対応の遅れ
日程調整、面接官アサイン、合否連絡など、候補者対応の遅れも顕著な課題です。
特に、複数部門が関わる選考フローでは、調整・確認に時間がかかりやすく、結果的にリードタイム(応募~内定までの期間)が長期化します。
候補者側から見れば「返信が遅い=関心が薄い」と映り、候補者体験の低下 → 辞退・他社流出につながります。採用競争が激化する中では、スピードそのものが競争力です。
ひとり人事でも採用を成功させる4つのポイント
ここからは、ひとり人事でも採用成功を実現するために押さえておきたい「4つのポイント」を紹介します。
① 業務をアウトソースし、RPOを活用する
採用業務を短期間で立て直したい場合、RPO(Recruitment Process Outsourcing:採用代行)の活用は有効な選択肢です。
限られたリソースの中で母集団形成や選考対応を一人で行うのは現実的ではなく、「実務を外に出して、思考の時間を取り戻す」ことが、ひとり人事の生産性向上の第一歩になります。
■ RPOでカバーできる領域
RPOは、採用業務全体のうち“時間を奪う作業”を代行する仕組みです。
たとえば以下のような領域を委託できます。
| 業務内容 | 概要 |
| スカウト送信 | ターゲット定義に基づく個別送信、文面最適化、進捗管理 |
| 面談・面接代行 | 面談・面接を実施し、評価や意欲上げを代行 |
| エージェント対応 | 募集要件共有、推薦精度のフィードバック、面談設定 |
| 面接調整 | 候補者・面接官双方のスケジュール調整、連絡代行 |
| 媒体運用 | 求人票の更新、効果測定、レポート作成 |
| 採用広報 | SNS・オウンドメディアでの発信 |
■ 人事が注力すべき領域
RPOに任せられる部分が増えるほど、人事が本来注力すべき仕事が明確になります。
たとえば、
- 採用要件の定義と精度向上
- 選考プロセスごとの歩留まり分析と改善
- 候補者体験(CX)の設計
- 経営層・現場との情報共有・意思決定
といった“採用の質”に直結する業務です。
この分業構造を設計できると、「数」と「質」の両立が可能になります。
■ ひとり人事のRPO活用事例:株式会社クラステクノロジー
製造業向けDX支援を行う 株式会社クラステクノロジー(従業員約100名) では、採用専任者が不在の中、1名の人事担当者が新卒・中途採用を兼務。
スカウト送信やエージェント対応、書類選考といった実務が滞り、「何をどのように進めればよいか分からない」状態に陥っていました。
そこで同社は、アールナインのRPO(採用代行)を導入。
スカウト送付・エージェント対応の代行・書類選考代行・定例ミーティングでの改善提案など、実務から戦略設計まで一気通貫で支援しました。
結果、
- 新卒採用では苦戦していた理系エンジニア採用に成功
- 中途採用でもエンジニア・経理・営業事務など複数職種の採用を達成
- 採用業務に費やす時間を約40%削減し、要件定義・求人票改善に集中可能に
- エージェントとの連携強化により、推薦精度と内定承諾率がともに向上
担当者は次のように語っています。
「単なる実務代行ではなく、市場データに基づく提案や壁打ちが非常に有効でした。
採用を“外注する”のではなく、“共に採用を作り上げるパートナー”という感覚です。」
同社は現在、アールナインの支援を通じて蓄積したノウハウを活かし、自社での内製化に移行しています。このようにRPOを活用することで、ひとり人事でも採用成功を実現することができます。
■ 注意点・リスク
RPOには明確なデメリットも存在します。
- コストがかかる:月額・成果報酬など契約形態によって負担が発生する
- 品質にばらつきがある:担当者や企業によって対応の粒度・スピードが異なる
- 管理負荷が増える:定例ミーティング・進捗共有の設計を怠ると、逆に情報分断が起きる
- 依存リスクがある:内製化やノウハウ移管に対応していないRPOの場合、長期的に社内に知見が残らない
そのため、導入時は「自社がどの業務を内製し、どこを外出しするか」を明確に線引きしたうえで、
内製化支援・データ共有を前提としたRPOパートナーを選定することが重要です。
② 人事担当を新たに採用する
採用のボトルネックが「人手不足」にある場合、人事担当を新たに採用して体制を拡充するのも有効な打開策です。
特に、他社での採用実務や制度構築の経験を持つ人材であれば、ノウハウの社内移転と採用力の底上げを同時に実現できます。
■ ノウハウの内製化と属人化の解消
ひとり人事体制では、どうしても業務が属人的になり、再現性のある仕組みづくりが難しくなります。
人事担当を増やすことで、
- 面接設計や評価基準の標準化
- 採用データの蓄積・分析体制の整備
- 各チャネル運用や候補者対応の分担
といった 「仕組みとしての採用」 に移行しやすくなります。
また、2名体制になることで、現場巻き込みや経営報告の分担も容易になり、採用活動全体のスピードと質が向上します。
結果的に、ひとりで抱え込んでいた“採用の全責任”が分散され、持続的な運用体制を構築できるようになります。
■ 新しい視点・経験・ノウハウの獲得
新たに採用した人事担当者が、他社で得た実務知見やデータに基づく改善ノウハウを持ち込むことで、
社内にない視点や手法が加わります。
たとえば、
- スカウト文面のABテスト運用
- 候補者体験(CX)の定量評価指標の導入
- 面接官トレーニングや評価フレームの整備
など、現場感と仕組み化の両立を図る動きを加速できます。この「外部の知見を内部化する」プロセスは、長期的に見ても人事組織の資産となります。
■ コスト面のリスク
一方で、採用担当を社員として迎える場合は、繁忙期と閑散期の波に注意が必要です。
年間を通じて採用ボリュームが安定しない企業では、
一定期間は業務量が減り、固定コストが過大になるリスクがあります。
そのため、
- 採用以外の業務(人材育成・労務・広報など)も兼務できる設計にする
- 採用ピーク期のみRPOや業務委託で補完する
といった柔軟なハイブリッド体制を検討すると、費用対効果を高めやすくなります。
人事を増員することは“業務の分担”にとどまらず、採用の質を上げるための投資として捉えることが重要です。
組織としての「採用力」を内製化できるかどうかは、ここでの判断にかかっています。
③ 経営陣・現場を採用業務に巻き込む
採用の成果を左右する最大の要因の一つが、「経営と現場の巻き込み力」です。
現場は日々の業務に追われ、「採用は人事の仕事」という認識を持つ社員も少なくありません。
しかし、候補者にリアルな魅力や課題を最も伝えられるのは現場自身です。
■ 現場が関わることで、採用の「質」が変わる
現場社員が採用プロセスに関与することで、以下のような効果が得られます。
- スカウト文面の説得力が増す
現場の視点から具体的な業務内容やチームの雰囲気を伝えられる。 - エージェント・候補者との打ち合わせが立体的になる
採用要件やカルチャーを人事よりも具体的に説明でき、ミスマッチが減る。 - カジュアル面談・面接で“働くリアル”を伝えられる
候補者が入社後の姿をイメージしやすくなり、内定承諾率が高まる。
人事にとっても、現場の協力によってスカウト送信や候補者対応の精度が上がり、
作業負担が軽減されながら、採用の質を高められる構造が生まれます。
■ 経営陣の「採用コミット」が前提
この仕組みを機能させるには、まず経営陣の理解と後押しが欠かせません。
経営が「採用は経営課題である」と明言し、全社にスタンスを示すことで、現場の協力を得やすくなります。
また、経営陣自身が採用活動に関与する場面も多くあります。
たとえば、最終面接や面談で経営メッセージを直接伝えることは、候補者の意思決定を左右する重要な瞬間です。
逆に、「忙しいから面接は任せる」といった姿勢では、優秀層ほど他社に流れてしまいます。
「採用の最終責任を持つのは経営である」という意識が社内に浸透している企業ほど、採用成功率は高い傾向にあります。
■ 採用は「団体戦」
採用は人事ひとりの努力で成立するものではありません。
経営が旗を振り、現場が協力し、人事が仕組みを整える。この「団体戦」の構図をいかに早くつくれるかが、成長企業の分かれ道になります。
④ 採用手法を見直す
ひとり人事にとって最も大切なのは、「すべてを自分でやらない仕組み」をつくることです。
限られた工数の中で成果を最大化するには、多少のコストをかけても工数対効果の高い手法を選ぶ判断が欠かせません。
■ 工数を生まないチャネル設計
スカウト・ナビ・SNS・リファラルなど、採用チャネルは多様化しています。
しかし、リソースが限られる中で複数チャネルを同時運用するのは現実的ではありません。
そんなときは、「母集団形成を外に出す」発想も有効です。
とくに、エージェント活用は初期費用が不要で成果報酬型のため、一定の採用ボリュームが見込めるフェーズでは非常に効果的です。
エージェントを活用すれば、下記のような効果が得られます。
- 候補者のリサーチ・推薦を外部に委ねられる
- 人事は要件定義・面接・クロージングに集中できる
- ハイクラスや専門職など、スキルの高い人材へのアクセスが可能
「費用が高い」と敬遠されがちですが、採用単価とリードタイムの両面で見ると、結果的に最短で採用成功に近づくケースが多いのも実情です。
■ 数字で振り返り、リソースを最適化する
重要なのは、チャネルごとの費用対効果・工数対効果を定期的に可視化することです。
たとえば以下のような観点で振り返ると、改善の方向性が明確になります。
| 指標 | 例 | 見直しポイント |
| 応募単価 | 媒体費 ÷ 応募数 | 高すぎる媒体は撤退検討 |
| 書類通過率 | 応募数 ÷ 通過数 | 要件ミスマッチがないか |
| 面接実施率 | 書類通過数 ÷ 面接実施数 | 候補者対応速度に課題はないか |
| 内定承諾率 | 内定数 ÷ 承諾数 | 候補者体験や魅力づけの改善余地 |
これらのデータをもとに、成果につながるチャネルにリソースを集中投下する。
このサイクルを回すことで、ひとり人事でも“仕組みで勝てる採用”を実現できます。
まとめ
いかがでしたか?
ひとり人事は、採用以外の幅広い業務に追われながら、母集団形成・質の改善・候補者対応を同時にこなさなければならない、とても大変なポジションです。
限られたリソースで採用を成功させるためには、業務を外部に委ねる・採用手法を見直す・人事を増やす・経営や現場を巻き込むといった工夫が欠かせません。
アールナインでは、ひとり人事の方が抱える
「採用業務に手が回らない」
「今進めている方法が合っているか不安」
といった課題に対し、月額制の採用代行サービス 【人事ライト】 で、採用戦略~実務まで一気通貫で伴走いたします。
「社内に相談できる相手がいない」「忙しすぎて改善に手が回らない」と感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事の監修者:
1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。