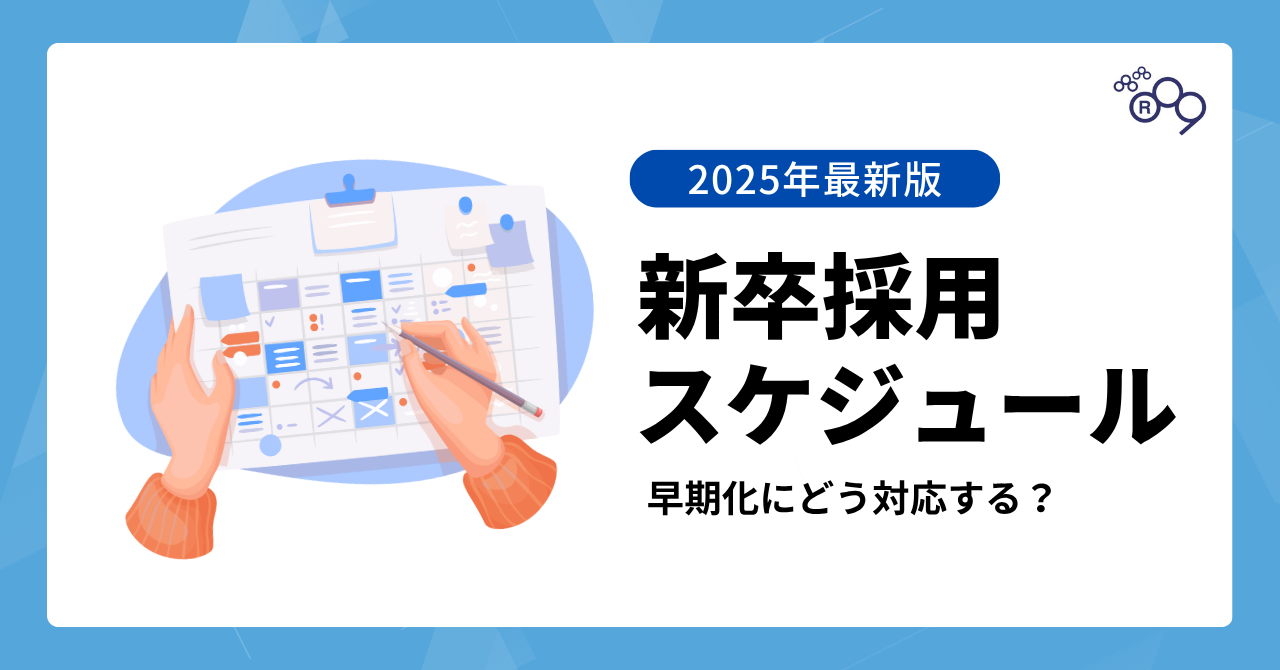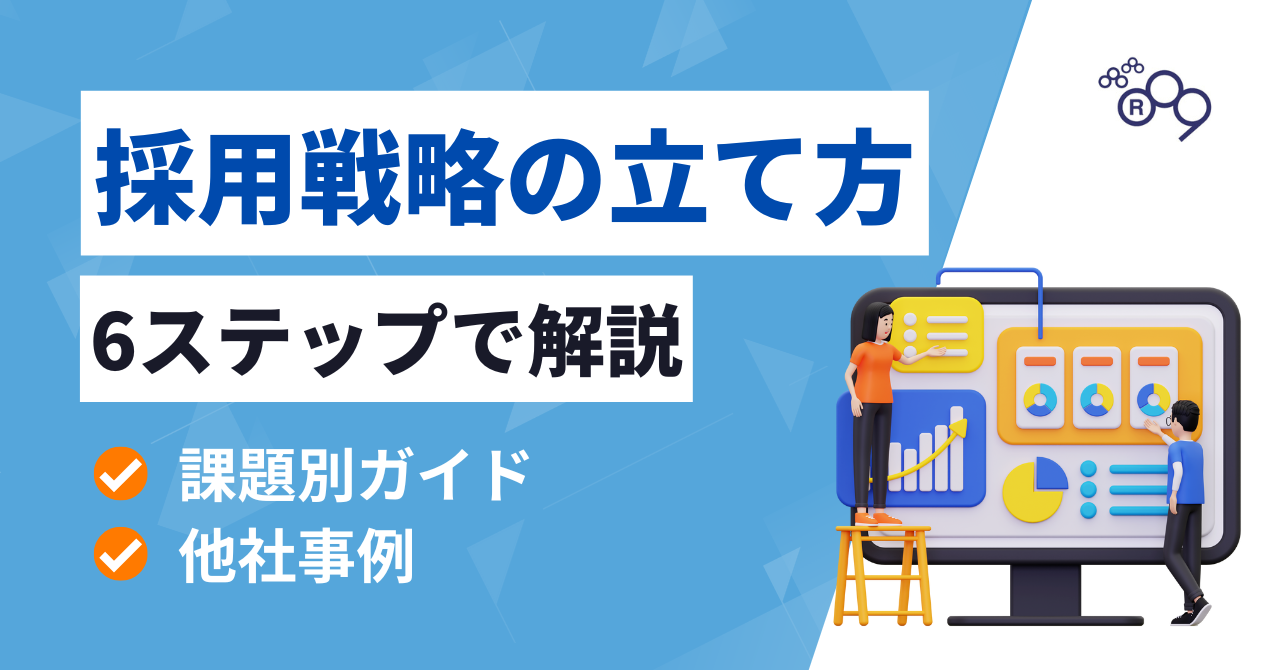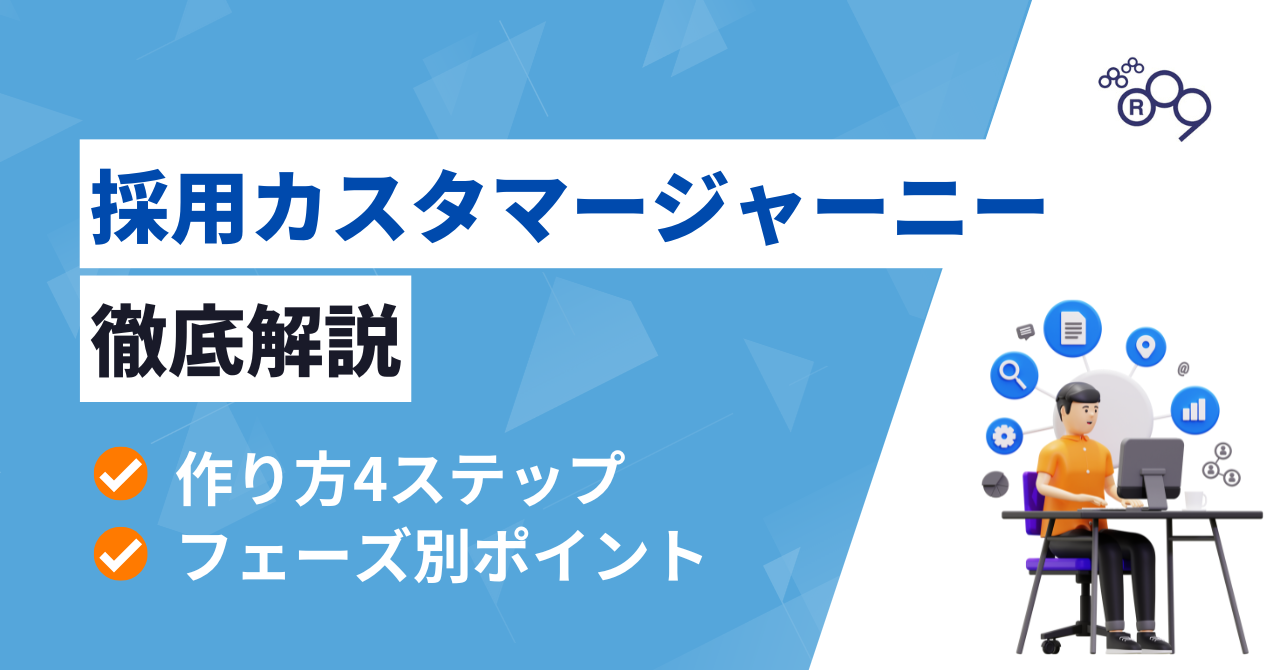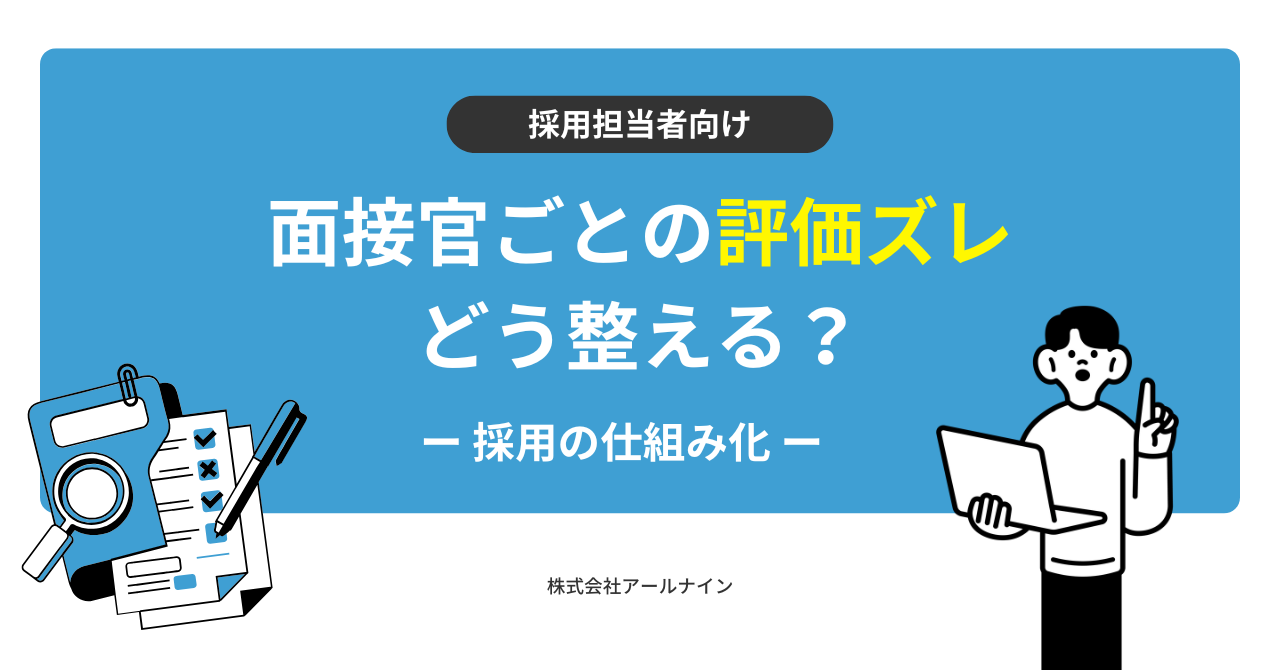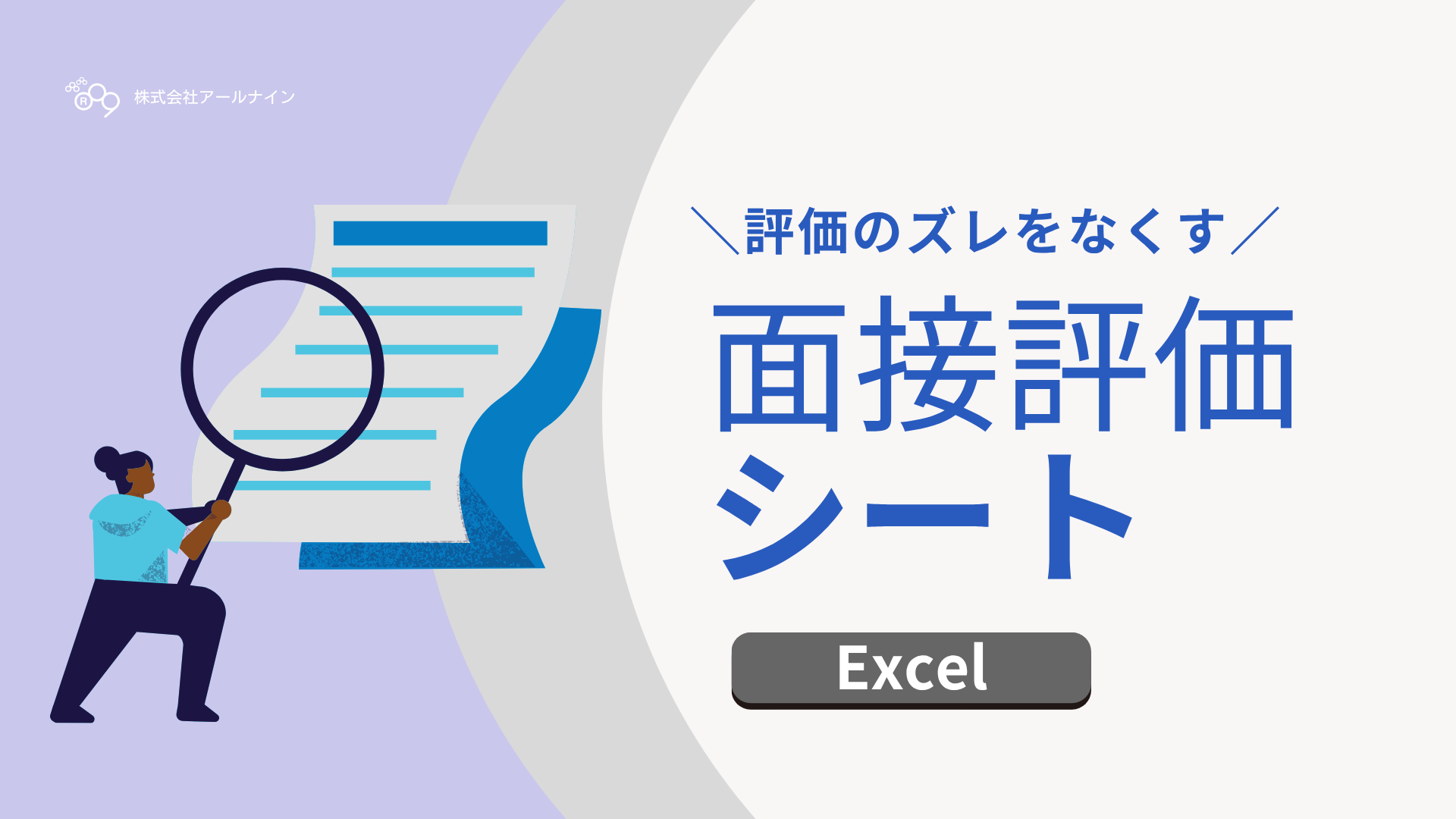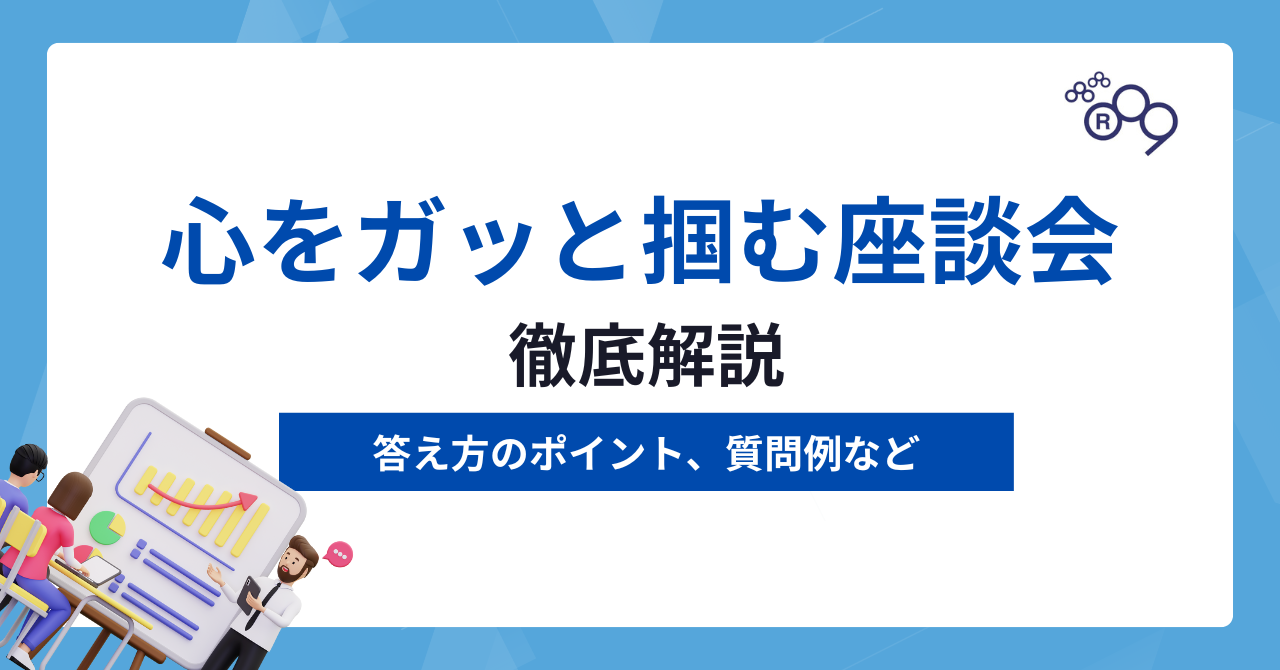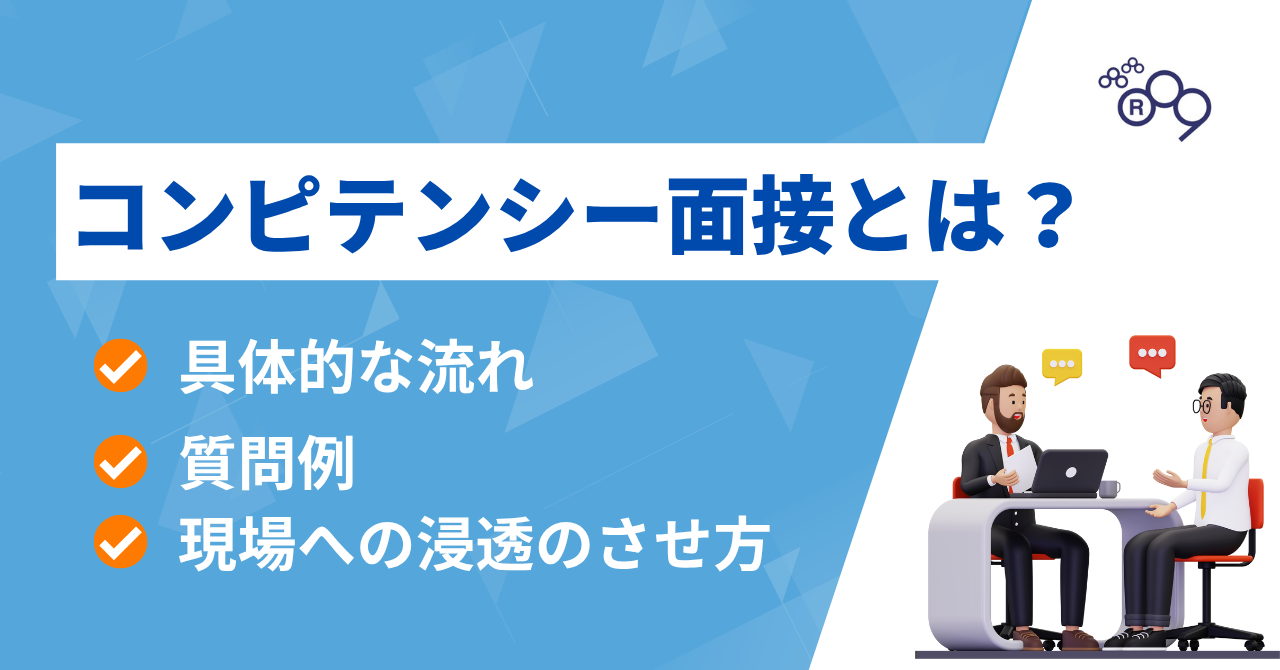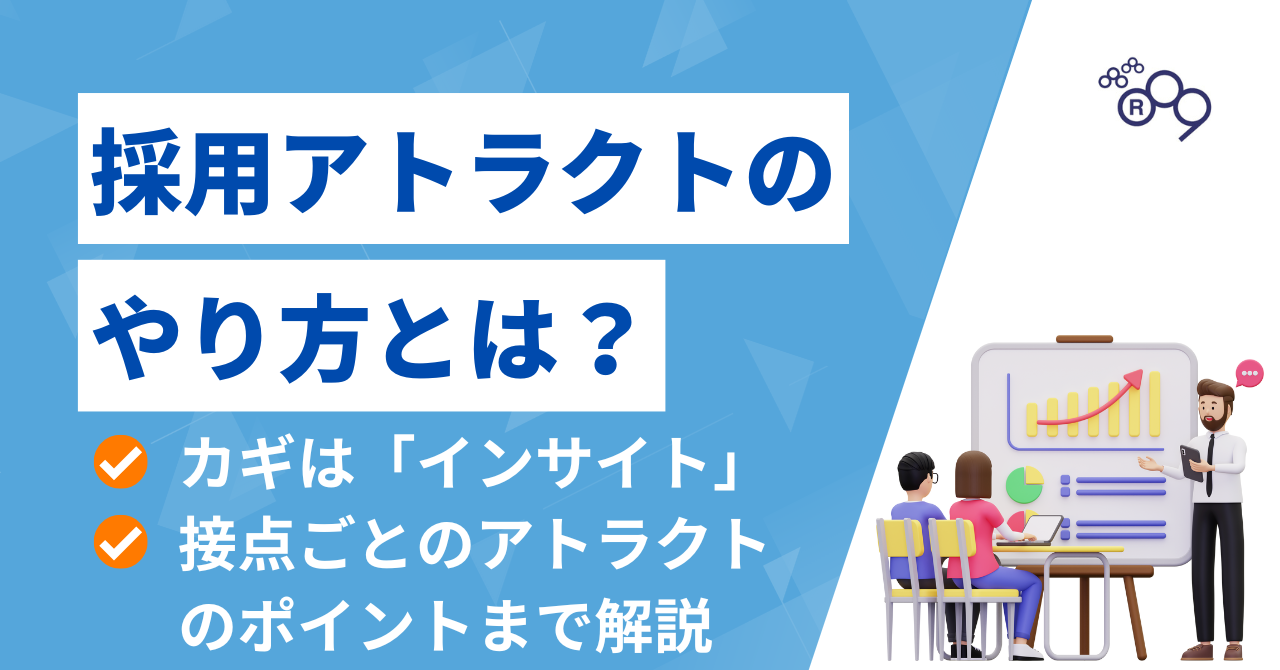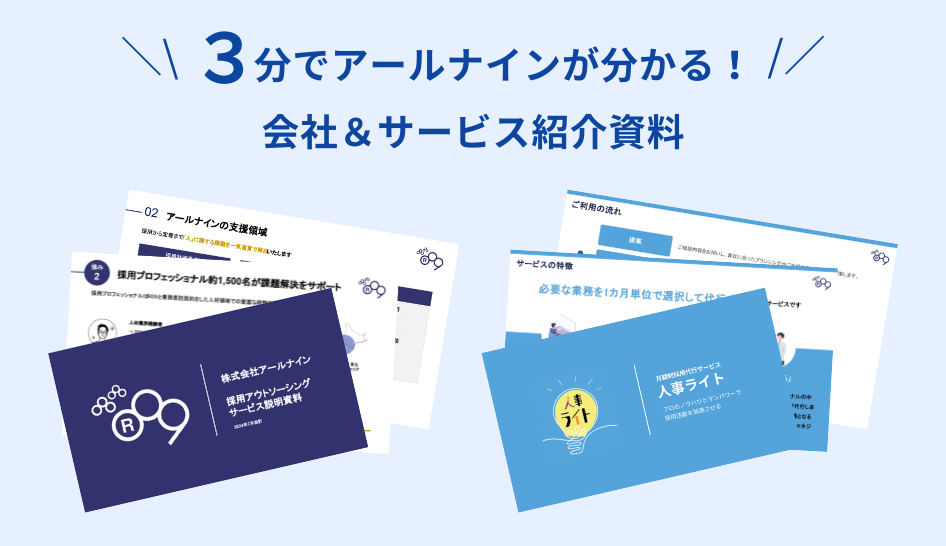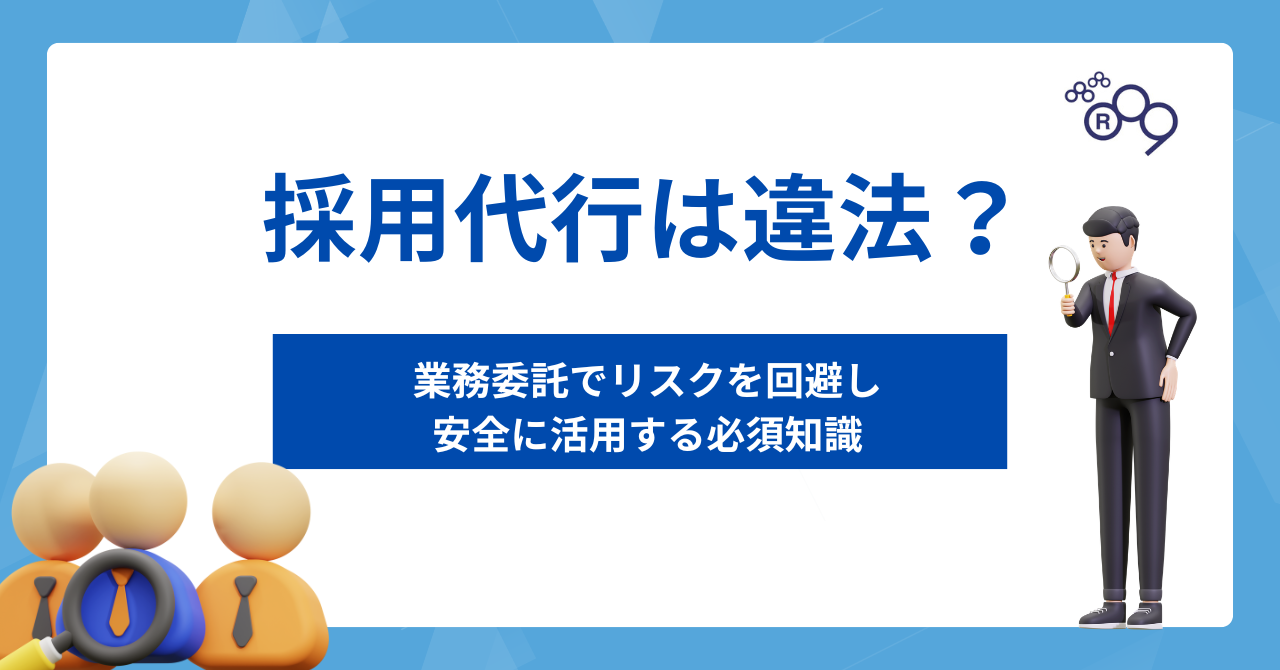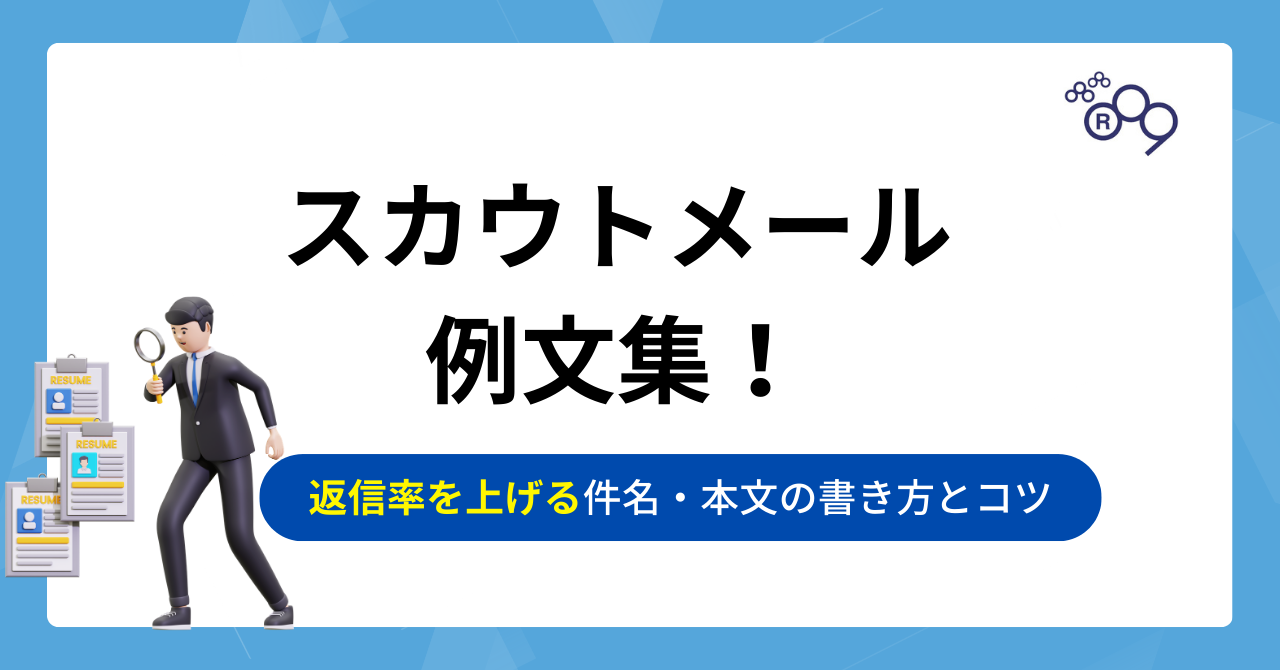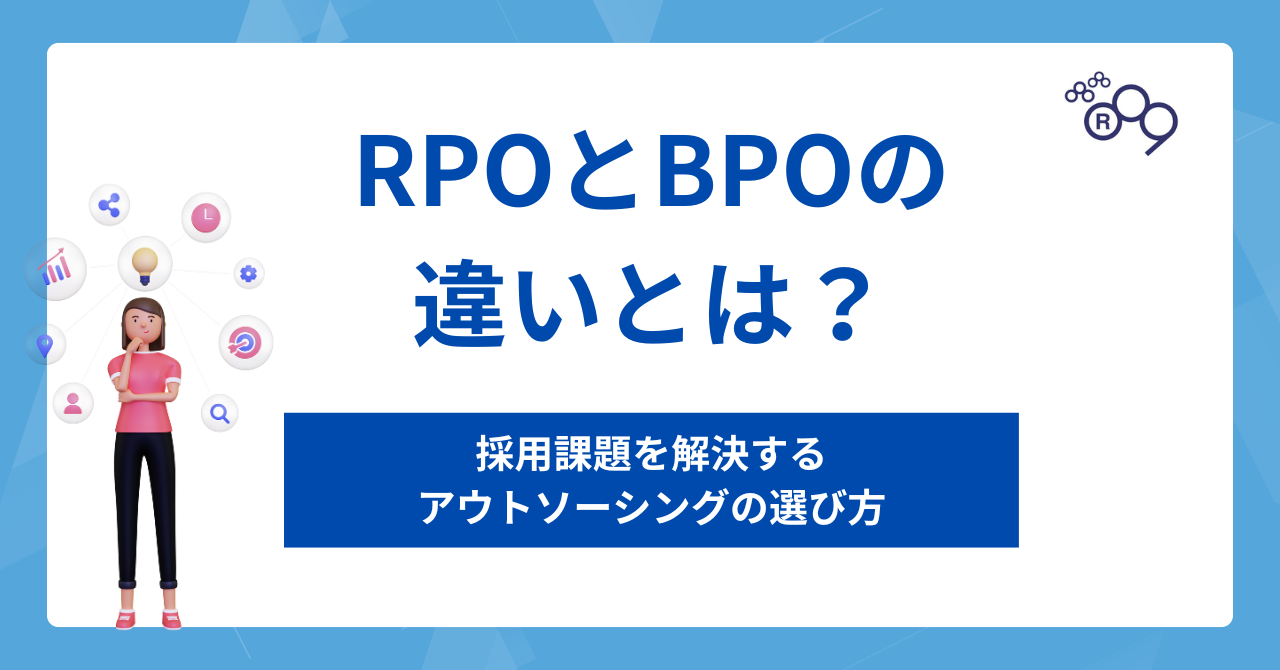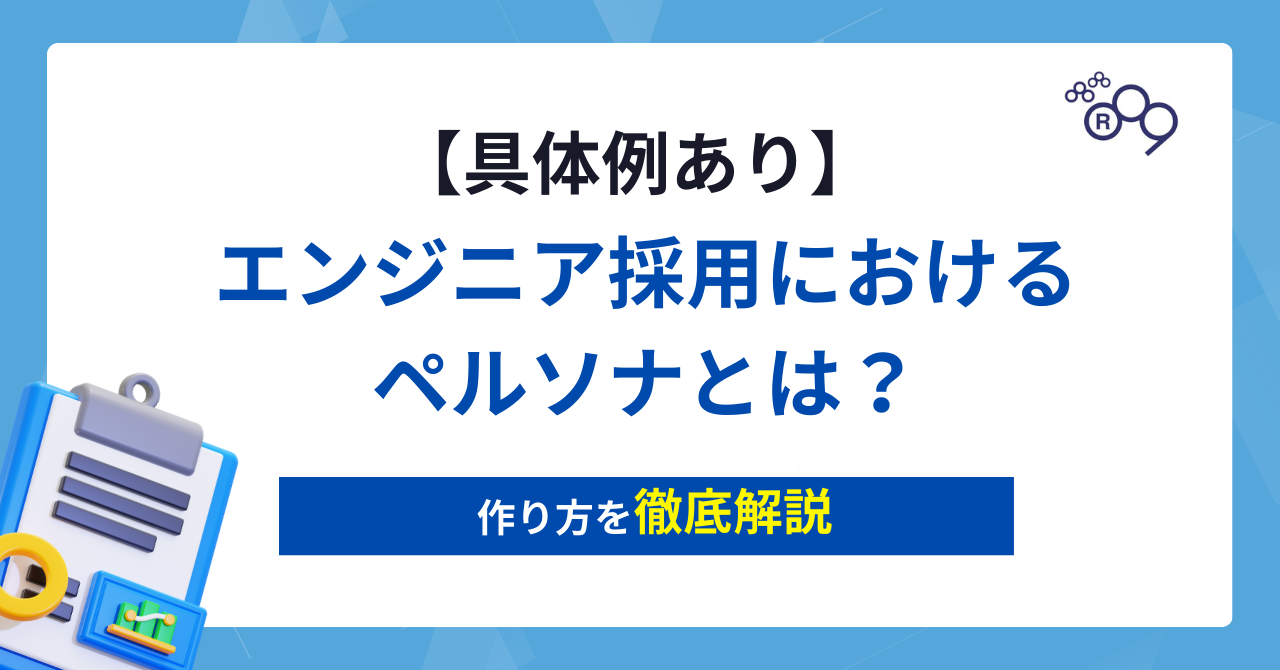【事例あり】初めての新卒採用でも迷わない!スケジュールからやること一覧まで徹底解説
公開日: 2025年11月10日 | 最終更新日: 2025年11月11日
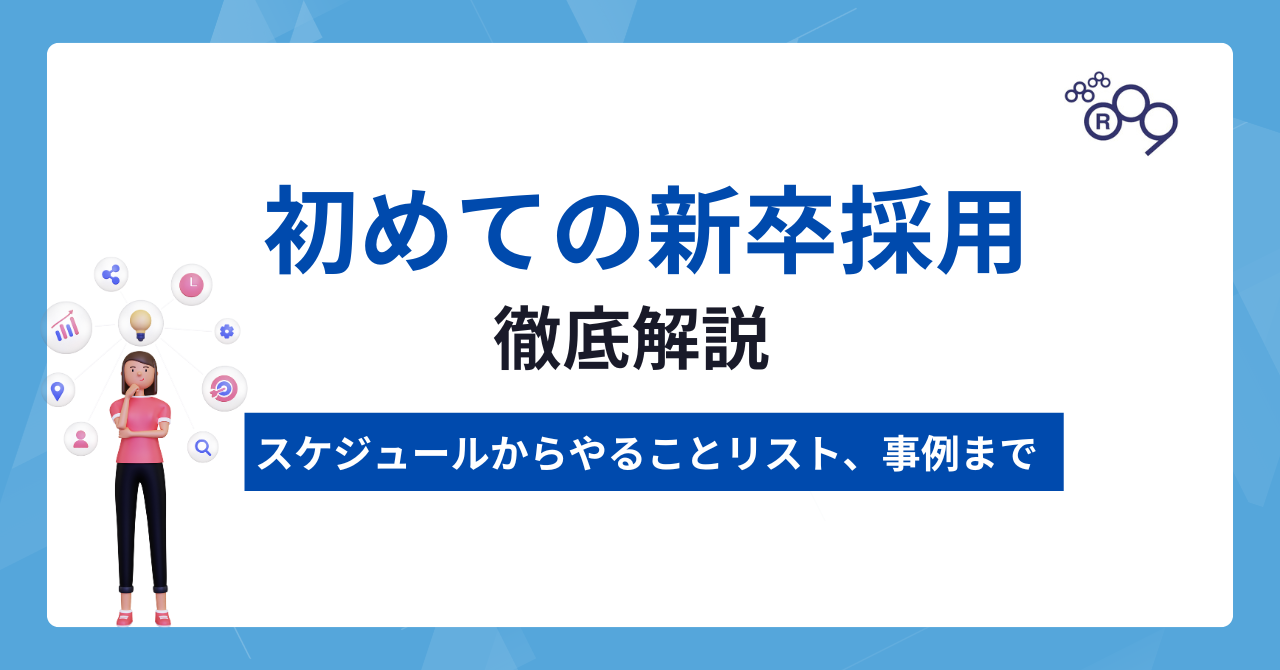
「新卒採用を初めて任されたけれど、何から始めていいのか分からない……。」
中途採用とはスケジュールも進め方もまったく異なり、手探りのまま動き出すと「母集団が集まらない」「内定辞退が続く」といった失敗につながることも少なくありません。
本記事では、初めて新卒採用を担当する方向けに、スケジュールの全体像から、準備・集客・選考・内定フォローまでのやることを時系列で整理しました。
読み進めることで、新卒採用の全体像を理解し、“自社で再現できる”進め方を自信を持って実践できるようになります。
学生の動きから考える、新卒採用の一般的なスケジュール
採用活動は、企業が動き出す時期ではなく、学生が動き出す時期から逆算して設計することが重要です。
特に、大学3年の夏休みまでに「行きたい業界」を決める学生が多く、4〜7月の期間にいかに接点を持てるかが母集団形成の成果を左右します。
| 時期(27卒の例) | 学生の動き | 企業の主な対応・施策 |
| 〜2025年3月(大学2年後期) | 興味業界の情報収集開始 | 採用チーム立ち上げ、採用戦略立案、ターゲット・採用人数の定義 |
| 2025年4〜7月(大学3年前期) | ナビサイト・スカウト媒体の閲覧が最も活発。インターン応募が増加 | 採用サイト整備、スカウト送信開始、夏季インターン募集(母集団形成の最重要期) |
| 2025年8〜9月(大学3年夏) | インターン参加、業界絞り込み | インターン実施、座談会開催、早期選考導線の構築 |
| 2025年10〜12月(大学3年秋〜冬) | 本命企業の選考が本格化。理系学生の約4割が12月末までに内定 | 早期選考開始・内定出し、冬季インターン実施、追加母集団形成 |
| 2026年1〜3月(大学3年末〜4年初) | 文系学生が本格的に選考開始 | 公募選考準備、内定者フォロー開始 |
| 2026年4〜9月(大学4年) | 内定承諾・辞退・比較検討 | 懇親会・面談などフォロー施策実施、内定式、辞退防止施策 |
| 2027年4月(大学卒業) | 入社 | ― |
また、理系・文系で少し動き方が異なる点にも注意が必要です。
理系学生は研究や卒論との両立を考え、就職活動を早期に終える傾向があります。
2026年卒学生を対象とした調査では、12月末時点で理系の43.8%が内々定を獲得しており(株式会社学情「2026年卒学生の12月末時点内々定率調査」)、3月までに就活を終えたい志向が強いことが分かります。
一方、文系学生は6月以降に活動のピークを迎えるケースが多く、ナビサイトやスカウトを通じた継続的な接触が有効です。
採用設計では、こうした文理別の動きの違いを踏まえ、ターゲット層に合わせたスケジュールを立てることが重要です。
※参考:「2026年卒学生の12月末時点内々定率調査」株式会社学情https://service.gakujo.ne.jp/jinji-library/report/26naiteiritsu0107/
政府主導のスケジュール
政府(内閣官房・関係省庁)が示す「就職・採用活動に関する要請」では、形式上は以下のように定められています。
・ 広報活動開始 :卒業・修了年度に入る3月1日以降
・ 採用選考活動開始:卒業・修了年度の6月1日以降
・ 正式な内定日 :卒業・修了年度の 10 月1日以降
ただし、実際には多くの企業が インターンやスカウト、座談会を通じて前年から動いている のが実態です。特に母集団形成や早期選考は、指針よりも半年〜1年以上早く行われるケースが一般的になっています。
つまり、「公式ルールは頭に入れつつも、実態スケジュールで逆算して動く」ことが重要です。
参考:内閣官房・関係省庁「2025年(令和7)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou_yousei/2025nendosotu/index.html?
新卒採用の始め方とやることを、時期ごとに具体的に解説
上で書いたスケジュールを、もっと詳しく解説していきます。
新卒採用の始め方①:まず「採用戦略」と「体制」を固める(〜大学2年3月)
学生は、大学3年の3月までに業界研究を一気に進め、その後の4月〜7月ごろに企業選びやインターンへの応募が加速します。
そのため、企業側はこの時期までに採用の体制や戦略、ターゲット像を明確にし、学生の活動が活発化するタイミングでスムーズにアプローチできる状態を整えておくことが重要です。
本章では、立ち上げ期(〜3月)に経営・現場・人事がそれぞれどのような役割を担い、どのように準備を進めていけばよいのかを、具体的な手順で解説していきます。
やること① 採用チームを立ち上げる
まずは、採用を「人事だけの業務」ではなく全社プロジェクトとして設計します。
新卒採用では、経営・現場・人事の3者がそれぞれの強みを発揮する体制づくりが欠かせません。
ここでは部門ごとの具体的な役割と、最初の3か月でやるべきことを整理します。
| 部門 | 主な役割 | この時期にやること(〜3月) |
|---|---|---|
| 経営陣 | 採用の最終責任者。目的・方向性を定め、意思決定を下す。 | ・採用の目的を経営戦略と紐づけて明文化(例:「5年後に新規事業を担う層を育成する」など) ・採用方針(新卒比率・採用数の目安)を決定 ・採用広報や面接で“自社の顔”となるメンバーを選定 |
| 現場マネージャー | 採用現場のハブ。学生と接する社員を巻き込み、リアルを伝える役割。 | ・自部署で「採りたい人物像」を具体化し、人事と共有 ・面接・座談会に登壇できる社員をピックアップ ・若手社員へ「採用文化の種まき」(協力依頼・OJT計画など) |
| 人事 | 採用全体の旗振り役。戦略設計から実務運用・分析まで担う。 | ・採用目的・ターゲット像を経営・現場とすり合わせ、戦略を設計 ・スケジュールとKPI(例:説明会実施数・スカウト送信数・応募CVR)を設計 ・採用定例(週1〜隔週)を設定し、進捗・課題を可視化 ・求人票作成・スカウト運用・エージェント対応・会社説明会の企画/運営・選考の日程調整などの実行 ・母集団データ・選考データをもとにPDCAを回し、改善サイクルを確立 |
やること② 採用の目的を決めて、判断軸を一本化する
次に、「なぜ今、新卒を採るのか」を明確にします。
目的が曖昧だと、求人票・面接基準・フォロー施策すべてがブレます。
▶ 具体例:
受託案件が増加し、既存社員は手一杯。
今後は自社サービスを伸ばしたいが、それをリードできる層がいない。
採用単価が高騰している今、将来のリーダー層を自社で育てたい。
このように、経営戦略と採用を結びつけたストーリーをつくるのがポイントです。
ここまでで「目的→狙う層→採用のゴール」が言語化できれば、全体設計がぶれません。
やること③ 求める人物像を定義する
採用の目的が明確になったら、次に行うべきは「どんな人を採るのか」を具体的に定義することです。
このステップの目的は、理想の人物像を“感覚”ではなく言葉と基準で共有できる状態にすることにあります。
1. 自社の現状を正しく把握する
まずは、現場の「今」を整理しましょう。
成果を出している社員を3〜5名ほどピックアップし、どんなスキル・行動特性・価値観が成果につながっているかを分析します。
| 観点 | 具体例 |
| スキル面 | 論理的思考力、調整力、コミュニケーション力 |
| 行動特性 | 自ら課題を見つけて動ける、他者を巻き込める、変化に強い |
| 価値観・志向性 | 成長意欲が高い、挑戦を楽しめる、チームで成果を出すことを重視 |
この分析は、「いまの組織が持っている強み」を可視化するプロセスです。
「どんなタイプが自社で活躍しているのか」を整理することで、採用の基準軸が見えてきます。
2. 未来に必要な資質を見極める
新卒採用の目的は、現状を補強することではなく、未来の組織をつくることにあります。
そのため、現状分析だけでなく、採用の目的、事業や組織の方向性を踏まえて「今後必要になる資質」を見極めましょう。
| 現状 | 未来に求める人材 |
| ロジカルで堅実だが守りが強い | スピード感と挑戦力を持ち、まず動ける |
| 受託業務に強い | 自社サービスを企画・推進できる |
| 実行力は高いが発信が弱い | 社内外に影響を与える発信力がある |
「現状の強み」と「未来に必要な要素」を対比することで、“未来から逆算した人物像”が浮かび上がります。
3. 経営・現場・人事で目線を合わせる
「どんな人を採るべきか」の方向性が見えてきたら、次に行うべきは経営・現場・人事の三者での認識合わせです。
ここで合意が取れていないと、求人票のトーンや面接評価の基準がバラつき、採用全体がブレてしまいます。
| 立場 | 主な視点 | よくある考え方の方向性 |
| 経営層 | 事業戦略・中長期方針との整合性 | 「将来的に事業を任せられる人材を育てたい」 |
| 現場マネージャー | 即戦力性・チームへのフィット | 「自分たちのチームで早く活躍できる人がいい。育成の手間をかけたくない」 |
| 人事 | 採用市場の現実性・全体最適 | 「自社の条件で採用できる現実的なレベルに設定したい」 |
三者がそれぞれの立場から“同じ人物像”を描けているかどうかが鍵です。
4. 採用要件をMUST/WANT/NEGATIVEで整理する
採用要件を3分類で言語化すると、求人票・スカウト・面接評価など、選考プロセス全体を通して一貫性が持つことができます。
| 分類 | 定義 | 例 |
| MUST(必須条件) | 活躍に不可欠な条件 | 自走力がある/他者を巻き込める/変化を楽しめる |
| WANT(歓迎条件) | あれば理想的、育成でカバー可能 | 学生時代に企画・運営・リーダー経験がある |
| NEGATIVE(懸念要素) | 活躍・定着を妨げる傾向 | 指示待ち傾向が強い/変化にストレスを感じやすい |
会社全体で「このような学生がほしい」という共通認識を持つことで、ブレずに採用活動を進めていけます。
やること④ 採用KPIと管理体制を設計する
採用戦略を「動かせる仕組み」に落とし込むために、数値設計と運用サイクルを整えます。
ここでは、“採用目標から逆算して考える”ことがポイントです。
採用目標(入社人数)から、各フェーズに必要な数を逆算して設計します。
| フェーズ | 目安指標(例) |
| 採用目標人数 | 2名 |
| 内定承諾数 | 2名(承諾後入社率100%想定) |
| 内定数 | 4名(承諾率50%想定) |
| 最終面接通過者 | 8名(通過率50%) |
| 一次面接通過者 | 25名(通過率30%) |
| 応募・接点数 | 約100名(応募率10〜15%) |
KPIは設定するだけでは意味がありません。
常に測定し、振り返りができる状態にすることが重要です。
採用管理ツール(ATS)を導入できる場合は、データを自動で蓄積・可視化し、改善のスピードを高めましょう。
また、週1〜隔週で経営・人事・現場が集まる定例ミーティングを設け、
進捗の確認や課題の共有を行いながらPDCAを回していくことで、採用を継続的に最適化できます。
やること⑤ 採用チャネルを選定する(どこで・どう出会うのか)
求める人物像とKPIが明確になったら、次に考えるべきは「どこで、どう出会うか」です。チャネルは学生との“入口”であり、どんな経路で接点をつくるかが採用成功を左右します。
一方で、すべてのチャネルに一律で投資するのは非効率です。
自社の知名度・リソース・採用目標に合わせて、優先順位をつけて選定することが重要です。
代表的な採用チャネルと特徴
| チャネル | メリット | 注意点 |
| ナビサイト(マイナビ・リクナビなど) | 幅広い学生にリーチでき、一定の応募が見込める | 競合が多く、知名度の低い企業は埋もれやすい。差別化を意識したページ設計が必須。 |
| スカウト媒体(ダイレクトリクルーティング) | ターゲット学生に直接アプローチでき、精度が高い | 文面の個別最適化が不可欠。運用リソースの確保が前提。 |
| 紹介・エージェント | 成果報酬型でリスクが低く、自社に合う学生を紹介してもらえる | 手数料が高めで、担当者とのすり合わせコストが発生。“共創”姿勢が成果を左右する。 |
| SNS・採用サイト | 自社の魅力を継続的に発信でき、中長期的なブランド形成につながる | 短期的な応募にはつながりにくい。運用の継続性が求められる。 |
| 学校・研究室連携/リファラル | 信頼性の高い母集団にアクセスできる | ネットワーク構築に時間がかかる。継続的な関係づくりが鍵。 |
特に知名度がまだ低い企業や、初めて新卒採用を行う企業は、待ちの採用ではなく“攻めの採用”が有効です。
学生が自ら探してくるのを待つのではなく、企業側から積極的に接点を取りに行く設計をしましょう。
おすすめは「スカウト × エージェント」の組み合わせです。
▶ スカウトは“攻めの採用”の代表格
スカウト媒体は、企業から学生に直接アプローチできる点が最大の特徴です。
知名度に左右されにくく、初めて新卒採用に取り組む企業でも母集団を形成しやすいメリットがあります。
一方で、成果を出すためには安定した配信量と文面の個別最適化が不可欠です。
人事部門だけで運用が難しい場合は、
- 現場社員を巻き込み、メッセージ作成や候補者選定を分担する
- スカウト代行など外部リソースを活用して運用負荷を軽減する
といった方法も効果的です。
スカウト運用は、「継続力」と「質の磨き込み」が成果を分けます。
▶ エージェントは、初期費用なしで質の高い母集団を獲得できる可能性も
エージェントは、初期費用をかけずに自社に合う学生を紹介してもらえる成果報酬型のチャネルです。
母集団形成に十分なリソースを割けない企業にとって、効率的な選択肢となります。
コスト面での懸念を持つ企業もありますが、社内での集客工数や歩留まり改善にかかる時間を考慮すれば、費用対効果は高いといえます。
成果を最大化するためのポイントは、
- 自社の魅力・人物要件を明確に共有すること
- 紹介後のフィードバックを丁寧に返すこと
です。
エージェント担当者との連携精度が高まるほど、紹介される候補者の質も向上します。
コミュニケーションに工数を割くのが難しい場合は、エージェント対応を代行・最適化する外部パートナーを活用する方法も有効です。
やること⑥ 採用カスタマージャーニーを設計する(候補者視点で“入社まで”を描く)
ターゲットと入口(チャネル)が定まったら、候補者が「認知→興味→理解→比較・検討→意思決定」に進む一連の体験を設計します。
大手のように「大量に集めて選抜する」モデルを取りづらい企業ほど、少ない母集団でも高い歩留まりで入社に導く体験設計が成果の分岐点になります。
Step1. 行動フェーズを分解する(5段階)
認知 → 興味・関心 → 理解 → 比較・検討 → 意思決定
※新卒は学年進行と密接です(〜3月に業界研究、4–7月に接点活性、秋〜早期選考 など)。
Step2. フェーズごとの候補者ニーズを定義
- 認知:何の会社か分かるか
- 興味:自分にマッチしている要素、分かりやすい魅力はあるか
- 理解:仕事内容・人・評価・カルチャーの具体像は見えるか
- 比較:他社より選ぶ根拠はあるか
- 意思決定:後悔しない理由が言語化されているか
Step3. タッチポイント×伝える内容を設計
| フェーズ | 主なタッチポイント | 伝えるべき中身(要点) |
| 認知 | ナビ/スカウト/SNS/学校連携 | 事業の要点・採用の狙い・誰に来てほしいかを簡潔に |
| 興味・関心 | 求人票/スカウト文/紹介 | ペルソナに刺さる仕事の魅力+Why You(なぜあなたか) |
| 理解 | カジュアル面談/採用ピッチ/社員記事 | 1日の流れ、配属・評価、若手の成長事例、行動で示すカルチャー |
| 比較・検討 | 座談会/フォロー面談/FAQ | 懸念の先回り(実残業・教育・オンボーディング・働き方)/弱みの言い換え |
| 意思決定 | オファー面談/経営面談 | 選考フィードバック+Why You再提示+初年度ロードマップ |
フェーズごとに、学生のニーズに合わせた魅力づけを行うことで、「選ばれる」採用の仕組みを実現していきます。
同時に、採用基準や面接評価シートや評価シートの整備も進めておきましょう。
新卒採用の始め方②:募集を開始し、母集団を形成する(大学3年4月〜9月)
大学3年の4月以降、学生の就職活動は一気に活発化します。
ナビサイトの閲覧数やスカウトの開封率もピークを迎えるこの時期は、
企業にとって「いかに早く・多く・的確に接点をつくるか」が勝負です。
ここでは、学生が動き出す3〜7月に取り組むべき“集客フェーズ”のポイントを解説します。
やること① 採用広報と募集をスタートする
ナビサイトのエントリー開始に合わせて、求人を作成・公開します。
ただし、「とりあえず掲載」では他社に埋もれてしまうため、差別化された情報発信が欠かせません。
ポイント:
- 「どんな学生に向けたメッセージか」を明確にする
- 事業内容や働き方などを具体的に伝える
- 写真・動画・社員インタビューを活用し、“リアルな空気感”を届ける
やること② スカウト・エージェントを本格稼働させる
ナビ掲載だけでは母集団の幅に限界があります。
学生が動き始めるこのタイミングで、スカウトとエージェントを並行稼働させましょう。
- スカウト運用:
条件検索でターゲット学生を抽出し、個別文章を作成して送信します。
返信率・開封率などの数値を分析しながら、文面を磨き込みましょう。 - エージェント活用:
まずは「求める人物像」「選考フロー」「採用目的」を明確に共有します。
紹介を受けた学生については、
「合格理由・不合格理由」「どこがマッチした/しなかったか」まで丁寧にフィードバックを返しましょう。
この積み重ねが、紹介の精度を高め、より自社に合う学生との出会いにつながります。
やること③ カジュアル面談・会社説明会・インターンなどで接点を深める
募集初期に出会った学生とは、いきなり選考に進めるよりも、
まず「相互理解の場」をつくることが大切です。
学生が安心して本音を話せる環境を整えることで、企業理解と志望度の双方を高められます。
代表的な手法と目的:
| 手法 | 目的・ポイント |
| カジュアル面談/座談会 | 人事や現場社員と直接話せる場を設け、リアルな雰囲気や働くイメージを伝える。「どんな人と働くのか」を体感してもらうことで、心理的ハードルを下げられる。 |
| 会社説明会 | 企業としてのストーリーを一貫して発信する場。事業内容・カルチャー・育成方針を整理し、「なぜこの会社で働くのか」を伝える。 |
| 1day仕事体験/選考直結型インターン | 実際の業務体験を通じて、学生の“納得感”を高める。スキルや価値観のフィットを確認し、早期選考につなげやすい導線をつくる。 |
学生にとって、こうした“リアルな接点”は志望度を高めるきっかけになります。
新卒採用の始め方③:本格的な選考開始。惹きつけながら見極める(大学3年10月〜3月)
秋以降は、学生の就活活動が本格化し、“本命企業の選考”が続々と始まります。
理系学生はやや早め、文系学生は12月ごろからがピークです。
この時期のポイントは、
「学生を見極める」と同時に、「学生から選ばれる採用体験をつくる」こと。
特に初めての新卒採用では、“評価と魅力づけの両立”が採用成功を左右します。
やること① 評価シートに従い、行動特性と価値観を見極める
新卒採用では、スキルよりも「再現性」を見ることが大切です。
学生の過去の経験から、“なぜそう動いたのか”の背景を掘り下げましょう。
| 主な評価軸 | 質問例 |
| 主体性 | 自分から課題を見つけ、動いた経験は? |
| 協働性 | 他者と協力して成果を出した経験は? |
| 挑戦意欲 | 未経験のことに挑戦したとき、どう考え動いた? |
| 成長志向 | 失敗や壁に直面したとき、どう乗り越えた? |
ポイントは「何をしたか」よりも「なぜそうしたか」を深掘りすること。
行動の“意思決定プロセス”を見ることで、その人の価値観と成長の再現性が見えてきます。
始め方①で設計した採用基準や評価シートに則り、選考結果を出し、社内共有・学生への伝達をしていきます。評価結果は面接官だけで完結させず、経営・現場・人事で週次共有していきましょう。
やること② 面接を“魅力づけの場”として活かす
学生にとって面接は「企業に見られる場」であると同時に、
「企業を見極める場」でもあります。
そのため、面接の中で安心感と納得感を与えることが大切です。
ポイントは次の3つです。
- 面接冒頭で学生の話をよく聞き、心理的安全性をつくる
- 学生の価値観に応じて、自社の魅力を伝えていく
- 実際の例を用いることで、入社後のイメージを湧かせる
やること③ 面接官トレーニングを実施する
面接官の力量が、学生の印象と採用結果を左右します。
初めての新卒採用では、「学生と話すスキル」そのものを磨く場を設けましょう。
チェックポイント例:
- 学生への質問が一方通行になっていないか
- 志望動機を深掘りできているか
- 回答を評価する際の基準が共有できているか
- 自社の魅力を一貫して伝えられているか
新卒採用の始め方④:内定フォローと入社準備を行う(大学4年4月〜翌3月)
大学4年の春以降は、内定承諾・辞退防止・入社準備のフェーズです。
この時期は「採用できた!」と安心しがちですが、
内定承諾後の辞退や、入社後の早期退職も最も起こりやすい要注意フェーズです。
やること① 内定出し~内定承諾を得る
内定を出した後、学生が他社へ流れないように、スピードと信頼関係が鍵。
「内定を出して終わり」ではなく、“どう伝え、どうつなげるか”まで設計しましょう。
内定通知〜承諾までの基本ステップ
- 内定通知面談を実施(即日または翌営業日)
└ メール連絡だけで終わらせず、オファー面談で意向・不安・期待を丁寧に確認。 - 内定承諾書を送付し、期日を明示
└ 迷っている学生には「比較してもいい。率直に話してね」と言葉を添える。
承諾前も定期的に面談を設定し、“継続的な接点”をつくる。
やること② 内定者フォローを計画的に行う
承諾後でも、「なにか違う」と感じて辞退するケースは少なくありません。
先輩社員や同期との接点が持ち、エンゲージメントを継続的に高めていきましょう。
フォローの基本3ステップ
| 時期 | 主な目的 | 具体的なアクション例 |
| 内定直後(4〜6月) | 信頼関係の定着 | 内定者懇親会/1on1面談/社内イベント招待 |
| 夏〜秋(7〜10月) | エンゲージメント維持 | メンター制度/同期交流会/現場社員との座談会 |
| 冬〜入社前(11〜翌3月) | 入社準備・不安解消 | 研修案内/配属発表/事前課題・個別相談 |
やること③ 入社前準備を進める(人事・現場の二人三脚)
入社直前期(1〜3月)は、学生の期待と不安が最も入り混じる時期。
このタイミングでのサポートが、早期離職防止のカギになります。
| 項目 | 担当 | 内容 |
| 入社手続き | 人事 | 契約書・各種書類・入社案内の送付/期日管理 |
| 配属・受け入れ準備 | 現場 | OJT担当者決定/業務セットアップ/PC・アカウント準備 |
| 事前研修 | 人事+現場 | 社会人マナー/業界理解/プロジェクト体験型ワーク |
| メンタリング体制 | 現場 | 入社後3ヶ月の伴走設計(1on1/フォロー面談) |
この時期に“迎え入れる側”の準備が整っていると、
学生は「ちゃんと受け入れてくれる会社だ」と安心できます。
やること④ 現場を巻き込み、“入社後まで続く採用”にする
初めての新卒採用では、「採用=内定で終わり」になりがちです。
しかし本当の採用成功は、“入社後に活躍しているか”で判断されます。
- OJT担当者やメンターを早期に決定し、目的を共有する
- 入社初日〜3ヶ月のオンボーディング計画を作成
- 採用担当が“入社後の定着”までモニタリングする
採用活動は、内定出しで終わらず、入社後の成長まで含めて設計していきましょう。
初めての新卒採用で特に注意すべきポイント
初めて新卒採用に取り組む企業がつまずきやすいのは、「中途採用の感覚」で進めてしまうことです。
採用市場の構造も、候補者心理も、採用スケジュールもまったく異なります。
ここでは、初年度から成果を出すために押さえておきたい注意点を解説します。
① 採用の早期化に後れを取らない
近年、新卒採用の早期化に拍車がかかっています。
キャリタスの調査(2024年10月)によると、
「採用活動の開始時期を前年度より早めた」と回答した企業は、前年より10ポイント以上増加しています。
初めての新卒採用だからこそ、余裕を持って、早めに準備をスタートしましょう。
出典:キャリタス「2026年卒・新卒採用に関する企業調査」
https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/02/202502_kigyochosa.pdf
② 母集団の“数”よりも“歩留まり”を重視する
採用は、「母集団 × 歩留まり(移行率)」で決まります。
特に、初めて新卒採用に取り組む中小・ベンチャー企業にとって、 大量の母集団を集めるのはコスト・リソースの両面で現実的ではありません。
大切なのは、「自社にマッチした層を、適切な数だけ集めて、離脱させない」という考え方です。
“集める”よりも、“惹きつけながら繋ぎ止める”ことに力をかけることで、
限られた母集団からでも高い採用成果を生み出せます。
③ 歩留まりを高めるため「採用CX」を意識する
上記の歩留まりを高める最大のカギは、採用CX(候補者体験)です。
「自社が選ぶ採用」ではなく、「学生から選ばれる採用」への転換が求められています。
ターゲットを明確にし、その学生が何を重視し、どんな価値観で就活しているのかを正確に捉える。そのうえで、自社のリアルな魅力を、相手の心に届く順番と方法で伝えていくことがポイントです。同時に、「日程調整・合否連絡のスピードは十分か」「面談や面接での印象は良いか」なども重要になってきます。
④ 採用を「団体戦」で行う
初めての新卒採用では、採用担当だけで進めようとすると破綻します。そもそも人的なリソースが足りないこともあります。さらに、新卒採用は「会社全体の取り組み」であり、経営・現場・人事の3者が同じメッセージを発信する必要があります。
社内全体で目線を合わせて、採用成功に向けて進んでいきましょう。
⑤ 学生をスキルでなく「伸びしろ」で見る
中途採用のように「経験・実績」で判断すると、新卒採用では失敗します。
重要なのは、どの方向に成長する可能性があるか(伸びしろ)です。
- 目標に向かって行動を続けた経験があるか
- 挫折をどう乗り越えたか
- チームの中でどんな役割を担ったか
こうした行動特性や価値観を見ることで、
“数年後に伸びる人”を見極めることができます。
面接では「何をしたか」よりも「なぜそうしたか」「その後どう変わったか」を掘り下げる質問を意識しましょう。
初めての新卒採用事例:株式会社ライオンハート
従業員20名規模のライオンハート社は、これまで中途採用が中心で、新卒採用のノウハウはほとんどありませんでした。オフィス移転をきっかけに「会社の未来を担う仲間を迎えたい」と決断し、初めての新卒採用に挑戦。しかし、何から始めればよいのか分からない状況に直面し、月額制の採用代行サービス【人事ライト】を活用しました。
実際に取り組んだこと
- ターゲット設計
社内のハイパフォーマーを適性検査で分析し、求める行動特性を抽出。「逆境でも粘り強く動ける」「カルチャーを共に育てられる」などを人物像として定義。 - メッセージングの工夫
スカウト463件を配信。件名や文面を改善し、「なぜあなたに声をかけたのか」を明記して返信率を向上。 - 採用プロセスの設計
応募から内定までの流れを整理。選考ステップごとに「学生が何を感じるか」を設計し、安心感と期待感を持たせる体験づくりを重視。 - フォロー施策
説明会や面談後には必ずお礼メールやフィードバックを送付。学生が「この会社は自分を見てくれている」と感じられる工夫を実施。 - データを振り返り改善
週次の定例ミーティングで、応募数・返信率・辞退理由を数字で可視化。その場で改善策を議論し、次週の運用に即反映。
結果として、目標としていた3名の内定承諾を獲得に成功しました。
担当者は「成果も嬉しいが、それ以上に“プロとチームで取り組めた経験”が大きな価値だった」と振り返っています。採用は孤軍奮闘だと負担が大きいですが、信頼できる外部パートナーと連携することで、プロセス自体が学びと楽しさを伴ったプロジェクトになりました。
まとめ
今回は、初めて新卒採用に取り組む際のスケジュールや流れ、やること一覧、注意すべきポイント、実際の事例について解説しました。
初めての新卒採用はノウハウもリソースも不足しがちで、「何から手をつければいいのか分からない」「思ったように学生が集まらない」と悩むケースが非常に多く見られます。だからこそ、基本の流れを押さえつつ、自社の状況にあわせて柔軟に戦略・計画を組み立てることが成功の鍵になります。
もし、自社での初めての新卒採用に不安がある場合や、スカウト・説明会・内定者フォローなどの実務でサポートが必要な場合は、株式会社アールナインの月額制RPOサービス「人事ライト」をご活用ください。ターゲット設計からスカウト代行、説明会運営、フォロー体制づくりまで一気通貫でサポートし、初めての新卒採用でも着実に成果につなげられるよう伴走します。
初めての新卒採用を確実に成功させたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事の監修者:
1999年青山学院大学経済学部卒業。株式会社リクルートエイブリック(現リクルート)に入社。 連続MVP受賞などトップセールスとして活躍後、2009年に人材採用支援会社、株式会社アールナインを設立。 これまでに2,000社を超える経営者・採用担当者の相談や、5,000人を超える就職・転職の相談実績を持つ。